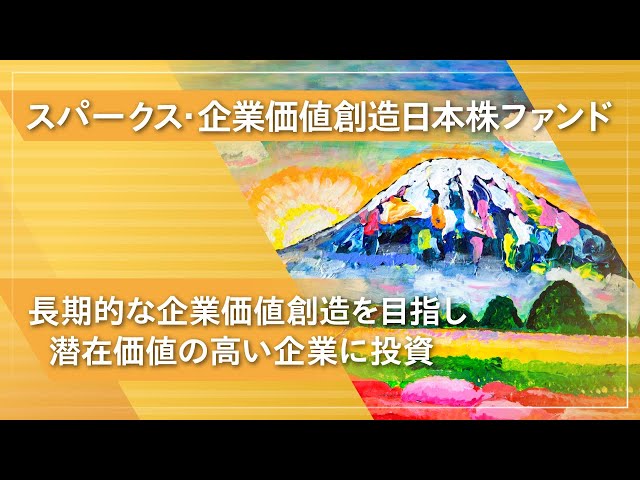スパークス・企業価値創造日本株ファンド
- NISA成長投資枠対象ファンド
- 日経新聞掲載名
- 企業価値創造
- 分類
- 追加型投信/国内/株式
- 設定日
- 決算日
- 毎年5月14日
基準日:2026.02.16
- 基準価額
- 14,973円
- 前日比
-
-63円
-0.42% - 純資産総額
- 639.1億円
- 分配金情報(税引前)
- 210円
- 販売用資料 (2.1 MB)
- 交付目論見書(2.0 MB)
- 請求目論見書(3.6 MB)
- 月次報告書 (411.2 KB)
- 交付運用報告書(933.3 KB)
- 運用報告書(全体版)(918.3 KB)
- 当ファンドは、NISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
基準価額推移
分配金実績
決算頻度:1回/年
- 設定来合計
- 420円
- 直近12期計
- 420円
分配金実績一覧
- 2025年05月14日
- 210円
- 2024年05月14日
- 210円
- 上記以前の分配金については、「選択した期間のデータをダウンロード」ボタンからご確認いただけます。
月次報告書
2026年
- 1月(411.2 KB)
2025年
- 12月(405.9 KB)
- 11月(411.0 KB)
- 10月(413.8 KB)
- 9月(414.0 KB)
- 8月(409.6 KB)
- 7月(424.0 KB)
- 6月(427.5 KB)
- 5月(426.0 KB)
- 4月(426.7 KB)
- 3月(427.6 KB)
- 2月(422.9 KB)
- 1月(429.4 KB)
2024年
- 12月(424.1 KB)
- 11月(428.0 KB)
- 10月(428.2 KB)
- 9月(430.2 KB)
- 8月(425.0 KB)
- 7月(428.4 KB)
- 6月(419.1 KB)
- 5月(412.1 KB)
- 4月(411.0 KB)
- 3月(416.3 KB)
- 2月(405.6 KB)
- 1月(430.1 KB)
2023年
- 発表年
- キーワード検索
「」の検索結果
2026年1月の運用コメント
株式市場の状況
2026年1月、日本株式市場の代表的な指数であるTOPIX(配当込み)は前月末比4.62%上昇し、日経平均株価は同5.93%の上昇となりました。
月前半は、米国半導体関連株の大幅上昇を受けて日本の半導体・AI(人工知能)関連株が買われ、大発会から日経平均株価は大幅高でスタートしました。中国政府によるレアアース関連製品を含めた対日輸出規制が強化されるとの報道で、日本株式市場が一時急落する場面はあったものの、衆院解散・総選挙観測を受けて高市首相が掲げる成長戦略が進めやすくなるとの見方を背景に、月半ばにかけて主要指数の高値更新が続きました。
月後半は相場の様相が一変しました。選挙戦の本格化や野党の新党結成を受けて国内の政治情勢の不透明感が台頭したことに加え、米欧の貿易摩擦懸念など地政学的リスクも意識され、投資家心理が悪化しました。さらに、財政拡張による財政悪化懸念から国内長期金利が想定を上回るペースで上昇し、株式市場は調整色を強めました。月末にかけては、日米当局による「レートチェック」報道をきっかけに為替相場が急変し、円は一時対ドルで153円台まで上昇するなど不安定な動きとなり、輸出関連株を中心に株式市場は揺さぶられました。日本株式市場は月後半に伸び悩みましたが、前月末比で大幅高の水準を維持して当月の取引を終えました。
ファンドの運⽤状況
当月、当ファンドは前⽉末⽐2.24%上昇し、参考指数であるTOPIX(配当込み)の同4.62%の上昇を2.38%下回りました。パフォーマンスにプラスに寄与した企業は、PILLAR、三菱重工業、ダイフクなどでした。⼀⽅、マイナスに影響した企業は、リクルートホールディングス、全国保証、マックスなどでした。
当ファンドでは、企業経営者が誠実であり、高い競争優位性を有する企業の中から、更なる成長余地のある潜在価値の高い企業に長期集中投資を行い、企業との対話を通じて価値の顕在化を図ることを基本戦略とします。
日本には、高い技術力・開発力を持ち、ニッチ市場でグローバルに高いシェアやブランド力を持つ企業が多く存在します。そうした企業の中には、基礎的な収益力が高く、中長期的な成長余地が大きいにも関わらず、「玉に瑕(きず)」があるために株式市場で実態価値を正当に評価されていない企業があります。
当ファンドでは、そのような企業の長期的なパートナー株主※として、良好な関係を築きながら粘り強く対話を行っています。企業の事業戦略や資本配分、IR体制などの改善を促すことで、企業の実態価値の顕在化に努め、株価上昇のカタリストの一つとなることを目指します。
当運用レポートでは、投資先企業に対する投資見解や対話の進捗などをご報告させていただきます。
当月は、当ファンドの投資先である「EIZO」に対する投資見解、対話内容をご説明します。
EIZOは1967年に石川県七尾市で七尾電機として設立された高機能モニターメーカーです。当ファンドは、同社の一貫した自社開発・自社生産による徹底した品質へのこだわりと、クラフトマンシップに支えられた医療・映像制作・航空管制・船舶などの特定用途における高いシェアを評価し、投資を行いました。内視鏡検査や放射線検査といった低侵襲医療の浸透に伴って重要度が増す、同社の主力製品の一つである医療用モニター、さらには同社の技術を統合したEVS(EIZO Visual Systems)事業の成長に注目しています。
一方で、同社は手元現預金や投資有価証券などの金融資産を約849億円保有しており、総資産の約48%を占めています。(2025年12月末時点)。このような保守的なバランスシートが重石となり、過去最高益を記録した2022年3月期においても、同社のROE(株主資本利益率)は6.7%にとどまっています。当戦略は、同社にはバランスシートマネジメントによる資本収益性に改善余地があると考え、ROE向上に関して、経営陣と対話を続けてきました。
同社は2022年5月に40億円の自社株買いを実施し、買収防衛策の廃止を発表するなど、資本市場への向き合い方に徐々に変化が見られておりました。2023年3月期決算説明会では、ROE8%以上を資本収益性の目標とし、総還元性向70%という明確な株主還元方針を掲げ、資本政策における姿勢を鮮明にしました。
2025年3月期は、欧州でのオフィス用モニター需要および中国での医療用モニター需要の減速により、厳しい事業環境にありました。しかし、同社は総還元性向70%+αを維持する方針を崩さず、2025年10月にも40億円の自社株買いを発表しており、一貫した株主還元強化の姿勢が表れています。また、直近の2026年3月期第3四半期の決算においても、欧州を中心に低迷が続いたことで、通期業績予想を下方修正していますが、同時に、政策保有株の純資産比率を10%未満まで縮減する方針を示しており、資本効率改善に向けた大きな転換が進展しています。
中期経営計画においては、厳しい市況下で2027年3月期に向けた計画目標は見直し中であるものの、医療用モニターやEVS事業など成長領域への注力によって収益力の回復を目指しています。また、政策保有株の縮減に加え、機動的な自社株買いおよび連続増配を通じ、ROE8%以上の達成を目指し続ける姿勢には、市場の期待に応えようとする経営陣の強い意志が表れており、当ファンドとしては高く評価しています。
当ファンドはパートナー株主として、同社の中長期的な成長を実現する上で、対処が求められる様々な経営課題について経営陣との対話を続け、同社の本源的な企業価値の向上を積極的に後押ししていく方針です。
今後の運⽤⽅針
当ファンドでは潜在価値の高い企業に選別して集中投資を行い、長期的なリターンを追求しています。潜在価値の高い企業とは、スパークスの投資アプローチである3つの着眼点(経営者の質・企業収益の質・市場の成長性)に照らし、企業の実態価値や成長性が株式市場で十分に評価されていないと考えられる企業を指します。
日本には強固な事業基盤を有していながら、事業戦略や資本配分、株式市場への向き合い方に改善余地があることから株価が実態価値よりも低く評価されている企業が数多く存在します。当ファンドはパートナー株主として、投資先企業との中長期的な関係構築と丁寧な対話に努め、課題の改善を促すことで、企業価値の顕在化を積極的に後押しします。
※当ファンドは企業オーナーとして短期業績や株価変動に惑わされない⻑期保有を前提としています。投資先企業と共に企業価値向上を⽬指すとの考えから、短期的に株式を売買する投資家と区別する為、「パートナー株主」との文言を使⽤しています。
2025年12月の運用コメント
株式市場の状況
2025年12月、日本株式市場の代表的な指数であるTOPIX(配当込み)は前月末比1.03%上昇し、日経平均株価は同0.17%の上昇となりました。
月前半は、植田日銀総裁の発言を受けて12月会合での利上げ観測が高まり、長期金利が急上昇しました。この影響から銀行株を除く幅広い銘柄が売られ、主要指数は大きく下落しました。その後、米国の利下げ期待や、米政府がロボット産業を支援する方針を示したことを受け、FA(ファクトリーオートメーション)、ロボットなど「フィジカルAI(人工知能)」関連株が急伸し、相場全体をけん引し、TOPIXは史上最高値を更新しました。
月半ばには、米国の利下げ決定後に一時的な調整も見られましたが、米国株が堅調で主要指数が高値を更新するなか、日本市場でも買いが優勢となり、TOPIXは再び最高値を更新しました。しかしその後、米IT大手Oracle社のAIデータセンター完成の遅れや、半導体大手Broadcom社の決算が市場期待に届かなかったことなどから、AI投資の収益性に対する警戒感が高まり、半導体関連株を中心に売りが広がり、相場は調整色を強めました。
月後半は、日銀が利上げを決定したものの、総裁会見がハト派的と受け止められたことから円安が進行し、輸出関連株や半導体株を中心に買いが入りました。ただし、月末にかけては薄商いの影響もあり、相場は方向感を欠く展開となりました。結果として、TOPIXは相対的に底堅く上昇基調を維持し、日経平均株価も小幅ながら前月を上回って当月の取引を終えました。年間を通してみると、年前半に大きな下落に見舞われる場面があったものの、年後半には両指数とも高値更新を続け、高水準での推移となりました。
ファンドの運⽤状況
当月、当ファンドは前⽉末⽐0.28%下落し、参考指数であるTOPIX(配当込み)の同1.03%の上昇を1.31%下回りました。パフォーマンスにプラスに寄与した企業は、リクルートホールディングス、キーエンス、コニカミノルタなどでした。⼀⽅、マイナスに影響した企業は、SHOEI、サイゼリヤ、全国保証などでした。
当ファンドでは、企業経営者が誠実であり、高い競争優位性を有する企業の中から、更なる成長余地のある潜在価値の高い企業に長期集中投資を行い、企業との対話を通じて価値の顕在化を図ることを基本戦略とします。
日本には、高い技術力・開発力を持ち、ニッチ市場でグローバルに高いシェアやブランド力を持つ企業が多く存在します。そうした企業の中には、基礎的な収益力が高く、中長期的な成長余地が大きいにも関わらず、「玉に瑕(きず)」があるために株式市場で実態価値を正当に評価されていない企業があります。
当ファンドでは、そのような企業の長期的なパートナー株主※として、良好な関係を築きながら粘り強く対話を行っています。企業の事業戦略や資本配分、IR体制などの改善を促すことで、企業の実態価値の顕在化に努め、株価上昇のカタリストの一つとなることを目指します。
当運用レポートでは、投資先企業に対する投資見解や対話の進捗などをご報告させていただきます。
当月は、当ファンドの投資先である「SHOEI」に対する投資見解、対話内容をご説明します。
SHOEIは、バイク用高級ヘルメットの製造・販売を手掛ける企業です。1959年に設立され、その卓越した製品デザインや機能性、品質の高さからグローバルに多くのファンを抱えています。販売網は日本、欧米、中国をはじめとする世界60か国以上に広がり、世界の高級ヘルメット市場において約60%のトップシェアを誇ります。
同社は設計・開発・製造を一貫して日本国内で行っており、製造工程の多くは自動化されていますが、機械では代替できない高度で精密な作業は現在でも人の手で行われています。また、同社は「カイゼン企業」を標榜し、生産効率の向上に継続的に取り組んでいます。このような現場力こそが同社の競争力の源泉であり、長年にわたり蓄積されたノウハウと人材育成を重視する企業風土が、今後もSHOEIブランドへの信頼性を高めていくと当ファンドでは考えています。さらに、高いブランド力と商品開発力を背景にデザイン性・機能性に優れた新製品を戦略的に投入することで、継続的な製品単価の上昇が期待できると見ています。
一方で、2025年9月期の業績は厳しい結果となりました。国内では二輪関連市場の減速や流通における在庫調整の長期化が影響し、またグローバルにおいては主力モデルのモデルチェンジの端境期にあったことから、販売数量が減少しました。その結果、同社は9期ぶりの営業減益となりました。
2026年9月期の同社公表の業績予想では、在庫調整の一巡や新モデル投入による販売数量の回復が見込まれているものの、一時的な未実現利益の影響などにより、増収減益の見通しとなっています。同社は販売数量拡大に向けて、グラフィックモデルの拡充やカーボンヘルメットの投入を進めているほか、従来と異なる客層の獲得を目的に、ガンダムや初音ミクなどのIPとのコラボレーションといった多様な商品戦略を展開しています。なお、同社の業績予想は、価格改定効果を十分に織り込まない点や過去の予実を踏まえると、保守的に策定される傾向があると当ファンドでは認識しています。当ファンドとしては、同社の中長期的な事業成長に対する見方に変更はなく、今後も個別面談を通じて慎重にフォローアップしていく方針です。
また、当ファンドは同社の資本政策には改善の余地があると考えています。同社は約27%と高い営業利益率(2025年9月期)と強固なキャッシュフロー創出力を有し、現金が積み上がりやすい構造にあり、2025年9月末時点で総資産の約5割を現預金が占めています。当ファンドは、現行の同社の還元方針(配当性向50%)を前提とすると、資本の蓄積ペースが早く、将来的なROE(株主資本利益率)の低下が懸念されることから、規律ある資本政策の実行を求め、トップマネジメントとの対話を継続してまいりました。2025年9月期の決算説明会において、同社からキャピタルアロケーション、最低限預金水準について初めて開示がなされ、同社の資本政策に対する姿勢の変化が見られました。さらに、25億円の自社株買いの実施に加え、今期は減益予想ながら一株当たり配当金を維持するなど、現金の積み上がりに対する具体的な対応も示されています。当ファンドは長期のパートナー株主として、今後も同社の企業価値向上に向けた建設的な対話を粘り強く続けてまいります。
今後の運⽤⽅針
当ファンドでは潜在価値の高い企業に選別して集中投資を行い、長期的なリターンを追求しています。潜在価値の高い企業とは、スパークスの投資アプローチである3つの着眼点(経営者の質・企業収益の質・市場の成長性)に照らし、企業の実態価値や成長性が株式市場で十分に評価されていないと考えられる企業を指します。
日本には強固な事業基盤を有していながら、事業戦略や資本配分、株式市場への向き合い方に改善余地があることから株価が実態価値よりも低く評価されている企業が数多く存在します。当ファンドはパートナー株主として、投資先企業との中長期的な関係構築と丁寧な対話に努め、課題の改善を促すことで、企業価値の顕在化を積極的に後押しします。
※当ファンドは企業オーナーとして短期業績や株価変動に惑わされない⻑期保有を前提としています。投資先企業と共に企業価値向上を⽬指すとの考えから、短期的に株式を売買する投資家と区別する為、「パートナー株主」との文言を使⽤しています。
2025年11月の運用コメント
株式市場の状況
2025年11月、日本株式市場の代表的な指数であるTOPIX(配当込み)は前月末比1.42%上昇し、日経平均株価は同4.12%の下落となりました。
月前半は、AI(人工知能)関連銘柄の前月までの上昇に対する過熱感が意識され、米国株式市場にて関連銘柄が大幅に調整した影響が日本株式市場にも波及しました。一方でバリュー株や内需株等は底堅く推移し、これらのウェイトの差異が指数の変動に大きな影響を与えた結果、日経平均株価の下落が大きくなり、他方TOPIXは相対的に底堅さを維持しました。
月半ばには、日中関係の緊張を背景に中国政府が渡航自粛を要請したことが嫌気され、日経平均株価、TOPIXの両指数とも再び大きく下落し、日経平均株価は節目の5万円を割り込む場面も見られました。その後は、米国株式市場においてNVIDIA社が好決算を受け、時間外取引で同社株が上昇したことが追い風となり、日本株式市場でもアドバンテスト、東京エレクトロン、ソフトバンクグループの3銘柄が日経平均株価を約700円押し上げる場面も見られるなど株価は持ち直しましたが、AI投資の過熱感に対する警戒は根強く、上値の重い展開が続きました。
月後半にかけては、FRB(米連邦準備制度理事会)高官のハト派的発言を受けて12月利下げ観測が再び高まり、米国株の持ち直しとともに日本株式市場も反発しました。結果として、日経平均株価は8か月ぶりの下落となった一方、TOPIXは小幅ながらも上昇を確保し、両指数のパフォーマンスはまちまちとなり、当月の取引を終えました。
ファンドの運⽤状況
当月、当ファンドのパフォーマンスは、前⽉末⽐4.42%の上昇となり、参考指数であるTOPIX(配当込み)の同1.42%の上昇を3.00%上回りました。
当ファンドのパフォーマンスにプラスに寄与した企業は、横浜ゴム、コニカミノルタ、SHOEIなどでした。⼀⽅、マイナスに影響した企業は、三菱重工業、キーエンス、ホシザキなどでした。
当ファンドでは、企業経営者が誠実であり、高い競争優位性を有する企業の中から、更なる成長余地のある潜在価値の高い企業に長期集中投資を行い、企業との対話を通じて価値の顕在化を図ることを基本戦略とします。日本には、高い技術力・開発力を持ち、ニッチ市場でグローバルに高いシェアやブランド力を持つ企業が多く存在します。そうした企業の中には、基礎的な収益力が高く、中長期的な成長余地が大きいにも関わらず、「玉に瑕(きず)」があるために株式市場で実態価値を正当に評価されていない企業があります。当ファンドでは、そのような企業の長期的なパートナー株主※として、良好な関係を築きながら粘り強く対話を行っています。企業の事業戦略や資本配分、IR体制などの改善を促すことで、企業の実態価値の顕在化に努め、株価上昇のカタリストの一つとなることを目指します。
当運用レポートでは、投資先企業に対する投資見解や対話の進捗などをご報告させていただきます。
当月は、当ファンドの投資先である「美津濃(ミズノ)」に対する投資見解、対話内容をご説明します。
美津濃は1906年に水野利八氏、弟の利三氏の兄弟によって創業されたスポーツ用品メーカーです。野球ボールや運動着等の販売を起点に、ゴルフ、スキー、陸上など様々なスポーツ用品を開発し、長年にわたりスポーツ振興を支えてきました。高品質なものづくりに裏打ちされた技術力と、競技者のパフォーマンス向上に寄与する研究開発を強みとし、国内外でブランド価値を確立しています。
当ファンドでは、同社の1.ワークビジネス、2.ゴルフ、3.サッカーの三つの事業に注目しています。
- ワークビジネスは2016年度から始まった歴史の浅い事業ですが、すでに国内1,600社以上で採用されており、同社の国内事業における成長の柱となっています。同社が競技スポーツで蓄積してきた3DCG(3次元コンピューターグラフィックス)による身体動作解析技術や、高耐久素材の開発力をワークウエアやワークシューズに応用することで、単なるユニフォーム供給に留まらず、現場での作業効率や安全性向上まで踏み込んだ価値を提供している点が成功要因と考えられます。スポーツ由来の高機能素材や設計思想を産業分野に展開することで、同社の既存技術を高度に再活用できていることも特筆すべき点です。
- ゴルフ事業においては、特に米国市場で顕著な存在感を示し始めています。同社のアイアンは、1本の丸棒からヘッドを成形する独自の鍛造製法により、“打感の良さ”や“フィーリング性能”といった感性価値を高いレベルで実現しており、トッププレーヤーからアマチュアに至るまで幅広い支持を獲得しています。
- サッカーシューズでは、同社の技術が存分に活かされたレザーモデルが高い評価を得ています。特に東南アジア市場では、2017年のサッカー専任チーム設立を契機に事業が急拡大し、タイ市場を中心にミズノブランドの浸透が進みました。Jリーグでプレーしたチャナティップ選手との契約を皮切りに、現地有力選手との契約が広がったこともブランド浸透の追い風となりました。
こうした魅力的な成長事業を複数有しているにもかかわらず、同社はスポーツシューズ・アパレルを手掛ける競合他社と比較すると、株式市場では割安に評価される傾向が続いています。その背景には、1.事業ポートフォリオの過度な多角化、2.非効率的な資本配分という構造的な課題が存在します。同社は競技人口が少ないマイナー競技向け製品や、公共フィットネス施設の運営受託事業といった収益性の低い事業も抱えており、これらの事業が全体の資本収益性を下押しする要因となっています。また多角化の結果、研究開発費や宣伝費など経営資源が分散し、重点領域へ十分な投資を行いにくい状況が生じていることも懸念点です。
当ファンドでは、事業ポートフォリオ改革と資本配分の最適化が進展すれば、同社の市場評価は改善する余地があると考えています。美津濃には長年の製品開発で蓄積された独自技術や素材開発力があり、自己資本比率も70%超と財務体質は極めて健全です。現預金や投資有価証券などの金融資産の活用余地も大きく、資本効率向上に向けた施策は幅広く検討可能と推察しています。当ファンドは長期的なパートナー株主として、事業戦略と資本政策の両面について建設的な対話を重ね、企業価値向上に向けた取り組みを後押ししてまいります。
今後の運⽤⽅針
当ファンドでは潜在価値の高い企業に選別して集中投資を行い、長期的なリターンを追求しています。潜在価値の高い企業とは、スパークスの投資アプローチである3つの着眼点(経営者の質・企業収益の質・市場の成長性)に照らし、企業の実態価値や成長性が株式市場で十分に評価されていないと考えられる企業を指します。
日本には強固な事業基盤を有していながら、事業戦略や資本配分、株式市場への向き合い方に改善余地があることから株価が実態価値よりも低く評価されている企業が数多く存在します。当ファンドはパートナー株主として、投資先企業との中長期的な関係構築と丁寧な対話に努め、課題の改善を促すことで、企業価値の顕在化を積極的に後押しします。
※当ファンドは企業オーナーとして短期業績や株価変動に惑わされない⻑期保有を前提としています。投資先企業と共に企業価値向上を⽬指すとの考えから、短期的に株式を売買する投資家と区別する為、「パートナー株主」との文言を使⽤しています。
2025年10月の運用コメント
株式市場の状況
2025年10月、日本株式市場の代表的な指数であるTOPIX(配当込み)は前月末比6.20%上昇、日経平均株価は同16.64%上昇いたしました。
月前半は、米政府機関の一部閉鎖懸念を背景に軟調なスタートとなりましたが、高市早苗氏が自民党総裁に就任すると、市場では積極財政や成長戦略への期待が高まり、「高市トレード」と呼ばれる株高・円安の動きが急速に進行しました。月半ばにかけては、公明党の連立離脱報道が伝わり、政局不安が広がりました。さらに、米国による対中追加関税発表とそれに対する中国の報復措置が加わり、リスクオフムードが強まったことで、日経平均株価は一時急落しました。その後、一転して日本維新の会との連立協議入り報道を受けて政局の不透明感が後退し、米SOX指数(フィラデルフィア半導体株指数)の上昇も追い風となり、相場は反発に転じました。
月後半には、米中貿易摩擦の再燃や米地銀の信用不安が断続的な重荷となり、短期的な過熱感から一時的な調整局面もみられたものの、20日に自民党と日本維新の会が正式に連立合意に至り、高市新政権の誕生を受けて政策期待が一段と高まったことから市場は再び上昇基調となりました。
月末にかけては、FOMC(米連邦公開市場委員会)で予想通り0.25%の利下げを決定した一方、FRB(米連邦準備制度理事会)議長の発言を受けて12月の追加利下げ観測は後退しました。また、日銀の金融政策決定会合では利上げが見送られ、追加利上げに慎重な姿勢が示されたことで円安基調が継続しました。さらに、米中協議の進展や中国によるレアアース輸出規制延期が好感され、リスク選好姿勢が一段と強まりました。こうした環境下で、アドバンテストの好決算やレーザーテックの大幅株高など、AI(人工知能)・半導体関連株が連日上昇し、日経平均株価も連日で史上最高値を更新しました。結果として、指数間の上昇率の差が広がりながらも、日本株式市場は前月末比で大幅高の水準で10月の取引を終えました。
ファンドの運⽤状況
当月、当ファンドのパフォーマンスは、前⽉末⽐0.16%の上昇となり、参考指数であるTOPIX(配当込み)の同6.20%の上昇を6.04%下回りました。
当ファンドのパフォーマンスにプラスに寄与した企業は、三菱重工業、PILLAR、メックなどでした。⼀⽅、マイナスに影響した企業は、全国保証、SHOEI、京成電鉄などでした。
当ファンドでは、企業経営者が誠実であり、高い競争優位性を有する企業の中から、更なる成長余地のある潜在価値の高い企業に長期集中投資を行い、企業との対話を通じて価値の顕在化を図ることを基本戦略とします。
日本には、高い技術力・開発力を持ち、ニッチ市場でグローバルに高いシェアやブランド力を持つ企業が多く存在します。そうした企業の中には、基礎的な収益力が高く、中長期的な成長余地が大きいにも関わらず、「玉に瑕(きず)」があるために株式市場で実態価値を正当に評価されていない企業があります。
当ファンドでは、そのような企業の長期的なパートナー株主※として、良好な関係を築きながら粘り強く対話を行っています。企業の事業戦略や資本配分、IR体制などの改善を促すことで、企業の実態価値の顕在化に努め、株価上昇のカタリストの一つとなることを目指します。
当運用レポートでは、投資先企業に対する投資見解や対話の進捗などをご報告させていただきます。
当月は、当ファンドの投資先である「三菱重工業」に対する投資見解、対話内容をご説明します。
当ファンドは同社が掲げているエネルギーの供給と需要の両面のグリーン転換「エナジートランジション」戦略に注目し、投資を行っています。当月は、2025年4月に就任された伊藤新CEOが掲げる経営方針と、事業ポートフォリオ改革の進展について、ご説明させていただきます。
同社は「リアリティのあるトランジション」を重視し、エネルギーの供給と需要の両面のグリーン転換を成長の柱に掲げています。同社は2024年5月に、2024年度から2026年度までの3か年を対象期間とする2024事業計画(24事計)を発表しました。24事計のテーマは①伸長事業の着実な遂行、②成長領域の事業化推進、③事業競争力の強化の3つに集約されます。この3か年で成長を牽引する伸長事業は、ガスタービンと原子力のエネルギー関連製品と防衛事業です。特に、伸長事業は2024年度末時点で、7.5兆円と巨額の受注残を抱えており、24事計期間中の業績成長を牽引するドライバーとして、株式市場からも高い評価を受けていると考えています。
伊藤新CEOは、「全体最適」と「領域拡大」に取組み、グループシナジーを創出する「Innovative Total Optimization(ITO)」という画期的な経営モデルを提唱しました。事業間の連携を通じた効率化の追求によって、事業利益率の更なる改善余地があることや、需給のひっ迫が目立つガスタービンに関して、技術ライセンス供与によるスケール拡大の可能性が示唆されたことなど、革新的な経営方針を掲げる新経営陣のチャレンジ精神が感じられ、ポジティブな印象です。
当ファンドでは、投資開始時から一貫して、三菱重工業は、今後益々増えるグローバルのエネルギー需要と脱炭素目標の両立や、世界的な安全保障強化の潮流において、中心的な役割を担う成長企業であると考えています。他方で、世界トップシェアを誇るエネルギー・インフラ領域に経営資源を集中すべく、競争力やシナジーの乏しい製品について、事業ポートフォリオの見直しが急務であると対話を行ってまいりました。その中でも、フォークリフトなど物流機器を手掛ける上場子会社である三菱ロジスネクストは、事業規模の大きさや親子上場というガバナンス面の課題があることから、特に注目をしてきました。
三菱ロジスネクストは、2023年度に過去最高の当期純利益を達成して以降、主要市場の米州での需要減や競争環境の悪化に伴い、関税等のコストアップの価格転嫁が進まないなど、苦しい事業環境にありました。2024年12月に事業売却の観測報道が出た後、2025年9月末には持分の譲渡を進めることが正式に発表されました。同社は事業売却に伴う損失を計上したことで、当期利益の下方修正も発表しました。当ファンドでは、24事計における事業競争力の強化に沿った経営判断であり、今後は事業利益率改善を通じたROE(株主資本利益率)の向上も見込まれることから、高く評価すべき動きだと考えています。
当ファンドは長期的なパートナー株主として、さらなる事業ポートフォリオの見直しを中心に、今後の進捗を見守っていく方針です。
今後の運⽤⽅針
当ファンドでは潜在価値の高い企業に選別して集中投資を行い、長期的なリターンを追求しています。潜在価値の高い企業とは、スパークスの投資アプローチである3つの着眼点(経営者の質・企業収益の質・市場の成長性)に照らし、企業の実態価値や成長性が株式市場で十分に評価されていないと考えられる企業を指します。
日本には強固な事業基盤を有していながら、事業戦略や資本配分、株式市場への向き合い方に改善余地があることから株価が実態価値よりも低く評価されている企業が数多く存在します。当ファンドはパートナー株主として、投資先企業との中長期的な関係構築と丁寧な対話に努め、課題の改善を促すことで、企業価値の顕在化を積極的に後押しします。
※当ファンドは企業オーナーとして短期業績や株価変動に惑わされない⻑期保有を前提としています。投資先企業と共に企業価値向上を⽬指すとの考えから、短期的に株式を売買する投資家と区別する為、「パートナー株主」との文言を使⽤しています。
2025年9月の運用コメント
株式市場の状況
2025年9月、日本株式市場の代表的な指数であるTOPIX(配当込み)は前月末比2.98%上昇、日経平均株価は同5.18%上昇いたしました。
月前半は、Alibaba Group Holding社(中国)による新AI(人工知能)チップ発表をきっかけに米中の技術競争激化が意識され、米国のAI関連株が軟調となり、日本株式市場でもハイテク株中心に下落いたしました。その後、トランプ米大統領が日米間の自動車関税引き下げを盛り込んだ大統領令に署名したことが安心感につながり、相場は持ち直しました。
月半ばにかけては、米国雇用統計が市場予想を下回り、FRB(米連邦準備制度理事会)の利下げ観測が高まったことや、石破茂首相の辞任表明を受けて次期政権への政策期待から日本株式市場は上昇しました。米国株式市場では半導体やAI関連銘柄が市場を牽引し、日本株式市場でも関連株の物色が広がったほか、その他幅広い銘柄に買いが波及しました。日経平均株価やTOPIXは高値更新を続け、相場上昇のモメンタムが継続しました。
月後半は、FOMC(米連邦公開市場委員会)で利下げ再開の決定と年内の継続的な利下げ見通しが示されました。翌日の日銀金融政策決定会合では、政策金利は据え置かれたものの2名の審議委員が利上げを提案し10月の利上げ確率が上昇した他、保有するETF(上場投資信託)の売却を決定したことで指数が一時急落しましたが、売りが一服すると下げ幅を縮め、相場は底堅さを維持しました。
月末にかけては、米国経済指標が堅調だったことから米国の積極的な利下げ期待が後退し、米国株が反落した流れが波及した他、自民党総裁選を控えていることなども重なって日本株式市場は軟調に推移しましたが、月全体としては前月末対比大幅高の水準で当月の取引を終えました。
ファンドの運⽤状況
当月、当ファンドのパフォーマンスは、前⽉末⽐1.26%の上昇となり、参考指数であるTOPIX(配当込み)の同2.98%の上昇を1.72%下回りました。
当ファンドのパフォーマンスにプラスに寄与した企業は、メック、パイロットコーポレーション、ワコムなどでした。⼀⽅、マイナスに影響した企業は、リクルートホールディングス、サイゼリヤ、SHOEIなどでした。
当ファンドでは、企業経営者が誠実であり、高い競争優位性を有する企業の中から、更なる成長余地のある潜在価値の高い企業に長期集中投資を行い、企業との対話を通じて価値の顕在化を図ることを基本戦略とします。
日本には、高い技術力・開発力を持ち、ニッチ市場でグローバルに高いシェアやブランド力を持つ企業が多く存在します。そうした企業の中には、基礎的な収益力が高く、中長期的な成長余地が大きいにも関わらず、「玉に瑕(きず)」があるために株式市場で実態価値を正当に評価されていない企業があります。
当ファンドでは、そのような企業の長期的なパートナー株主※として、良好な関係を築きながら粘り強く対話を行っています。企業の事業戦略や資本配分、IR体制などの改善を促すことで、企業の実態価値の顕在化に努め、株価上昇のカタリストの一つとなることを目指します。
当運用レポートでは、投資先企業に対する投資見解や対話の進捗などをご報告させていただきます。
当月は、当ファンドの投資先である「住友林業」に対する投資見解、対話内容をご説明します。
住友林業は1691年、別子銅山(愛媛県新居浜市)の備林経営に端を発し、1955年に住友林業として設立されました。木材商社として事業を拡大し、その後戸建住宅事業へ参入。以降は森林経営から木材・建材流通、住宅建築、不動産事業まで幅広く事業領域を広げ、木の価値を軸にした総合的な住生活企業へと成長してきました。特に直近10年程は、成長余地の大きい米国住宅事業に注力しており、現地の有力住宅会社を相次いで買収することで市場シェアを拡大しています。その結果、現在では売上・利益の過半を米国事業が占めるに至っています。米国では人口増加を背景に住宅需要が底堅い一方、建築人員不足や施工の複雑化が課題となっており、さらに移民規制強化により建設労働者不足は一層深刻化する可能性があります。この環境下で、住友林業が進める工場での住宅部材生産・加工による「プレハブ工法」は、現場での作業削減や工期短縮、品質安定化を実現する有効な手段となり、同社の競争優位性を高めると期待しています。
しかしながら、同社は米国大手住宅メーカー等と比較して株式市場において割安に評価されてきました。その背景として、①事業ポートフォリオの過度な多角化、②資本配分に関する明確な方針の欠如、という二つの要因が挙げられます。①については、ゴルフ場や高齢者施設の運営といった木材加工技術とのシナジーが低い事業を有しており、収益性は低迷しています。また、バイオマス発電事業も採算性に課題があり、これらの事業が全体の資本収益性を下押しする要因となっています。②については、シナジーの低い持分法適用会社である熊谷組の株式などを含む金融資産を約1,200億円保有しており、資本効率の改善余地が大きいと考えられます。
当ファンドでは、事業ポートフォリオの改革と資本配分の適正化が進展すれば、ROE(株主資本利益率)は同社の中期経営計画目標である15%を超えることが可能と考えており、これらの課題について同社と議論を続けて参ります。米国事業の成長性や「プレハブ工法」による同社の競争優位性の高まりを踏まえれば、企業価値向上のポテンシャルは十分に存在します。当ファンドはパートナー株主として、経営陣との建設的な対話を継続し、企業価値最大化に向けた取り組みを後押ししてまいります。
今後の運⽤⽅針
当ファンドでは潜在価値の高い企業に選別して集中投資を行い、長期的なリターンを追求しています。潜在価値の高い企業とは、スパークスの投資アプローチである3つの着眼点(経営者の質・企業収益の質・市場の成長性)に照らし、企業の実態価値や成長性が株式市場で十分に評価されていないと考えられる企業を指します。
日本には強固な事業基盤を有していながら、事業戦略や資本配分、株式市場への向き合い方に改善余地があることから株価が実態価値よりも低く評価されている企業が数多く存在します。当ファンドはパートナー株主として、投資先企業との中長期的な関係構築と丁寧な対話に努め、課題の改善を促すことで、企業価値の顕在化を積極的に後押しします。
※当ファンドは企業オーナーとして短期業績や株価変動に惑わされない⻑期保有を前提としています。投資先企業と共に企業価値向上を⽬指すとの考えから、短期的に株式を売買する投資家と区別する為、「パートナー株主」との文言を使⽤しています。
2025年8月の運用コメント
株式市場の状況
2025年8月、日本株式市場の代表的な指数であるTOPIX(配当込み)は前月末比で4.52%上昇、日経平均株価も同4.01%の上昇となりました。
月前半は、米国の雇用統計で非農業部門雇用者数が市場予想を下回り、労働市場の軟化が意識されたことで米国株が急落しました。その影響を受けて日経平均株価も急落し、一時4万円を割り込む場面もありましたが、雇用統計の弱さが米国利下げ期待を高め、世界的な株高を誘発しました。加えて、国内では主要企業の好決算により企業業績の底堅さが再認識され、日本株式市場は一段と騰勢を強める展開となりました。こうした強い上昇基調のなか、月半ばにはトランプ米大統領が対中相互関税の一部を再び90日間延期すると発表し、投資家心理に安心感を与えたことから株式市場は続伸し、日経平均株価は連日史上最高値を更新しました。
その後、月後半にかけてはジャクソンホール会議を控え様子見ムードが広がり、利益確定売りも重なって調整色が優勢となりました。ジャクソンホール会議では、米連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長の講演が9月の利下げ観測を一段と強めるものとなったほか、米国のNVIDIA社が中国向け輸出に関する不安を残しつつも堅調な決算を発表したことも市場を支え、米国株式市場は堅調に推移し、日本株式市場も底堅い動きを見せ、前月末比で大幅高となって当月を終えました。
ファンドの運⽤状況
当月、当ファンドのパフォーマンスは、前⽉末⽐6.45%の上昇となり、参考指数であるTOPIX(配当込み)の同4.52%の上昇を1.93%上回りました。
当ファンドのパフォーマンスにプラスに寄与した企業は、横浜ゴム、ダイフク、全国保証などでした。⼀⽅、マイナスに影響した企業は、リクルートホールディングス、美津濃、ルネサスエレクトロニクスなどでした。
当ファンドでは、企業経営者が誠実であり、高い競争優位性を有する企業の中から、更なる成長余地のある潜在価値の高い企業に長期集中投資を行い、企業との対話を通じて価値の顕在化を図ることを基本戦略とします。
日本には、高い技術力・開発力を持ち、ニッチ市場でグローバルに高いシェアやブランド力を持つ企業が多く存在します。そうした企業の中には、基礎的な収益力が高く、中長期的な成長余地が大きいにも関わらず、「玉に瑕(きず)」があるために株式市場で実態価値を正当に評価されていない企業があります。
当ファンドでは、そのような企業の長期的なパートナー株主※として、良好な関係を築きながら粘り強く対話を行っています。企業の事業戦略や資本配分、IR体制などの改善を促すことで、企業の実態価値の顕在化に努め、株価上昇のカタリストの一つとなることを目指します。
当運用レポートでは、投資先企業に対する投資見解や対話の進捗などをご報告させていただきます。
当月は、当ファンドの投資先である「横浜ゴム」に対する投資見解、対話内容をご説明します。
横浜ゴムは1917年に横浜で創業したタイヤメーカーです。スノータイヤやオールシーズンタイヤなど数々の日本初となる画期的な製品を発売し、1990年以降は生産・販売網の海外展開を進めることで、グローバルに成長を続けてきました。
タイヤ業界は、労働集約型かつ装置産業であることから、規模が競争力に直結する産業です。2010年以降、低コスト・低価格を武器とした新興国のタイヤメーカーが生産能力を拡大しており、競争は年々激しくなっています。特に、中国タイヤメーカーの拡大は著しく、トラック・バス用タイヤについては、既に中国が世界の生産量の約半分を占めています。近い将来、乗用車用タイヤについても、中国メーカーの生産能力増強は続いており、業界全体に価格下落圧力をもたらすことが予想されています。一見すると、タイヤ市場は成熟化が進みつつあり、魅力的な業界ではないように見受けられます。
当ファンドが注目しているのは、独自の戦略によって、市場を上回る成長を追求する同社の攻めの経営姿勢です。消費財タイヤでは、高級車への装着実績をブランド力・性能の裏付けとして、価格を引き上げていくプレミアムタイヤ戦略を採用していますが、これは大手タイヤメーカー、いわゆるTier1/2メーカーに共通したトレンドです。同社はコーポレートブランドである“YOKOHAMA”ブランドに注力し、複数のブランドを展開する他社がアプローチしにくい、絶妙な価格帯でのプライシングを実践しています。また、グローバルの各地で地域に精通したプロフェッショナル経営人材を登用することで、地域ごとに異なるニーズを捉えた製品の投下を行ったことも乗用車用タイヤの高成長に繋がっていると考えられます。
同社はタイヤ市場の約2割を占める、農機・鉱山機械などに装着されるOff-Highway Tire(OHT)では、2016年から積極的なM&Aを推進することで、世界トッププレイヤーにまで昇り詰めました。OHT事業は消費財タイヤと比較して高い市場成長性が期待され、多品種・少量生産かつ複雑な製造工程を背景に、高い参入障壁を誇る魅力的なビジネスです。買収によって、安価なバリュー製品から新車に強いプレミアム製品まで幅広いラインナップが揃い、多様なニーズに対応できる体制が整いました。一方、OHTの需要は、コモディティ市況や景気変動の影響を受けやすく、下降局面では厳しい業績を強いられます。好況期にあった2022年12月期から一転し、農機新車の生産調整を背景に、2023年12月期からはOHT販売量は減少が続き、回復時期が見通しにくいことが、同社固有のリスクとなっていました。
当ファンドでは、OHT事業の高いポテンシャルに注目し、市場にもその価値が正しく認識されれば、PBR1.0倍を下回る株価の割安さは解消されると考え、OHTの事業戦略を中心に対話を継続してまいりました。当ファンドは、新車需要の下降局面という厳しい冬の時期にこそ、逆風をいかに乗り越え、景気サイクルごとに過去を上回る成長を実現するという、未来志向の展望を示すことが重要であるとの考えを共有してきました。同社は2024年12月期の決算説明会において、OHT市場の成長性を改めて発信するともに、利益体質の強靭化に向けて、補修用タイヤの強化と生産拠点の最適化などの具体施策を発表しました。
2025年12月期第2四半期決算において、通期計画の上方修正とOHT事業の販売量回復が好感され、同社の株価は大きく上昇しました。一時、2019年11月以来約6年ぶりに、同社のPBRは1.0倍を上回りました。積極的な成長投資と並行して、市場からの信認を得るべく、リターン創出に向けた施策の有言実行と、その説明に努めてきた真摯な経営姿勢が評価された成果だと考えております。
当ファンドはパートナー株主として、同社の企業価値の最大化の一助となれるよう、今後とも対話を続けていきたいと思います。
今後の運⽤⽅針
当ファンドでは潜在価値の高い企業に選別して集中投資を行い、長期的なリターンを追求しています。潜在価値の高い企業とは、スパークスの投資アプローチである3つの着眼点(経営者の質・企業収益の質・市場の成長性)に照らし、企業の実態価値や成長性が株式市場で十分に評価されていないと考えられる企業を指します。
日本には強固な事業基盤を有していながら、事業戦略や資本配分、株式市場への向き合い方に改善余地があることから株価が実態価値よりも低く評価されている企業が数多く存在します。当ファンドはパートナー株主として、投資先企業との中長期的な関係構築と丁寧な対話に努め、課題の改善を促すことで、企業価値の顕在化を積極的に後押しします。
※当ファンドは企業オーナーとして短期業績や株価変動に惑わされない⻑期保有を前提としています。投資先企業と共に企業価値向上を⽬指すとの考えから、短期的に株式を売買する投資家と区別する為、「パートナー株主」との文言を使⽤しています。
2025年7月の運用コメント
株式市場の状況
2025年7月、日本株式市場の代表的な指数であるTOPIX(配当込み)は前月末比3.17%上昇、日経平均株価も同1.44%の上昇となりました。
月前半の日本株式市場は、前月末の急騰を受けた利益確定売りが優勢となるなか、米国による相互関税の動向や参議院議員選挙で与党が苦戦するとの見通しなど、先行きへの不透明感が強まり、株価の動きは限定的となりました。また、米NVIDIAによる中国向けAI半導体の輸出再開報道や、米連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長解任を巡る話題など、強弱入り混じる材料が相次いだこともあり、株式市場は方向感に乏しく、もみ合いが続く展開となりました。
月後半に入ると、20日に実施された参議院議員選挙では、与党が非改選議席と合わせても過半数を獲得できなかったものの、市場では想定内の結果と受け止められたため、連休明けの22日の株式市場への影響は限定的に留まりました。翌23日には、日米通商交渉の合意が報じられたことで株価が一気に押し上げられ、24日のTOPIXは過去最高値を更新し、日経平均株価も急騰する展開となりました。その後は、急ピッチな株価上昇に対する過熱感から一時的な調整が入ったものの、月末には米ハイテク銘柄の好決算の影響などを受けて反発し、日本株式市場は前月末比で大幅高となって当月を終えました。
ファンドの運⽤状況
当月、当ファンドのパフォーマンスは、前⽉末⽐2.41%の上昇となり、参考指数であるTOPIX(配当込み)の同3.17%の上昇を0.76%下回りました。
当ファンドのパフォーマンスにプラスに寄与した企業は、横浜ゴム、パイロットコーポレーション、サイゼリヤなどでした。⼀⽅、マイナスに影響した企業は、京成電鉄、キーエンス、スクウェア・エニックス・ホールディングスなどでした。
当ファンドでは、企業経営者が誠実であり、高い競争優位性を有する企業の中から、更なる成長余地のある潜在価値の高い企業に長期集中投資を行い、企業との対話を通じて価値の顕在化を図ることを基本戦略とします。
日本には、高い技術力・開発力を持ち、ニッチ市場でグローバルに高いシェアやブランド力を持つ企業が多く存在します。そうした企業の中には、基礎的な収益力が高く、中長期的な成長余地が大きいにも関わらず、「玉に瑕(きず)」があるために株式市場で実態価値を正当に評価されていない企業があります。
当ファンドでは、そのような企業の長期的なパートナー株主※として、良好な関係を築きながら粘り強く対話を行っています。企業の事業戦略や資本配分、IR体制などの改善を促すことで、企業の実態価値の顕在化に努め、株価上昇のカタリストの一つとなることを目指します。
当運用レポートでは、投資先企業に対する投資見解や対話の進捗などをご報告させていただきます。
当月は、当ファンドの投資先である「全国保証」に対する投資見解、対話内容をご説明します。
全国保証は、国内唯一の独立系住宅ローン保証会社です。住宅ローン保証事業とは、住宅ローンの借入人から保証料をもらう代わりに、連帯保証人となる事業を言います。住宅ローンの借入人が返済を出来なくなった場合、保証会社である同社が金融機関に住宅ローンを弁済し、金融機関に代わって借入人から住宅ローンを回収する、もしくは住宅ローンの担保物件(住宅・土地等)を売却して弁済資金を回収する事業モデルです。住宅ローン保証は、通常、金融機関の子会社である保証会社が提供するのが一般的です。しかし同社は、金融機関に属さない国内唯一の独立系保証会社であり、全国の様々な金融機関の住宅ローン保証の引き受けが可能です。また、40年以上のローン審査のデータの蓄積から、延滞リスクの低い顧客に保証を行うため、代位弁済に関わるコストは限定的であり、営業利益率が7割を超える非常に収益性の高いビジネスとなっています。
同社は1981年に厚生年金転貸住宅融資の保証業務を担う目的で設立されましたが、業容転換のために1997年から民間金融機関向け住宅ローンの保証業務に参入します。当時、大手金融機関は子会社の保証会社を使っていたため、全国保証は、信金・信組など、中堅・中小金融機関への保証業務に注力し成長してきました。中堅・中小金融機関への保証業務の提供を通じて、同社は与信能力や審査時間の短縮化などサービス品質を磨き上げてきました。今日では、同社はその強みを活かし、メガバンクを含む多数の金融機関に住宅ローン保証を提供しています。
同社の保証残高は1998年の1兆円から2025年3月末には19.4兆円まで増加しています。民間住宅ローン残高に占める同社シェアも2025年3月末で9.5%まで上昇してきました。その背景には、同社のサービス品質の高さに加えて、銀行に対するリスク規制強化に伴い、住宅ローン保証リスクを銀行グループから隔離したいニーズの高まりがあります。
当ファンドでは、同社の業績拡大が持続すると考えています。上記理由から、銀行子会社によるローン保証から、独立系の同社へのシフトが続くことが想定されます。同社は現在、金融機関に対し、保証子会社の買収など、多様なスキームによる保証債務の引き受けを提案しており、今後も継続的に残高シェアを上げていくことができると思われます。
しかしながら、同社の株価は、企業の実態価値を反映できていないと思われます。課題は主に2点あり、①成長投資や株主還元といった資本政策に大きな改善余地があること、②事業の安全性に対する理解を株式市場から十分に得られていないこと、であると当ファンドでは考えています。これらの課題についてスパークスはこれまで青木社長と何度も面談を実施し、議論を重ねてきました。2023年3月に発表された新中期経営計画では、「住宅ローンプラットフォーマー」としてリスクを抑えながら更なる事業成長が可能なことや、成長投資・株主還元などに余剰資本を積極活用していく方針が示されました。2024年3月期の通期決算説明では、配当性向の引き上げに加え、同社初となる自社株買いの発表をしました。さらに2025年3月期の通期決算説明では、着実なM&A等のインオーガニック成長の積み上げにより増収増益を達成し、増配および前期に続く自社株買いを発表しました。同社の成長投資および株主還元への姿勢は、改善傾向にあります。
こうした一連の資本政策を進める一方で、同社は、金利上昇に伴う個人の返済額への影響について、株式市場に対し繰り返し丁寧に説明を行ってきました。今後、事業の安全性に対する市場の認知が徐々に広がっていくことが期待されます。
当ファンドでは引き続き、同社の企業価値が株式市場で顕在化する一助となれるよう、経営陣との対話を継続していく方針です。
今後の運⽤⽅針
当ファンドでは潜在価値の高い企業に選別して集中投資を行い、長期的なリターンを追求しています。潜在価値の高い企業とは、スパークスの投資アプローチである3つの着眼点(経営者の質・企業収益の質・市場の成長性)に照らし、企業の実態価値や成長性が株式市場で十分に評価されていないと考えられる企業を指します。
日本には強固な事業基盤を有していながら、事業戦略や資本配分、株式市場への向き合い方に改善余地があることから株価が実態価値よりも低く評価されている企業が数多く存在します。当ファンドはパートナー株主として、投資先企業との中長期的な関係構築と丁寧な対話に努め、課題の改善を促すことで、企業価値の顕在化を積極的に後押しします。
※当ファンドは企業オーナーとして短期業績や株価変動に惑わされない⻑期保有を前提としています。投資先企業と共に企業価値向上を⽬指すとの考えから、短期的に株式を売買する投資家と区別する為、「パートナー株主」との文言を使⽤しています。
2025年6月の運用コメント
株式市場の状況
2025年6月、日本株式市場の代表的な指数であるTOPIX(配当込み)が前月末比1.96%上昇、日経平均株価も同6.64%の上昇となりました。
全体としては、米国の関税政策や地政学的リスクの動向に市場が影響を受ける場面も見られたものの、外部環境の改善や米国金融緩和への期待を背景に、リスク選好姿勢が強まった月となりました。
月前半から月半ばにかけての日本株式市場は、米国の関税政策や景気減速への懸念から軟調に推移しましたが、堅調な米雇用統計や米半導体関連株の上昇を受け、市場は持ち直しました。しかし、イスラエルがイランを攻撃したとの報道によって中東情勢への懸念が高まり、一時的にリスク回避の動きが市場を下押ししました。一方で、日銀が政策金利据え置きと国債買い入れ減額ペースの緩和を示し、米連邦公開市場委員会(FOMC)でも政策金利が据え置かれたことが投資家心理を下支えし、外部要因に振らされながらも市場はもみ合いを続けつつ、徐々にレンジを切り上げる展開となりました。
月後半にかけては、中東情勢の激化や米国によるイラン核施設への空爆報道により、一時的にリスク回避ムードが広がりましたが、その後は地政学的な懸念が早期に沈静化したことや米国株式市場の反発を受けて、日本株式市場も上昇基調に転じました。さらに、トランプ米大統領の停戦に関する発言や米連邦準備制度理事会(FRB)高官による利下げ示唆が投資家心理を押し上げ、リスクオンムードが広がりました。値がさ半導体関連株が相場をけん引し、配当権利落ちに伴う再投資の需要も追い風となり、日経平均株価は年初来高値を更新しました。株式市場全体も前月末比で大幅に上昇して当月を終えました。
ファンドの運⽤状況
当月、当ファンドのパフォーマンスは、前⽉末⽐2.37%の上昇となり、参考指数であるTOPIX(配当込み)の同1.96%の上昇を0.41%上回りました。
当ファンドのパフォーマンスにプラスに寄与した企業は、横浜ゴム、スクウェア・エニックス・ホールディングス、三菱重工業などでした。⼀⽅、マイナスに影響した企業は、ホシザキ、キーエンス、山陰合同銀行などでした。
当ファンドでは、企業経営者が誠実であり、高い競争優位性を有する企業の中から、更なる成長余地のある潜在価値の高い企業に長期集中投資を行い、企業との対話を通じて価値の顕在化を図ることを基本戦略とします。
日本には、高い技術力・開発力を持ち、ニッチ市場でグローバルに高いシェアやブランド力を持つ企業が多く存在します。そうした企業の中には、基礎的な収益力が高く、中長期的な成長余地が大きいにも関わらず、「玉に瑕(きず)」があるために株式市場で実態価値を正当に評価されていない企業があります。
当ファンドでは、そのような企業の長期的なパートナー株主※として、良好な関係を築きながら粘り強く対話を行っています。企業の事業戦略や資本配分、IR体制などの改善を促すことで、企業の実態価値の顕在化に努め、株価上昇のカタリストの一つとなることを目指します。
当運用レポートでは、投資先企業に対する投資見解や対話の進捗などをご報告させていただきます。
当月は、当ファンドの投資先である「山陰合同銀行」に対する投資見解、対話内容をご説明します。
山陰合同銀行は、島根県と鳥取県を基盤とする地方銀行です。同行は、松江銀行と米子銀行が合併する形で1941年に設立されました。マザーマーケットである山陰両県においては、約50%と圧倒的な預貸金のシェアを有しています。一方で、山陰両県は同行が「課題先進地域」と呼ぶように、公共事業への産業依存度が高く、全国でも人口減少と高齢化が進んでいるなど、同行を取り巻く環境は厳しいものでした。事実、本業の稼ぐ力の指標である顧客向けサービス業務利益は、2020年度までの11年間赤字が続いており、長らく有価証券運用によって収益をカバーしている状況にありました。持続可能な金融サービスの提供を実現すべく、県外に成長の活路を見出した同行は、山陽・関西地区を中心に2012年から法人営業に特化した支店の出店を積極化させてきました。
地方銀行業界は、一般的にその地に根差した銀行が大きなシェアを握っており、他地域からの市場参入が難しいビジネスと考えられます。同行は逆風下にある地元市場において、主体的に資金需要を掘り起こすべく、金融仲介機能だけではない、経営密着型のコンサルティングモデルの強化や、人材の教育・再配置などの構造改革を推進してきました。地元で培った経営支援のノウハウを武器に県外進出に成功し、2021年度からは貸出金平残の半分以上を山陰両県以外の地域が占めるまでに拡大させています。
また、預貸利ざやの拡大が見込まれない低金利環境下において、非金利収益の拡大を目指し、2015年には100%出資の証券子会社を設立しました。2019年には野村證券との包括的業務提携を行い、証券子会社は解散となりましたが、単なるコスト体質の改善に留まることなく、顧客対応に特化する体制が整ったことで、提携スタート時から預かり資産残高・関連利益を順調に増加させています。また同行は、リスキリング(職業能力の再開発・再教育)を通じて窓口・事務部門の人員の配置転換を進め、戦略部門である法人営業や預かり資産ビジネスを強化するなど、環境変化に素早く対応することで、全国の地銀と比較して非常に高い経費効率を達成している点が大きな特徴です。
当ファンドでは、県外進出をドライバーとした貸出金残高の力強い伸びと生産性の高さを背景に、高い利益成長とROE(株主資本利益率)改善を実現するポテンシャルに注目しています。銀行セクター全体が円金利上昇による利ざや拡大の恩恵を受けると想定されますが、利ざやを左右する日本銀行の到達金利という外部要因を正確に予測することは難しいと考えております。直近の日本銀行は、2025年4月に発表された米国関税政策や中東情勢に伴うエネルギー価格変動の景気影響を勘案し、様子見姿勢を維持するなど、金融政策運営の不確実性は高まっております。同行は県外進出の加速によって、総貸出金平残を2023年度の4.4兆円から、2026年度には約5.5兆円まで拡大させるという力強い中期経営計画を掲げており、残高の積み上げに伴う貸出金利息の増加という独自要因を備えている点が魅力です。
しかしながら、全国の地銀平均を上回る貸出残高の成長実績に対して、同行のPER(株価収益率)は時価総額1,500億円以上の規模の地方銀行の平均程度に留まっています。当ファンドでは、期初計画を上回る与信費用の計上が続いており、株式市場から貸出資産の質を懸念されていることが要因だと考えております。
当ファンドでは、不良債権比率は低位で維持されており、県外での正常先割合は改善傾向にあることから、同行の資産の健全性に強い懸念は抱いておりません。一方で、同行が積極的な県外進出という戦略を採っていることから、成長とリスクマネジメントの両立に向けた明確なメッセージを発信することが重要と考え、対話を行っております。中期経営計画最終年度である2026年度の目標を着実に達成し、その後も持続的な利益成長とROEの改善が可能であると株式市場の信認を得られれば、野心的に資金利益成長を志向する経営戦略に対して、再評価の余地が大きいと考えています。当ファンドはパートナー株主として、同社の本源的な企業価値の向上・顕在化に向けた対話を続けてまいります。
今後の運⽤⽅針
当ファンドでは潜在価値の高い企業に選別して集中投資を行い、長期的なリターンを追求しています。潜在価値の高い企業とは、スパークスの投資アプローチである3つの着眼点(経営者の質・企業収益の質・市場の成長性)に照らし、企業の実態価値や成長性が株式市場で十分に評価されていないと考えられる企業を指します。
日本には強固な事業基盤を有していながら、事業戦略や資本配分、株式市場への向き合い方に改善余地があることから株価が実態価値よりも低く評価されている企業が数多く存在します。当ファンドはパートナー株主として、投資先企業との中長期的な関係構築と丁寧な対話に努め、課題の改善を促すことで、企業価値の顕在化を積極的に後押しします。
※当ファンドは企業オーナーとして短期業績や株価変動に惑わされない⻑期保有を前提としています。投資先企業と共に企業価値向上を⽬指すとの考えから、短期的に株式を売買する投資家と区別する為、「パートナー株主」との文言を使⽤しています。
2025年5月の運用コメント
株式市場の状況
2025年5月、日本株式市場の代表指数であるTOPIX(配当込み)が前月末比5.10%の上昇、日経平均株価も同5.33%の上昇となりました。当月の日本株式市場は、月前半に大幅上昇した後、月半ばに調整を挟みつつも月後半にかけて持ち直し、レンジ内での回復基調を維持したまま当月を終えました。
月前半は、前月末から続く米国の関税交渉進展への期待が支援材料となったことや、日銀が展望リポートで実質GDP成長率と物価上昇率の見通しを下方修正し追加利上げに慎重な姿勢を示したことや進行した円安も相まって、株式市場は堅調に推移しました。こうした中、米英貿易協定の合意や米中双方による市場の想定以上の関税率の引き下げを受け、指数は大幅に上昇しました。月半ばには好材料が一巡したことに加え、円高・ドル安の進行や、米国債格下げをきっかけに米国の財政悪化懸念が高まったことも相場の重荷となりました。月後半にかけては、米国による対EU追加関税の延期や、日本国内での超長期国債発行計画の見直し観測による円安の進行等により主力株を中心に買いが入り、日本株式市場は再び上昇に転じました。さらに、28日に米国際貿易裁判所がトランプ政権の関税政策を違法と判断し関税の差し止めを命じたことを受けて円安が加速し、株式市場も大幅高となりました。しかしその後、米連邦巡回区控訴裁判所が関税差し止めの執行を一時的に停止する判断を下したことでドル円相場とともに株式市場は反落しました。
結果として、米国の関税政策をめぐる不透明感に振り回されながらも、日本株式市場は前月末比で上昇して取引を終えました。
ファンドの運⽤状況
当月、当ファンドのパフォーマンスは、前⽉末⽐3.93%の上昇となり、参考指数であるTOPIX(配当込み)の同5.10%の上昇を1.17%下回りました。
当ファンドのパフォーマンスにプラスに寄与した企業は、横浜ゴム、三菱重工業、全国保証などでした。⼀⽅、マイナスに影響した企業は、ホシザキ、森永製菓、京成電鉄などでした。
当ファンドでは、企業経営者が誠実であり、高い競争優位性を有する企業の中から、更なる成長余地のある潜在価値の高い企業に長期集中投資を行い、企業との対話を通じて価値の顕在化を図ることを基本戦略とします。
日本には、高い技術力・開発力を持ち、ニッチ市場でグローバルに高いシェアやブランド力を持つ企業が多く存在します。そうした企業の中には、基礎的な収益力が高く、中長期的な成長余地が大きいにも関わらず、「玉に瑕(きず)」があるために株式市場で実態価値を正当に評価されていない企業があります。
当ファンドでは、そのような企業の長期的なパートナー株主※として、良好な関係を築きながら粘り強く対話を行っています。企業の事業戦略や資本配分、IR体制などの改善を促すことで、企業の実態価値の顕在化に努め、株価上昇のカタリストの一つとなることを目指します。
当運用レポートでは、投資先企業に対する投資見解や対話の進捗などをご報告させていただきます。
当月は、当ファンドの投資先である「スクウェア・エニックス・ホールディングス」に対する投資見解、対話内容をご説明します。
スクウェア・エニックス・ホールディングスは、ゲームソフトを展開するスクウェアとエニックスの二社が合併して2003年に設立されました。2005年にはゲームセンター運営のタイトーを子会社化するなど、ゲームを中心としたコンテンツ企業として成長してきました。
当ファンドが注目しているポイントは、1.マルチプラットフォーム戦略による収益機会の多角化、2.適切な開発費コントロール、3.高いフリー・キャッシュ・フロー(FCF)創出能力の三点です。
- 同社が掲げるマルチプラットフォーム戦略とは、ソニー、任天堂、PCなどゲームを動かす機器メーカーを限定せず、幅広いプラットフォームでユーザーが遊べる環境を提供することを指します。1980年代から1990年代初頭の日本では任天堂の「ファミコン」や「スーパーファミコン」が全盛期でしたが、1990年代半ばにソニーが「PlayStation(プレイステーション)」を開発しゲーム業界に参入しました。当時、旧スクウェアは看板タイトルである『ファイナルファンタジー』をプレイステーション向けに展開することを決め、任天堂の「NINTENDO64」向けには展開しませんでした。プレイステーションに偏った戦略の名残は2020年代にも見られ、ファイナルファンタジーシリーズは新ハード発売時にプレイステーション専売とされる慣習が続いていました。
ファイナルファンタジーシリーズに限らず、同社タイトルは開発費が高額であり、販売本数が伸びなければ利益に貢献しない事もあります。直近数年間では2023年発売の『ファイナルファンタジー16』を代表として、複数のタイトルで会社想定を下回ったと考えています。
しかし近年、同社の戦略は変化しつつあります。過去のファイナルファンタジーシリーズの一部を任天堂の「Switch2」やPC向けに展開し、販路を拡大することでコンテンツごとの収益力向上を目指しています。 - 同社はゲーム開発費の適正化にも取り組んでいます。当ファンドでは、同社のコンテンツ当たりの開発費が相対的に高い理由を、外注費の高さや予算管理の不十分さ、職人気質によるこだわりの強さにあると推察しています。同社の作品はグローバルで高く評価されており、その映像美や緻密なストーリーによりコアファンを獲得していますが、開発および運用面で過剰な費用投下も見られます。経営陣はこれを課題と認識し、既に開発タイトルの経費管理を強化しています。コアタイトルの開発費は抑制せず、新規タイトルやモバイルゲームの運用体制の適正化を図っています。ゲームの開発期間は一般的に3〜5年かかるため、現在市場に出ている製品には過去の高コストが反映されていますが、今後発売されるタイトルは収益性の高いものが増えると期待しています。
- ゲームソフト以外の事業として、PCユーザーを主な対象としたMMO(多人数同時参加型オンラインゲーム)事業や出版、グッズなどの収益性が高く、安定的で大規模な設備投資を必要としないキャッシュ創出力の高いビジネスを有しています。ゲーム事業の収益力改善により、同社全体の業績安定性と利益水準の向上が見込まれます。
同社は約2,478億円の現預金を保有(2025年3月末時点)しており、今後の構造改革に伴い、この金額規模はさらに増加すると試算しています。当ファンドは、適切なキャッシュアロケーションが行われないことによる株主利益の毀損の可能性を懸念しており、株主還元策やM&Aを含め、企業価値向上につながる資本政策の実現に向けて根気強く対話を続けてまいります。
今後の運⽤⽅針
当ファンドでは潜在価値の高い企業に選別して集中投資を行い、長期的なリターンを追求しています。潜在価値の高い企業とは、スパークスの投資アプローチである3つの着眼点(経営者の質・企業収益の質・市場の成長性)に照らし、企業の実態価値や成長性が株式市場で十分に評価されていないと考えられる企業を指します。
日本には強固な事業基盤を有していながら、事業戦略や資本配分、株式市場への向き合い方に改善余地があることから株価が実態価値よりも低く評価されている企業が数多く存在します。当ファンドはパートナー株主として、投資先企業との中長期的な関係構築と丁寧な対話に努め、課題の改善を促すことで、企業価値の顕在化を積極的に後押しします。
※当ファンドは企業オーナーとして短期業績や株価変動に惑わされない⻑期保有を前提としています。投資先企業と共に企業価値向上を⽬指すとの考えから、短期的に株式を売買する投資家と区別する為、「パートナー株主」との文言を使⽤しています。
2025年4月の運用コメント
株式市場の状況
2025年4月、日本株式市場の代表指数であるTOPIX(配当込み)は前月末比0.33%の上昇、日経平均株価は同1.20%の上昇となりました。当月の日本株式市場は、米国の通商・金融政策を巡る不透明感に大きく揺さぶられる展開となりました。
月前半には、米国においてスタグフレーション(景気の後退と物価の上昇が同時進行する経済状況)の懸念が強まる中、トランプ政権が全世界を対象とした最大50%の「相互関税」を発表し、中国やEUが即座に報復措置を講じたことで、世界的にリスク回避の動きが広がりました。これを受けて、日本株式市場は大幅な下落となり、先物市場では「サーキットブレーカー」が発動されるなど、市場の混乱が際立ちました。その後、9日に米政府が一部関税の90日間一時停止を発表すると、過度な悲観ムードが和らぎ、市場は急反発しました。ただし、翌10日には米国が対中関税を累計145%まで引き上げる方針を明らかにしたことで、市場は再び警戒感を強めました。加えて、トランプ米大統領が米連邦準備制度理事会(FRB)に利下げを要求し、パウエル議長の解任懸念が浮上したことにより、FRBの独立性に対する不信感が高まりました。この影響で、米国市場では株式・債券・ドルがそろって下落する「トリプル安」となり、日本株式市場でも上値の重い展開が続きました。
一方、22日にはベッセント米財務長官が「関税は持続不可能」との見解を示したほか、23日にはトランプ米大統領がパウエル議長の解任を否定したとの報道が伝わったことで、市場には安堵感が広がり、日本株式市場も上昇に転じました。さらに、対中国の関税率を見直す旨の報道も好感され、米中対立の緩和への期待からリスクオン姿勢が続き、日本株式市場は前月末比で上昇して当月の取引を終えました。
ファンドの運⽤状況
当月、当ファンドのパフォーマンスは、前⽉末⽐0.89%の上昇となり、参考指数であるTOPIX(配当込み)の同0.33%の上昇を0.56%上回りました。
当ファンドのパフォーマンスにプラスに寄与した企業は、三菱重工業、全国保証、スクウェア・エニックス・ホールディングスなどでした。⼀⽅、マイナスに影響した企業は、横浜ゴム、コニカミノルタ、ルネサスエレクトロニクスなどでした。
当ファンドでは、企業経営者が誠実であり、高い競争優位性を有する企業の中から、更なる成長余地のある潜在価値の高い企業に長期集中投資を行い、企業との対話を通じて価値の顕在化を図ることを基本戦略とします。
日本には、高い技術力・開発力を持ち、ニッチ市場でグローバルに高いシェアやブランド力を持つ企業が多く存在します。そうした企業の中には、基礎的な収益力が高く、中長期的な成長余地が大きいにも関わらず、「玉に瑕(きず)」があるために株式市場で実態価値を正当に評価されていない企業があります。
当ファンドでは、そのような企業の長期的なパートナー株主※として、良好な関係を築きながら粘り強く対話を行っています。企業の事業戦略や資本配分、IR体制などの改善を促すことで、企業の実態価値の顕在化に努め、株価上昇のカタリストの一つとなることを目指します。
当運用レポートでは、投資先企業に対する投資見解や対話の進捗などをご報告させていただきます。
当月は、当ファンドの投資先である「森永製菓」に対する投資見解、対話内容をご説明します。
森永製菓は1899年創業の大手菓子メーカーです。米国で菓子製造技術を学んだ創業者森永太一郎氏が、「日本の人々にもおいしく栄養価の高い西洋菓子を食べてもらいたい」という想いをもって日本の菓子産業の礎を築いたのが同社の始まりです。今では菓子だけでなく、アイス、「inゼリー」に代表されるゼリー飲料、通販など、製品・事業の幅を広げ、海外にも積極的に展開しています。
当ファンドが注目しているのは、MORINAGAブランドの海外での成長です。米国では「HI-CHEW(ハイチュウ)」が、メジャーリーガーの間でブームとなったことをきっかけに評判となり、これまで成長を続けてきました。足元では、米国内の景気減速によりハイチュウのメインチャネルであるコンビニでの販売が苦戦しています。一方で、取扱SKU(在庫管理の最小管理単位)拡大や新たな販売チャネルへの取り組みは着実に進展しています。米国では第2工場が2027年1月に稼働を予定しており、安定的な供給体制が整うことで、催事などの大きな販売戦略が可能となり、更なる成長が期待できると考えています。
課題である国内菓子事業の収益性は、原材料価格高騰、円安の影響で改善しているとは言えない状況です(2025年3月期第3四半期の営業利益率は5.3%(前期比1.0pt減少))。外部環境としては、2023年3月期以降、毎期50億円から80億円程度の原材料費等の高騰の影響(為替含む)で厳しい状況が継続しています。そのような環境において、同社は複数回の価格改定を実施しながらも、販売数量を伴った売上高の拡大を実現してきています。同時にハイチュウを中心としたカテゴリーミックスの改善やコスト低減などの収益性改善の取組は着実に実行されており、現状、業績としては表れていないものの、同社の収益体質は改善し始めていると考えております。また、中期経営計画では、選択と集中による事業の生産性向上に努めるため、「段階的なアセットライト」を進め、同社の基盤事業として持続的成長および投下資本収益性(ROIC)向上を目指すことが謳われています。次回の決算説明会では、中期経営計画発表から一年を経て、ROIC向上に向けてもう一段踏み込んだ経営陣の考えや説明に期待しています。当ファンドでは、同社との対話が進展し始めていると評価していますが、売上高の大きい国内菓子事業の収益性改善は同社の企業価値向上に不可欠となるため、構造改革の進捗を見守りながら今後も対話を続けてまいります。
今後の運⽤⽅針
当ファンドでは潜在価値の高い企業に選別して集中投資を行い、長期的なリターンを追求しています。潜在価値の高い企業とは、スパークスの投資アプローチである3つの着眼点(経営者の質・企業収益の質・市場の成長性)に照らし、企業の実態価値や成長性が株式市場で十分に評価されていないと考えられる企業を指します。
日本には強固な事業基盤を有していながら、事業戦略や資本配分、株式市場への向き合い方に改善余地があることから株価が実態価値よりも低く評価されている企業が数多く存在します。当ファンドはパートナー株主として、投資先企業との中長期的な関係構築と丁寧な対話に努め、課題の改善を促すことで、企業価値の顕在化を積極的に後押しします。
※当ファンドは企業オーナーとして短期業績や株価変動に惑わされない⻑期保有を前提としています。投資先企業と共に企業価値向上を⽬指すとの考えから、短期的に株式を売買する投資家と区別する為、「パートナー株主」との文言を使⽤しています。
2025年3月の運用コメント
株式市場の状況
2025年3月、日本株式市場の代表指数であるTOPIX(配当込み)は前月末比0.22%の上昇、日経平均株価は同4.14%の下落となりました。当月の日本株式市場は、米国の関税政策に対する不安や地政学的リスクの影響を受けて投資家心理が動揺し、荒い値動きが続きました。
月前半にはトランプ米大統領の相次ぐ関税発動によって世界的な景気減速懸念が台頭し、景気敏感株を中心に日本株式市場は大きく下落しました。
月半ばには植田日銀総裁の利上げ継続を示唆する発言、フィラデルフィア半導体株指数(SOX指数)の大幅上昇、ウクライナ情勢を巡る地政学的リスクの後退などに加え、ウォーレン・バフェット氏が率いる米国Berkshire Hathaway社による日本の商社株の保有増が好感されてバリュー株を中心に買いが集まり、日経平均株価が弱含むのに対してTOPIXは底堅く推移し、日経平均株価をTOPIXで除したNT倍率は5年ぶりの低水準となりました。
月後半に入ると、トランプ米大統領が輸入車に対して一律25%の関税を課すと発表したことで自動車株や半導体株が大きく売られ、リスク回避ムードが強まりました。さらに、米国で物価上昇と景気停滞が同時に起きる「スタグフレーション」への懸念が一層強まり主要株価指数が大きく下落したことを受け、日本株式市場もほぼ全面安となり、日経平均株価は約7か月半ぶりの安値で当月の取引を終えました。
ファンドの運⽤状況
当月、当ファンドのパフォーマンスは、前⽉末⽐0.22%の上昇となり、参考指数であるTOPIX(配当込み)の同0.22%の上昇と概ね同水準となりました。
当ファンドのパフォーマンスにプラスに寄与した企業は、三菱重工業、全国保証、森永製菓などでした。⼀⽅、マイナスに影響した企業は、ルネサスエレクトロニクス、日産自動車、リクルートホールディングスなどでした。
当ファンドでは、企業経営者が誠実であり、高い競争優位性を有する企業の中から、更なる成長余地のある潜在価値の高い企業に長期集中投資を行い、企業との対話を通じて価値の顕在化を図ることを基本戦略とします。
日本には、高い技術力・開発力を持ち、ニッチ市場でグローバルに高いシェアやブランド力を持つ企業が多く存在します。そうした企業の中には、基礎的な収益力が高く、中長期的な成長余地が大きいにも関わらず、「玉に瑕(きず)」があるために株式市場で実態価値を正当に評価されていない企業があります。
当ファンドでは、そのような企業の長期的なパートナー株主※として、良好な関係を築きながら粘り強く対話を行っています。企業の事業戦略や資本配分、IR体制などの改善を促すことで、企業の実態価値の顕在化に努め、株価上昇のカタリストの一つとなることを目指します。
当運用レポートでは、投資先企業に対する投資見解や対話の進捗などをご報告させていただきます。
当月は、当ファンドの投資先である「パイロットコーポレーション」に対する投資見解、対話内容をご説明します。
パイロットコーポレーションは、世界的にも有名な大手筆記具メーカーです。筆記具メーカーのシェアでは、Newell Brands社(米国)が世界首位ですが、パイロットコーポレーションは「PARKER」や「WATERMAN」など複数のブランドを展開し、単⼀ブランドでは「パイロット」が世界トップクラスのシェアを誇ります。
同社は⽇本初の純国産万年筆の製造を⽬指して、1918年に創業しました。その後万年筆の開発に成功すると、1920年代には海外への輸出を開始し、着実に売上を伸ばし続けてきました。その結果、世界190か国以上の国と地域で同社の筆記具が展開され、現在は海外売上比率が7割を超えています。
代表的なヒット商品である消えるボールペン「フリクションシリーズ」は、日本だけでなく欧州を中心に海外でも広く愛用されています。また、北米では「G-2」が大ヒットし、ゲルインキボールペンカテゴリーでシェアNo.1を獲得しています。このように、同社の製品は世界中の生活に浸透し、着実にシェアを拡大しています。
同社のボールペンは、インク詰まりが起こりにくく、最後までスムーズに使いきれるインクフローに定評があります。これは、ペン先の金属ボールの寸法精度による回転の安定性と、インクの粘度バランスによって成り立っており、同社独自の設計技術・成型技術・インク配合技術が支えています。
さらに同社は、高品質なペンを安価に製造する量産技術にも優れ、製品不良率は極めて低く、高い歩留まりを誇ります。こうした生産コストの管理や安定供給力は、長年の現場で培われた技術力によるものです。
当ファンドは、同社が長年培ってきた技術力とブランド力に加え、各地域に根差したマーケティング力や商品開発力、安定供給を可能にする製造・販売体制といった強みが、今後も同社の収益性と市場シェアを拡大すると考えています。特に新興国では、中間層の増加や進学率の上昇に伴い、高品質な筆記具の需要が高まることが期待されます。特にインドや中国では、入学試験でボールペンの使用が一般的であり、試験時間内にインク詰まりが起こりにくい同社のペンは、現地の学生からも高い支持を得ております。
一方で、当ファンドは同社のIR・資本政策に課題があると考え、これまで経営陣と対話を重ねてきました。過去、同社は株式市場に対する情報開示を最低限に留めていたため、投資家の関心が低く、本来の企業価値が株価に反映されていないと当ファンドは提言してまいりました。そのような中、同社はIR部門を新設し、初めてとなる決算説明会を2024年2月に開催しました。以降、機関投資家の関心が高まり、セルサイドのカバレッジもつくなど、注目度が向上しています。
さらに、2025年2月に開示された中期経営計画では、キャッシュアロケーションが示され、3か年で500億円の成長投資を実施し、かつ総還元性向を50%以上とする方針が開示されました。しかし、投資による売上の年平均成長率は約5%に留まり、株主還元も従来比で大幅な向上と言えず、株式市場の期待を十分に高めるものとはなっていないと考えます。また、ROE(株主資本利益率)目標も11%以上とし、現状水準を上回るものではありませんでした。
一方で藤﨑社長は、社長就任後初となる機関投資家との対話を、当ファンドと1on1形式で応じてくださり、その中で海外でのより高い成長と、ROE水準や株主還元の強化について議論をすることが出来ました。同社の中期経営計画は慎重な見通しに基づいており、実際の経営陣の思いを株式市場に伝えていくべきと当ファンドでは働きかけております。これまでのエンゲージメントの結果、IR体制が大きく改善してきたと認識しており、今後も対話を継続する方針です。
今後の運⽤⽅針
当ファンドでは潜在価値の高い企業に選別して集中投資を行い、長期的なリターンを追求しています。潜在価値の高い企業とは、スパークスの投資アプローチである3つの着眼点(経営者の質・企業収益の質・市場の成長性)に照らし、企業の実態価値や成長性が株式市場で十分に評価されていないと考えられる企業を指します。
日本には強固な事業基盤を有していながら、事業戦略や資本配分、株式市場への向き合い方に改善余地があることから株価が実態価値よりも低く評価されている企業が数多く存在します。当ファンドはパートナー株主として、投資先企業との中長期的な関係構築と丁寧な対話に努め、課題の改善を促すことで、企業価値の顕在化を積極的に後押しします。
※当ファンドは企業オーナーとして短期業績や株価変動に惑わされない⻑期保有を前提としています。投資先企業と共に企業価値向上を⽬指すとの考えから、短期的に株式を売買する投資家と区別する為、「パートナー株主」との文言を使⽤しています。
2025年2月の運用コメント
株式市場の状況
2025年2月、日本株式市場の代表指数であるTOPIX(配当込み)は前月末比3.79%の下落、日経平均株価は同6.11%の下落となりました。当月の日本株式市場は、トランプ米大統領の関税政策に関する言動に振り回され、月後半にかけて大幅な下落となりました。
月前半にトランプ米大統領がメキシコ、カナダ、中国に対する追加関税の検討を表明したことを受けて日本株式市場は急落しましたが、その後メキシコとカナダの関税発効が延期され株式市場は一時的に回復しました。しかし、複数の米国経済指標の結果からスタグフレーション(景気の後退と物価の上昇が同時進行する経済状況)懸念が再浮上する中で投資家は慎重な姿勢を保ち、日本株式市場も方向感のない、上値の重い相場が続きました。
月後半には、日銀の追加利上げ観測が高まり国内長期金利は一時約15年ぶりの高水準まで上昇しました。また、米国の消費者信頼感指数や購買担当者景気指数(PMI)が予想を下回る結果となり、米国経済の先行きに対する懸念が強まりました。これを受けて、為替市場では円高ドル安が進行し、日本株式市場の重石となりました。さらに、トランプ米政権による対中半導体規制強化の観測や、米国ハイテク株の下落、米国の関税政策を巡る不透明感などが影響し、日本株式市場は大幅に下落し当月の取引を終えました。
ファンドの運⽤状況
当月、当ファンドのパフォーマンスは、前⽉末⽐3.87%の下落となり、参考指数であるTOPIX(配当込み)の同3.79%の下落を0.08%下回りました。
当ファンドのパフォーマンスにプラスに寄与した企業は、ダイフク、ルネサスエレクトロニクス、スクウェア・エニックス・ホールディングスなどでした。⼀⽅、マイナスに影響した企業は、三菱重工業、リクルートホールディングス、SHOEIなどでした。
当ファンドでは、企業経営者が誠実であり、高い競争優位性を有する企業の中から、更なる成長余地のある潜在価値の高い企業に長期集中投資を行い、企業との対話を通じて価値の顕在化を図ることを基本戦略とします。
日本には、高い技術力・開発力を持ち、ニッチ市場でグローバルに高いシェアやブランド力を持つ企業が多く存在します。そうした企業の中には、基礎的な収益力が高く、中長期的な成長余地が大きいにも関わらず、「玉に瑕(きず)」があるために株式市場で実態価値を正当に評価されていない企業があります。
当ファンドでは、そのような企業の長期的なパートナー株主※として、良好な関係を築きながら粘り強く対話を行っています。企業の事業戦略や資本配分、IR体制などの改善を促すことで、企業の実態価値の顕在化に努め、株価上昇のカタリストの一つとなることを目指します。
当運用レポートでは、投資先企業に対する投資見解や対話の進捗などをご報告させて頂きます。
当月は、当ファンドの投資先である「コニカミノルタ」に対する投資見解、対話内容をご説明します。
コニカミノルタは、オフィス複合機を主力事業とする精密機器メーカーです。同社は、写真用カメラフィルムを祖業とする「コニカ株式会社」と、カメラや光学機器を祖業とする「ミノルタ株式会社」が、2003年に経営統合することで誕生しました。2006年にはカメラ事業から撤退したものの、化学合成技術の賜物である写真用カメラフィルムや、精巧な動作が求められるカメラの開発で培った材料・光学・微細加工・画像を4つのコア技術として、オフィス複合機だけでなく、商業用印刷機やディスプレイ関連の機能性フィルム、計測機器などを展開しています。
同社はペーパーレス化による複合機の構造的な市場縮小を見据えて、新たな事業の柱を創出すべく、2017年には合計で約1,000億円を超える金額を投じ、ヘルスケア関連事業の大型M&Aを実行するなど、新規領域に経営資源を集中させました。しかし、コロナ禍の影響を受け遺伝子検査数が停滞するなど、買収時の事業計画を大きく見直す必要に駆られました。2022年4月に就任した大幸社長は、総花的となっていた前経営陣の中期経営計画を刷新し、買収を行ったプリシジョンメディシン事業ののれんを中心に約1,000億円を減損し、非重点事業として位置付ける勇気ある決断をしました。同時に、大型買収の結果として傷んだ財務の健全性回復を図るべく、オフィス複合機の稼ぐ力の強化などを通じ、2025年度には再び飛躍するための基盤を確立するとの集中的な経営改善施策を発表しました。
当ファンドでは、大幸社長の有言実行型のリーダーシップと同社のコア技術を活かした成長市場への進出に注目しています。現実的な前提に立った計画を約束通りに達成するという「等身大の経営」の考えの下、2024年3月期には計画通り、2019年3月期ぶりの最終利益の黒字化を達成しました。2025年3月期第2四半期決算では、非重点事業と定めた遺伝子検査事業の全株式を譲渡することを発表しました。他の赤字事業も選択と集中による損失縮小が奏功し始め、経営戦略の“仕切り直し”が最終局面に差し掛かっているとの期待が高まる内容でした。
かつては遺伝子検査やオフィスITサービスなど、未踏の市場に成長の牽引役を求めた同社でしたが、現在では既存の技術資産や顧客との強固な関係を活用した隣接領域への進出を重視しています。その代表例が、高シェア領域を多く抱え、強化領域の営業利益率20%を目標とするインダストリー事業です。ディスプレイやレーザープリンター向けに培った光学技術を展開し、自動車外観計測や半導体製造装置など、高い成長率が見込まれる市場へと参入し、着実に実績を積み重ねています。
2025年3月期第3四半期には、インダストリー事業で大幅な減損損失を発表し、その後株価はPBR(株価純資産倍率)0.5倍を下回る水準に回帰しました。同社の強化事業が対面市場の逆風を受け、計画に対して遅れていることは事実ですが、組織体制・営業方針の変更を実施するなど、再成長に向けた手を打っています。加えて、主要事業であるオフィス事業の収益性が底上げされており、稼ぐ力は以前よりも高まっています。当ファンドでは、改革フェーズを終える2025年3月期以降は持続的成長を実現するビジョンに注目が移ると考えており、オフィス複合機の構造的な市場縮小を跳ね返し、企業価値拡大を成し遂げる戦略について、本質的な議論を行っています。
当ファンドはパートナー株主として、同社の本源的な企業価値の向上・顕在化に向けた対話を続けて参ります。
今後の運⽤⽅針
当ファンドでは潜在価値の高い企業に選別して集中投資を行い、長期的なリターンを追求しています。潜在価値の高い企業とは、スパークスの投資アプローチである3つの着眼点(経営者の質・企業収益の質・市場の成長性)に照らし、企業の実態価値や成長性が株式市場で十分に評価されていないと考えられる企業を指します。
日本には強固な事業基盤を有していながら、事業戦略や資本配分、株式市場への向き合い方に改善余地があることから株価が実態価値よりも低く評価されている企業が数多く存在します。当ファンドはパートナー株主として、投資先企業との中長期的な関係構築と丁寧な対話に努め、課題の改善を促すことで、企業価値の顕在化を積極的に後押しします。
※当ファンドは企業オーナーとして短期業績や株価変動に惑わされない⻑期保有を前提としています。投資先企業と共に企業価値向上を⽬指すとの考えから、短期的に株式を売買する投資家と区別する為、「パートナー株主」との文言を使⽤しています。
2025年1月の運用コメント
株式市場の状況
2025年1月、日本株式市場の代表指数であるTOPIX(配当込み)は前月末比0.14%の上昇、日経平均株価は同0.81%の下落となりました。
月前半は、米国の堅調な景況感指数や雇用統計の結果を受け、米国の利下げ期待の後退から日米長期金利が上昇したことや、米バイデン政権がAI(人工知能)向け半導体の輸出規制を強化する計画であると報じられたこと、その後当規制案が発表されたこと等を受け、株式市場は下落しました。
月半ばには、日銀総裁および副総裁から当月の金融政策決定会合で「利上げを行うかどうか議論して判断する」と、利上げを行う可能性が示唆されたことで円高が進行し株式市場の重しとなりました。しかし、昨秋からのレンジ下限として意識されている水準に近づくと下げ止まりの動きを見せ、株式市場は一転して上昇いたしました。
月後半は、トランプ米大統領が公約に掲げてきた対中関税の即時発動を見送ったことや、ソフトバンクグループ、OpenAI(米国)、Oracle社(米国)等が今後4年間で米国のAI開発事業に最大5,000億米ドルを投資すると発表し、AI・半導体関連銘柄が上昇をけん引したことなどにより、株式市場は堅調に推移しました。
一方、月の終盤にかけては、中国のAI開発企業DeepSeekが、米国製競合モデルを上回る性能を持った大規模言語モデルを低コストで開発したと公表したことで、米半導体企業の独占的地位が揺らぐとの警戒感から日米のAI・半導体関連銘柄が大幅に下落し、株式市場全体を下押しする局面がありました。しかし、月末にかけては揺り戻しの動きが見られ、前月末と概ね同水準で当月の取引を終えました。
当月もしばらく続くレンジ内での推移に終始した格好となりました。また、月中に日銀は政策金利の0.25%の引き上げを実施いたしましたが、事前の日銀総裁および副総裁の発言や、利上げ観測報道で市場への織り込みが進んでいたことから、影響は限定的なものとなりました。
ファンドの運⽤状況
当月、当ファンドのパフォーマンスは、前⽉末⽐1.49%の下落となり、参考指数であるTOPIX(配当込み)の同0.14%の上昇を1.63%下回りました。
当ファンドのパフォーマンスにプラスに寄与した企業は、マックス、三菱重工業、横浜ゴムなどでした。⼀⽅、マイナスに影響した企業は、サイゼリヤ、パイロットコーポレーション、ホシザキなどでした。
当ファンドでは、企業経営者が誠実であり、高い競争優位性を有する企業の中から、更なる成長余地のある潜在価値の高い企業に長期集中投資を行い、企業との対話を通じて価値の顕在化を図ることを基本戦略とします。
日本には、高い技術力・開発力を持ち、ニッチ市場でグローバルに高いシェアやブランド力を持つ企業が多く存在します。そうした企業の中には、基礎的な収益力が高く、中長期的な成長余地が大きいにも関わらず、「玉に瑕(きず)」があるために株式市場で実態価値を正当に評価されていない企業があります。
当ファンドでは、そのような企業の長期的なパートナー株主※として、良好な関係を築きながら粘り強く対話を行っています。企業の事業戦略や資本配分、IR体制などの改善を促すことで、企業の実態価値の顕在化に努め、株価上昇のカタリスト(きっかけ)の一つとなることを目指します。
当レポートでは、投資先企業に対する投資見解や対話の進捗などをご報告させていただきます。
当月は、当ファンドの投資先である「ダイフク」に対する投資見解、対話内容をご説明します。
ダイフクは、物流や製造現場で材料や製品などを運搬するマテリアルハンドリングシステムを提供する企業です。同社は、「モノを効率的に保管、搬送、仕分け・ピッキングする」機械設備およびそれらを制御するソフトウェアを組み合わせ、システムを構築することで、顧客の物流業務において重労働や反復作業の軽減に貢献しています。同社は1937年に、「坂口機械製作所」として発足し、船舶の蒸気機関や航空機製造用の鍛圧機械を製造しました。1947年には当時の生産拠点であった大阪、福知山から「大福機工」に社名を変更しております。その後、荷役搬送機などを製造し、1950年代にはトヨタ自動車工業へ自動車製造用コンベヤシステムを、1966年には松下電器産業(現パナソニック ホールディングス)へ日本初の高層自動倉庫を、1982年にはファナックに無人搬送車のFA(ファクトリーオートメーション)システムを納入し、1984年には半導体ウエハの自動搬送装置を開発するなど、様々な領域で日本の製造・物流現場の自動化・量産化を支えてきました。また同1984年には現在の「ダイフク」に社名を変更、その後次々に海外法人を設立し、グローバル展開を加速させております。
このような経緯から、同社のビジネス領域は、製造業・流通業向けのイントラロジスティクス事業、半導体業界向けのクリーンルーム事業、自動車業界向けのオートモーティブ事業、空港施設向けのエアポート事業など、多岐にわたっています。同社は、顧客のマテリアルハンドリングの企画・コンサルティングから設計・製造・アフターサービスまで一貫してサポート対応できることで、顧客から長期にわたる信頼を得てきたと考えられます。また、ハードからソフトまで主要製品のすべてを内製化することで品質の高い製品を短納期で提供し、かつ価格競争力を高めていると考えられます。このような高品質な製品・サービスを、グローバルに展開し、日本・北米・中国・アジアなどの地域で今後ますます高まる省人化ニーズに応え続けています。
当ファンドでは、同社の今後の企業価値向上には、事業領域の拡大とプロジェクトの採算性改善、CCC(キャッシュ・コンバージョン・サイクル:企業の資金繰りの状態を表す指標)の適正化が有効であると考えます。同社は高い製品品質と顧客サポート体制に裏打ちされた製品・サービスを有しています。特に当ファンドが直近注目しているのはクリーンルーム事業における後工程向け案件の拡大です。半導体製造工程は大まかに前工程と後工程に分かれており、従来は前工程向けの案件がほとんどを占めていました。しかしながら、昨今の自動化ニーズの高まりから組立を中心とする後工程においても自動化プロジェクトが進捗しています。今後も半導体に留まらず、こうした新たな自動化ニーズを捉え収益機会を獲得していくことに期待をしています。また、同社は建設コストや人件費等が上昇する中でも適切な価格転嫁やプロジェクト管理によって収益性を改善してきました。同社の過去の営業利益率は概ね9%台で推移してきたものの、2024年12月期第2四半期決算においては12%台まで改善しています。一方で、CCCの適正化は未だ大きな課題として残っています。同社の事業は受注から完成までの期間が長く、数か月から数年を要すため受注から売上債権の回収までにタイムラグが生じています。顧客との関係性を維持しつつも、顧客からの支払いタイミングの適正化を図ることでこのタイムラグが短くなり、資本効率の改善につながると当ファンドでは考えており、引き続き対話を続けてまいります。
今後の運⽤⽅針
当ファンドでは潜在価値の⾼い企業に選別して集中投資を⾏い、⻑期的なリターンを追求しています。潜在価値の⾼い企業とは、スパークスの投資アプローチである3つの着眼点(経営者の質・企業収益の質・市場の成⻑性)に照らし、企業の実態価値や成⻑性が株式市場で⼗分に評価されていないと考えられる企業を指します。
⽇本には強固な事業基盤を有していながら、事業戦略や資本配分、株式市場への向き合い⽅に改善余地があることから株価が実態価値よりも低く評価されている企業が数多く存在します。当ファンドはパートナー株主として、投資先企業との中⻑期的な関係構築と丁寧な対話に努め、課題の改善を促すことで、企業価値の顕在化を積極的に後押しします。
※当ファンドは企業オーナーとして短期業績や株価変動に惑わされない⻑期保有を前提としています。投資先企業と共に企業価値向上を⽬指すとの考えから、短期的に株式を売買する投資家と区別する為、「パートナー株主」との文言を使⽤しています。
2024年12月の運用コメント
株式市場の状況
2024年12月、日本株式市場の代表指数であるTOPIX(配当込み)は前月末比4.02%の上昇、日経平均株価は同4.41%の上昇となりました。年間では両指数とも2年連続で上昇し、年末終値としては日経平均株価が最高値を更新しました。
月前半には、厚生労働省が年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)を通じて運用する資産の利回り目標を引き上げる方針を明らかにしたことで、日本株式の資産配分比率が高まるとの思惑が高まったことや、好調なハイテク株に支えられた堅調な米国株式市場、さらには米国の利下げ鈍化懸念からの円安進行等が日本株式市場の上昇につながりました。
月後半には、18日に米連邦準備制度理事会(FRB)は米連邦公開市場委員会(FOMC)において予想通り政策金利の引き下げを決定し、2025年については2回の利下げに留まることを示唆しました。これを受けて米国長期債利回りは上昇し、米国株式市場は調整に転じ、その影響で日本株式市場も軟調に推移しました。しかしながら19日には日銀は金融政策決定会合にて金利を据え置くことを決定し、その後の記者会見で植田日銀総裁がハト派的な発言を行ったことで為替市場では円安ドル高が進みました。その後は好調な米国の半導体株及びさらなる円安に支えられ、日本株式市場は再び上昇に転じ、27日には日経平均株価は4万円の大台を回復しました。
ファンドの運⽤状況
当月、当ファンドのパフォーマンスは、前⽉末⽐2.45%の上昇となり、参考指数であるTOPIX(配当込み)の同4.02%の上昇を1.57%下回りました。
当ファンドのパフォーマンスにプラスに寄与した企業は、横浜ゴム、全国保証、リクルートホールディングスなどでした。⼀⽅、マイナスに影響した企業は、SHOEI、京成電鉄、森永製菓などでした。
当ファンドでは、企業経営者が誠実であり、高い競争優位性を有する企業の中から、更なる成長余地のある潜在価値の高い企業に長期集中投資を行い、企業との対話を通じて価値の顕在化を図ることを基本戦略とします。
日本には、高い技術力・開発力を持ち、ニッチ市場でグローバルに高いシェアやブランド力を持つ企業が多く存在します。そうした企業の中には、基礎的な収益力が高く、中長期的な成長余地が大きいにも関わらず、「玉に瑕(きず)」があるために株式市場で実態価値を正当に評価されていない企業があります。
当ファンドでは、そのような企業の長期的なパートナー株主※として、良好な関係を築きながら粘り強く対話を行っています。企業の事業戦略や資本配分、IR体制などの改善を促すことで、企業の実態価値の顕在化に努め、株価上昇のカタリスト(きっかけ)の一つとなることを目指します。
当レポートでは、投資先企業に対する投資見解や対話の進捗などをご報告させていただきます。
当月は、当ファンドの投資先である「SHOEI」に対する投資見解、対話内容をご説明します。
SHOEIは、バイク用の高級ヘルメットを製造・販売している企業です。同社は1959年に設立され、その卓越した製品デザインや機能性、品質の高さからグローバルに多くのファンを抱えています。販売網は日本、欧米、中国など世界60か国以上を網羅し、ほとんど全ての国でシェアNo.1を獲得し、世界のプレミアムヘルメット(高い安全性・機能性・デザイン性を兼ね揃えたヘルメット)市場で約60%のトップシェアを誇ります。
同社は設計、開発、製造を一貫して日本国内で展開しており、製造プロセスの多くは自動化されていますが、機械では代替できない非常に精巧な作業は現在でも人の手で行われています。そして同社は「カイゼン企業」を標榜しており、生産効率の向上を常に推進しています。同社の競争力の源泉はまさにこの「現場力」にあると当ファンドでは考えています。長年にわたって蓄積されたノウハウと人材を育成する企業風土が、今後もSHOEIブランドへの信頼性を高めていくことを期待しています。
こうした高いブランド力と商品開発力を武器にグローバルに販売数量を伸ばしながら、デザイン性・機能性に優れた新製品の投入を戦略的に行うことで、価格を引き上げることに成功しています。価格が上がったとしても、SHOEIのヘルメットを欲しいと考える消費者が増えていることに他なりません。このブランド価値とカイゼン文化を背景として、2024年9月期の営業利益率は28.9%と非常に高い収益性を誇っています。
一方で、市場環境は全般的に芳しくなく、販売数量は中国が緩やかに持ち直すも、その他地域で減少する見込みであり、平均単価についてもモデルの端境期で減少が見込まれることから、同社公表の2025年9月期では減収減益予想となっております。しかし、同社も手をこまねている訳ではなく、海外現地での需要動向調査・マーケティングの拡充など、積極的かつ着実に対応を進めています。また、同社の業績予想はボトムアップでの積み上げにより策定されており、過年度の予実に鑑みても、保守的な見立てとなる傾向にあると考えています。当ファンドでは同社の中長期的な事業成長に対する見方に変更はありませんが、個別面談を通じて注意深くフォローアップしてまいります。
また、当ファンドは、同社の資本政策に改善の余地があると考えています。同社は直近数年の大幅な事業成長により多くのキャッシュを稼ぎ、2024年9月末時点で総資産の約4割を現預金が占める状況となっています。同社は配当性向50%を基本とした株主還元を行っていますが、ROE(株主資本利益率)の分母である資本の蓄積スピードが早く、ROEには下押し要因となっています。直近2期の数字を見ても、最終利益が増益するなかで、ROEは28.3%から26.1%に下がっています。設備や人への投資を実施した後の余剰資金を今後どのように活用していくか、同社からは明確な発信がありません。この点について当ファンドは経営陣との個別面談を通じて対話を継続しています。経営陣は長期的な事業継続のために財務健全性を確保したいと主張していますが、保守的すぎる財務運営によって株主の利益であるROEが低下していく懸念を当ファンドは伝えています。対話の中では、同社から「自己資本比率が高ければいいわけではない」などの資本収益性に対する発言の変化が見られましたが、具体的なアクションには落とし込まれていません。同社の資本政策に対する株式市場の目は厳しくなっていると考えられます。当ファンドは長期のパートナー株主として、引き続き同社の企業価値向上に向けた対話を粘り強く続けてまいります。
今後の運⽤⽅針
当ファンドでは潜在価値の高い企業に選別して集中投資を行い、長期的なリターンを追求しています。潜在価値の高い企業とは、スパークスの投資アプローチである3つの着眼点(経営者の質・企業収益の質・市場の成長性)に照らし、企業の実態価値や成長性が株式市場で十分に評価されていないと考えられる企業を指します。
日本には強固な事業基盤を有していながら、事業戦略や資本配分、株式市場への向き合い方に改善余地があることから株価が実態価値よりも低く評価されている企業が数多く存在します。当ファンドはパートナー株主として、投資先企業との中長期的な関係構築と丁寧な対話に努め、課題の改善を促すことで、企業価値の顕在化を積極的に後押しします。
※当ファンドは企業オーナーとして短期業績や株価変動に惑わされない⻑期保有を前提としています。投資先企業と共に企業価値向上を⽬指すとの考えから、短期的に株式を売買する投資家と区別する為、「パートナー株主」との文言を使⽤しています。
2024年11月の運用コメント
株式市場の状況
2024年11月、日本株式市場の代表指数であるTOPIX(配当込み)は前月末比0.51%の下落、日経平均株価は同2.23%の下落となりました。
月前半は一進一退の展開となりました。5日に実施された米大統領選挙で共和党のトランプ前大統領が優勢と伝わったことから日経平均株価は大幅に上昇し、7日には40,000円に迫る場面もありました。しかしその後、トランプ次期米大統領が政権人事で対中強硬派の人物を起用する方針が報じられ、次期政権が掲げる関税強化策への警戒感が強まったことで半導体関連株に売り圧力がかかり、株式市場は下落に転じました。一方、14日には米連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長が「利下げを急ぐ必要はない」旨の発言をしたことで円安が進行し輸出関連株が買われ、半導体関連株の反発もあって株式市場の連日の下落が一服しました。
月後半は狭いレンジで推移し、米国の金融政策の先行き不透明感や米国半導体株の動向に一喜一憂する動きが続きました。また、トランプ次期米大統領が中国、メキシコ、カナダに対する関税措置を発表したことを受け、相場は軟調な動きが続き、前月末比で下落して当月の取引を終えました。
ファンドの運⽤状況
当月、当ファンドのパフォーマンスは、前⽉末⽐1.09%の下落となり、参考指数であるTOPIX(配当込み)の同0.51%の下落を0.58%下回りました。
当ファンドのパフォーマンスにプラスに寄与した企業は、ホシザキ、リクルートホールディングス、京成電鉄などでした。⼀⽅、マイナスに影響した企業は、東洋炭素、全国保証、ルネサスエレクトロニクスなどでした。
当ファンドでは、企業経営者が誠実であり、高い競争優位性を有する企業の中から、更なる成長余地のある潜在価値の高い企業に長期集中投資を行い、企業との対話を通じて価値の顕在化を図ることを基本戦略とします。
日本には、高い技術力・開発力を持ち、ニッチ市場でグローバルに高いシェアやブランド力を持つ企業が多く存在します。そうした企業の中には、基礎的な収益力が高く、中長期的な成長余地が大きいにも関わらず、「玉に瑕(きず)」があるために株式市場で実態価値を正当に評価されていない企業があります。
当ファンドでは、そのような企業の長期的なパートナー株主※として、良好な関係を築きながら粘り強く対話を行っています。企業の事業戦略や資本配分、IR体制などの改善を促すことで、企業の実態価値の顕在化に努め、株価上昇のカタリスト(きっかけ)の一つとなることを目指します。
当レポートでは、投資先企業に対する投資見解や対話の進捗などをご報告させていただきます。
当月は、当ファンドの投資先である「EIZO」に対する投資見解、対話内容をご説明します。
EIZOは1967年に石川県七尾市で七尾電機㈱として設立されたコンピューター用の高機能モニターメーカーです。当ファンドは、同社の一貫した自社開発・自社生産による徹底した品質への拘りと、クラフトマンシップに支えられた医療・映像制作・航空管制・船舶・鉄道などの特定用途における高いシェアを評価し、投資を行いました。内視鏡検査や放射線検査といった非侵襲医療の浸透に伴って重要度が増す、同社の主力製品の一つである医療用モニター、さらには国際情勢の先行きの不透明さが増す中での防衛用モニターの成長に注目しています。
一方で、EIZOは手元現預金や投資有価証券などの金融資産を約770億円保有しており、総資産の約48%を占めています。(2024年9月末時点)。このような余剰な非事業用資産を抱えていることが重石となり、過去最高益を記録した2022年3月期においても、同社のROE(株主資本利益率)は6.7%にとどまっています。当戦略は、同社はバランスシートマネジメントによる資本収益性に改善余地があると考え、2022年初頭からROE向上に関して、経営陣と対話を続けてきました。
その後、同社は2022年5月に自社株買い(40億円)および、買収防衛策の廃止を発表するなど、資本市場への向き合い方に少しずつ変化が見られておりました。より明確な変化として、2023年3月期決算説明会の場にて、ROE8%以上を資本収益性の目標として、総還元性向の目標水準を70%に設定し、株主還元を強化する方針を掲げました。2025年3月期は、欧州でのオフィス向けモニターや、中国での医療用モニターの需要減速に苦しみ、通期業績予想を下方修正しておりますが、総還元性向70%+αを維持する方針を、当ファンドは高く評価しています。
当ファンドはパートナー株主として、同社の中長期的な成長を実現する上で、対処が求められる様々な経営課題について経営陣との対話を続け、同社の本源的な企業価値の向上を積極的に後押ししていく方針です。
今後の運⽤⽅針
当ファンドでは潜在価値の高い企業に選別して集中投資を行い、長期的なリターンを追求しています。潜在価値の高い企業とは、スパークスの投資アプローチである3つの着眼点(経営者の質・企業収益の質・市場の成長性)に照らし、企業の実態価値や成長性が株式市場で十分に評価されていないと考えられる企業を指します。
日本には強固な事業基盤を有していながら、事業戦略や資本配分、株式市場への向き合い方に改善余地があることから株価が実態価値よりも低く評価されている企業が数多く存在します。当ファンドはパートナー株主として、投資先企業との中長期的な関係構築と丁寧な対話に努め、課題の改善を促すことで、企業価値の顕在化を積極的に後押しします。
※当ファンドは企業オーナーとして短期業績や株価変動に惑わされない⻑期保有を前提としています。投資先企業と共に企業価値向上を⽬指すとの考えから、短期的に株式を売買する投資家と区別する為、「パートナー株主」との⽂⾔を使⽤しています。
2024年10月の運用コメント
株式市場の状況
2024年10月、日本株式市場の代表指数であるTOPIX(配当込み)は前月末比1.88%の上昇、日経平均株価は同3.06%の上昇となりました。
月前半は、全米企業エコノミスト協会の年次総会に登壇したパウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長が今後の利下げについて「急ぐ必要はない」と強調したことや、米国雇用統計が市場予想を大幅に上回ったこと等から利下げ観測が後退したこと、石破茂首相から日銀の早期の追加利上げに否定的な見解が示されたこと等からドル高円安が進行しました。また、中東情勢の悪化により株価が一時的に下落する局面もありましたが、前述のように円安の進行や米国経済の底堅さ、石破政権が岸田前政権の経済政策を継承するとの方針が確認されたこと等から株式市場は上昇いたしました。
月半ばから後半にかけては、オランダの半導体製造装置大手ASML Holding社の決算発表で2025年12月期の業績見通しが引き下げられたことで半導体関連株に売りが広がったことや、日米長期金利の上昇基調の継続が意識されたこと、27日投開票の衆議院選挙で与党自民・公明両党が過半数議席の確保が微妙な状況と報じられたこと等から株式市場は軟調な推移となりました。
衆議院選挙では連立与党が2009年以来15年ぶりに過半数を割り込む結果となり、今後の政権の枠組みは少数与党が政策や法案ごとに野党に協力を求める「パーシャル(部分)連合」になるのではないかという見方が強まりました。財政拡張的な政策を掲げる野党との協力により景気刺激的な政策が実行される可能性が意識されたことや、リスクイベント通過に伴う先物の買戻し等から株式市場は衆議院選挙を境に一転し、前月末比で上昇して当月の取引を終えました。
ファンドの運⽤状況
当月、当ファンドのパフォーマンスは、前⽉末⽐1.09%の上昇となり、参考指数であるTOPIX(配当込み)の同1.88%の上昇を0.79%下回りました。
当ファンドのパフォーマンスにプラスに寄与した企業は、リクルートホールディングス、三菱重工業、パイロットコーポレーションなどでした。⼀⽅、マイナスに影響した企業は、東洋炭素、全国保証、京成電鉄などでした。
当ファンドでは、企業経営者が誠実であり、高い競争優位性を有する企業の中から、更なる成長余地のある潜在価値の高い企業に長期集中投資を行い、企業との対話を通じて価値の顕在化を図ることを基本戦略とします。
日本には、高い技術力・開発力を持ち、ニッチ市場でグローバルに高いシェアやブランド力を持つ企業が多く存在します。そうした企業の中には、基礎的な収益力が高く、中長期的な成長余地が大きいにも関わらず、「玉に瑕(きず)」があるために株式市場で実態価値を正当に評価されていない企業があります。
当ファンドでは、そのような企業の長期的なパートナー株主※として、良好な関係を築きながら粘り強く対話を行っています。企業の事業戦略や資本配分、IR体制などの改善を促すことで、企業の実態価値の顕在化に努め、株価上昇のカタリスト(きっかけ)の一つとなることを目指します。
当レポートでは、投資先企業に対する投資見解や対話の進捗などをご報告させていただきます。
当月は、当ファンドの投資先である「ルネサスエレクトロニクス」に対する投資見解、対話内容をご説明します。
ルネサスエレクトロニクスは、半導体を製造・販売する企業です。同社は、㈱日立製作所・三菱電機㈱の半導体事業とNECエレクトロニクス㈱の統合により、2010年に設立されました。世界トップシェアを有するマイコンを基軸に、2017年以降は海外の半導体デバイスメーカーを買収することにより、成長市場であるデータセンターやスマートデバイス向けの製品・顧客ラインナップを拡大してきました。2024年8月には、米国の電子機器設計ソフトウェア企業であるAltium社を約8,879億円で買収し、ハードウェアだけでなくソフトウェア製品まで手掛けるユニークな半導体メーカーへと進化を遂げました。
コロナ禍から経済活動が正常化し、財の需要が回復する過程において、世界的な半導体不足も追い風になり、同社は2022年12月期には過去最高の売上高を記録しました。2023年12月期も、自動車向け事業は顧客である完成車メーカーの生産台数増を背景に成長を継続しました。一方、産業・インフラ・IoT向け事業は中国の景気鈍化を受けて、2023年から大きく調整が始まりました。しかしながら同社は、厳しい局面にあっても、顧客へのヒアリングによる需要動向の精査や販売チャネルの在庫情報を生産稼働計画に反映させることで、営業利益率を高水準で維持し、エグゼキューション能力の向上を示しました。
成長軌道への回帰が待ち望まれていた2024年12月期 第2四半期決算説明会では、楽観視しすぎていた産業用とマスマーケット向けの需要見通しを引き下げたとの言及を受け、決算発表当日に株価は急落しました。
当月末に発表された2024年12月期 第3四半期決算では事前のガイダンス通り、低位な需要環境が継続している事が鮮明となりましたが、「需要が落ちる中でブレーキを十分に踏めなかった」と自らの経営判断の誤りを素直に認める柴田英利CEOのリーダーシップを当ファンドは高く評価しております。事実、同社は逆境を乗り切るべく、より慎重な在庫コントロールや営業費用のスリム化、生産ライン立ち上げ時期の調整等、大胆な戦略の見直しを図る予定です。このような機動力と決断力は、変動の激しい半導体業界において不可欠な姿勢だと考えております。
半導体業界の需要下降局面に晒されたことにより、2024年12月期は2年連続での減収となる見通しを発表しています。一方、同社は外部要因を跳ね返して、成長し続けるための仕込みを進めております。例えば、既に業界でのリーディングポジションを誇る車載半導体について、先進運転支援システムや電気自動車等の伸長領域での新製品を強化し、成長を加速するという目標を掲げています。特に、自動車の機能をソフトウェアで定義し、アップデート可能な次世代自動車であるSDV(Software Defined Vehicle)や自動運転の早期実現を支援すべく、独自の開発プラットフォームを新たに発表しております。
当ファンドでは、同社の中でサイクルに左右されにくい、成長領域の売上構成が着実に高まりつつある点に注目しています。現在のように短期業績の不透明感が悲観視されやすい状況にこそ、買収したAltium社との連携も含めて、同社固有の力強い戦略ビジョンを株式市場に対して示すべきタイミングだと考えております。当ファンドはパートナー株主として、引き続き同社の企業価値向上に向けた対話を粘り強く続けて参ります。
今後の運⽤⽅針
当ファンドでは潜在価値の高い企業に選別して集中投資を行い、長期的なリターンを追求しています。潜在価値の高い企業とは、スパークスの投資アプローチである3つの着眼点(経営者の質・企業収益の質・市場の成長性)に照らし、企業の実態価値や成長性が株式市場で十分に評価されていないと考えられる企業を指します。
日本には強固な事業基盤を有していながら、事業戦略や資本配分、株式市場への向き合い方に改善余地があることから株価が実態価値よりも低く評価されている企業が数多く存在します。当ファンドはパートナー株主として、投資先企業との中長期的な関係構築と丁寧な対話に努め、課題の改善を促すことで、企業価値の顕在化を積極的に後押しします。
※当ファンドは企業オーナーとして短期業績や株価変動に惑わされない⻑期保有を前提としています。投資先企業と共に企業価値向上を⽬指すとの考えから、短期的に株式を売買する投資家と区別する為、「パートナー株主」との⽂⾔を使⽤しています。
2024年9月の運用コメント
株式市場の状況
2024年9月、日本株式市場の代表指数であるTOPIX(配当込み)は前月末比1.53%の下落、日経平均株価は同1.88%の下落となりました。
月前半は米国のISM製造業景況感指数や雇用統計が予想を下回ったことで、米国経済の減速懸念が高まり市場心理に影響を与えました。さらに米連邦公開市場委員会(FOMC)による利下げ期待と日銀の利上げ期待の高まりにより、月半ばにかけて円高が進行しました。このような状況の中、株式市場は一時的に下落した後、反発が見られたものの上値は重く、投資家は慎重な姿勢を維持しました。
月後半はFOMCが0.5%の利下げを決定した後、パウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長が緩和を急がない姿勢を示したことや、日銀が金融政策を現状維持したことから円高が一服し、輸出関連株や半導体関連株の買い戻しが進みました。また、自民党総裁選挙で高市早苗氏が当選し、金融緩和が再開されるとの見通しが高まったことで日経平均株価は26日から27日にかけて大きく上昇しました。しかし、最終的には石破茂氏が勝利し、経済政策への警戒感が高まったことなどから30日の日本株式市場は全面安の展開となり、前月末比で下落して当月の取引を終えました。
ファンドの運⽤状況
当月、当ファンドのパフォーマンスは、前⽉末⽐0.86%の下落となり、参考指数であるTOPIX(配当込み)の同1.53%の下落を0.67%上回りました。
当ファンドのパフォーマンスにプラスに寄与した企業は、三菱重工業、サイゼリヤ、MARUWAなどでした。⼀⽅、マイナスに影響した企業は、ルネサスエレクトロニクス、全国保証、メックなどでした。
当ファンドでは、企業経営者が誠実であり、高い競争優位性を有する企業の中から、更なる成長余地のある潜在価値の高い企業に長期集中投資を行い、企業との対話を通じて価値の顕在化を図ることを基本戦略とします。
日本には、高い技術力・開発力を持ち、ニッチ市場でグローバルに高いシェアやブランド力を持つ企業が多く存在します。そうした企業の中には、基礎的な収益力が高く、中長期的な成長余地が大きいにも関わらず、「玉に瑕(きず)」があるために株式市場で実態価値を正当に評価されていない企業があります。
当ファンドでは、そのような企業の長期的なパートナー株主※として、良好な関係を築きながら粘り強く対話を行っています。企業の事業戦略や資本配分、IR体制などの改善を促すことで、企業の実態価値の顕在化に努め、株価上昇のカタリスト(きっかけ)の一つとなることを目指します。
当レポートでは、投資先企業に対する投資見解や対話の進捗などをご報告させていただきます。
当月は、当ファンドの投資先である「東洋炭素」に対する投資見解、対話内容をご説明します。
東洋炭素は1941年に創業した特殊黒鉛製品の世界的大手メーカーです。世界で初めて大型の等方性黒鉛製品の量産に成功し、ニッチな市場ではありますが世界トップレベルのシェアを維持しています。同社の主力製品は半導体ウエハー製造時の炉材として使用されています。一般的なシリコンウエハーだけでなく、SiC(シリコンカーバイド)ウエハーと呼ばれる高機能材料の製造にも必要不可欠な部材となっています。
同社は日本で等方性黒鉛を集中的に生産し、用途に応じて形状を加工しています。生産期間はおよそ6~8か月と言われており、この長期間にわたる繊細な製造管理や品質の作り込みが高い参入障壁になっていると考えられます。また同社は中長期的な成長が見込める半導体関連の需要を捕捉するため、積極的な設備投資に踏み切っています。今後も付加価値の高い製品でシェアを維持・向上するための事業基盤が整備されつつあると当ファンドでは評価しています。
足元ではEV(電気自動車)市場が踊り場を迎えており、EV向けに需要が期待されているSiCウエハーの出荷にも影響が出ているようです。同社は豊富な受注残を背景に現時点では堅調な売上成長を続けていますが、市場環境の悪化を認めており、一部SiC向け製品の売上には市場環境悪化の兆候が見られるとのことです。同社株価が軟調に推移しているのもそうした背景と思われます。一方で、スマートフォン、サーバー等の半導体に使われるシリコンウエハーの需要回復も観測されており、当ファンドでは同社がSiCウエハー製造向けの黒鉛素材をシリコンウエハー製造向けに振り替えることで、全体での業績拡大を継続できると考えています。世界の中長期的なデジタル化・電動化に対する方向性は変わっていないことから、同社の製品ポートフォリオの強靭さ、差別化技術、収益性の高さなどが株式市場で再度見直されることを期待しています。
そのためには適時適切な情報開示や、株式市場で過度に悲観/楽観されないようなコミュニケーションが肝要となります。同社は従前から第1四半期、第3四半期に決算説明資料を開示しておらず、そのため一般に適切な情報が知れ渡りにくい状況にあると当ファンドでは考えています。特に情勢の移り変わりが早い半導体市場においては、様々な憶測で株価の変動が激しくなる傾向にあります。当ファンドでは社長・経営層との対話を通じて、情報開示の充実化が資本コストの低下に繋がることをお伝えしています。過去からの継続的な対話の結果、同社はROE(株主資本利益率)向上に向けたキャッシュアロケーションを明示するなど、開示姿勢の改善が見られてきています。当ファンドはパートナー株主として、同社の本源的な企業価値の向上・顕在化に向けた対話を続けてまいります。
今後の運⽤⽅針
当ファンドでは潜在価値の高い企業に選別して集中投資を行い、長期的なリターンを追求しています。潜在価値の高い企業とは、スパークスの投資アプローチである3つの着眼点(経営者の質・企業収益の質・市場の成長性)に照らし、企業の実態価値や成長性が株式市場で十分に評価されていないと考えられる企業を指します。
日本には強固な事業基盤を有していながら、事業戦略や資本配分、株式市場への向き合い方に改善余地があることから株価が実態価値よりも低く評価されている企業が数多く存在します。当ファンドはパートナー株主として、投資先企業との中長期的な関係構築と丁寧な対話に努め、課題の改善を促すことで、企業価値の顕在化を積極的に後押しします。
※当ファンドは企業オーナーとして短期業績や株価変動に惑わされない⻑期保有を前提としています。投資先企業と共に企業価値向上を⽬指すとの考えから、短期的に株式を売買する投資家と区別する為、「パートナー株主」との⽂⾔を使⽤しています。
2024年8月の運用コメント
株式市場の状況
2024年8月、日本株式市場の代表指標であるTOPIX(配当込み)は前月末比2.90%下落し、日経平均株価は前月末比1.16%下落しました。
当月の日本株式市場は歴史的な乱高下を演じ、日経平均株価の月間値幅(高値と安値の差、終値ベース)がバブル経済崩壊時期を超えて過去最大となりました。
7月31日の日銀金融政策決定会合での追加利上げが円高を呼び、さらに市場予想を下回った7月の米ISM製造業景気指数で米国景気減速懸念が台頭し円高が一層進行したことで、月前半の日本株式市場はリスク回避の流れが強まり暴落しました。5日には米国経済や雇用の減速への警戒などから円高が大幅に進み、午後には日経平均先物でサーキットブレーカーが13年ぶりに1日に2回発動され、日経平均株価は前日比4,451円の下落と過去最大の値下がりを記録しました。しかしながら翌6日には為替市場がいったん落ち着いたことで日本株式市場も落ち着きを取り戻し、TOPIXおよび日経平均株価は史上最大の上げ幅となりました。加えて、翌7日の内田日銀副総裁のハト派発言も投資家の安心感につながり、月半ばにかけて日本株式市場は急反発しました。
月後半は米国経済への先行きに対する警戒感がひとまず和らぎ、日本株式市場は緩やかなペースで回復し、月前半の急落分の大半を取り戻して当月の取引を終えました。
ファンドの運⽤状況
当月、当ファンドのパフォーマンスは、前⽉末⽐2.73%の下落となり、参考指数であるTOPIX(配当込み)の同2.90%の下落を0.17%上回りました。
当ファンドのパフォーマンスにプラスに寄与した企業は、三菱重工業、SHOEI、キーエンスなどでした。⼀⽅、マイナスに影響した企業は、全国保証、三井住友フィナンシャルグループ、フジミインコーポレーテッドなどでした。
当ファンドでは、企業経営者が誠実であり、高い競争優位性を有する企業の中から、更なる成長余地のある潜在価値の高い企業に長期集中投資を行い、企業との対話を通じて価値の顕在化を図ることを基本戦略とします。
日本には、高い技術力・開発力を持ち、ニッチ市場でグローバルに高いシェアやブランド力を持つ企業が多く存在します。そうした企業の中には、基礎的な収益力が高く、中長期的な成長余地が大きいにも関わらず、「玉に瑕(きず)」があるために株式市場で実態価値を正当に評価されていない企業があります。
当ファンドでは、そのような企業の長期的なパートナー株主※として、良好な関係を築きながら粘り強く対話を行っています。企業の事業戦略や資本配分、IR体制などの改善を促すことで、企業の実態価値の顕在化に努め、株価上昇のカタリスト(きっかけ)の一つとなることを目指します。
当レポートでは、投資先企業に対する投資見解や対話の進捗などをご報告させていただきます。
当月は、当ファンドの投資先である「横浜ゴム」に対する投資見解、対話内容をご説明します。
横浜ゴムは1917年に横浜で創業したタイヤメーカーです。横濱電線製造(現古河電気工業㈱)と米国のBFグッドリッチ社の合弁会社として設立され、戦前のコードタイヤ開発に始まり、戦後にはスノータイヤやスポーツラジアルタイヤなど数々の日本初となる画期的な製品を発売し、グローバルに成長を続けてきました。
乗用車向けのタイヤ消費財市場では2010年以降、低コスト・低価格を武器とした新興国のタイヤメーカーが生産能力を拡大しており、競争は年々激しくなっています。特に、中国タイヤメーカーの拡大は著しく、上位10社の増産投資計画を合算すると、10年以内に中国メーカーの生産比率は全世界の乗用車タイヤの50%を占めることが予想されています。このようにタイヤメーカーを取り巻く急速な環境変化に対して、同社を含むメジャータイヤメーカーはブランド力や技術投資を強化し、本数成長以上に価格の引き上げを優先するプレミアムカー戦略で対抗してきました。
当ファンドが注目しているのは、厳しい環境下でも徹底的に成長を追求する同社の経営姿勢です。消費財ブランドの“深化”と並行して“探索”と銘打ち、農機・建機などいわゆる「はたらくくるま」に搭載されるタイヤ生産財の強化に向けたM&Aを継続しています。2016年のオランダの農機・建機用タイヤメーカーAlliance Tire Group社(ATG)買収を皮切りに、2023年には農機・産業車両タイヤのトップブランドを有するスウェーデンのTrelleborg Wheel Systems Holding社(TWS)を買収することで、農機向けタイヤでは世界トップメーカーに昇り詰めました。農機や建機は舗装されていない道で稼働しており、これらの機械に搭載されるタイヤは「Off-Highway Tire(OHT)」と呼ばれます。OHTは消費財と比較して高い市場成長性が期待され、多品種少量生産かつ製造の複雑さを背景に高い参入障壁を誇ります。
2024年7月には、新たに米国のタイヤメーカーであるThe Goodyear Tire & Rubber社から鉱山・建機向けタイヤ事業を買収する契約の締結を発表し、OHT業界での市場シェアをより一層盤石なものとする戦略を強化している点も高く評価しています。
一方で、乗用車タイヤ主要市場での販売減速が観測される中、メキシコと中国で立て続けに大規模な成長投資の計画を発表した同社の株価は7月以降下落基調にあり、PBR(株価純資産倍率)は一時0.5倍程度の水準となりました。当月前半に開示された2024年度第2四半期決算では、株式市場でのタイヤ市場減速懸念をよそに、通期計画の上方修正を発表する好調な業績を示しました。同時に、現行の中期経営計画最終年度である2026年度の事業利益目標も上方修正しており、力強いメッセージを受け、株価指標は回復に転じています。
当ファンドでは、中期経営計画の中の柱の一つである、抜本的な製造コストダウンを目指す「1年工場」というコンセプトに注目しています。成長投資による規模の拡大だけでなく、投資リターンの刈取り時期や蓋然性といった“質”を並行して高めるべく、ものづくりのあり方を根本から見直すという挑戦的な取り組みとして大いに期待しています。同社はタイヤ業界随一の成長志向企業であり、戦略的投資へのキャピタルアロケーションを重視していることから、同業他社と比較して、株主還元の比重は決して高くありません。裏を返せば、競争が激化する市場の中で、それだけ有望な投資案件を豊富に抱えている稀な企業であるとも言えます。当ファンドは、従前から対話を通じ、同社の経営陣の資本収益性に対する強いコミットメントを確認しており、成長戦略の追及こそが企業価値向上への最短ルートであると強く共感しています。
同社のPBRは現在も1倍を下回る状態が続いており、市場からは株主資本コストを上回るROE(株主資本利益率)を持続的に達成することが難しいとの評価を受けていることが推察されます。厳しいタイヤ市場の中でも際立った成果を実現すべく、投資リターンの刈取りを着実に積み重ねようとする同社の経営姿勢は、山石CEO就任の2017年以降の実績からして、信頼できるものだと考えています。当ファンドはパートナー株主として、同社の持続可能な成長力についての市場からの理解浸透、具体的には期待ROEとPER(株価収益率)の向上をサポートするため、腰を据えて対話を続けていきたいと思います。
今後の運⽤⽅針
当ファンドでは潜在価値の高い企業に選別して集中投資を行い、長期的なリターンを追求しています。潜在価値の高い企業とは、スパークスの投資アプローチである3つの着眼点(経営者の質・企業収益の質・市場の成長性)に照らし、企業の実態価値や成長性が株式市場で十分に評価されていないと考えられる企業を指します。
日本には強固な事業基盤を有していながら、事業戦略や資本配分、株式市場への向き合い方に改善余地があることから株価が実態価値よりも低く評価されている企業が数多く存在します。当ファンドはパートナー株主として、投資先企業との中長期的な関係構築と丁寧な対話に努め、課題の改善を促すことで、企業価値の顕在化を積極的に後押しします。
※当ファンドは企業オーナーとして短期業績や株価変動に惑わされない⻑期保有を前提としています。投資先企業と共に企業価値向上を⽬指すとの考えから、短期的に株式を売買する投資家と区別する為、「パートナー株主」との⽂⾔を使⽤しています。
2024年7月の運用コメント
株式市場の状況
2024年7月、日本株式市場の代表指数であるTOPIX(配当込み)は前月末比0.54%下落し、日経平均株価は前月末比1.22%下落しました。
当月の日本株式市場はボラティリティの大きい相場展開となりました。月前半は、前月からの好調な流れを引き継ぎ堅調に推移しました。米国の雇用統計で労働需給の逼迫が緩和される兆しが見られ、FRB(米連邦準備制度理事会)の年内利下げ観測が高まったことで、長期金利が低下し、米国のハイテク株が上昇しました。日本でも半導体関連銘柄が相場を支え、日経平均株価は連日で史上最高値を更新し、11日には4万2,000円台に到達しました。しかしながら米国消費者物価指数が想定以上に軟化し、米国ハイテク株に利益確定売りが入ったことやドル円が円高方向に振れたことなどから、日本株式市場は下落に転じました。そして月後半に入ると下げが一層加速しました。トランプ氏が大統領選で優勢と伝わると、米中対立の深刻化やドル高是正などの自国優位政策が懸念され、半導体関連株に売りが膨らみ、日本株にも影響が及びました。さらに日銀の追加利上げやFRBの利下げ観測から「円キャリー取引」の巻き戻しが発生し、ドル円は一時151円台を付け、日本株式市場も幅広く売りが広がり、日経平均株価は3万8,000円を割り込む水準まで大幅に下落しました。
31日に日銀は金融政策決定会合で政策金利を0.25%程度に引き上げることを決定し、国債買い入れの減額計画も明らかにしました。また、米国政府が対中国の半導体輸出規制で日本などを除外すると報じられると、半導体関連株が反発し日本株式市場は下げ幅を縮小して当月の取引を終えました。
ファンドの運⽤状況
当月、当ファンドのパフォーマンスは、前⽉末⽐0.96%の下落となり、参考指数であるTOPIX(配当込み)の同0.54%の下落を0.42%下回りました。
当ファンドのパフォーマンスにプラスに寄与した企業は、森永製菓、全国保証、三菱重工業などでした。⼀⽅、マイナスに影響した企業は、ルネサスエレクトロニクス、メック、東洋炭素などでした。
当ファンドでは、企業経営者が誠実であり、高い競争優位性を有する企業の中から、更なる成長余地のある潜在価値の高い企業に長期集中投資を行い、企業との対話を通じて価値の顕在化を図ることを基本戦略とします。
日本には、高い技術力・開発力を持ち、ニッチ市場でグローバルに高いシェアやブランド力を持つ企業が多く存在します。そうした企業の中には、基礎的な収益力が高く、中長期的な成長余地が大きいにも関わらず、「玉に瑕(きず)」があるために株式市場で実態価値を正当に評価されていない企業があります。
当ファンドでは、そのような企業の長期的なパートナー株主※として、良好な関係を築きながら粘り強く対話を行っています。企業の事業戦略や資本配分、IR体制などの改善を促すことで、企業の実態価値の顕在化に努め、株価上昇のカタリスト(きっかけ)の一つとなることを目指します。
当レポートでは、投資先企業に対する投資見解や対話の進捗などをご報告させていただきます。
当月は、当ファンドの投資先である「全国保証」に対する投資見解、対話内容をご説明します。
全国保証は、国内唯一の独立系住宅ローン保証会社です。住宅ローン保証事業とは、住宅ローンの借入人から保証料等をもらう代わりに、連帯保証人となる事業を言います。住宅ローンの借入人が返済を出来なくなった場合、保証会社である同社が金融機関に住宅ローンを弁済し、金融機関に代わって借入人から住宅ローンを回収する、もしくは住宅ローンの担保物件(住宅・土地等)を売却して弁済資金を回収する事業モデルです。住宅ローン保証は金融機関の子会社保証会社が提供するのが一般的ですが、同社は金融機関に属さない国内唯一の独立系企業であり、全国のどの金融機関の住宅ローン保証でも引き受けが可能です。また、40年以上のローン審査のデータの蓄積から、延滞リスクの低い顧客に保証を行うため、代位弁済に関わるコストは限定的であり、営業利益率が約8割に上る非常に収益性の高いビジネスとなっています。
同社は1981年に厚生年金転貸住宅融資の保証業務を担う目的で設立されましたが、業容転換のために1997年から民間金融機関向け住宅ローンの保証業務に参入します。当時、大手金融機関は子会社の保証会社を使っていたため、全国保証は、信金・信組など、中堅・中小金融機関への保証業務に注力し成長してきました。中堅・中小金融機関への保証業務の提供を通じて、同社は与信能力や審査時間の短縮化などサービス品質を磨き上げてきました。今日では、同社はその強みを活かし、メガバンクを含む多数の金融機関に住宅ローン保証を提供しています。
同社の保証残高は1998年の1兆円から2024年3月末には17.6兆円まで増加しています。特にリーマンショック以降大きく増大し、民間住宅ローン残高に占める同社シェアも2024年3月末で8.9%まで上昇してきました。その背景には、同社のサービス品質の高さに加えて、銀行に対するリスク規制強化に伴い、住宅ローン保証リスクを銀行グループから隔離したいニーズの高まりがあります。
当ファンドでは、同社の業績拡大が持続すると考えています。上記理由から、銀行子会社によるローン保証から、独立系の同社へのシフトが続くことが想定されます。同社は現在、金融機関に対し、保証子会社の買収など、多様なスキームによる保証債務の引き受けを提案しており、今後も継続的に残高シェアを上げていくことができると思われます。
また、同社の株価は、企業の実態価値を反映できていないと思われます。課題は主に2点あり、①事業の安全性に対する理解を株式市場から十分に得られていないこと、②成長投資や株主還元といった資本政策に大きな改善余地があること、であると当ファンドでは考えています。これらの課題について当ファンドはこれまで青木社長と何度も面談を実施し、議論を重ねてきました。2023年3月に発表された新中期経営計画では、「住宅ローンプラットフォーマー」としてリスクを抑えながら更なる事業成長が可能なことや、成長投資・株主還元などに余剰資本を積極活用していく方針が示されました。2024年3月期の通期決算説明では、配当性向の引き上げに加え、同社初となる自社株買いの発表をし、株主還元への積極的な姿勢も見られました。
当ファンドでは引き続き、同社の企業価値が株式市場で顕在化する一助となれるよう、経営陣との対話を継続していく方針です。
今後の運⽤⽅針
当ファンドでは潜在価値の高い企業に選別して集中投資を行い、長期的なリターンを追求しています。潜在価値の高い企業とは、スパークスの投資アプローチである3つの着眼点(経営者の質・企業収益の質・市場の成長性)に照らし、企業の実態価値や成長性が株式市場で十分に評価されていないと考えられる企業を指します。
日本には強固な事業基盤を有していながら、事業戦略や資本配分、株式市場への向き合い方に改善余地があることから株価が実態価値よりも低く評価されている企業が数多く存在します。当ファンドはパートナー株主として、投資先企業との中長期的な関係構築と丁寧な対話に努め、課題の改善を促すことで、企業価値の顕在化を積極的に後押しします。
※当ファンドは企業オーナーとして短期業績や株価変動に惑わされない⻑期保有を前提としています。投資先企業と共に企業価値向上を⽬指すとの考えから、短期的に株式を売買する投資家と区別する為、「パートナー株主」との⽂⾔を使⽤しています。
2024年6月の運用コメント
株式市場の状況
2024年6月、日本株式市場の代表指数であるTOPIX(配当込み)は前月末比1.45%上昇し、日経平均株価も前月末比2.85%上昇しました。
当月の日本株式市場は、日米の金融政策の動向に注目が集まるなかレンジ内でもみ合いの推移となった後、円安の進行とともに月末にかけて上昇しました。月前半は、米国金融政策の動向を巡り米国マクロ経済指標に注目が集まるなか、雇用・物価関連指標等の結果を受けインフレ鈍化の見方が支持され、目先のFRB(米連邦準備制度理事会)の利下げ観測の高まりから米国長期金利が大幅に低下し、米国株式市場は半導体・ハイテク株中心に上昇しました。この流れを受けて、日本株式市場も上昇しました。月半ばには、日銀金融政策決定会合で、日銀が国債買い入れ減額の方針を固めたものの、具体策については公表が見送られ、円安の進行とともに日本株式市場は上昇しました。その後は、会合後の記者会見にて日銀総裁より買い入れ減額規模について「相応の規模になる」との発言があったことや、7月の会合で利上げを行う可能性も否定しない主旨の発言があったこと、また、フランス政治不安が改めて意識され下落した欧州市場の影響などいくつかの材料が出るなか、日本株式市場は下落する場面がありましたが、月後半にかけて株価は持ち直しました。月後半は、ドル円レートが一時161円台まで下落し、1986年12月以来およそ37年ぶりの安値を更新しました。円安が支えとなったほか、日本長期金利の上昇を受けた銀行株などの上昇も相場をけん引し、月末にかけては配当金の再投資の観測もあるなかで日本株式市場は前月末対比で上昇し、当月の取引を終えました。
ファンドの運⽤状況
当月、当ファンドのパフォーマンスは、前⽉末⽐3.68%の上昇となり、参考指数であるTOPIX(配当込み)の同1.45%の上昇を2.23%上回りました。
当ファンドのパフォーマンスにプラスに寄与した企業は、三菱重工業、テレビ東京ホールディングス、全国保証などでした。⼀⽅、マイナスに影響した企業は、横浜ゴム、ホシザキ、京成電鉄などでした。
当ファンドでは、企業経営者が誠実であり、高い競争優位性を有する企業の中から、更なる成長余地のある潜在価値の高い企業に長期集中投資を行い、企業との対話を通じて価値の顕在化を図ることを基本戦略とします。
日本には、高い技術力・開発力を持ち、ニッチ市場でグローバルに高いシェアやブランド力を持つ企業が多く存在します。そうした企業の中には、基礎的な収益力が高く、中長期的な成長余地が大きいにも関わらず、「玉に瑕(きず)」があるために株式市場で実態価値を正当に評価されていない企業があります。
当ファンドでは、そのような企業の長期的なパートナー株主※として、良好な関係を築きながら粘り強く対話を行っています。企業の事業戦略や資本配分、IR体制などの改善を促すことで、企業の実態価値の顕在化に努め、株価上昇のカタリスト(きっかけ)の一つとなることを目指します。
当レポートでは、投資先企業に対する投資見解や対話の進捗などをご報告させていただきます。
当月は、当ファンドの投資先である「森永製菓」に対する投資見解、対話内容をご説明します。
森永製菓は1899年創業の大手菓子メーカーです。米国で菓子製造技術を学んだ創業者森永太一郎氏が、「日本の人々にもおいしく栄養価の高い西洋菓子を食べてもらいたい」という想いをもって日本の菓子産業の礎を築いたのが同社の始まりです。今では菓子だけでなく、アイス、「inゼリー」に代表されるゼリー飲料、通販など、製品・事業の幅を広げ、日本だけでなく海外に積極的に展開しています。
当ファンドが注目しているのは、MORINAGAブランドの海外での成長です。特に米国では「HI-CHEW(ハイチュウ)」の売上が著しい成長をみせています。メジャーリーガーの間でHI-CHEWブームが起こったことをきっかけに、ソフトな食感とフルーツのおいしさを合わせた商品特性が評判となり、米国小売大手ウォールマート等も取り扱うようになりました。2024年3月期の米国売上高はHI-CHEW以外の商品も含め191億円に達し、足元も順調に成長が続いています。先日発表された新中期経営計画の中で、HI-CHEWの更なる拡大とともに米国版inゼリーである「Chargel(チャージェル)」の導入促進が打ち出されました。そして2030年に向けては、米国だけでなく欧州・アジア等にも事業拡大し、海外売上高750億円を目標とする計画も同時に発表されています。同社は、生産体制の拡充など積極的な海外投資を行う姿勢を示しており、当ファンドは引き続き海外での事業成長を期待しています。
一方で、本業ともいえる国内菓子事業は、低い収益性が課題となっています。原材料価格高騰の影響を価格改定・コスト改善で跳ね返そうと努力しているものの、2024年3月期の営業利益率は5.1%に留まりました。当ファンドでは、この国内菓子事業の在り方について同社と何度も議論してきました。議論の中で同社の太田社長は、「総合菓子屋」としての看板を下ろすことなく、老朽化した製造ラインの廃止を通じた商品の選択と集中により、事業の生産性向上に努める意思を示していました。実際に新中期経営計画では、商品価値強化を図りつつも「段階的なアセットライト」を進め、同社の基盤事業として持続的成長および投下資本利益率(ROIC)向上を目指すことが謳われました。当ファンドでは、対話の成果が徐々に顕在化し始めていると評価しています。売上高の大きい国内菓子事業の収益性改善は同社の企業価値向上に不可欠となるため、構造改革の進捗を見守りながら今後も対話を続けてまいります。
最後に、同社が合理的な資本政策の実行に舵を切り始めていることにも当ファンドは注目しております。当ファンドでは従来から、ROE(株主資本利益率)の改善についても同社と議論を重ねてきました。同社はROE目標を、2026年に12%以上、2030年に15%以上と明示しましたが、事業成長と収益性改善を追求しながら資本を適切な水準に保ち続ける必要があります。先日開催された株主総会の場で、株主還元の強化を太田社長が力を込めて説明していましたが、当ファンドはパートナー株主として、対話を通じて同社のROE改善の取り組みをサポートしてまいります。
今後の運⽤⽅針
当ファンドでは潜在価値の高い企業に選別して集中投資を行い、長期的なリターンを追求しています。潜在価値の高い企業とは、スパークスの投資アプローチである3つの着眼点(経営者の質・企業収益の質・市場の成長性)に照らし、企業の実態価値や成長性が株式市場で十分に評価されていないと考えられる企業を指します。
日本には強固な事業基盤を有していながら、事業戦略や資本配分、株式市場への向き合い方に改善余地があることから株価が実態価値よりも低く評価されている企業が数多く存在します。当ファンドはパートナー株主として、投資先企業との中長期的な関係構築と丁寧な対話に努め、課題の改善を促すことで、企業価値の顕在化を積極的に後押しします。
※当ファンドは企業オーナーとして短期業績や株価変動に惑わされない⻑期保有を前提としています。投資先企業と共に企業価値向上を⽬指すとの考えから、短期的に株式を売買する投資家と区別する為、「パートナー株主」との⽂⾔を使⽤しています。
2024年5月の運用コメント
株式市場の状況
2024年5月、日本株式市場の代表指数であるTOPIX(配当込み)は前月末比1.16%上昇し、日経平均株価も前月末比で0.21%上昇しました。
当月の日本株式市場は、月前半は4月の米国雇用者数が市場予想を下回り、米利下げ観測が強まったことから日米株式市場ともに上昇しましたが、日銀の金融政策正常化観測などから上値が抑えられました。月半ばには米消費者物価指数や米小売売上高など予想を下回る指標が発表され、金融引き締めの長期化への懸念が後退しました。その結果、米国の主要3株価指数が史上最高値を更新し、日経平均株価も一時39,000円を回復しました。さらに、NVIDIA社(米国)が市場予想を上回る好決算を発表し、半導体株が軒並み上昇して相場を支えました。月後半は、米景気の底堅さを背景とする利下げ動向への懸念や、日銀総裁の追加金融引き締めを示唆する講演が再び注目されて日米長期金利の上昇により株価が下落しましたが、最終的には金利上昇がひとまず一服したとの見方が買い戻しにつながり、前月末を上回る水準で月を終えました。
ファンドの運⽤状況
当月、当ファンドのパフォーマンスは、前⽉末⽐0.25%の上昇となり、参考指数であるTOPIX(配当込み)の同1.16%の上昇を0.91%下回りました。
当ファンドのパフォーマンスにプラスに寄与した企業は、リクルートホールディングス、ルネサスエレクトロニクス、三井住友フィナンシャルグループなどでした。⼀⽅、マイナスに影響した企業は、東洋炭素、ダイフク、フジミインコーポレーテッドなどでした。
当ファンドでは、企業経営者が誠実であり、高い競争優位性を有する企業の中から、更なる成長余地のある潜在価値の高い企業に長期集中投資を行い、企業との対話を通じて価値の顕在化を図ることを基本戦略とします。
日本には、高い技術力・開発力を持ち、ニッチ市場でグローバルに高いシェアやブランド力を持つ企業が多く存在します。そうした企業の中には、基礎的な収益力が高く、中長期的な成長余地が大きいにも関わらず、「玉に瑕(きず)」があるために株式市場で実態価値を正当に評価されていない企業があります。
当ファンドでは、そのような企業の長期的なパートナー株主※として、良好な関係を築きながら粘り強く対話を行っています。企業の事業戦略や資本配分、IR体制などの改善を促すことで、企業の実態価値の顕在化に努め、株価上昇のカタリスト(きっかけ)の一つとなることを目指します。
当レポートでは、投資先企業に対する投資見解や対話の進捗などをご報告させていただきます。
当月は、当ファンドの投資先である「三菱重工業」に対する投資見解、対話内容をご説明します。
当ファンドは同社が掲げているエネルギーの供給と需要の両面のグリーン転換「エナジートランジション戦略」に注目し、投資を行っています。同社は「リアリティのあるエナジートランジション」を重視し、エネルギーの供給と消費の両面のグリーン転換を成長の柱に掲げています。当月は、2024年度から2026年度までの3か年を対象期間とする同社の2024事業計画(24事計)について、ご説明させていただきます。
2021年度から2023年度を対象期間とした2021事業計画(21事計)は、新型コロナウイルスの影響に伴う民間航空機需要の急減や、脱化石燃料のトレンドによる新設石炭火力の大幅な縮小という逆風の中、危機対応のために半年前倒しで策定されました。21事計は次期事計期間での飛躍に向けて、収益力の回復・強化に主眼が置かれた内容でした。拠点再編や事業譲渡による固定費抑制や、経済再開による中量産品の需要回復を捉えることで、一過性費用を除くと、2023年度には2020年10月発表の当初計画2,800億円を大きく上回る事業利益を達成しました。また、外部環境が不透明な中でも、水素・アンモニア、CO2回収やデータセンターといった新規領域への成長投資を継続した経営姿勢を当ファンドは高く評価しております。
24事計のテーマは“事業成長と収益力の更なる強化の両立”であり、成長性の側面がより強調された計画となっております。この3か年で成長を牽引するのは、ガスタービンと原子力のエネルギー関連製品と防衛事業です。ロシアとウクライナの紛争勃発によるエネルギー資源価格の高騰を経験して以降、国家安全保障と気候変動対応の両立のためにも、信頼性が高く、CO2排出量の低いベースロード電源の需要が世界的に高まっています。
また、最近では電力を大量に使用するデータセンターや半導体工場の新規建設計画が、世界各地で進んでおり、電力需要の見通しは上向き傾向にあることも、ガスタービンや原子力等の安定電源への追い風となっています。世界トップシェアを誇る同社のガスタービンは、高性能・高信頼性・将来的な水素混焼への転換のオプションを武器に更なるシェア拡大が期待されます。既に21事計の最終年度である2023年度には、当該3事業の合計で3兆円を超える受注高が計上されております。
事業化を推進する成長領域では、発電・インフラ関連と親和性の高いCO2回収や水素・アンモニアバリューチェーンの構築に向けて、大きく先行投資を行います。グループ総合力を活かした事業開発体制の強化のために、2024年4月1日付で組織再編を行い、「GXセグメント」という事業部門を設立しています。また、先述のデータセンター領域においても、蓄電システムやターボ冷凍機などデータセンターの安定運用に必要な製品群をワンストップで供給することで、独自の事業機会の獲得を目指します。
当ファンドでは、三菱重工業は、今後ますます増える世界のエネルギー需要とネットゼロ目標の両立という「理想」と「現実」のギャップを満たす解決策を提供し、長期にわたって中心的な役割を担う企業であると考えています。しかし、当月前半の2023年度通期決算発表と当月末の事業計画発表の翌日には、株価は両日とも下落しました。成長投資の積極化による費用増や事業ポートフォリオ改革による収益性の底上げについて、具体的な言及がなされなかったことが市場の期待を下回ったものと思われます。一方、当ファンドでは、CO2回収や水素バリューチェーンへの投資は24事計期間以降の持続的な成長のために必須のものと考えており、費用が先行する中でも事業利益率を8%以上の水準に改善させるという経営目標をポジティブに捉えております。成長を担う重点領域以外の事業群については、生産拠点・販売網の最適化による事業構成の最適化との説明があることから、具体的な改善施策の検討が進んでいると当ファンドでは推察しております。
当ファンドは長期的なパートナー株主として、株式市場から見過ごされている同社の企業価値拡大のドライバーや、事業計画の理解促進を意識したコミュニケーション方法について、根気強く対話を継続していきます。
今後の運⽤⽅針
当ファンドでは潜在価値の高い企業に選別して集中投資を行い、長期的なリターンを追求しています。潜在価値の高い企業とは、スパークスの投資アプローチである3つの着眼点(経営者の質・企業収益の質・市場の成長性)に照らし、企業の実態価値や成長性が株式市場で十分に評価されていないと考えられる企業を指します。
日本には強固な事業基盤を有していながら、事業戦略や資本配分、株式市場への向き合い方に改善余地があることから株価が実態価値よりも低く評価されている企業が数多く存在します。当ファンドはパートナー株主として、投資先企業との中長期的な関係構築と丁寧な対話に努め、課題の改善を促すことで、企業価値の顕在化を積極的に後押しします。
※当ファンドは企業オーナーとして短期業績や株価変動に惑わされない⻑期保有を前提としています。投資先企業と共に企業価値向上を⽬指すとの考えから、短期的に株式を売買する投資家と区別する為、「パートナー株主」との⽂⾔を使⽤しています。
2024年4月の運用コメント
株式市場の状況
2024年4月、日本株式市場の代表指数であるTOPIX(配当込み)は前月末比0.91%下落し、日経平均株価は前月末比4.86%の大幅下落となりました。
月前半は利益確定売りや、⽶連邦準備制度理事会(FRB)高官の年内利下げ先送り示唆に伴い米長期金利上昇が懸念され、米国株式市場の下落を招き、日本株式市場は上値を抑えられました。月半ばには米CPI(消費者物価指数)の市場予想を超える上昇や半導体関連企業の大幅下落、また中東情勢の悪化などから日経平均株価は一時37,000円を割り込みました。月後半には中東情勢の落ち着きから買い戻しの動きが見られ、日経平均株価は38,000円台を回復しました。26日まで開かれた日銀金融政策決定会合では緩和的な金融政策の維持が決定され、日本が祝日だった29日にドル円相場は一時160円台へ急伸し約34年ぶりの高値を更新しました。しかしながら、その後一転して154円台まで大きく円高に振れ、市場では政府による為替介入が行われたとの観測が広がりました。
ファンドの運⽤状況
当月、当ファンドのパフォーマンスは、前⽉末⽐0.97%の下落となり、参考指数であるTOPIX(配当込み)の同0.91%の下落を0.06%下回りました。
当ファンドのパフォーマンスにプラスに寄与した企業は、シップヘルスケアホールディングス、マックス、横浜ゴムなどでした。⼀⽅、マイナスに影響した企業は、SHOEI、ダイフク、東洋炭素などでした。
当ファンドでは、企業経営者が誠実であり、高い競争優位性を有する企業の中から、更なる成長余地のある潜在価値の高い企業に長期集中投資を行い、企業との対話を通じて価値の顕在化を図ることを基本戦略とします。
日本には、高い技術力・開発力を持ち、ニッチ市場でグローバルに高いシェアやブランド力を持つ企業が多く存在します。そうした企業の中には、基礎的な収益力が高く、中長期的な成長余地が大きいにも関わらず、「玉に瑕(きず)」があるために株式市場で実態価値を正当に評価されていない企業があります。
当ファンドでは、そのような企業の長期的なパートナー株主※として、良好な関係を築きながら粘り強く対話を行っています。企業の事業戦略や資本配分、IR体制などの改善を促すことで、企業の実態価値の顕在化に努め、株価上昇のカタリスト(きっかけ)の一つとなることを目指します。
当レポートでは、投資先企業に対する投資見解や対話の進捗などをご報告させていただきます。
当月は、当ファンドの投資先である「パイロットコーポレーション」に対する投資見解、対話内容をご説明します。
パイロットコーポレーションは、日本で高い知名度を持ちますが、世界的にも有名な大手筆記具メーカーです。筆記具メーカーのシェアとしては、Newell Brands社(米国)が世界首位ですが、パイロットコーポレーションは傘下に「PARKER」や「WATERMAN」といった複数のブランドを持っており、単⼀ブランドでは「パイロット」が世界トップクラスのシェアを誇ります。同社は⽇本初の純国産万年筆の製造を⽬指して、1918年に創業しました。その後万年筆の開発に成功すると、1920年代には海外への輸出を開始し、着実に売上を伸ばし続けてきました。その結果、世界190か国以上の国と地域で同社の筆記具が展開され、同社のヒット商品である消えるボールペン「フリクションシリーズ」は日本だけでなく、欧州を中心として海外でも愛用されるなど、現在は海外売上比率が7割を超えています。
当ファンドは、同社が長年培ってきた技術力とブランド力に加え、各地域に根差したマーケティング力と商品開発力、安定供給を可能にする製造・販売体制といった強みが、今後も同社の収益性と市場シェアを高めていくと考えています。とりわけ新興国では、中長期的には中間層の増加・進学率の上昇に伴い、同社の高品質な筆記具の浸透が進んでいくことに期待しています。
一方、当ファンドは同社のIR体制や資本政策に課題があると考え、これまで経営陣と対話をしてまいりました。同社は過去、株式市場に対する情報開示を最低限に絞っていたため、投資家からの注目度が低く、本来の企業価値が株価に反映されていなかったと当ファンドでは考えておりました。そのような中、同社にとって初めてとなる決算説明会が2024年2月に開催されました。多くの機関投資家が出席し、事業成長性や財務戦略に関する活発な質疑応答が交わされました。今回の決算説明会開催をきっかけに、同社と株式市場との対話が活性化され、同社の魅力が市場に広がっていくと考えております。
また、決算説明会の質疑で一部の投資家から資本効率に関する指摘を受けておりますが、同社はバランスシートに現預金を約400億円抱えております。この現預金を有効活用することでROE(株主資本利益率)の改善が期待でき、同社は2024年度の成長戦略として海外拠点開設を含む130億円規模の設備投資を計画しております。しかしながら同社の収益構造を鑑みると、中期的には現預金の比率は高まっていくため、さらなる資本効率改善のためには、株主還元の強化も含めたキャッシュアロケーションの検討が必要であると当ファンドは考えており、引き続き対話を通じて積極的に働きかけていく方針です。
今後の運⽤⽅針
当ファンドでは潜在価値の高い企業に選別して集中投資を行い、長期的なリターンを追求しています。潜在価値の高い企業とは、スパークスの投資アプローチである3つの着眼点(経営者の質・企業収益の質・市場の成長性)に照らし、企業の実態価値や成長性が株式市場で十分に評価されていないと考えられる企業を指します。
日本には強固な事業基盤を有していながら、事業戦略や資本配分、株式市場への向き合い方に改善余地があることから株価が実態価値よりも低く評価されている企業が数多く存在します。当ファンドはパートナー株主として、投資先企業との中長期的な関係構築と丁寧な対話に努め、課題の改善を促すことで、企業価値の顕在化を積極的に後押しします。
※当ファンドは企業オーナーとして短期業績や株価変動に惑わされない⻑期保有を前提としています。投資先企業と共に企業価値向上を⽬指すとの考えから、短期的に株式を売買する投資家と区別する為、「パートナー株主」との⽂⾔を使⽤しています。
2024年3月の運用コメント
株式市場の状況
2024年3月、日本株式市場の代表指数であるTOPIX(配当込み)は前月末比4.44%上昇し、日経平均株価は前月末比3.07%の上昇となりました。
当月の日本株式市場は、月前半は前月から引き続き半導体関連銘柄の上昇などが相場をけん引し、日経平均は史上初となる4万円台に到達するなど堅調な推移となりましたが、月半ばにかけては米国半導体関連銘柄が下落した影響や、日銀のマイナス金利政策解除を示唆する報道、春季労使交渉(春闘)での高い賃上げ実現への期待の高まりなどから日銀の金融政策正常化への思惑が広がって円高が進行したことなどが重しとなり、下落しました。月後半にかけては、日銀が金融政策決定会合でマイナス金利政策の解除や長短金利操作の撤廃、上場投資信託(ETF)の買い入れ終了などを決定したものの、当面は緩和的な金融環境が継続するとの見通しが示されたことなどを受けて円安進行とともに上昇し、最終的に前月末を上回る水準で取引を終えました。
ファンドの運⽤状況
当月、当ファンドのパフォーマンスは、前⽉末⽐3.51%の上昇となり、参考指数であるTOPIX(配当込み)の同4.44%の上昇を0.93%下回りました。
当ファンドのパフォーマンスにプラスに寄与した企業は、三菱重工業、東洋炭素、リクルートホールディングスなどでした。⼀⽅、マイナスに影響した企業は、京成電鉄、MARUWAなどでした。
当ファンドでは、企業経営者が誠実であり、高い競争優位性を有する企業の中から、更なる成長余地のある潜在価値の高い企業に長期集中投資を行い、企業との対話を通じて価値の顕在化を図ることを基本戦略とします。
日本には、高い技術力・開発力を持ち、ニッチ市場でグローバルに高いシェアやブランド力を持つ企業が多く存在します。そうした企業の中には、基礎的な収益力が高く、中長期的な成長余地が大きいにも関わらず、「玉に瑕(きず)」があるために株式市場で実態価値を正当に評価されていない企業があります。
当ファンドでは、そのような企業の長期的なパートナー株主※として、良好な関係を築きながら粘り強く対話を行っています。企業の事業戦略や資本配分、IR体制などの改善を促すことで、企業の実態価値の顕在化に努め、株価上昇のカタリスト(きっかけ)の一つとなることを目指します。
当レポートでは、投資先企業に対する投資見解や対話の進捗などをご報告させて頂きます。
当月は、当ファンドの投資先である「ダイフク」に対する投資見解、対話内容をご説明します。
ダイフクは、物流や製造現場で材料や製品などを運搬するマテリアルハンドリングシステムを提供する企業です。同社は、「モノを効率的に保管、搬送、仕分け・ピッキングする」機械設備およびそれらを制御するソフトウェアを組み合わせ、システムを構築することで、顧客の物流業務において重労働や反復作業の軽減に貢献しています。同社は1937年に「㈱坂口機械製作所」として発足し、船舶の蒸気機関や航空機製造用の鍛圧機械を製造しました。1947年には当時の生産拠点であった大阪、福知山から「大福機工㈱」に社名を変更しております。その後、荷役搬送機などを製造し、1950年代にはトヨタ自動車工業㈱へ自動車製造用コンベヤシステムを、1966年には松下電器産業㈱(現パナソニックホールディングス)へ日本初の自動倉庫を、1982年にはファナック㈱に無人搬送車のFA(ファクトリーオートメーション)システムを納入し、1984年には半導体ウエハの自動搬送装置を開発するなど、様々な領域で日本の製造・物流現場の自動化・量産化を支えてきました。また同1984年には現在の「ダイフク」に社名を変更、その後次々に海外法人を設立し、グローバル展開を加速させております。
このような経緯から、同社のビジネス領域は、製造業・流通業向けのイントラロジスティクス事業、半導体業界向けのクリーンルーム事業、自動車業界向けのオートモーティブ事業、空港施設向けのエアポート事業など多岐にわたっています。同社は、顧客のマテリアルハンドリングの企画・コンサルティングから設計・製造・アフターサービスまで一貫してサポート対応できることで、顧客から長期にわたる信頼を得てきたと考えられます。また、ハードからソフトまで主要製品のすべてを内製化することで品質の高い製品を短納期で提供し、かつ価格競争力を高めていると考えられます。このような高品質な製品・サービスを、グローバルに展開し、日本・北米・中国・アジアなどの地域で今後ますます高まる省人化ニーズに応え続けています。
当ファンドでは、同社の今後の成長には、シェア拡大等による競争環境の緩和とブランド活用による単価上昇が有効であると考えます。同社の高い製品品質と顧客サポート体制に裏打ちされた製品・サービスには、値上げの余地があると考えられ、同社も2024年3月期の第3四半期決算説明会では価格転嫁の進展を報告しております。一方で同社の過去の営業利益率は概ね9%台で推移してきました。長期にわたりグローバルにトップの売上を維持していながら利益率が横ばいとなっていた背景としては、競争環境の厳しさが影響していると考えられます。同社の対象とする事業領域は、上場・非上場含む複数の競合企業が混在し、常に価格競争に晒されております。同社のシェア成長には製品・サービスのさらなる品質向上やM&A等の可能性があると考えており、どのような施策が有効か、今後経営陣と対話を深めたいと考えております。また、同社は四半期ごとに営業利益率の変動が大きくなる傾向があります。市場の同社への安心感が高まるよう、IR開示を強化することが同社の評価をさらに高められると当ファンドでは考えており、引き続き対話を続けて参ります。
今後の運⽤⽅針
当ファンドでは潜在価値の高い企業に選別して集中投資を行い、長期的なリターンを追求しています。潜在価値の高い企業とは、スパークスの投資アプローチである3つの着眼点(経営者の質・企業収益の質・市場の成長性)に照らし、企業の実態価値や成長性が株式市場で十分に評価されていないと考えられる企業を指します。
日本には強固な事業基盤を有していながら、事業戦略や資本配分、株式市場への向き合い方に改善余地があることから株価が実態価値よりも低く評価されている企業が数多く存在します。当ファンドはパートナー株主として、投資先企業との中長期的な関係構築と丁寧な対話に努め、課題の改善を促すことで、企業価値の顕在化を積極的に後押しします。
※当ファンドは企業オーナーとして短期業績や株価変動に惑わされない⻑期保有を前提としています。投資先企業と共に企業価値向上を⽬指すとの考えから、短期的に株式を売買する投資家と区別する為、「パートナー株主」との⽂⾔を使⽤しています。
2024年2月の運用コメント
株式市場の状況
2024年2月、日本株式市場の代表指数であるTOPIX(配当込み)は前月末比4.93%上昇し、日経平均株価は前月末比7.94%の大幅上昇となりました。
当月の日本株式市場は、月前半はFOMC(⽶連邦公開市場委員会)の内容を受け早期の米利下げ期待が後退し一進一退の動きで推移しましたが、月半ばから後半にかけては内田日銀副総裁がマイナス金利解除後も日銀は緩和的な金融環境を維持するとの認識を示したことや、生成AI(人工知能)向け半導体需要の増加が期待される米国で半導体関連企業の株価上昇が続き、日本の半導体関連企業にも資金が集中したことから、続伸しました。22日には日経平均株価は39,098.68円で終え、約34年ぶりに最高値を更新しました。その後の日本株式市場の推移は緩やかだったものの、月末まで日経平均株価は3万9,000円台を維持したまま当月の取引を終えました。
ファンドの運⽤状況
当月、当ファンドのパフォーマンスは、前⽉末⽐4.82%の上昇となり、参考指数であるTOPIX(配当込み)の同4.93%の上昇を0.11%下回りました。
当ファンドのパフォーマンスにプラスに寄与した企業は、東洋炭素、三菱重工業、ダイフクなどでした。⼀⽅、マイナスに影響した企業は、森永製菓、ホシザキ、テレビ東京ホールディングスなどでした。
当ファンドでは、企業経営者が誠実であり、高い競争優位性を有する企業の中から、更なる成長余地のある潜在価値の高い企業に長期集中投資を行い、企業との対話を通じて価値の顕在化を図ることを基本戦略とします。
日本には、高い技術力・開発力を持ち、ニッチ市場でグローバルに高いシェアやブランド力を持つ企業が多く存在します。そうした企業の中には、基礎的な収益力が高く、中長期的な成長余地が大きいにも関わらず、「玉に瑕(きず)」があるために株式市場で実態価値を正当に評価されていない企業があります。
当ファンドでは、そのような企業の長期的なパートナー株主※として、良好な関係を築きながら粘り強く対話を行っています。企業の事業戦略や資本配分、IR体制などの改善を促すことで、企業の実態価値の顕在化に努め、株価上昇のカタリスト(きっかけ)の一つとなることを目指します。
当レポートでは、投資先企業に対する投資見解や対話の進捗などをご報告させて頂きます。
当月は、当ファンドの投資先である「ルネサスエレクトロニクス」に対する投資見解、対話内容をご説明します。
ルネサスエレクトロニクスは、半導体を製造・販売する企業です。同社は、㈱日立製作所・三菱電機㈱の半導体事業とNECエレクトロニクス㈱の統合により、2010年に設立されました。世界トップシェアを有するマイコンを基軸として、2017年以降は海外の同業他社を買収することにより、成長市場であるデータセンターやスマートデバイス向けの製品・顧客ラインナップを拡大し、成長してきました。
同社は、2023年5月に開催されたアナリストやメディア向け戦略説明会「Capital Market Day」において、2030年までに時価総額を当時の6倍まで成長させるとのビジョンを示しました。業績を2倍に、株価バリュエーションを3倍に拡大することが、目標への道筋となっています。特にバリュエーション拡大の文脈で強調されたのは、業績のダウンサイクル局面でもしっかりとマージンを確保することでした。同社は2018年から2019年にかけての半導体市場の下降局面において、大きく収益性を低下させました。この期間においてマージン低下を最小限に抑えられた競合他社とバリュエーションで差がついておりました。当ファンドでは、業績への信頼感がバリュエーションのギャップに繋がったと考えています。2019年以降、同社は製造の外注比率を高めることで、固定費水準を引き下げてきました。2023年12月期決算は、前年比2.1%の減収となったものの、売上総利益率は前年比0.1pt減と、2019年の逆風下と比較して、高いレジリエンスを示す結果となりました。
また同社は、2024年2月には米国のプリント基板(PCB)の設計ソフトウェア企業であるAltium社を約8,879億円で買収することを発表しました。同社はバリュエーションのもう一段の拡大に向けたキャピタルアロケーション方針の中で、M&Aによる製品ポートフォリオの充実を掲げています。アナログ半導体の同業他社を対象とした過去の大型M&Aでは、上手くシナジーを発現し、素晴らしい実績を残した同社ですが、ソフトウェア企業の買収は初の試みとなります。
なお同社は、2023年6月に社内のPCB設計開発ツールをAltium社のものに統一し、自社エンジニアが検証済みの基板デザインをAltium社のプラットフォーム上で公開するというパートナーシップを結んでいます。
同社の顧客は、電子機器のデザインが益々複雑化する中でも、迅速に市場への製品投入をする必要があり、リソースのひっ迫に直面しています。そのため、設計から、デバイス選択、動作のシミュレーションまで、クラウド上で効率的なデザインを可能にするAltium社のプラットフォームは、同社との協業を一層深めることで、より大きな付加価値をもたらすサービスとなることが期待されます。
一方、同社は買収が完了した後も、Altium社は独立での事業運営を継続すると説明しています。そのため、短期的な財務シナジーもAltium社の最終利益が加わることによるEPS(1株当たり利益)の増加に限られる見込みです。過去のDialog Semiconductor社(英国)やIntegrated Device Technology社(米国)のM&Aプロセスでは、買収後の経営統合プロセスによる定量的なシナジーが語られましたが、今回は定性的な説明に留まりました。これまでと異なる成長戦略の不透明感から、発表当日に株価は約2.5%下落しました。当ファンドでは、“To Make Our Lives Easier”というパーパスに基づき、電子機器設計への参画の容易にし、イノベーションを促進するという同社の壮大なビジョンを高く評価しています。ただし、Altium社は同社によって子会社化された後も、オープンなプラットフォームとして顧客から受け入れられるのかなど、いくつか課題が散見されると当ファンドでは認識しており、資本市場の不安を払しょくすべく、継続的なフォローアップを求めております。当ファンドはパートナー株主として、引き続き同社の企業価値向上に向けた対話を粘り強く続けてまいります。
今後の運⽤⽅針
当ファンドでは潜在価値の高い企業に選別して集中投資を行い、長期的なリターンを追求しています。潜在価値の高い企業とは、スパークスの投資アプローチである3つの着眼点(経営者の質・企業収益の質・市場の成長性)に照らし、企業の実態価値や成長性が株式市場で十分に評価されていないと考えられる企業を指します。
日本には強固な事業基盤を有していながら、事業戦略や資本配分、株式市場への向き合い方に改善余地があることから株価が実態価値よりも低く評価されている企業が数多く存在します。当ファンドはパートナー株主として、投資先企業との中長期的な関係構築と丁寧な対話に努め、課題の改善を促すことで、企業価値の顕在化を積極的に後押しします。
※当ファンドは企業オーナーとして短期業績や株価変動に惑わされない⻑期保有を前提としています。投資先企業と共に企業価値向上を⽬指すとの考えから、短期的に株式を売買する投資家と区別する為、「パートナー株主」との⽂⾔を使⽤しています。
2024年1月の運用コメント
株式市場の状況
2024年1⽉、⽇本株式市場の代表指数であるTOPIX(配当込み)は前⽉末⽐7.81%の上昇となりました。
当⽉の⽇本株式市場は、能登半島地震の影響精査のため⽇銀が利上げを⾒送るとの⾒⽅が⾼まったことや、⽶連邦準備制度理事会(FRB)⾼官のタカ派な発⾔を受けた⽶⻑期⾦利の上昇を背景に円安が進み、⽉前半は⼤きく上昇しました。また、新NISA制度の開始による個⼈投資家の買い需要や、東京証券取引所の市場改⾰への期待感から海外投資家の資⾦も多く流⼊しました。⽉半ばから後半にかけては、利益確定の売り圧⼒や、⽶国半導体⼤⼿の業績⾒通しが市場予想を下回ったことから半導体関連銘柄を中⼼に⼀時下落基調に転じる場⾯もあったものの、最終的に前⽉末を上回る⽔準で⽉を終えました。
ファンドの運⽤状況
2024年1⽉、当ファンドのパフォーマンスは前⽉末⽐3.86%の上昇となりました。
当⽉、当ファンドの保有上位銘柄でパフォーマンスにプラスに寄与した企業は、三菱重⼯業、任天堂などでした。重⼯業メーカーの三菱重⼯業は、⽉後半に決算発表を⾏った競合の⽶国重⼯業メーカーが2024年の発電機器事業に対して安定成⻑の⾒通しを⽰し、同社の先⾏きにも安⼼感が⾼まったことから株価が上昇したものと思われます。ゲームメーカーの任天堂は、有⼒タイトルの映画化によるコンテンツ収⼊拡⼤への期待感継続に加え、2024年内の次世代ゲーム機発売の可能性を⽶国有⼒メディアが報道したことを受け、株価が上昇したと思われます。⼀⽅、マイナスに影響した企業は、リクルートホールディングスなどでした。⼈材サービス企業のリクルートホールディングスは、⽉半ばに決算を発表した国内競合企業が、求⼈広告市場の悪化を理由に業績の下⽅修正を⾏ったことから、同社の主⼒事業である国内⼈材マッチングサービスへの業績懸念が広まり、株価は調整したものと思われます。
当ファンドでは、企業経営者が誠実であり、⾼い競争優位性を有する企業の中から、更なる成⻑余地のある潜在価値の⾼い企業に⻑期集中投資を⾏い、企業との対話を通じて価値の顕在化を図ることを基本戦略とします。
⽇本には、⾼い技術⼒・開発⼒を持ち、ニッチ市場でグローバルに⾼いシェアやブランド⼒を持つ企業が多く存在します。そうした企業の中には、基礎的な収益⼒が⾼く、中⻑期的な成⻑余地が⼤きいにも関わらず、「⽟に瑕(きず)」があるために株式市場で実態価値を正当に評価されていない企業があります。
当ファンドでは、そのような企業の⻑期的なパートナー株主※として、良好な関係を築きながら粘り強く対話を⾏っています。企業の事業戦略や資本配分、IR体制などの改善を促すことで、企業の実態価値の顕在化に努め、株価上昇のカタリスト(きっかけ)の⼀つとなることを⽬指します。
当レポートでは、投資先企業に対する投資⾒解や対話の進捗などをご報告させて頂きます。
当⽉は、当ファンドの投資先である「SHOEI」に対する投資⾒解、対話内容をご説明します。
SHOEIは、バイク⽤の⾼級ヘルメットを製造・販売している企業です。同社は1959年に設⽴され、その卓越した製品デザインや機能性、品質の⾼さからグローバルに多くのファンを抱えています。販売網は⽇本、欧⽶、中国など世界60か国以上を網羅し、ほとんど全ての国と地域でシェアNo.1を獲得し、世界のプレミアムヘルメット(⾼い安全性・機能性・デザイン性を兼ね揃えたヘルメット)市場で約60%のトップシェアを誇ります。
同社は設計、開発、製造を⼀貫して⽇本国内で展開しており、製造プロセスのほとんどは⾃動化されていますが、機械では代替できない⾮常に精巧な作業は現在でも⼈の⼿で⾏われています。そして同社は「カイゼン企業」を標榜しており、⽣産効率の向上を常に推進しています。同社の競争⼒の源泉はまさにこの「現場⼒」にあると当ファンドでは考えています。⻑年にわたって蓄積されたノウハウと⼈材を育成する企業⾵⼟が、今後もSHOEIブランドへの信頼性を⾼めていくことを期待しています。
こうした⾼いブランド⼒と商品開発⼒を武器にグローバルに販売数量を伸ばしながら、デザイン性・機能性に優れた新製品の投⼊を戦略的に⾏うことで、価格を引き上げることに成功しています。価格が上がったとしても、SHOEIのヘルメットを欲しいと考える消費者が増えていることに他なりません。このブランド価値とカイゼン⽂化を背景として、同社の事業は⾮常に⾼い収益性を誇っており、2023年9⽉期には営業利益率29.2%に到達しました。
⼀⽅、⾜元は欧州・中国を中⼼とした景況悪化等により、同社公表の2024年9⽉期の営業利益は減益予想となっています。1⽉後半に発表された2024年9⽉期第1四半期決算では、前年同期⽐で増収・増益を確保したものの、同社は先⾏きに対して慎重な⾒⽅を崩していません。しかし同社も⼿をこまねている訳ではなく、海外現地での需要動向調査・マーケティングの拡充や、⽣産能⼒拡⼤に向けた⼯場⽤地の確保など、積極的かつ着実に対応を進めています。当ファンドでは同社の中⻑期的な事業成⻑に対する⾒⽅に変更はありませんが、個別⾯談を通じて注意深くフォローアップして参ります。
また、当ファンドは同社の資本政策に改善の余地があると考えています。同社は直近数年の⼤幅な事業成⻑により多くのキャッシュを稼ぎ、2023年9⽉末時点で総資産の約45%を現預⾦が占める状況となっています。同社は配当性向50%を基本とした株主還元を⾏っていますが、資本の蓄積スピードが早く、ROE(株主資本利益率)には下押し要因となっています。設備や⼈への投資を実施した後の余剰資⾦を今後どのように活⽤していくか、同社からは発信がありません。この点について当ファンドはCEO・CFOとの個別⾯談を通じて対話を継続しています。経営陣は⻑期的な事業継続のために財務健全性を確保したいと主張していますが、保守的すぎる財務運営によって株主の利益であるROEが低下していく可能性があり、当ファンドは懸念を伝えています。また、同の株主総会に出席した際には、複数の個⼈株主からも同様の懸念が表明されていることを確認しました。同社の資本政策に対する株式市場の⽬が厳しくなっていると考えられることから、当ファンドは⻑期的なパートナー株主として、引き続き同社の企業価値向上に向けた対話を粘り強く続けて参ります。
今後の運⽤⽅針
当ファンドでは潜在価値の⾼い企業に選別して集中投資を⾏い、⻑期的なリターンを追求しています。潜在価値の⾼い企業とは、スパークスの投資アプローチである3つの着眼点(経営者の質・企業収益の質・市場の成⻑性)に照らし、企業の実態価値や成⻑性が株式市場で⼗分に評価されていないと考えられる企業を指します。
⽇本には強固な事業基盤を有していながら、事業戦略や資本配分、株式市場への向き合い⽅に改善余地があることから株価が実態価値よりも低く評価されている企業が数多く存在します。当ファンドはパートナー株主として、投資先企業との中⻑期的な関係構築と丁寧な対話に努め、課題の改善を促すことで、企業価値の顕在化を積極的に後押しします。
※当ファンドは企業オーナーとして短期業績や株価変動に惑わされない⻑期保有を前提としています。投資先企業と共に企業価値向上を⽬指すとの考えから、短期的に株式を売買する投資家と区別する為、「パートナー株主」との⽂⾔を使⽤しています。
2023年12月の運用コメント
株式市場の状況
2023年12⽉、⽇本株式市場の代表指数であるTOPIX(配当込み)は前⽉末⽐0.23%の下落となりました。
当⽉の⽇本株式市場は、⽉前半は⽇銀の植⽥総裁と氷⾒野副総裁両名の発⾔を受けて⾦融政策修正の思惑が⾼まったことや、FOMC(⽶連邦公開市場委員会)のハト派の内容を受けて⽶⻑期⾦利が低下したことで、円⾼が進み下落しました。⽉後半は、⽇銀⾦融政策決定会合における⾦融緩和維持の決定が好感される場⾯もありましたが、年末の閑散相場もあって円⾼基調が継続する展開が重しとなり、最終的に前⽉末を下回る⽔準で⽉を終えました。
ファンドの運用状況
2023年12⽉、当ファンドのパフォーマンスは前⽉末⽐2.15%の上昇となりました。
当⽉、当ファンドの保有上位銘柄でパフォーマンスにプラスに寄与した企業は、全国保証、京成電鉄などでした。住宅ローン保証会社の全国保証は、2024年3⽉期第2四半期決算を発表し、新規保証実⾏が件数・⾦額ともに堅調に推移していることが好感され、株価上昇が継続しているものと思われます。成⽥空港と都⼼部を繋ぐ京成電鉄は、インバウンドの堅調な回復や資本効率の改善への期待から株価が上昇したものと思われます。
⼀⽅、マイナスに影響した企業は、SHOEIなどでした。バイクヘルメットメーカーのSHOEIは、2023年9⽉期通期決算で、営業利益が会社計画未達となったことや、2024年9⽉期の営業減益予想が嫌気され、株価の下落が継続しているものと思われます。
当ファンドでは、企業経営者が誠実であり、⾼い競争優位性を有する企業の中から、更なる成⻑余地のある潜在価値の⾼い企業に⻑期集中投資を⾏い、企業との対話を通じて価値の顕在化を図ることを基本戦略とします。
⽇本には、⾼い技術⼒・開発⼒を持ち、ニッチ市場でグローバルに⾼いシェアやブランド⼒を持つ企業が多く存在します。そうした企業の中には、基礎的な収益⼒が⾼く、中⻑期的な成⻑余地が⼤きいにも関わらず、「⽟に瑕(きず)」があるために株式市場で実態価値を正当に評価されていない企業があります。
当ファンドでは、そのような企業の⻑期的なパートナー株主※として、良好な関係を築きながら粘り強く対話を⾏っています。企業の事業戦略や資本配分、IR体制などの改善を促すことで、企業の実態価値の顕在化に努め、株価上昇のカタリスト(きっかけ)の⼀つとなることを⽬指します。
当レポートでは、投資先企業に対する投資⾒解や対話の進捗などをご報告させて頂きます。
当⽉は、当ファンドの投資先である「京成電鉄」に対する投資⾒解、対話内容をご紹介します。
京成電鉄は、東京都東部・千葉県を中⼼に営業路線を有する私鉄です。中でも京成上野駅と成⽥空港駅間を結ぶ京成本線、成⽥スカイアクセス線が収益の柱となっています。また、東京ディズニーリゾートの運営会社である㈱オリエンタルランドの創業時からの株主であり、現在も㈱オリエンタルランドの22.15%を有する筆頭株主でもあります。
当ファンドでは、訪⽇旅⾏者の拡⼤に伴う空港輸送需要の増加と、同社が保有する㈱オリエンタルランドの株式価値が適正に評価される可能性に注⽬し、投資しています。
同社は短期的には訪⽇旅⾏者の回復による業績改善が期待できるとともに、⽇本が観光⽴国を⽬指す中で中⻑期的な業績拡⼤が期待できると考えます。⽇本政府は現在、2030年に年間6,000万⼈の訪⽇旅⾏者を⽬指すビジョンを掲げています。その過程で、成⽥空港では現在3本⽬のC滑⾛路を新設するとともにB滑⾛路を延伸する計画が進んでおり、将来的な空港利⽤客は⼤幅に増加すると考えられます。同社は成⽥空港機能強化に伴う中⻑期的な輸送需要増への対応として、プロジェクト推進部を設置するなど組織体制を強化しており、⻑期にわたって同社収益にプラスが続くと当ファンドでは期待しています。
更に当ファンドでは、同社が保有する㈱オリエンタルランドの株式価値が今後適正に評価される可能性にも注⽬しています。同社は㈱オリエンタルランドが運営する東京ディズニーリゾートの創業に携わった会社の⼀つとして知られています。⻑年保有している㈱オリエンタルランドの株式を時価評価すれば実質的なPBR(株価純資産倍率)は1倍を下回る状況であり、株価は同社の企業価値に対して割安と考えます。⼀⽅、同社が保有する㈱オリエンタルランドの株式は有効活⽤される可能性が低い、⾔わば「開かない貯⾦箱」であり、株式市場から適切に評価されてこなかった可能性があると当ファンドは考えています。当ファンドでは、今後の成⻑戦略について議論を進める中で、保有する㈱オリエンタルランドの株式の価値が顕在化されるよう、対話を進めてまいりました。
2023年10⽉、同社に対し英ファンドから、㈱オリエンタルランドの株式が時価評価されるべく、現状の保有⽐率22.15%から、持分法が適⽤外となる15%未満になるまで売却することを主旨とする提案が公表されました。この提案に対し、同社としては、保有を継続する意向を⽰しております。当ファンドとしては同社の⼤きな⻑期成⻑ビジョンを描くべく、ひいては同社の資産を含めた価値が顕在化されるべく、引き続き対話を継続していく⽅針です。
今後の運用方針
当ファンドでは潜在価値の⾼い企業に選別して集中投資を⾏い、⻑期的なリターンを追求しています。潜在価値の⾼い企業とは、スパークスの投資アプローチである3つの着眼点(経営者の質・企業収益の質・市場の成⻑性)に照らし、企業の実態価値や成⻑性が株式市場で⼗分に評価されていないと考えられる企業を指します。
⽇本には強固な事業基盤を有していながら、事業戦略や資本配分、株式市場への向き合い⽅に改善余地があることから株価が実態価値よりも低く評価されている企業が数多く存在します。当ファンドはパートナー株主として、投資先企業との中⻑期的な関係構築と丁寧な対話に努め、課題の改善を促すことで、企業価値の顕在化を積極的に後押しします。
※当ファンドは企業オーナーとして短期業績や株価変動に惑わされない⻑期保有を前提としています。投資先企業と共に企業価値向上を⽬指すとの考えから、短期的に株式を売買する投資家と区別する為、「パートナー株主」との⽂⾔を使⽤しています。
2023年11月の運用コメント
株式市場の状況
2023年11⽉、⽇本株式市場の代表指数であるTOPIX(配当込み)は前⽉末⽐5.42%の上昇となりました。
当⽉の⽇本株式市場は、⽉前半はFOMC(⽶連邦公開市場委員会)での政策⾦利の据え置きや、市場予想を下回る⽶雇⽤統計を受けての⽶⻑期⾦利の低下を背景に上昇しました。⽉半ばは、⽇本企業の良好な決算や、市場予想を下回る⽶国のCPI(消費者物価指数)を受けた⽶追加利上げ観測の後退などから、⽉中⾼値をつけました。⽉後半に⼊ると、中東情勢の地政学リスクの後退や⽶⻑期⾦利低下等を好材料に上昇した後、⼀時1ドル=146円台後半まで進⾏した円⾼が重しとなって下落基調に転じましたが、最終的に前⽉末を上回る⽔準で⽉を終えました。
ファンドの運用状況
2023年11⽉、当ファンドのパフォーマンスは前⽉末⽐3.59%の上昇となりました。
当⽉、当ファンドの保有上位銘柄でパフォーマンスにプラスに寄与した企業は、リクルートホールディングス、MARUWAなどでした。⼈材関連サービスを提供するリクルートホールディングスは、⽶アクティビストファンドによる同社株式の取得により、企業変⾰への要求が強まるとの思惑から株価が上昇したものと思われます。セラミック部品メーカーのMARUWAは、⽣成AI関連の需要拡⼤が期待されたものと思われます。
⼀⽅、マイナスに影響した企業は、ナカニシなどでした。⻭科医療⽤機器メーカーのナカニシは、買収した⽶国デンタルチェアメーカーの業績悪化で通期計画の下⽅修正を発表し、株価は調整したものと思われます。
当ファンドでは、企業経営者が誠実であり、⾼い競争優位性を有する企業の中から、更なる成⻑余地のある潜在価値の⾼い企業に⻑期集中投資を⾏い、企業との対話を通じて価値の顕在化を図ることを基本戦略とします。
⽇本には、⾼い技術⼒・開発⼒を持ち、ニッチ市場でグローバルに⾼いシェアやブランド⼒を持つ企業が多く存在します。そうした企業の中には、基礎的な収益⼒が⾼く、中⻑期的な成⻑余地が⼤きいにも関わらず、「⽟に瑕(きず)」があるために株式市場で実態価値を正当に評価されていない企業があります。
当ファンドでは、そのような企業の⻑期的なパートナー株主※として、良好な関係を築きながら粘り強く対話を⾏っています。企業の事業戦略や資本配分、IR体制などの改善を促すことで、企業の実態価値の顕在化に努め、株価上昇のカタリスト(きっかけ)の⼀つとなることを⽬指します。
当レポートでは、投資先企業に対する投資⾒解や対話の進捗などをご報告させて頂きます。
当⽉は、当ファンドの投資先である「ナカニシ」に対する投資⾒解、対話内容をご紹介します。
ナカニシは、⻭科治療⽤ハンドピース(ドリル)などを⼿掛ける⻭科医療⽤機器メーカーです。現社⻑の祖⽗が1930年に創業し、第⼆次世界⼤戦下の混乱を経て、1951年に現本社がある栃⽊県⿅沼市で再興しました。独⾃技術を活⽤し、現在は⻭科向けのみならず、外科医療や機械⼯業向けに⾼品質で利便性の⾼い製品を提供しています。また、同社は早い時期から海外市場の開拓に取り組み、今⽇では世界135ヵ国以上で同社製品が販売され、約8割の海外売上⾼⽐率(2023年12⽉期第3四半期時点)を誇ります。
同社の強みは、1分間で45万回転を実現する「超⾼速回転技術」、1秒間に3万往復振動する「超⾳波技術」、超低速域から⾼速域まで安定したトルク(回転⼒)と滑らかさを実現する「マイクロモータ技術」の3つのコア技術に集約された「削るテクノロジー」にあります。これらの独⾃技術をもとに、約85%の部品を内製化していることが差別化となり、⾼い収益性を実現しています。
同社の⼿掛ける⻭科・外科向け医療機器に対する需要は、健康寿命に対する世界的な意識の⾼まりを背景に、安定的に伸びることが期待されます。当ファンドでは、特に北⽶市場でのシェア拡⼤が同社の成⻑を牽引すると考えます。⾜元では、買収した⽶国デンタルチェア企業の業績悪化に伴う通期予想下⽅修正が発表され株価は下落しましたが、本業の⻭科機器については、北⽶の⻭科医の間でNSKブランド(同社の⾃社ブランド名)が本格的に認知され始めており、中⻑期的な成⻑期待は引き続き⾼いと考えられます。
⼀⽅、同社は過去から内部留保を積み上げた結果、株主資本⽐率は8割を超過し、約30%という⾼い営業利益率に⽐して、ROE(株主資本利益率)は14.4%に留まっています(2022年度通期業績)。そうした中で、同社経営陣がROE改善へ向けた取り組みに着⼿し始めたことに当ファンドは期待しています。2022年8⽉に発表した新たな中期経営計画の中で、「PL経営から資本効率も重視した経営へ進化」することが謳われ、総還元性向50%を中期的な基準とすることなどが発表されました。ROE⽬標は2025年12⽉期で11%と保守的な印象を受けるものの、同社が資本効率指標を定量的に明⽰したことは評価できます。今後、過度な内部留保によりROEが劣化することを回避すべく、当ファンドも対話を通じて資本効率の改善を積極的に後押ししていく⽅針です。
また、当ファンドは同社が企業価値向上のためにプライム市場へ移⾏することを期待しています。同社が属するスタンダード市場が上場企業としての最低限のガバナンス⽔準を求めているのに対して、プライム市場は企業がより⾼いガバナンスの質を備え、投資家と建設的に対話し、共に企業価値向上を追求する場として期待されています。プライム市場ではなくスタンダード市場を選ぶという判断が取られたことは株主として残念ですが、当ファンドは引き続きプライム市場への移⾏についても同社と粘り強く対話を続けていきます。
今後の運用方針
当ファンドでは潜在価値の⾼い企業に選別して集中投資を⾏い、⻑期的なリターンを追求しています。潜在価値の⾼い企業とは、スパークスの投資アプローチである3つの着眼点(経営者の質・企業収益の質・市場の成⻑性)に照らし、企業の実態価値や成⻑性が株式市場で⼗分に評価されていないと考えられる企業を指します。
⽇本には強固な事業基盤を有していながら、事業戦略や資本配分、株式市場への向き合い⽅に改善余地があることから株価が実態価値よりも低く評価されている企業が数多く存在します。当ファンドはパートナー株主として、投資先企業との中⻑期的な関係構築と丁寧な対話に努め、課題の改善を促すことで、企業価値の顕在化を積極的に後押しします。
※当ファンドは企業オーナーとして短期業績や株価変動に惑わされない⻑期保有を前提としています。投資先企業と共に企業価値向上を⽬指すとの考えから、短期的に株式を売買する投資家と区別する為、「パートナー株主」との⽂⾔を使⽤しています。
2023年10月の運用コメント
株式市場の状況
2023年10⽉、⽇本株式市場の代表指数であるTOPIX(配当込み)は前⽉末⽐2.99%の下落となりました。
当⽉の⽇本株式市場は、⽉前半は堅調な⽶雇⽤統計を受けての⽶⻑期⾦利の変動や、中東情勢の緊迫化などを受け乱⾼下の展開となりました。⽉後半に⼊ると、中国の景気刺激策が好感される場⾯があったものの、⽇銀の政策再修正への思惑や⽶テクノロジー企業の低調な決算への失望が株式市場の重しとなり、最終的に前⽉末を下回る⽔準で⽉を終えました。
ファンドの運用状況
2023年10⽉、当ファンドのパフォーマンスは前⽉末⽐2.57%の下落となりました。
当⽉、当ファンドの保有上位銘柄でパフォーマンスにプラスに寄与した企業は、MARUWAなどでした。⼀⽅、マイナスに影響した企業は、三菱重⼯業などでした。
MARUWAは、当⽉後半に発表された2024年3⽉期第2四半期決算で、前年同期⽐減収減益の着地となったものの、先⾏きに対して楽観的な⾒通しが⽰されたことが好感され、株価は上昇したものと思われます。三菱重⼯業は、⽶国製航空機エンジンの品質問題を受けて、業績影響に対する不透明感が強まり、株価の下⽅圧⼒となったものと思われます。
当ファンドでは、企業経営者が誠実であり、⾼い競争優位性を有する企業の中から、更なる成⻑余地のある潜在価値の⾼い企業に⻑期集中投資を⾏い、企業との対話を通じて価値の顕在化を図ることを基本戦略とします。
⽇本には、⾼い技術⼒・開発⼒を持ち、ニッチ市場でグローバルに⾼いシェアやブランド⼒を持つ企業が多く存在します。そうした企業の中には、基礎的な収益⼒が⾼く、中⻑期的な成⻑余地が⼤きいにも関わらず、「⽟に瑕(きず)」があるために株式市場で実態価値を正当に評価されていない企業があります。
当ファンドでは、そのような企業の⻑期的なパートナー株主※として、良好な関係を築きながら粘り強く対話を⾏っています。企業の事業戦略や資本配分、IR体制などの改善を促すことで、企業の実態価値の顕在化に努め、株価上昇のカタリスト(きっかけ)の⼀つとなることを⽬指します。
当レポートでは、投資先企業に対する投資⾒解や対話の進捗などをご報告させて頂きます。
当⽉は、当ファンドの投資先である「全国保証」に対する投資⾒解、対話内容をご紹介します。
全国保証は、国内唯⼀の独⽴系住宅ローン保証会社です。住宅ローン保証事業とは、住宅ローンの借⼊⼈から保証料等をもらう代わりに、連帯保証⼈となる事業を⾔います。住宅ローンの借⼊⼈が返済を出来なくなった場合、保証会社である同社が⾦融機関に住宅ローンを弁済し、⾦融機関に代わって借⼊⼈から住宅ローンを回収する、もしくは住宅ローンの担保物件(住宅・⼟地等)を売却して弁済資⾦を回収する事業モデルです。住宅ローン保証は⾦融機関の⼦会社保証会社が提供するのが⼀般的ですが、同社は⾦融機関に属さない国内唯⼀の独⽴系企業であり、全国のどの⾦融機関の住宅ローン保証でも引き受けが可能です。また、40年以上のローン審査のデータの蓄積を活かし、延滞リスクの低い顧客に保証を⾏うため、代位弁済に関わるコストは限定的であり、営業利益率が約8割に上る⾮常に収益性の⾼いビジネスとなっています。
同社は1981年に厚⽣年⾦転貸住宅融資の保証業務を担う⽬的で設⽴されましたが、業容転換のために1997年から⺠間⾦融機関向け住宅ローンの保証業務に参⼊します。当時、⼤⼿⾦融機関は⼦会社の保証会社のみを使っていたため、全国保証は、信⾦・信組など、中堅・中⼩⾦融機関への保証業務に注⼒し成⻑してきました。中堅・中⼩⾦融機関への保証業務の提供を通じて、同社は与信能⼒や審査時間の短縮化などサービス品質を磨き上げて来ました。今⽇では、同社はその強みを活かし、メガバンクを含む多数の⾦融機関に住宅ローン保証を提供しています。
同社の保証債務残⾼は1998年の1兆円から2023年3⽉末には15.9兆円まで増加しています。特にリーマンショック以降⼤きく増⼤し、⺠間住宅ローン残⾼に占める同社シェアも2023年3⽉末で8.3%まで上昇してきました。その背景には、同社のサービス品質の⾼さに加えて、銀⾏に対するリスク規制強化に伴い、住宅ローン保証リスクを銀⾏グループから隔離したいニーズの⾼まりがあります。
当ファンドでは、同社の業績拡⼤が持続すると考えています。前述の理由から、銀⾏⼦会社によるローン保証から、独⽴系の同社へのシフトが続くことが想定されます。加えて、銀⾏の保証⼦会社の買収や、他社の保証債務の引き受けなどを通じ、残⾼シェアを上げていくことができると思われます。当ファンドでは特に保証⼦会社の買収に注⽬しています。2023年には主要先進国では⻑期⾦利が上昇し、⾦融機関は利ざやを稼ぎやすい環境になりつつあります。⼀⽅、⽇本では依然として⾦融緩和状態が続いていることに加え、銀⾏間の住宅ローンの貸出競争も激しいままです。このような環境では、銀⾏の住宅ローン実⾏によるリターンに対し、⼦会社の住宅ローン保証のリスクをとる合理性は少なくなっていると思われます。こうした背景から銀⾏が同社に保証⼦会社を売却する動きに当ファンドは注⽬しています。
また、同社の株価は、企業の実態価値を反映できていないと思われます。課題は主に2点あり、①事業の安全性に対する理解を株式市場から⼗分に得られていないこと、②成⻑投資や株主還元といった資本政策に⼤きな改善余地があること、であると当ファンドでは考えています。これらの課題についてスパークスはこれまで⻘⽊社⻑と何度も⾯談を実施し、議論を重ねてきました。2023年3⽉に発表された新中期経営計画では、「住宅ローンプラットフォーマー」としてリスクを抑えながら更なる事業成⻑が可能なことや、成⻑投資・株主還元などに余剰資本を積極活⽤していく⽅針が⽰されました。当ファンドでは引き続き、同社の企業価値が株式市場で顕在化する⼀助となれるよう、経営陣との対話を継続していく⽅針です。
今後の運用方針
当ファンドでは潜在価値の⾼い企業に選別して集中投資を⾏い、⻑期的なリターンを追求しています。潜在価値の⾼い企業とは、スパークスの投資アプローチである3つの着眼点(経営者の質・企業収益の質・市場の成⻑性)に照らし、企業の実態価値や成⻑性が株式市場で⼗分に評価されていないと考えられる企業を指します。
⽇本には強固な事業基盤を有していながら、事業戦略や資本配分、株式市場への向き合い⽅に改善余地があることから株価が実態価値よりも低く評価されている企業が数多く存在します。当ファンドはパートナー株主として、投資先企業との中⻑期的な関係構築と丁寧な対話に努め、課題の改善を促すことで、企業価値の顕在化を積極的に後押しします。
※当ファンドは企業オーナーとして短期業績や株価変動に惑わされない⻑期保有を前提としています。投資先企業と共に企業価値向上を⽬指すとの考えから、短期的に株式を売買する投資家と区別する為、「パートナー株主」との⽂⾔を使⽤しています。
2023年9月の運用コメント
株式市場の状況
2023年9⽉、⽇本株式市場の代表指数であるTOPIX(配当込み)は前⽉末⽐0.51%の上昇となりました。
当⽉の⽇本株式市場は、⽉前半は中国製造業購買担当者景気指数(PMI)の改善により中国の景気後退不安が⼀時的に後退したほか、国内では早期衆院解散・総選挙への期待感が⾼まったことを受け、上昇基調となりました。⼀⽅⽉後半は、FOMC(⽶連邦公開市場委員会)で⾦融引き締めの⻑期化が⽰唆されたことや、⽶議会の予算協議が難航し政府機関閉鎖への警戒感が⾼まったことから、市場⼼理が悪化し値を戻す展開となり、最終的に前⽉末を若⼲上回る⽔準で⽉を終えました。
ファンドの運用状況
2023年9⽉、当ファンドのパフォーマンスは前⽉末⽐2.32%の下落となりました。
当⽉、当ファンドの保有上位銘柄でパフォーマンスにプラスに寄与した企業は、パイロットコーポレーションなどでした。⼀⽅、マイナスに影響した企業は、MARUWAなどでした。パイロットコーポレーションは、外部環境の不透明感が強い中でも、主要市場である⽇本と⽶州では底堅い業績を⽰しており、堅調な需要継続が期待されたことが好感されたものと思われます。MARUWAは、半導体やEV(電気⾃動⾞)などテクノロジー関連の需要回復に時間を要するとの懸念が市場全体に広がり、株価の調整に繋がったと思われます。
当ファンドでは、企業経営者が誠実であり、⾼い競争優位性を有する企業の中から、更なる成⻑余地のある潜在価値の⾼い企業に⻑期集中投資を⾏い、企業との対話を通じて価値の顕在化を図ることを基本戦略とします。
⽇本には、⾼い技術⼒・開発⼒を持ち、ニッチ市場でグローバルに⾼いシェアやブランド⼒を持つ企業が多く存在します。そうした企業の中には、基礎的な収益⼒が⾼く、中⻑期的な成⻑余地が⼤きいにも関わらず、「⽟に瑕(きず)」があるために株式市場で実態価値を正当に評価されていない企業があります。
当ファンドでは、そのような企業の⻑期的なパートナー株主※として、良好な関係を築きながら粘り強く対話を⾏っています。企業の事業戦略や資本配分、IR体制などの改善を促すことで、企業の実態価値の顕在化に努め、株価上昇のカタリスト(きっかけ)の⼀つとなることを⽬指します。
当レポートでは、投資先企業に対する投資⾒解や対話の進捗などをご報告させて頂きます。
当⽉は、当ファンドの投資先である「三菱重⼯業」に対する投資⾒解、対話内容をご紹介します。
前⽉は、同社の成⻑戦略であるエネルギーの供給と需要の両⾯のグリーン転換「エナジートランジション戦略」の具体例として、エネルギー供給の脱炭素化を推進するエナジー事業についてご紹介させて頂きました。当⽉は、エネルギーの需要側である社会インフラの脱炭素化を牽引する、物流・冷熱・ドライブシステム事業についてご説明します。
三菱重⼯業の物流・冷熱・ドライブシステム事業は、主にフォークリフトなどの物流機器、冷熱製品、エンジン・ターボチャージャから構成されています。この事業セグメントは、ガスタービンのような受注⽣産品と⽐較して、製品の出荷数量が多いことから中量産品事業とも呼ばれます。フォークリフト事業は、ニチユ三菱フォークリフト㈱とユニキャリア㈱が統合して発⾜した三菱ロジスネクスト㈱が運営しており、eコマース(電⼦商取引)市場拡⼤による物流機器の需要増⼤の恩恵を受けて成⻑してきました。冷熱機器は冷凍冷蔵倉庫や⼤型空調機器などの業務⽤冷熱機器が、エンジン・ターボチャージャは⾮常⽤発電装置とガソリン⾞向けの⾞両⽤過給機が、それぞれ主⼒製品になっています。ターボチャージャは⾃動⾞の電動化による市場縮⼩が予想されますが、冷熱機器はデータセンター向けという新市場を開拓することで、成⻑機会を捉えることが出来ています。eコマース物流、コールドチェーン(⽣産・輸送・消費の過程で途切れることなく低温に保つ物流⽅式)、データセンターなど、同社の中量産品の対⾯市場は現代の社会インフラであり、消費電⼒が⼤きく、安定的な運⽤が求められる点が共通しています。
当ファンドは、カーボンニュートラルの達成のためには、エネルギーの川上にある発電インフラの脱炭素化に加えて、川下の製品群で効率的な電⼒利⽤を⾏うことは必須であると認識しており、多⾓的な事業ポートフォリオを保有する三菱重⼯業は、脱炭素に向けた広範な設備投資の恩恵を受けることの出来る貴重な企業であると考えています。
⼀⽅で、多⾓化した事業ポートフォリオの複雑さゆえ、株式市場において企業価値が低く評価されるコングロマリットディスカウントの議論はつきものですが、当ファンドでは、エネルギーの供給から消費まで⼀貫して関わることが可能な同社の事業ポートフォリオは、単⼀プロダクトでは難しい、事業間シナジーを創出できると考えています。当ファンドは、同社の価値創造の基盤である技術資産・顧客資産・⼈的資本などの無形資産に関する議論を深め、それらが今後どのようにして持続的な価値を⽣むのか、適切にコミュニケーションするための対話を⾏っています。将来的には、コングロマリット“ディスカウント”から“プレミアム”への転換を⽬指して、今後もエンゲージメントを継続していきます。
今後の運用方針
当ファンドでは潜在価値の⾼い企業に選別して集中投資を⾏い、⻑期的なリターンを追求しています。潜在価値の⾼い企業とは、スパークスの投資アプローチである3つの着眼点(経営者の質・企業収益の質・市場の成⻑性)に照らし、企業の実態価値や成⻑性が株式市場で⼗分に評価されていないと考えられる企業を指します。
⽇本には強固な事業基盤を有していながら、事業戦略や資本配分、株式市場への向き合い⽅に改善余地があることから株価が実態価値よりも低く評価されている企業が数多く存在します。当ファンドはパートナー株主として、投資先企業との中⻑期的な関係構築と丁寧な対話に努め、課題の改善を促すことで、企業価値の顕在化を積極的に後押しします。
※当ファンドは企業オーナーとして短期業績や株価変動に惑わされない⻑期保有を前提としています。投資先企業と共に企業価値向上を⽬指すとの考えから、短期的に株式を売買する投資家と区別する為、「パートナー株主」との⽂⾔を使⽤しています。
2023年8月の運用コメント
株式市場の状況
2023年8⽉、⽇本株式市場の代表指数であるTOPIX(配当込み)は前⽉末⽐0.43%の上昇となりました。
当⽉の⽇本株式市場は、⼤⼿格付け会社フィッチ・レーティングス社(⽶国)による⽶国債の格下げを背景とした⽶国株安の流れを受け、下落から始まりました。⽉半ばは、中国の軟調な経済指標(消費者物価指数など)や、中国不動産開発⼤⼿の⽶国破産法の申請が嫌気され、下げ幅を広げました。⽉後半は、中国の追加利下げが好感されたほか、ジャクソンホール会議においてさらなる利上げへの懸念が後退したことで値を戻す展開となり、最終的に前⽉末を上回る⽔準で⽉を終えました。
ファンドの運用状況
2023年8⽉、当ファンドのパフォーマンスは前⽉末⽐0.70%の上昇となりました。
当⽉、当ファンドの保有上位銘柄でパフォーマンスにプラスに寄与した企業は、三菱重⼯業、MARUWAなどでした。
三菱重⼯業は、8⽉に発表した2024年3⽉期第1四半期の決算で、市場の期待を上回る好決算であったことや、主要セグメントにおいて、好調な受注環境が⽰唆されたことなどが好感され、株価は上昇を継続しました。MARUWAは、2024年3⽉期第1四半期の決算説明会の中で、下期にかけて業績が成⻑軌道に回帰する⾒通しが述べられたことに伴って、株価が上昇したものと思われます。
当ファンドでは、企業経営者が誠実であり、⾼い競争優位性を有する企業の中から、更なる成⻑余地のある潜在価値の⾼い企業に⻑期集中投資を⾏い、企業との対話を通じて価値の顕在化を図ることを基本戦略とします。
⽇本には、⾼い技術⼒・開発⼒を持ち、ニッチ市場でグローバルに⾼いシェアやブランド⼒を持つ企業が多く存在します。そうした企業の中には、基礎的な収益⼒が⾼く、中⻑期的な成⻑余地が⼤きいにも関わらず、「⽟に瑕(きず)」があるために株式市場で実態価値を正当に評価されていない企業があります。
当ファンドでは、そのような企業の⻑期的なパートナー株主※として、良好な関係を築きながら粘り強く対話を⾏っています。企業の事業戦略や資本配分、IR体制などの改善を促すことで、企業の実態価値の顕在化に努め、株価上昇のカタリスト(きっかけ)の⼀つとなることを⽬指します。
当レポートでは、投資先企業に対する投資⾒解や対話の進捗などをご報告させて頂きます。
当⽉は、当ファンドの投資先である「三菱重⼯業」に対する投資⾒解、対話内容をご紹介します。
三菱重⼯業は1884年創業の重⼯業メーカーです。海運業で財を成した三菱グループ創設者の岩崎彌太郎⽒が、⻑崎にて興した造船事業が起源となっています。祖業である造船事業を営む三菱造船は、1934年には、重機、航空機、鉄道⾞両を事業に加え、現在の社名である三菱重⼯業となりました。第⼆次世界⼤戦後の財閥解体を⽬的とした会社の分割と合併という戦後の混乱期を乗り越え、発電設備、船舶、航空機等の社会インフラ供給を通じて、戦後⽇本の復興と⾼度経済成⻑期を⽀えてきました。
当ファンドが注⽬しているのは、脱炭素投資の恩恵を⼤きく受ける同社の事業ポートフォリオです。同社は「リアリティのあるエナジートランジション」を重視し、エネルギーの供給と消費の両⾯のグリーン転換を成⻑の柱に掲げています。当⽉は電⼒領域の脱炭素化に⼤きく貢献するエナジー事業について、ご説明させていただきます。
同社のエナジー事業は、主にガス⽕⼒発電⽤ガスタービン、⽯炭⽕⼒発電⽤スチームタービン、原⼦⼒発電事業から構成されています。2008年の世界⾦融危機以降、欧州を中⼼に、再⽣可能エネルギーへの移⾏の流れが強まり、化⽯燃料に対する開発投資が抑制されたことで、ガスタービンの市場は縮⼩の⼀途を辿ることとなりました。2011年の東⽇本⼤震災を経て、原⼦⼒発電についても、世界的に新設プロジェクトが減少し、同社のエナジー事業は低迷期を迎えました。
2022年2⽉にロシアとウクライナの紛争が勃発して以降、世界的にエネルギー供給が不安定化し、天然ガスの市況価格⾼騰など深刻な問題を引き起こしました。この混乱は、特定のエネルギー源や輸出国に依存しないエネルギーセキュリティの重要性が再認識されるきっかけとなりました。国家安全保障と気候変動対応の両⽴のためには、安定稼働が可能な信頼性の⾼い低炭素電源が要求されます。優れた発電効率から、ガス⽕⼒発電の低炭素化に貢献する同社の⼤型ガスタービンは、世界シェア1位を誇ります。加えて、同社のガスタービンは、アンモニアや⽔素といった次世代エネルギーとの混焼に対応しており、将来的には更なるCO2排出量削減を実現する可能性を秘めています。当ファンドでは、三菱重⼯業は、今後益々増える世界のエネルギー需要とネットゼロ⽬標の両⽴という「理想」と「現実」のギャップを満たす解決策を提供し、⻑期に亘って中⼼的な役割を担う企業であると考えています。
しかし、追い⾵が吹いている事業環境に反して、エナジー事業は過去3期連続で前年同期⽐減益を記録しています。その主因として、福島県で稼働中の新型⽯炭⽕⼒発電プラントでの度重なる不具合対策費⽤の発⽣が挙げられます。当ファンドでは、リスクマネジメント体制の強化に加えて、今後新設の可能性が低い⽯炭⽕⼒関連製品に対する中⻑期的な向き合い⽅について、様々な観点から議論を進めています。計画外の⼤型損失計上など、決算時のバッドサプライズを極⼒防ぎ、株式市場からの信頼を獲得することで、資本コストの抑制に繋がると考えています。エナジー事業が牽引する事業利益・資本収益性の改善と両輪となって、持続的に企業価値が拡⼤することを期待し、対話を継続していきます。
今後の運用方針
当ファンドでは潜在価値の⾼い企業を選別して集中投資を⾏い、⻑期的なリターンを追求しています。潜在価値の⾼い企業とは、スパークスの投資アプローチである3つの着眼点(経営者の質・企業収益の質・市場の成⻑性)に照らし、企業の実態価値や成⻑性が株式市場で⼗分に評価されていないと考えられる企業を指します。
⽇本には強固な事業基盤を有していながら、事業戦略や資本配分、株式市場への向き合い⽅に改善余地があることから株価が実態価値よりも低く評価されている企業が数多く存在します。当ファンドはパートナー株主として、投資先企業との中⻑期的な関係構築と丁寧な対話に努め、課題の改善を促すことで、実態価値の顕在化を積極的に後押しします。
※当ファンドは企業オーナーとして短期業績や株価変動に惑わされない⻑期保有を前提としています。投資先企業と共に企業価値向上を⽬指すとの考えから、短期的に株式を売買する投資家と区別する為、「パートナー株主」との⽂⾔を使⽤しています。
2023年7月の運用コメント
株式市場の状況
2023年7月、日本株式市場の代表指数であるTOPIX(配当込み)は前月末比1.49%の上昇となりました。
当月の日本株式市場は、FOMC(米連邦公開市場委員会)議事要旨にて年内2回以上の利上げが示唆されたことや、米国の雇用統計の結果を受け、利上げ継続への懸念が強まり下落して始まりました。一方で月半ばには、米国のCPI(消費者物価指数)が市場予想を下回り、利上げ停止が近いとの期待から堅調に推移しました。月後半は、日銀によるYCC(イールドカーブ・コントロール)の柔軟化が発表され、一時的に値動きの激しい展開となりましたが、現行の緩和姿勢を維持するとの受け止めから市場に安心感が広がり、最終的に期初を上回る水準で月を終えました。
ファンドの運用状況
2023年7月、当ファンドのパフォーマンスは前月末比2.86%の上昇となりました。
当月、当ファンドの保有上位銘柄でパフォーマンスにプラスに寄与した企業は、東洋炭素などでした。
東洋炭素は、株式市場における半導体業界の底打ち期待に伴って株価が上昇したものと思われます。電気自動車向けの半導体市場の成長とともに、同社の製品需要が長期的に拡大し続けると当ファンドは期待しております。
当ファンドでは、企業経営者が誠実であり、高い競争優位性を有する企業の中から、更なる成長余地のある潜在価値の高い企業に長期集中投資を行い、企業との対話を通じて価値の顕在化を図ることを基本戦略とします。
日本には、高い技術力・開発力を持ち、ニッチ市場でグローバルに高いシェアやブランド力を持つ企業が多く存在します。そうした企業の中には、基礎的な収益力が高く、中長期的な成長余地が大きいにも関わらず、「玉に瑕(きず)」があるために株式市場で実態価値を正当に評価されていない企業があります。
「玉に瑕(きず)」の一例として、非効率的な資本配分が挙げられます。基礎的な収益力が高く、キャッシュフロー創出力が秀でているにもかかわらず、過度に保守的な経営を志向して成長投資や株主還元を拡充せず、多くの現預金を貯めている企業などが該当します。他の例としては、IR(インベスターリレーションズ:企業が投資家に向けて経営状況や財務状況、業績動向等に関する情報を発信する活動)体制が不十分であることが挙げられます。セグメント開示が不明瞭であったり、決算説明会を実施していなかったりすることで、本来その企業がもつ価値を投資家に伝えられていない例などがあります。
当ファンドは、そのような企業の長期的なパートナー株主※として、良好な関係を築きながら対話を行っております。企業の事業戦略や資本配分、IR体制などの改善を促すことで、企業の実態価値の顕在化に努め、株価上昇のカタリスト(きっかけ)となることを目指します。
当レポートでは、投資先企業に対する投資見解や対話の進捗などをご報告させて頂きます。
当月は、当ファンドの投資先である「森永製菓」に対する投資見解、対話内容をご紹介します。
森永製菓は1899年創業の大手菓子メーカーです。アメリカで菓子製造技術を学んだ創業者森永太一郎氏が、「日本の人々においしく栄養価の高い西洋菓子を届けたい」という想いをもって日本の菓子産業の礎を築いたのが同社の始まりです。今では菓子だけでなく、アイス、「inゼリー」に代表されるゼリー飲料、通販など、製品・事業の幅を広げ、日本だけでなく海外にも積極的に展開しています。
当ファンドが注目しているのは、米国における「HI-CHEW(ハイチュウ)」の成長です。米国では、2008年に現地子会社を設立し本格的な販売を開始しました。メジャーリーガーの間でHI-CHEWブームが起こったことをきっかけに、ソフトな食感とフルーツのおいしさを合わせた商品特性が評判となり、米国小売大手ウォールマート等も取り扱うようになりました。2022年度の米国売上高はHI-CHEW以外の商品も含め146億円に達し、足元も順調に成長が続いています。今後は「inゼリー」の海外ブランドである「Chargel」の本格的な拡大も始まり、「HI-CHEW(ハイチュウ)」で培った営業網を生かして新しい市場を開拓できる可能性もあると考えます。同社は、生産体制の拡充など積極的な海外投資を行う姿勢を示しており、当ファンドは米国での更なる成長に期待をしています。
一方で、本業ともいえる国内菓子事業は、低い収益性が課題だと当ファンドでは考えています。特に直近は、原材料価格高騰の影響等を受け、2022年度のセグメント営業利益率は2.0%程度に留まっています。当ファンドでは、この国内菓子事業の在り方について同社と何度も議論してきました。議論の中で同社は、「総合菓子屋」としての看板を下ろすことなく、老朽化した製造ラインの廃止を通じ商品の選択と集中を進め、事業の生産性向上に努める意思を示しています。当ファンドでは、売上高の大きい国内菓子事業の収益性改善が同社の成長にとって不可欠であると考え、構造改革の進捗を見守るとともに、対話を続けております。
加えて、同社が食品企業「MORINAGA」としてグローバルにブランド力・存在感を高め、新たな成長ステージへの移行を加速するためには、森永乳業㈱との経営統合がカギになると当ファンドは考えております。森永製菓・森永乳業の両社の持つ高い技術力・品質に、資本や人材などの限られた経営資源をより効率的に活用することで、強固な一枚岩のブランドが生まれると当ファンドは考えます。このような考えから、当ファンドは両社の経営統合への期待も面談で伝えています。
最後に、同社が合理的な資本政策の実行に舵を切り始めていることにも当ファンドは注目しております。当ファンドでは従来から、株主還元の拡充についても議論を重ねてきました。同社は2022年度の決算説明会で、自己株の取得などによるネットキャッシュの大幅な圧縮を発表しました。今後のさらなる資本政策の改善により、ROE(株主資本利益率)が向上する可能性があると考え、対話を続けてまいります。
今後の運用方針
当ファンドでは潜在価値の高い企業を選別して集中投資を行い、長期的なリターンを追求しています。潜在価値の高い企業とは、スパークスの投資アプローチである3つの着眼点(経営者の質・企業収益の質・市場の成長性)に照らし、企業の実態価値や成長性が株式市場で十分に評価されていないと考えられる企業を指します。
日本には強固な事業基盤を有していながら、事業戦略や資本配分、株式市場への向き合い方に改善余地があることから株価が実態価値よりも低く評価されている企業が数多く存在します。当ファンドはパートナー株主として、投資先企業との中長期的な関係構築と丁寧な対話に努め、課題の改善を促すことで、実態価値の顕在化を積極的に後押しします。
※当ファンドは企業オーナーとして短期業績や株価変動に惑わされない⻑期保有を前提としています。投資先企業と共に企業価値向上を⽬指すとの考えから、短期的に株式を売買する投資家と区別する為、「パートナー株主」との⽂⾔を使⽤しています。
2023年6月の運用コメント
株式市場の状況
2023年6月、日本株式市場の代表指数であるTOPIX(配当込み)は前月末比7.55%の上昇となりました。
当月の日本株式市場は、月前半は米連邦債務の上限停止による米国株高の流れを受け、大幅に上昇いたしました。月半ばには、FRB(連邦準備制度理事会)による追加利上げの示唆を受けた軟調な米国株の影響や、衆院解散への期待剥落が嫌気された一方、日銀の金融緩和の維持、米著名投資家の日本株追加投資の発表が好感され、一進一退の動きで推移しました。月後半は、株価上昇の反発と見られる下落の局面もありましたが、米景気悪化懸念の後退と円安進行が下支えをし、最終的に前月末を上回る水準で月を終えました。
ファンドの運用状況
2023年6月、当ファンドのパフォーマンスは前月末比5.05%の上昇となりました。
当月、当ファンドの保有上位銘柄でパフォーマンスにプラスに寄与した企業は、MARUWA、三菱重工業などでした。
MARUWAは、株式市場における半導体業界の底打ち期待に伴って株価が上昇したものと思われます。三菱重工業は、5月に発表した2024年3月期の通期業績予想で当期純利益が過去最高を更新する見通しとなったことなどが好感され、株価は上昇を継続しました。
当ファンドでは、企業経営者が誠実であり、高い競争優位性を有する企業の中から、更なる成長余地のある潜在価値の高い企業に長期に集中投資し、企業との対話を通じて価値の顕在化を図ることを基本戦略とします。
日本には、高い技術力・開発力を持ち、ニッチ市場でグローバルに高いシェアや高いブランド力を持っている企業が多くあります。そうした企業の中には基礎的な収益力が高く、中長期的な成長余地が大きいにも関わらず、「玉に瑕(きず)」があるために株式市場で実態価値を評価されていない企業が存在します。
企業によって課題は様々ですが、当ファンドは長期的なパートナー株主※として、投資先企業と良好な関係を築きながら粘り強く対話を行い、事業戦略や資本配分、IR(インベスターリレーションズ:企業が投資家に向けて経営状況や財務状況、業績動向等に関する情報を発信する活動のこと)体制などの改善を促すことで、企業の実態価値の顕在化に努めます。
当レポートでは、投資先企業に対する投資見解や対話の進捗などをご報告させて頂きます。
当月は、当ファンドの投資先である「MARUWA」に対する投資見解、対話内容をご紹介します。
MARUWAはセラミック部品の世界的大手メーカーです。陶芸家の一族である神戸家が江戸時代から陶磁器の製造販売を営み、焼き物の技術を継承してきました。高度成長期の1960年、急速にニーズが拡大しつつあった電子部品(通信機器向け特殊磁器、固定抵抗器用セラミック)の分野へ進出し、現在のMARUWAに至ります。
セラミックは一般家庭の皿にも使われるなど、身近な素材であり、窯があれば作ることが出来ますが、同社が得意としている高付加価値セラミックの分野では高度な製造ノウハウが必要となります。セラミックは焼成前後でサイズが大きく変化するため、均質なセラミック製品を量産するのは簡単ではありません。この製造工程の秘匿化が参入障壁となり、同社は様々なセラミック製品で世界トップシェアを獲得していると当ファンドでは推定しています。そして、今後最も需要が伸びると期待されているのはEV(電気自動車)向けのセラミック製品です。EVでは、高い電圧を使う電子部品が使われており、発熱によって電子部品が膨張し部品寿命が悪化する可能性が高いため、発熱対策が課題となっています。同社のセラミック部品はそれを防ぐ放熱基板として使われています。自動車のように耐用年数が長期かつ発熱温度が高い分野では、セラミックは高価ではあるものの最も信頼できる素材とされています。
前述のようにMARUWAのセラミック部品が使われる市場は拡大する見通しであり、同社は参入障壁によって高い収益性と世界シェアを維持できる可能性が高い企業であると考えられますが、株式市場で評価される余地はまだ大きいと当ファンドでは考えています。
過去、MARUWAは長期にわたって決算説明資料を作っておらず、決算説明会も開催しておりませんでした。その点が株式市場で同社の知名度が上がらなかった要因と考え、IR体制の改善を期待して同社との対話を継続してきました。そうした粘り強いエンゲージメントの甲斐もあり、同社は2021年から決算説明会資料を作成し決算説明会をオンラインで開催しております。さらに2023年5月の通期決算説明会では、あまり公の場で発言することのなかった神戸誠会長が登壇し、自ら投資家からの質疑に回答しました。こうした点からも、当ファンドでは同社の株式市場との対話姿勢に大きな改善が見られていると考えています。
また、同社は高い収益性を誇る一方、余剰資金の蓄積スピードが早く同社のROE(株主資本利益率)が低下する可能性が高いことも、株式市場からの評価を押し下げている要因と思われます。当ファンドでは引き続き、同社の実態価値が株式市場で顕在化する一助となれるよう、IR体制とROEの改善を主題に、経営陣との対話を継続していく方針です。
今後の運用方針
当ファンドでは潜在価値の高い企業を選別して集中投資を行い、長期的なリターンを追求しています。潜在価値の高い企業とは、スパークスの投資アプローチである3つの着眼点(経営者の質・企業収益の質・市場の成長性)に照らし、企業の実態価値や成長性が株式市場で十分に評価されていないと考えられる企業を指します。
日本には強固な事業基盤を有していながら、事業戦略や資本配分、株式市場への向き合い方に改善余地があることから株価が実態価値よりも低く評価されている企業が数多く存在します。当ファンドは長期的なパートナー株主として、投資先企業との中長期的な関係構築と丁寧な対話に努め、課題の改善を促すことで、実態価値の顕在化を積極的に後押しします。
※当ファンドは企業オーナーとして短期業績や株価変動に惑わされない長期保有を前提としています。投資先企業と共に企業価値向上を目指すとの考えから、短期的に株式を売買する投資家と区別する為、「パートナー株主」との文言を使用しています。
交付運用報告書
-
交付運用報告書(第2期 2025年5月14日決算) (933.3 KB)
-
交付運用報告書(第1期 2024年5月14日決算) (913.0 KB)
運用報告書(全体版)
-
運用報告書(全体版)(第2期 2025年5月14日決算) (918.3 KB)
-
運用報告書(全体版)(第1期 2024年5月14日決算) (718.6 KB)
動画
レポート
-
- ファンドレポート
- スパークス・企業価値創造日本株ファンド
投資先企業との対話状況(2025年7月)(535.4 KB)
-
- ファンドレポート
- スパークス・企業価値創造日本株ファンド
米トランプ政権の政策がファンドに与える影響について(337.4 KB)
-
- ファンドレポート
- スパークス・企業価値創造日本株ファンド
-
- ファンドレポート
- スパークス・企業価値創造日本株ファンド
進捗を見せる企業との対話(1.2 MB)
-
- ファンドレポート
- スパークス・企業価値創造日本株ファンド
パフォーマンス状況と組入銘柄(1.1 MB)
-
- ファンドレポート
- スパークス・企業価値創造日本株ファンド
設定後のポートフォリオと組入銘柄(1.9 MB)
-
- ファンドレポート
- スパークス・企業価値創造日本株ファンド
"今"こそ、日本企業が変わる時(1.4 MB)
主な投資リスク、費用等
- 当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「投資リスク」をご覧ください。 (2.0 MB)
- 当ファンドに係る費用等については、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「ファンドの費用、税金」をご覧ください。 (2.0 MB)
- 本サイトに掲載されている情報は、スパークス・アセット・マネジメント株式会社のご案内のほか、投資信託および投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、特定の商品あるいは有価証券の投資勧誘を目的としたものではありません。提供している情報の正確性や完全性をスパークス・アセット・マネジメント株式会社が保証するものではありません。サイト内に記載されている情報の著作権は、スパークス・アセット・マネジメント株式会社に帰属し、スパークス・アセット・マネジメント株式会社の許可無しに転用・複製・転載等をすることはできません。