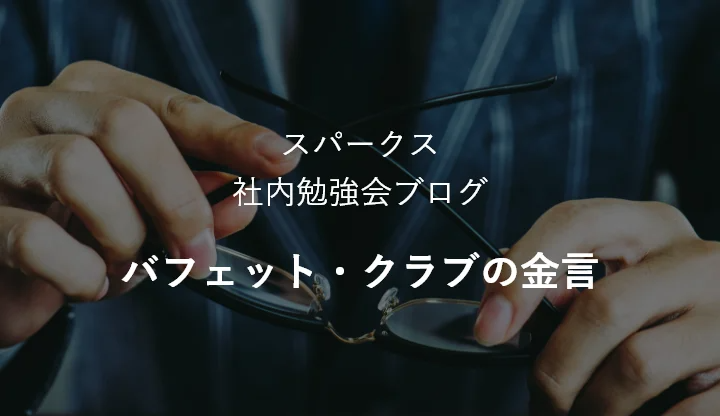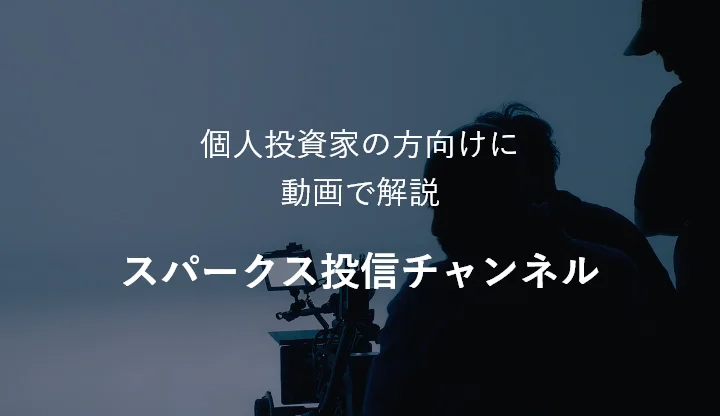スペシャルレポート インデックス運用の難しさ -インデックスへの過度な追従による弊害-
インデックス運用は簡単か?
インデックスファンドとは日経平均株価やTOPIX、S&P500などの株価指数(インデックス)と同じリターンになることを目指したファンドです。ここではインデックスファンドが行っている運用をインデックス運用とよびます。パッシブファンド、パッシブ運用もほとんど同じような意味で用いられますが、ここではインデックスとインデックス運用の違いに焦点をあてるため、インデックス運用とよびます。
さて、アクティブ運用に比べ、インデックス運用は決められた銘柄を買うだけだから簡単、とよく言われます。これは半分正しいですが半分間違いです。確かに、インデックスに大まかに追従すればよいのであれば簡単ですが、それらの乖離をとにかく小さくしようとすると非常に難しいものとなります。その難しさは、アクティブ運用の難しさとは全く異なる種類の難しさです。その難しさはいろいろあるのですが、そのなかには、インデックス運用のリターンを"見えないところ"で失わせたり、場合によっては市場を混乱させる要因になったりしています。また、インデックス運用の取引に先回りしようとして不公正取引をしてしまう人まであらわれました。つまり、インデックスへの過度な追従は、"見えないところで"リターンを失い、市場全体にも弊害をもたらす場合があるのです。
本レポートではインデックス運用の難しさとその弊害、そして一部のアセット・オーナーが行っている弊害を回避するための工夫などを紹介します。
そもそもインデックスとインデックス運用は全くの別物
そもそもインデックスとインデックス運用は全くの別物です。これについては以前のレポート*1でも紹介しましたが、改めて見ていきましょう。インデックスとは、日経平均株価やTOPIX、ダウジョーンズ工業株平均、S&P500などの株価指数です。これらの歴史は古く、ダウジョーンズ工業株平均のその前身の指数は1884年に公表が始まりました。その目的は多くの銘柄が取引されている中、その平均のリターンを知るためでした。当初は採用銘柄の株価の単純な平均でしたが、その後、連続性を保つため分割などがあった場合は調整するようになりました。また、S&P500やTOPIXのように、株価の単純な平均ではなく、時価総額で加重した平均を示すインデックスも登場しました。
インデックスの目的は多くの銘柄の平均的なリターンを知ることであって、その平均的なリターンを獲得することが目的ではありませんでした。そのため、実際にそのリターンを得るためのポートフォリオを構築することを考慮しておらず、例えば、構成銘柄が入れ替わるときも、一瞬ですべて入れ替わるなどの前提で計算されています。
その後80年以上経ってインデックス運用が開始
その後80年以上経った1970年代になって、インデックス運用の有効性について学術界で議論が始まりました*2。このころになると株価の単純な平均のインデックスだけでなく、それよりは合理的なポートフォリオとなった時価総額で加重した平均のインデックスも広がってきていました。そして、1976年にジョン・ボーグルが、時価総額加重のインデックスであるS&P500に追随するインデックス運用を始めたのです*2。彼はそれ以前には、仮にダウジョーンズ工業株平均でのインデックス運用をした場合の分析をしてインデックス運用を批判した論文を発表したりしていましたが、時価総額加重のインデックスならさまざまな欠点が回避できると考えたのだと思われます。
インデックス運用が始まってから、インデックス運用で問題が発生しないように、インデックスは多くの点で改善されてきました。銘柄の入れ替えも日にちを分けて行われたり、税金がかかる国では税金の効果を含めたインデックスも開発されたりされました。しかし、銘柄の入れ替えは一日の中で、終値で、一瞬で入れ替わるなど、現実の取引では実現が難しい操作がインデックスにはまだまだ残っています。140年の歴史のあるインデックスに対して、まだ50年弱の歴史しかないインデックス運用はまだ発展途上と言えるでしょう。
運用資金がすごく大きいわけではないインデックス運用の難しさ
インデックス運用の難しさにはいろいろな種類があります。まずは、運用資金がすごく大きいわけではないインデックス運用の難しさから見てみましょう。
そもそもインデックスと同じ銘柄を持てないという難しさがあります。これは特に時価総額加重のインデックスで顕著です。TOPIXの場合、2024年9月末現在で2100銘柄超の構成銘柄がありますが、ウエイトが0.0001%に満たない銘柄が40銘柄程度あります*3。例えば0.0001%の銘柄の最低購入単位が1万円(株価100円で100株単位)だったとすると、その最低購入単位だけを持った場合、ポートフォリオ全体の金額を逆算すると100億円となります。つまり、100億円ないとこのような銘柄を全く保有できないのです。しかも、最低単位の額なのでウエイトも調整できません。例えば150億円のポートフォリオになったら200株だと買いすぎだし100株だと少なすぎてその間を調整できないのです。全く問題なくウエイトが調整できるという意味ではポートフォリオはこの100倍くらいの1兆円は必要かもしれません。
もう少し具体的に見てみましょう。ETFは、インデックスと同じポートフォリオと交換することができます。つまり、ETFの設定は現金で行われるのではなく、インデックス構成銘柄の現物を差し出して行われるのです。しかしこれまでに述べたようにインデックスと全く同じポートフォリオとなると巨額になります。そのため、同じではないけれども近いポートフォリオを差し出して代わりにETFをもらうということが行われています。例えば20兆円程度あるTOPIXのETFの場合を見てみましょう*4(数値はいずれも2024年11月末ごろの概算値)。1000万口を設定する場合、このETFは1口2800円程度ですので、280億円程度のポートフォリオですが、それでも差し出すべきポートフォリオは1800銘柄程度しか組み入れられていません。残りの300銘柄程度はこの差し出すポートフォリオには組み入れられないのです。
また、インデックス運用はインデックスと違いキャッシュを持っています。インデックスはぴったり100%株式で構成されていますが、実際のファンドではキャッシュを持たざるを得ません。というのも、信託報酬を支払う必要がありますし、入金された配当を再投資するにしても端数がどうしても残ります。インデックスは配当が一瞬ですべて完全に再投資されたとして計算されますが、現実の運用ではできません。また、上記で説明したように全く同じウエイトで持つのは困難で端数が出るのは当然です。そのため、株式のウエイトは100%を下回ることが多いのですが、その足りない分は先物を使って埋めたりします。先物と現物にはわずかですが価格差があり、これもインデックスとの乖離になりえます。
運用資金がすごく大きいインデックス運用の難しさ
では、運用資金が数兆円となればこれら問題が解決し、簡単になるかと言ったらそうではありません。今度は別の難しさ、むしろこちらが本当に深刻な難しさがあらわれます。それは、終値で取引すること自体が難しいということです。インデックスは終値のみを使って計算されています。銘柄入れ替えがあった場合は終値によって瞬間的に入れ替わったとして計算しています。
しかし、運用資金が大きくなるほど終値だけで取引するのは難しくなってきます。取引の量が大きいので、すべてを市場が終わる直前に取引所に注文を出してしまうと、価格が大きく不利な方へ動いてしまいかねません。しかもインデックスの銘柄入れ替えは、あらかじめどの銘柄がいつ入れ替わるのか公表されていて、入れ替え日をむかえます。つまり、他の投資家から何を取引するのかばれている状態で、終値が決まる時間をむかえるのです。
証券会社と終値で取引する
運用会社がこのような難しい取引を自力で行うのは難しいので、証券会社に少し手数料を支払って、証券会社と相対で、終値で、取引を行う場合も多いようです。終値で特定の銘柄を売ってもらう、または引き取ってもらうということを証券会社とあらかじめ約束しておくのです。こうすればインデックス運用から見れば、めでたくぴったり終値で取引ができるわけです。しかし当然、その相手となる証券会社は別の方法で、その約束の時間までに、その銘柄を買ったり売ったりして用意しておかなければなりません。
証券会社にその銘柄を終値で買いたい、売りたいという投資家がちょうど同じくらいいれば、その投資家同士の株式を受け渡すだけで、取引所に注文を出さずに済みます。実は大量の取引を行いたい投資家が証券会社と終値で取引することはインデックス運用に限らず良くあることです。反対の取引をしたい投資家がいればお互い取引所に大量の注文を出さずに済み、価格を不利な方向に動かしてしまうことを回避できるからです。
しかしインデックスの銘柄入れ替えの時は当然、他のインデックス運用も同じ方向の取引となるので、どちらかに偏ってしまいます。証券会社は、さまざまな工夫をして、取引所などでなるべく終値に近い価格で取引をしないといけないのです。
世界的に終値での取引増加が問題に
このようなこともあり、世界的に株式の取引所では終値での取引が増えています。つまり取引終了間際の取引量がとても多くなっているのです。普通の投資家からすると、他の時間帯で有利な価格で取引できるかもしれないのに、なぜ取引終了間際に取引したがるのか理解しがたいでしょう。しかし、インデックス運用でインデックスとの乖離を防ぐためには、高かろうが安かろうが終値で取引するのが良いのです。いつでも有利な価格なら取引を行う普通の投資家と、不利な価格でも終値で取引したい特殊な投資家が存在することにより、終値だけ他の時間帯とは違う価格がつくことも増えているようです。大げさにいえば、終値と他の時間帯では参加投資家が異なり、価格形成も異なってしまっていて、違う世界になってしまっている、と言えるでしょう。
もし終値の決定が本当に取引時間の最後の瞬間だけで決まると、その瞬間の価格で買いたい特殊な投資家と、それを見越してその瞬間だけで儲けようとする高速取引との戦いになります。瞬きをしている間に繰り広げられる戦いの結果、結局値段がつかないなどの弊害も増えてきたともいわれます。
そのため、例えば東京証券取引所では2024年11月5日から、取引終了の最後の5分間はクロージング・オークションの時間を設けました*5。この5分間は、注文を受け付けるが取引は成立しないという、寄り付き前に似た仕組みとなり、大量の注文を集めて価格を決定するのに良い仕組みとなっています。このように、終値への需要の高まりは価格形成を変え、取引所のルールをも変えているのです。
終値に関わる不公正取引事件
残念ながら、終値に関わる不公正取引も多く起きてしまっています。ここでは少し古いですが、インデックスの銘柄入れ替えに関わる有名な不公正取引を紹介します*6。先ほど述べたように、インデックスの銘柄入れ替えがあるときは、証券会社は終値での取引を引き受けている場合が多いようです。これを逆手に不公正に利益を得た事例です。
インデックスに新たに組み入れられる銘柄をインデックス運用に終値で売る(インデックス運用側が買う)約束をした証券会社は、当然、売るための株式をなるべく終値に近い価格で集める必要があります。そこで終値で売ってくれる他の投資家があらわれると、とてもありがたいわけです。この不公正取引を行った業者はこれに目を付け、あらかじめ証券会社に、新規でインデックスに組み入れられる銘柄を終値で売ってあげる約束をし、取引が終了する直前に大量の買い注文を入れるなどして終値を上昇させ、不公正な高い終値で証券会社に売りつけたという事件でした。そして最終的には、不公正に高い終値でインデックス運用が買わされたわけです。
このようにインデックス運用の終値への需要を逆手に取り、不公正取引により利益を得ようとするものは、現在でも後を絶ちません。
不公正取引でなくても不利な方向に価格が動くことも
不公正取引でなくても、不利な方向に価格が動くことは多くあると考えられます。例えば、終値で売ることを約束した証券会社は、売るための株式を少しずつ取引所で買い集めることもあるでしょう。この時、どんなに工夫しても、結果的に少しずつ価格をあげてしまうことはあるでしょう。例えば、1日かけて少しずつ買い集め、価格も取引開始から少しずつ上昇し、終値が一番高かったとしましょう。証券会社が購入した価格の平均はお昼ごろの、終値より少し安い価格になるでしょうが、インデックス運用に売る価格は終値で約束しているので、一番高い終値でインデックス運用は買うことになります。
それ以外にも、インデックスの入れ替えはあらかじめ公表されていて、インデックス運用がその終値で取引することがばれているので、それを先回りして儲けようとする投資家の取引によって、終値がインデックス運用にとって不利な価格になっていることもあるでしょう。
インデックスのリターンが毀損され、その毀損したリターンに追従してしまっている
ここで大きな問題となるのは、例えインデックス運用が不利な価格で取引させられていたとしても、インデックスそのものも不利な価格となってしまった終値で計算されているので、インデックス運用のリターンはインデックスのリターンと乖離しないということです。つまり、インデックスそのもののリターンが毀損されていて、その毀損したリターンに追従してしまっているのです。まさに"目に見えないリターンの毀損"です。インデックス運用がインデックスに過度に追従しようとすると、終値で取引することがばれてしまい、それを逆手に儲けようとするものがあらわれ、そのものたちにより不利な方向に価格が動き、インデックスそのもののリターンが毀損してしまい、その毀損したリターンにインデックス運用が追随してしまうのです。
解決方法は簡単:過度な追従をやめる
この問題の解決は、実は簡単です。過度な追従をやめればよいのです。"おおむねインデックスと同じくらいのリターンならよい"とすれば、無理に終値で取引する必要はなくなります。それどころか、インデックスの銘柄入れ替えを絶対同じようにしなければならないこともなくなり、むしろ、入れ替え銘柄をあらかじめ予想してあらかじめ入れ替えておいて、あたればリターンを得ることさえ可能です。このリターンはまさに、過度な追従を行うインデックス運用が失ったリターンから生まれています。しかも、多くのインデックス運用が過度なインデックスへの追従をやめれば、終値をめぐる不毛な争いが減り、不公正取引を試みるものも減るので、価格形成が健全になり、市場全体に良い影響を与えます。
そもそも"インデックスに厳密に追従する"という目的が、何か意味があるものを生み出すでしょうか?そもそもインデックス運用の目的は、大量の資金でも問題なく運用できることや、アクティブ運用を適切に選べない人が無難なリターンを得ることであったはずです。インデックスに厳密に追従するせいでリターンを失うことは、本来の目的ではないはずです。
投資にはいろいろな目的があり得ます。しかし、インデックスに厳密に追従するというのは、あまりにも何も生み出さない目的であると言えるでしょう。"インデックスと同じ動きをするほど良いインデックス運用である"という考え方を改めない限り、インデックス運用は過度にインデックスに追従し、その結果インデックスそのもののリターンを毀損し、毀損したリターンに追従する、ということは終わらないでしょう。
一部のアセット・オーナーはすでに過度に追従しないインデックス運用を行っている
大きい資金を運用している年金基金やソブリン・ウエルス・ファンドなどのアセット・オーナーをユニバーサル・オーナーとよぶことがあります。ユニバーサル・オーナーは、運用資金が大きすぎて、世界中の多くの企業を保有せざるを得ません。そのため、地球全体の経済の発展の一部を享受するという戦略を取ることが多いのは、以前のレポートで書いた通りです*7*8。資金の多くでインデックス運用を行い、一部の資金でアクティブ運用を行い、インデックスそのもののリターンを引き上げようとするベータ・アクティビズムという戦略を行っているのです*7*8。
このようなユニバーサル・オーナーはインデックス運用を自ら行うこともあるのですが、その中には過度に追従しないインデックス運用を行っている場合があります。一例として、ノルウェー政府年金基金の運用実務を担うノルウェー銀行(ノルウェーの中央銀行)があげられます。ノルウェー銀行は2000年から過度に追従しないインデックス運用を自ら行っており、その狙いや効果を文章で公表しています*9。そのなかで、"The fund's indexing strategy is active fund management. Our enhancement strategies seek to create excess return and avoid the shortcomings of index replication."(我々のインデックス戦略はアクティブ運用である。インデックスを超えるリターンを追求し、インデックス追従の弊害を避ける。)と述べており、過度な追従がインデックス運用における弊害であると明言しています。
過度な追従を止められるのはインデックス運用に投資する投資家
インデックスへの過度な追従はさまざまな弊害があることが分かりました。それを止められるのはインデックス運用に投資する投資家です。投資家がインデックス運用の良し悪しを、どれくらいインデックスに追従しているかで評価している限り、過度な追従は終わりません。そのような無意味な評価をやめれば、過度な追従する必要がなくなり、これらの弊害はなくなるのです。
*1 水田孝信、"国際資本の舵を取ってしまったグローバルインデックス算出会社"、スパークス・アセット・マネジメント スペシャルレポート、 2020年1月24日
https://www.sparx.co.jp/report/detail/309.html
*2 岡田功太、幸田祐、"米国投信業界で圧倒的な資金流入額を誇るバンガード"、 野村資本市場研究所 野村資本市場クォータリー、2016年春号
https://www.nicmr.com/nicmr/report/repo/2016/2016spr11.html
*3 https://www.jpx.co.jp/markets/indices/topix/index.html
*4 https://nextfunds.jp/lineup/1306/#tab-investors
*5 https://www.jpx.co.jp/equities/strengthening/index.html
*6 日本経済新聞、"香港の運用会社、相場操縦で4.3億円の課徴金 監視委勧告"、 2014年12月6日
https://www.nikkei.com/article/DGXLASDG05H96_V01C14A2CC1000/
*7 水田孝信、"アセット・オーナーが行っている投資:"悪環境期に耐える"と"ユニバーサル・オーナー"" 、 スパークス・アセット・マネジメント スペシャルレポート、 2019年9月18日
https://www.sparx.co.jp/report/detail/318.html
*8 水田孝信、"株式投資で気候変動を考慮することに賛否があるのはなぜか?:気候変動解決でリターンを得る投資戦略"、スパークス・アセット・マネジメント スペシャルレポート、 2024年4月15日
https://www.sparx.co.jp/report/detail/1436.html
*9 Norges Bank Investment Management, "The first 20 years of investing in equities", 2020/12/9
当レポートは執筆者の見解が含まれている場合があり、スパークス・アセット・マネジメント株式会社の見解と異なることがあります。
上記の企業名はあくまでもご参考であり、特定の有価証券等の取引を勧誘しているものではございません。