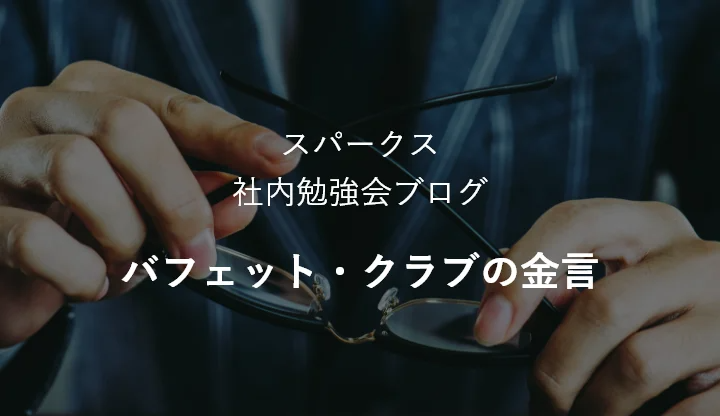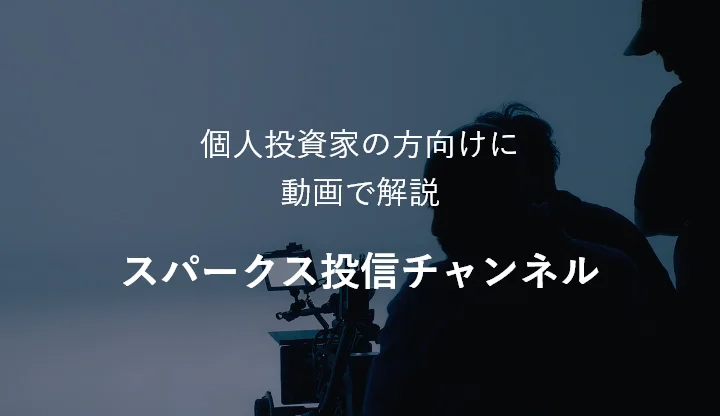スペシャルレポート ニッポン解剖~日本再興へのメカニズム~「増加するMBO:日本株式市場の新陳代謝」
昨今、日本の株式市場の新陳代謝が高まってきているように感じます。株式市場およびその参加者には、成長が見込まれる企業に資金調達の機会を提供するとともに、資本効率に課題のある企業に対して株式市場からの退出を促すことで、市場の新陳代謝を高め、ひいては日本経済の活性化をけん引することが期待されています。日本のIPO(新規株式公開)社数は、年間100社前後で推移している一方で、コーポレートアクション(MBO(※1)や上場会社による完全子会社化、M&Aなど)に伴う上場廃止(非公開化)が増加しており、2024年については、非公開化数を単純に年換算すると100社超のペースとなっており、まさに日本の株式市場の新陳代謝が高まりつつあると考えています。筆者が2024年1月に発行した「ニッポン解剖 ~日本再興へのメカニズム~ Vol.10『2024年のびっくり3大予想』」において、上場維持の意義が薄れた企業が上場廃止に踏み切り、その数がIPO数を上回ることで、日本の上場企業数が減少する可能性もある旨を記載しましたが、この予想が現実味を帯びてきているように感じます。
日本市場は相対的に上場企業数が多いという特徴があります。米国市場に上場する米国企業数は約4,300社、一方で日本市場に上場する日本企業数は約3,900社であり、両国の市場規模の差を考慮すると、日本の上場企業数が相対的に多いことが分かります。日本のプライム市場には、時価総額が1兆円以上の企業が176社ある一方で、時価総額の中央値はプライム市場で960億円、スタンダード市場で82億円、グロース市場で59億円となっており(2024年4月1日現在)、時価総額が小粒にとどまっている企業が多い傾向にあることから、玉石混交の株式市場と評されることがあります。IPO時の時価総額や資金調達額が小規模であるという状況に加えて、上場後も時価総額が増加していない企業が多いという課題も指摘されています。
非上場企業は株式市場に上場することによって、円滑な資金調達が可能となるほか、社会的信用や知名度の向上といったメリットが得られるとされています。一方で、上場することによって、株主が特定の少数者のみに限定された状態から、多数の株主に所有される状態になります。これに伴い、特定の株主にとっての利益のみを追求すればよかった状態から、株主共同の利益の追求が求められる状態になります。そのため、上場のメリットと引き換えに、企業経営の自由度は一定の制限を受けることになります。もし今、特定の少数の株主の下でしか抜本的な経営改革ができない状況であったり、そもそも上場を継続する意義が乏しい状態にあるのであれば、株式の非公開化も十分に選択肢に入ってくると考えられます。また冒頭で述べたように、非公開化が増えている現状を踏まえると、そのような選択肢を選ぶ企業が増えつつあるようです。このように、株式市場の新陳代謝が高まることで、魅力的な企業に資金が集まり、日本経済の活性化につながることを期待しています。
スパークス・アセット・マネジメント株式会社
チーフ・アナリスト 川部 正隆
当レポートは執筆者の見解が含まれている場合があり、スパークス・アセット・マネジメント株式会社の見解と異なることがあります。