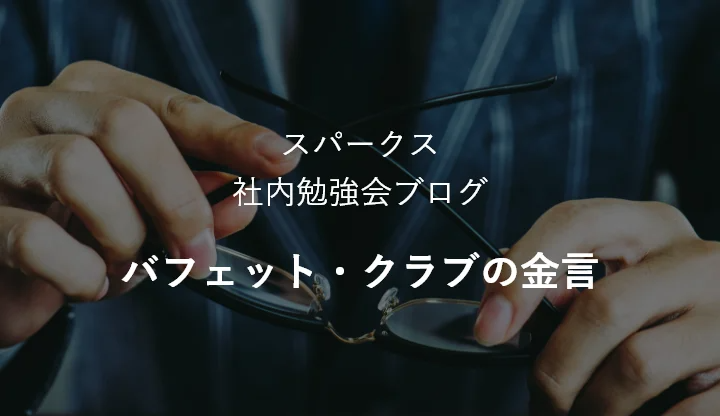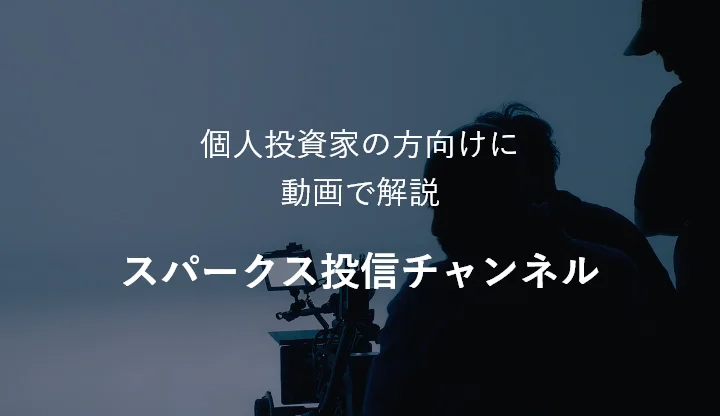スペシャルレポート ニッポン解剖~日本再興へのメカニズム~「利上げで問われる企業の稼ぐ力」
1月23-24日に開催された金融政策決定会合で、日銀は政策金利を約17年ぶりの水準となる0.5%に引き上げました。記者会見で、日銀の植田総裁は、中立金利(緩和的でも引き締め的でもない金利水準)に対しては、まだ相応の距離があるとみていると述べており、更なる利上げもあると考えられています。次の利上げで0.5%を超える政策金利となれば、約30年ぶりの金利水準となります。金利上昇による企業の事業活動への影響としては、資金調達コストの上昇による投資余力の減少が考えられます。一方で、金利変化の影響は、企業の事業活動に留まりません。今回のニッポン解剖では、利上げによる株価への影響を考えます。
企業価値の算定方法に、DCF法(割引キャッシュフロー法)があります。企業が将来生み出すと期待されるフリーキャッシュフローを現在価値に割り引くことで企業価値(株価)を算定する方法です。フリーキャッシュフローは、企業が稼いだ資金から設備投資などの費用を差し引いて残った資金を指します。このフリーキャッシュフローを現在価値に割り引く際に用いられる割引率の構成要素として、長期国債利回りを用いる場合が多くあります。政策金利の引き上げにより、長期国債利回りも上昇すると、割引率が引き上がることになります。すなわち、企業の稼ぐ力であるフリーキャッシュフローを一定とした場合、政策金利の引き上げは、DCF法で計算される企業価値(株価)の低下につながります。一般的に、金利が低下すると株価が上がり、金利が上昇すると株価が下がるとされる所以になります。
今回、日銀が利上げを行った背景として、植田総裁は会見で、企業が人件費や物流費などの上昇を販売価格に反映する動きが広まっており、金融緩和の度合いを調整することが適切であるという旨の発言をしています。上述の企業価値算定に照らし合わせると、企業がキャッシュフローを生み出す力が高まっていると判断されたと考えることができます。今後も更なる利上げが行われるとすれば、それはすなわち、日本企業の稼ぐ力が今よりもさらに高まっていることを示していると思います。なお、今回の決定会合において、利上げに反対した委員からは、企業が稼ぐ力が高まったことを確認したうえで、金融市場調整方針の変更をすべきであるという発言もあったとのことであり、企業の稼ぐ力の高まりについては、委員の中でも意見が分かれています。
加えて、全ての日本企業の稼ぐ力が高まっているのかといえば、玉石混交であるといえます。力強く成長している企業がある一方で、人件費などの高騰によるコスト増加を販売価格に転嫁できない企業は持続的な成長が難しくなると考えられ、企業間の優勝劣敗が進むと思われます。成長に必要な人材を集めるための賃上げについても、ハードルが高いという声も出ているようです。その場合、金利上昇に見合ったキャッシュフローを生み出すことができない企業の株価は、ファンダメンタルズ分析の観点からは、評価されづらい状態も想定されます。これまでの超低金利下では、キャッシュフロー創出能力による企業価値評価には大きな優劣が付きづらい局面もあったと思われますが、今般の利上げにより、稼ぐ力を持った企業が評価されやすい局面に入ったということを想定する必要があります。ありきたりな結論ではありますが、長年の金利がほぼなかった状態から「金利のある世界」に入った今、企業の稼ぐ力を改めて認識する必要があるように思います。
スパークス・アセット・マネジメント株式会社
チーフ・アナリスト 川部 正隆
当レポートは執筆者の見解が含まれている場合があり、スパークス・アセット・マネジメント株式会社の見解と異なることがあります。