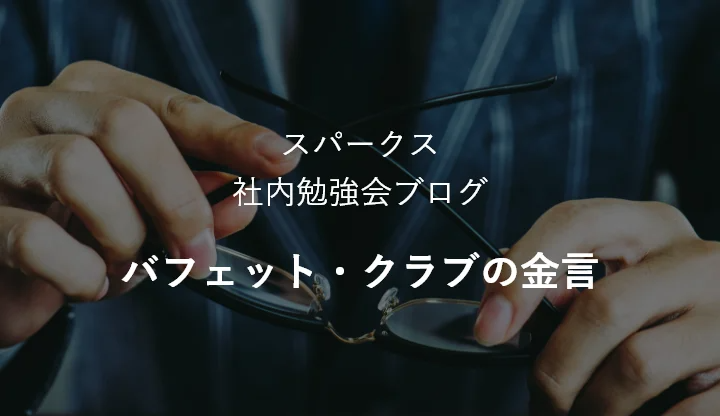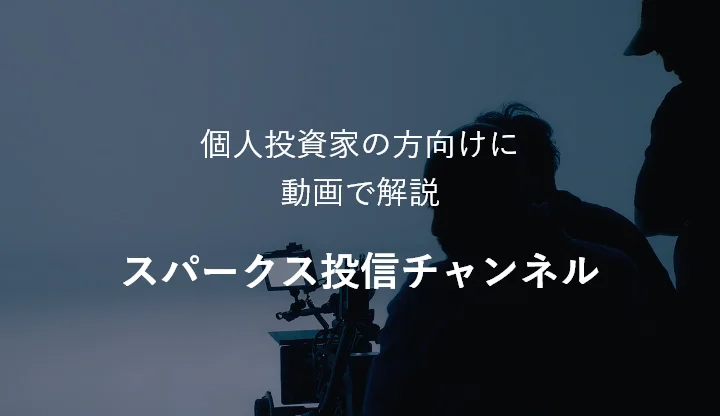スペシャルレポート ニッポン解剖~日本再興へのメカニズム~「エンゲージメントVSアクティビスト」
日本においてアクティビスト・ファンドやエンゲージメント・ファンドの存在感が目立ち始めていますが、結局のところ、企業変革の観点ではどちらが有効なのでしょうか。両者の企業との対話論点そのものは重なることが多くありますが、対話論点が同じだった場合でも、そのアプローチ手法が異なります。エンゲージメント・ファンドが、企業とのミーティングを通じた「対話」により企業の自発的な変化を促す一方で、アクティビスト・ファンドは、株主提案などの直接的な企業経営への介入を中心的な手法の一つとしています(詳細は、Vol.27「エンゲージメント・ファンドの対話論点」をご参照ください)。エンゲージメント・ファンドも、議決権行使などによって、企業経営に対して「NO」を突き付けるケースが増えていますので、その境界線は薄れつつあると言えますが、今回のニッポン解剖では、敢えてこの両者を対立軸として捉えて、エンゲージメント・ファンドの有効性を考えたいと思います。
アクティビスト・ファンドの代表的な手法の一つが「株主提案」です。日本は、株主総会における株主権が欧米と比較して強いという指摘があります。株主提案の要件が、日本は「総議決権の1%または300個の議決権を6カ月間継続して保有」に対して、例えば、欧州では「株式の5%以上の保有」などとなっている場合があり、この株主提案の要件の緩さから、日本は株主の権利が強いという指摘につながっていると思います。しかし実際には、日本では、株主から提案があったとしても、会社法や定款に定める事項以外は、株主総会に上程するか否かは会社側に裁量があります。加えて、定款変更については、議決権を持つ株主の過半数が株主総会に出席し、その議決権のうち、3分の2以上が賛成する必要があります。すなわち、日本においては株主提案が可決されるハードルは高いと言えます。そのため、アクティビスト・ファンドが株主提案を行う背景としては、提案の可決そのものを狙うというよりも、企業に対して、圧力をかけることが狙いとなる場合が多いように思います。
では、エンゲージメント・ファンドの企業とのミーティングによる「対話」についてはどのように考えるべきでしょうか。対話による企業変革には、法的拘束力はなく、どんなに株主が論理的な対話をしたとしても、受け入れるか否かは企業の判断に委ねられます。一方で、現在は外部環境の変化が見られてきています。一つは、2023年3月の東京証券取引所による資本効率改善に向けた要請を受けた、政策保有株を減らす動きです。政策保有株の削減は「物言わぬ安定株主」が減ることを意味します。加えて、2023年8月の経済産業省からの「企業買収における行動指針」により、「真摯な買収提案」に対しては「真摯な検討」をすることが求められるようになりました。これまでは買収の提案を受けても、経営陣が取締役会での検討を経ずに提案を拒否することもあったと推察されます。これらの「物言わぬ安定株主」の減少と買収提案に対する「真摯な検討」の要請により、企業はこれまで以上に買収リスクに晒されることになります。買収提案を避けるためには、株価が割安になった状態を放置しないことが肝要であり、企業には、「対話」により企業価値を向上させるインセンティブが働きやすくなると考えられます。
エンゲージメント・ファンドとアクティビスト・ファンド、どちらが企業価値向上において有効なのかは、企業が自らの意思によって変化する余地があるか否かによって変わってくると思いますが、少なくとも、株式市場の声に耳を傾ける必要性が高まっていると言えます。
スパークス・アセット・マネジメント株式会社
チーフ・アナリスト 川部 正隆
当レポートは執筆者の見解が含まれている場合があり、スパークス・アセット・マネジメント株式会社の見解と異なることがあります。