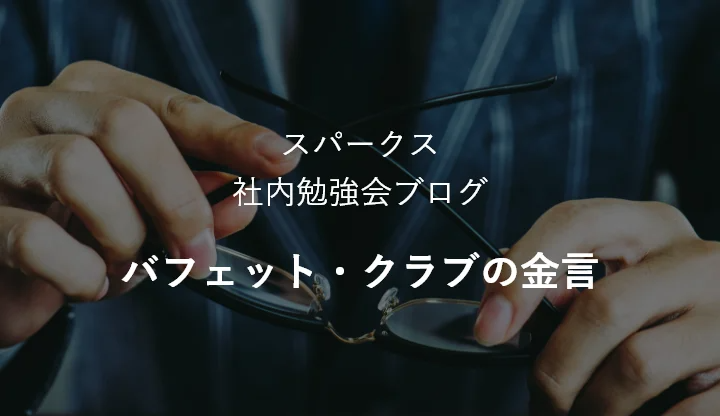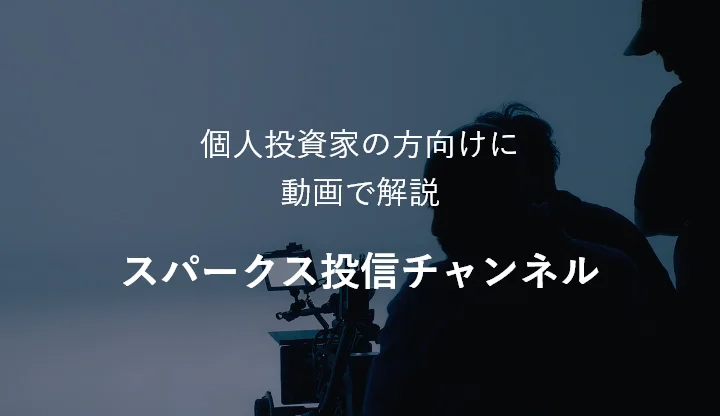スペシャルレポート ニッポン解剖~日本再興へのメカニズム~「実質株主は誰か」
現在、株主名簿上の株主ではなく、その背後で議決権を持つ実質的な株主を把握するための議論が進んでいます。今回のニッポン解剖では、この真の株主である「実質株主」について考えます。
まずは名簿上の「名義株主」と、実際に投資判断や株主総会での議決権を行使している「実質株主」について整理します。機関投資家は保有する株式の管理を信託銀行に委託することが一般的であり、その場合、企業の株主名簿にはこの信託銀行の名前が記載されます。この株主名簿に記載されている株主を、一般に「名義株主」といい、企業はこの名義株主までしか把握することができません。一方で、実際の投資判断や議決権を行使しているのは、この名義株主である信託銀行に株式の管理を委託している資産運用会社などです。資産運用会社に属するファンドマネージャーと企業との対話の現場において、例えば資本収益性の改善について議論していても、そのファンドマネージャーが、当該企業に投資を行っているのかが不明瞭のままで対話が進む、という不思議な状況が生じることがあります。企業と株主との建設的な対話が求められる中で、この実質的な株主が誰なのかを把握するための仕組み作りに関し、現在、議論が進められています。
なぜ今、実質株主を判明させる必要性が出てきているのでしょうか。過去、資産運用会社は、既存株主かどうかによって当該企業への調査面談を断られるリスクを避けるため、保有状況の開示に後ろ向きであったのではないかと推察されます。企業にとっても株主との積極的な対話は求められていなかったため、実質的な株主かどうかを把握する必要性は低かった可能性があります。また、名義株主である信託銀行にとっても、実質株主の開示は事務負担が増えると考えられます。結果として現状の名義株主による運用に至っているのではないでしょうか。昨今、政策保有株の削減により安定株主が減少し、株主構成が複雑化してきています。また日本においてもアクティビストの存在感が増しています。そのため、議決権を行使して企業に影響を及ぼす存在である実質株主の把握と対話の必要性が高まっています。
これまでの名義株主制度の課題として、筆者は、株主総会への参加を挙げたいと思います。投資信託の保有株式に係る議決権行使は、実質株主である資産運用会社が個別議案に対する賛否を判断し、議決権を行使することが実務として定着しています。一方で、実質株主である資産運用会社が株主総会に出席することは、明確な権利としては認められていません。そのため、当該資産運用会社のファンドマネージャーが株主総会に出席できるか否かは企業側の判断に任されており、実質的には出席のハードルは相当高いというのが実情です。株主総会は、本来的には株式会社における最高意思決定機関であるはずです。しかし、「シャンシャン総会」とも揶揄されるように、形式的なセレモニーに留まっていると思われる株主総会も数多くあります。株主総会においても、ファンドマネージャーと企業とが企業価値向上について適切に議論が行われる必要があると思います。実質株主と企業との建設的な対話がより円滑に行われることによって、日本企業ひいては日本社会全体がより良いものになっていくことを願っています。
スパークス・アセット・マネジメント株式会社
チーフ・アナリスト 川部 正隆
当レポートは執筆者の見解が含まれている場合があり、スパークス・アセット・マネジメント株式会社の見解と異なることがあります。