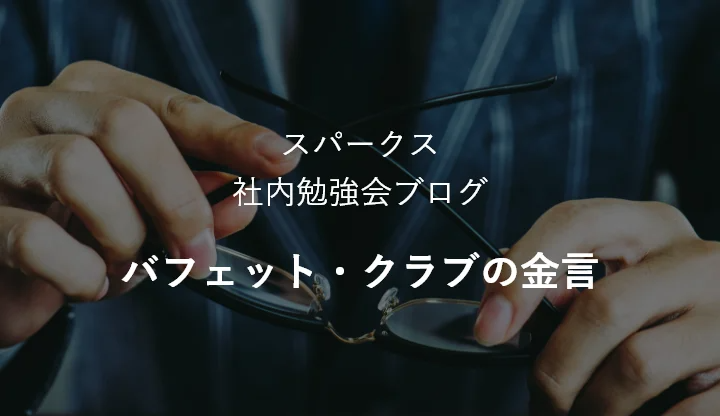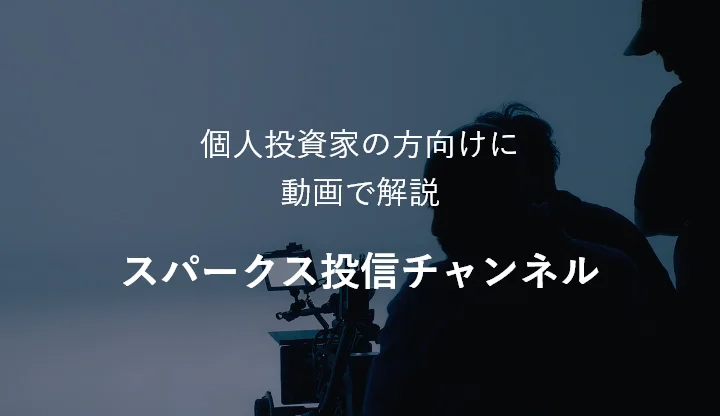スペシャルレポート ニッポン解剖~日本再興へのメカニズム~「IRの体制整備が義務化へ」
企業と株式市場の対話の重要性への理解が進んでいますが、一方でIR活動に対して消極的な上場企業もいまだ多くあります。先般、上場企業に対してIRの体制整備が義務化されるとの報道がありました。有価証券上場規程が定める企業行動規範の「遵守すべき事項」に、IR体制の整備に関する規定が検討されています。この「遵守すべき事項」に違反した場合には、公表措置や違約金の対象になる場合があります。つまりIR活動を行っていない企業に対してペナルティが課せられる可能性が出てきています。
筆者が所属する運用チームも企業にIR面談を申し込んで、拒否されるケースが稀にあります。拒否されるケースを類型化してみると、①メールによるIR面談の打診に対して返答無し、②電話での問い合わせに対して「担当から折り返します」と案内されるもののその後の返答無し、③回答があった場合でもIR体制が整っていないため対応不可、といったパターンです。そういった企業は固定的な既存株主とのみIR面談を行っている場合もあります。時価総額が小さく、安定株主が存在する場合に、不特定の潜在的な機関投資家とのIR面談に対して消極的なケースが多い傾向にあると感じます。企業の発行するコーポレート・ガバナンス報告書には株主や投資家との対話を行っている旨の記載があるにも関わらず、実際には、有名無実化しているケースがあるのは大変残念です。
ここで、なぜIRが上場企業にとって重要なのかを考えたいと思います。改めてIRとは、企業が投資家に対して、財務状況や業績、今後の見通しなどの投資判断に必要な情報を提供する活動全般を指します。バリュー投資の父と呼ばれるベンジャミン・グレアム氏は「投資とは、詳細な分析に基づいたものであり、元本の安全性を守りつつ、かつ適正な収益を得るような行動を指す。そしてこの条件を満たさない売買を、投機的行動であるという」※1 と述べています。詳細な分析を行うためには十分なIRによる企業理解が必要です。IRを通じた企業理解なしに行う投資は投機的行動とも言え、企業価値に基づいた株価形成のためには、IRの充実が肝要と考えます。
企業がIRに消極的となる要因としては、自社の株価への関心の低さが挙げられます。しかし、企業価値に対して株価が低く評価されている場合、買収されるリスクを高めることに繋がります。特に、2023年3月の東京証券取引所による資本効率の改善に向けた要請を受けた政策保有株を減らす動きは、買収防衛の要であった安定株主の縮小に繋がっています。また、2023年8月の経済産業省からの「企業買収における行動指針」により、「真摯な買収提案」に対しては「真摯な検討」をすることが求められるようになりました。つまり、日本企業が買収されるリスクは高まっていると言えます。この買収リスクを下げるためには、株価が企業価値に対して割安な状態を放置しないことが必要になります。IRによる十分な情報開示によって、企業価値を株価に適切に反映させる取り組みが重要となるのです。
今回検討されているIRの体制整備の義務化は、企業自身が買収されるリスクを下げるためにも必要な取り組みであると言えます。
スパークス・アセット・マネジメント株式会社
チーフ・アナリスト 川部 正隆
当レポートは執筆者の見解が含まれている場合があり、スパークス・アセット・マネジメント株式会社の見解と異なることがあります。
※1:ベンジャミン・グレアム、ジェイソン・ツバイク著 『新賢明なる投資家 上』