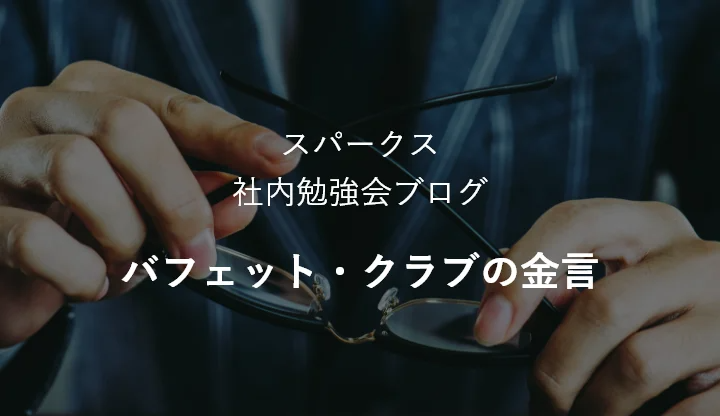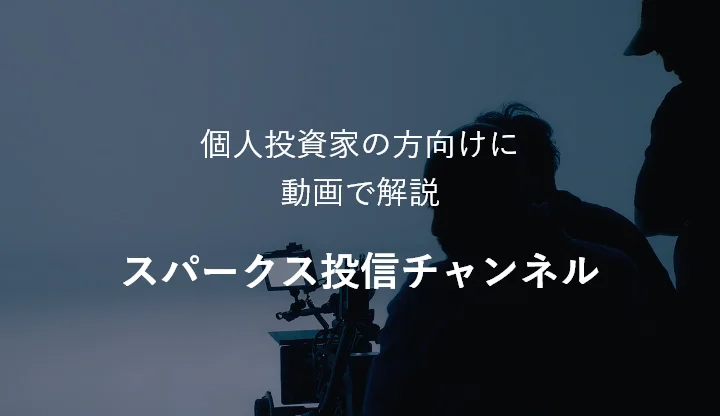スペシャルレポート ニッポン解剖~日本再興へのメカニズム~「社外取締役の真価とは:形式から実質へ」
6月は、3月期決算企業にとって株主総会のシーズンです。株式会社における最高意思決定機関である株主総会では、取締役の選任、剰余金の処分、定款の変更など、会社経営に関わる重要事項が決議されます。今回の「ニッポン解剖」では、株主からの付託を受けて選任される社外取締役の重要性について考えていきます。
社外取締役には、業務執行から独立した立場で、経営陣に対して遠慮なく意見を述べることが求められます。時には、社長交代を主導することも、その重要な役割の一つです。令和元年の会社法改正以降、上場企業には社外取締役の設置が義務づけられ、その浸透が加速しています。取締役会において社外取締役が3分の1以上を占める企業の割合は、2014年には東証一部上場企業でわずか6.4%でしたが、2024年にはプライム市場上場企業の98.1%にまで拡大しています。
コーポレートガバナンス改善などを通じ、企業価値の向上に役立つと期待される社外取締役の導入が進んできたことは評価に値すると思います。一方で、一部の企業においては、社外取締役の人数は増えてきたものの、取締役会の場で、適切な議論をすること無く賛成するなど、形式的な導入に留まっているという批判もあります。また、株主総会で議決権を行使する機関投資家も、社外取締役の実効性の判断が、取締役会への出席率や在任期間など外形的な基準に頼ったものになっている場合も多くあるように思います。2023年3月に始まった東証市場改革も3年目となり、日本の株式市場変革がグローバルな投資家から認められるためにも、社外取締役制度の導入が形式的なものから実質的なものへと変化していく必要があると感じます。
最近では、社外取締役と投資家が対話する機会も増えてきているように感じます。筆者自身も、投資先企業の社長との面談に社外取締役が同席したり、社外取締役と1対1で対話する機会が増えたりと、大きな変化を実感しています。かつては面談の申し出が断られることが多かっただけに、大きな進展であると思います。
ここで、社外取締役との対話で印象に残った事例をご紹介します。
「社内執行側には、事業計画の策定段階から社外取締役にも情報が共有されることを期待しています。完成後では、社外取締役が修正を加えるのは難しいと感じています」
これは、筆者が面談した社外取締役の言葉です。社外取締役が事業計画の詳細に立ち入りたいという意図ではありません。現場からの積み上げだけで作られた計画は、全社としての成長ストーリーに欠けていたり、企業全体の業績に対して十分なインパクトを与えられない場合があります。そういった場合に、社外取締役は、社内のしがらみにとらわれず、業務執行から独立した立場で再考を促すことができます。他にも、事業運営が過度に保守的になっている場合もあり、適切なリスクテイクを促していくことも、社外取締役の重要な役割となります。
社外取締役制度の導入がより実質的なものとなり、その効果が十分に発揮されることで、日本の株式市場の変革が一層良い方向へと進んでいくことを強く期待しています。
スパークス・アセット・マネジメント株式会社
チーフ・アナリスト 川部 正隆
当レポートは執筆者の見解が含まれている場合があり、スパークス・アセット・マネジメント株式会社の見解と異なることがあります。