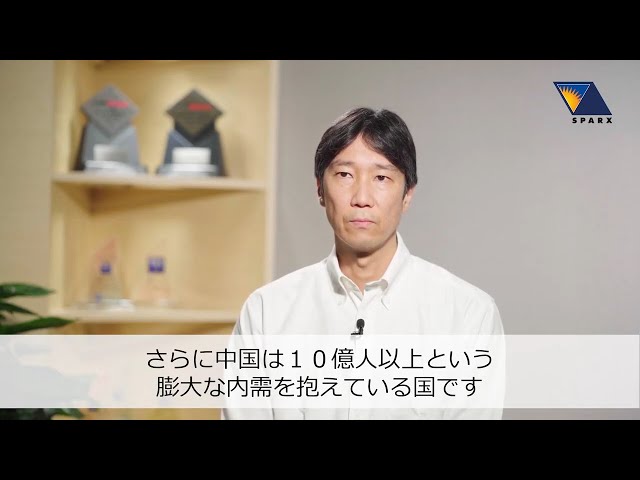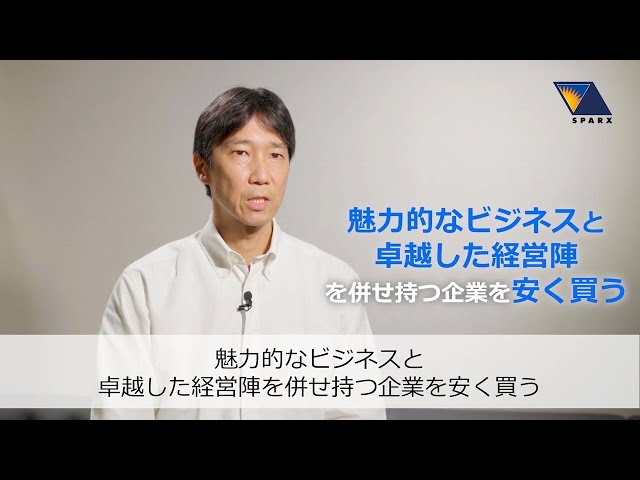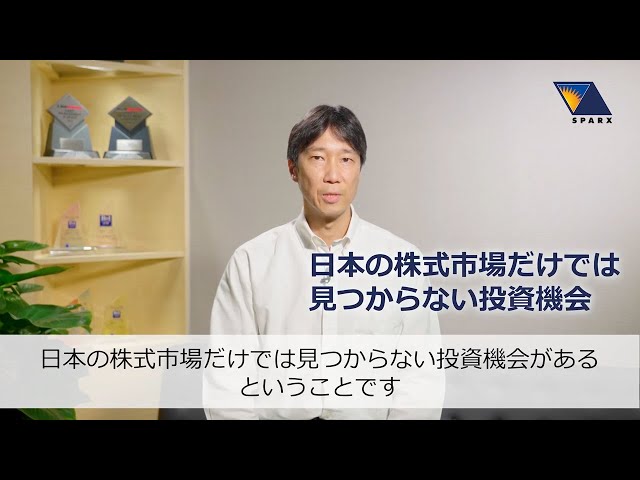スパークス・新・国際優良日本アジア株ファンド
(愛称:日本アジア厳選投資)
- NISA成長投資枠対象ファンド
- 日経新聞掲載名
- 日本アジ厳選
- 分類
- 追加型投信/内外/株式
- 設定日
- 決算日
- 毎年9月12日
基準日:2026.02.25
- 基準価額
- 24,674円
- 前日比
-
+474円
+1.96% - 純資産総額
- 50.7億円
- 分配金情報(税引前)
- 0円
- 当ファンドは、NISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
基準価額推移
分配金実績
決算頻度:1回/年
- 設定来合計
- 0円
- 直近12期計
- 0円
分配金実績一覧
- 2025年09月12日
- 0円
- 2024年09月12日
- 0円
- 2023年09月12日
- 0円
- 2022年09月12日
- 0円
- 2021年09月13日
- 0円
- 2020年09月14日
- 0円
- 2019年09月12日
- 0円
- 上記以前の分配金については、「選択した期間のデータをダウンロード」ボタンからご確認いただけます。
月次報告書
2026年
- 1月(507.3 KB)
2025年
- 12月(489.9 KB)
- 11月(483.2 KB)
- 10月(496.6 KB)
- 9月(496.2 KB)
- 8月(498.5 KB)
- 7月(525.4 KB)
- 6月(532.8 KB)
- 5月(528.6 KB)
- 4月(526.3 KB)
- 3月(528.9 KB)
- 2月(526.8 KB)
- 1月(508.6 KB)
2024年
- 12月(526.0 KB)
- 11月(527.1 KB)
- 10月(505.7 KB)
- 9月(589.8 KB)
- 8月(533.3 KB)
- 7月(557.7 KB)
- 6月(544.9 KB)
- 5月(542.9 KB)
- 4月(532.1 KB)
- 3月(531.1 KB)
- 2月(551.5 KB)
- 1月(530.8 KB)
2023年
- 12月(565.0 KB)
- 11月(527.1 KB)
- 10月(528.2 KB)
- 9月(500.7 KB)
- 8月(498.3 KB)
- 7月(498.0 KB)
- 6月(570.1 KB)
- 5月(562.9 KB)
- 4月(565.9 KB)
- 3月(566.9 KB)
- 2月(576.0 KB)
- 1月(562.1 KB)
2022年
- 12月(557.0 KB)
- 11月(603.9 KB)
- 10月(692.5 KB)
- 9月(616.2 KB)
- 8月(613.4 KB)
- 7月(609.6 KB)
- 6月(595.5 KB)
- 5月(565.4 KB)
- 4月(606.6 KB)
- 3月(789.0 KB)
- 2月(620.2 KB)
- 1月(676.8 KB)
2021年
- 12月(580.4 KB)
- 11月(583.0 KB)
- 10月(611.1 KB)
- 9月(584.0 KB)
- 8月(658.6 KB)
- 7月(599.3 KB)
- 6月(571.9 KB)
- 5月(580.0 KB)
- 4月(600.6 KB)
- 3月(826.7 KB)
- 2月(684.0 KB)
- 1月(684.6 KB)
2020年
- 12月(847.1 KB)
- 11月(631.0 KB)
- 10月(819.1 KB)
- 9月(645.3 KB)
- 8月(681.8 KB)
- 7月(822.5 KB)
- 6月(672.7 KB)
- 5月(669.9 KB)
- 4月(652.1 KB)
- 3月(635.7 KB)
- 2月(655.0 KB)
- 1月(641.7 KB)
2019年
- 12月(720.8 KB)
- 11月(637.7 KB)
- 10月(973.8 KB)
- 9月(675.4 KB)
- 8月(636.9 KB)
- 7月(575.0 KB)
- 6月(571.6 KB)
- 5月(644.7 KB)
- 4月(557.6 KB)
- 3月(612.6 KB)
- 2月(593.6 KB)
- 1月(579.3 KB)
2018年
- 発表年
- キーワード検索
「」の検索結果
2026年1月の運用コメント
株式市場の状況
<⽇本の株式市場>
2026年1月、日本株式市場の代表的な指数であるTOPIX(配当込み)は前月末比4.62%上昇し、日経平均株価は同5.93%の上昇となりました。
月前半は、米国半導体関連株の大幅上昇を受けて日本の半導体・AI(人工知能)関連株が買われ、大発会から日経平均株価は大幅高でスタートしました。中国政府によるレアアース関連製品を含めた対日輸出規制が強化されるとの報道で、日本株式市場が一時急落する場面はあったものの、衆院解散・総選挙観測を受けて高市首相が掲げる成長戦略が進めやすくなるとの見方を背景に、月半ばにかけて主要指数の高値更新が続きました。
月後半は相場の様相が一変しました。選挙戦の本格化や野党の新党結成を受けて国内の政治情勢の不透明感が台頭したことに加え、米欧の貿易摩擦懸念など地政学的リスクも意識され、投資家心理が悪化しました。さらに、財政拡張による財政悪化懸念から国内長期金利が想定を上回るペースで上昇し、株式市場は調整色を強めました。月末にかけては、日米当局による「レートチェック」報道をきっかけに為替相場が急変し、円は一時対ドルで153円台まで上昇するなど不安定な動きとなり、輸出関連株を中心に株式市場は揺さぶられました。日本株式市場は月後半に伸び悩みましたが、前月末比で大幅高の水準を維持して当月の取引を終えました。
<アジアの株式市場>
当月、⽇本を除くアジア市場に使⽤される⼀般的な指数であるMSCI AC Asia ex Japan Index(⽶ドル建て)は、前月末比8.21%上昇しました。パフォーマンスは地域によって大きく異なり、特に韓国と台湾が大幅に上昇する一方、インドネシアとインドは伸び悩みました。
韓国のKOSPI(韓国総合株価指数)は前月末比23.97%上昇し、初めて5,000ポイントの大台を超え、1月30日には史上最高値となる5,224ポイントに達しました。この上昇の背景には、AI(人工知能)アクセラレーター(AIの計算処理を高速化するために特化して作られた半導体)に不可欠な広帯域メモリー(HBM)チップの需給逼迫がありました。需要の急増により、Samsung Electronics社とSK hynix社は、四半期ベースで過去最高の営業利益を計上し、株価はそれぞれ前月末比33.6%、同38.7%上昇しました。さらに両社の生産ラインは少なくとも2027年まで予約で埋まっており、供給制約が当面解消しないとの見方が、価格決定力の強化や利益率改善の期待につながりました。こうした企業業績の改善が、韓国市場を押し上げる主因となりました。
台湾のTAIEX指数は、堅調な業績と2026年業績予想が市場に好感されたTaiwan Semiconductor Manufacturing Company社が市場をけん引する形で、前月末比10.70%上昇しました。同社は利益率の拡大とAI関連需要の継続を踏まえ、2026年の設備投資額は520~560億米ドルを費やすと発表し、収益成長率も30%に達する見込みであるとしました。この勢いはMediaTek社をはじめとする台湾の他の半導体企業にも及びました。
中国・香港市場も、政府の国内消費刺激策と技術革新促進策を追い風に、堅調に推移しました。香港では1月に新規株式公開(IPO)が複数実施され、さらに300件以上の申請が進行中であることが、市場の楽観姿勢を後押しする形となりました。
一方、インドネシアのジャカルタ総合指数は、米国の指数算出会社であるMSCI社が1月27日に株主構成の不透明さと浮動株比率の低さを理由に、算出する指数でのインドネシア銘柄の新規採用や組入比率の引き上げを凍結すると発表したことを受け、29日には一時27日比17%下落しました。MSCI社はさらに、2026年5月までに透明性が改善されなければ、同国が新興国市場からフロンティア市場へ格下げされる可能性もあり得ると警告しており、実現した場合には同市場から数十億ドル規模の資金流出が懸念されます。
インド市場は当月、投資家の志向が韓国と台湾のAI半導体銘柄に傾き、インド国内市場の成長シナリオが十分に評価されなかったことにより、前月に引き続き軟調に推移しました。加えて、トランプ政権の関税政策の先行きが読めず、インドの一部輸出品に50%の関税を課すという脅しがあったことも、逆風が強まるきっかけとなりました。
ファンドの運用状況
当月、当ファンドは前⽉末⽐5.55%上昇し、参考指数であるMSCI AC Asia Index(円ベース・配当込み)の同6.21%の上昇を0.66%下回りました。
セクター別では、資本財・サービスセクター、情報技術セクターなどがプラスに寄与した一方、一般消費財・サービスセクター、エネルギーセクターなどがマイナスに影響しました。
銘柄別では、Taiwan Semiconductor Manufacturing Company(台湾/半導体・半導体製造装置)、Samsung Electronics(韓国/テクノロジー・ハードウェアおよび機器)、Zijin Mining Group(中国/素材)などがプラスに寄与した一方、Hesai Group(中国/自動車・自動車部品)、NEC(ソフトウェア・サービス)、ソニーグループ(耐久消費財・アパレル)などがマイナスに影響しました。
世界は再び弱肉強食の時代へ
当月に米国はベネズエラで軍事作戦を実施し、マドゥロ大統領(当時)を拘束しました。さらに、トランプ米大統領がグリーンランドを米国に売却するようデンマークに要求し、米欧間の軍事的緊張が高まっています。グリーンランドの問題がどうなるのかは本コメントの執筆時点では依然不透明ですが、世界は弱肉強食の世界、すなわち経済的圧力と軍事力が支配する世界に戻ってしまったようです。こうした状況が追い風となって、貴金属に加え、例えば銅などの戦略物資(国の安全保障や戦争遂行に影響を与える食料・石油・重要金属などの物資)の中で供給不足に陥る危険性のある品目の価格が高騰しています。2025年10月の運用コメントで述べたように、当ファンドはアジア最大の鉱山会社、Zijin Mining Group(中国/素材)を保有していますが、同社の主な取扱品目は銅と金です。
貴金属はもちろん重要ですが、弱肉強食の世界で何よりも重要なのが防衛力であることは火を見るより明らかです。軍事力は弱肉強食の世界で国力を保つための礎なのです。防衛費は2022年以降上昇傾向にありますが、今後数年間にわたって上昇基調を維持すると考えられます。当ファンドは2023年後半より、装甲車両や自走砲など地上兵器を製造する韓国の大手メーカーHanwha Aerospace(韓国/資本財)を組み入れ、防衛セクターへの投資を開始しました。
アジアの防衛産業における投資先として当ファンドが主に韓国企業へ投資する理由は、欧州および中東市場向け輸出競争力が高いためです。韓国は比較的小さな国であるにも関わらず、米国、ロシア、中国といった超大国を除けば世界有数の軍事力を保有していると広く認識されています。韓国は恒常的に北朝鮮の脅威に晒されているため、GDPの約3%を防衛費に充てており、数十年にわたって投資を行った結果、韓国の兵器は世界的にみてきわめて高い競争力を保持するに至っています。過去約2年にわたり、当ファンドはHanwha Aerospace社またはLIG Nex1(韓国/資本財)に投資してきており、相対的なバリュエーションに応じて両銘柄を組み替えてきました。その結果、両銘柄とも大きなリターンを生み出し、過去3年間のパフォーマンスにおいて大きく貢献しました。なお、現時点ではLIG Nex1のみを保有しております。
当ファンドは韓国銘柄に加え、防衛関連銘柄としてインドのBharat Electronics(インド/資本財)にも投資をしています。さらに防衛装備品専業ではないものの、防衛分野に部分的に関与する企業として、NEC(レーダーや指揮管制システムを製造)やHD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING(韓国/資本財、海軍艦艇を製造)なども保有しています。一方、中国の防衛関連企業に関しては、制裁リスクが高いため、組み入れていません。アジアは製造効率が高いこと、サプライチェーンが強力であることで知られており、防衛関連のエコシステムで全域にかなりの投資機会があるとみています。
本運用コメントでは「LIG Nex1」をご紹介します。
実は同社を初めて組み入れたのは2024年半ばのことでした。しかし2025年半ばにイスラエルがイランに対しミサイル攻撃を行った後に株価が急騰した局面で利益確定を行いました。同社株価は2024年4月から2025年6月にかけて200%強上昇し、その後最高値からおよそ40%調整し、2025年12月に直近の底値に達しました。当ファンドは2025年12月に同銘柄を売却時点より安値で買い戻しました。LIG Nex1は精密誘導兵器(PGM)および戦車の戦闘システムや戦闘機の航空電子機器など防衛電子機器を製造する韓国の大手企業です。現在の戦争では戦車をはじめとする従来型の兵器に比べ、誘導ミサイルや電子戦機の重要性が高まっているため、同社は将来の戦闘環境に適した事業ポジションを有していると考えます。Hanwha Aerospace社が欧州や中東の陸上兵器の在庫補充と近代化を事業成長の主な原動力としているのに対し、LIG Nex1の成長の推進力は、兵器システム、特に防空システムの将来的な進歩にあります。
韓国防衛産業のビジネスモデル
韓国の新兵器開発プロジェクトは以下のような流れで進行します。
- 韓国軍がプロジェクトを立案し、国内の防衛関連企業を選定する。
- LIG Nex1をはじめとする防衛関連企業は営業利益率をきわめて低水準に抑えた状態で研究開発を行う。この研究開発は5年から10年続く場合があるが、基本的に韓国軍から資金提供を受けて実施する。
- 研究開発が終わると防衛関連企業は量産を開始し、兵器を韓国軍に売却するが、研究開発費を提供してもらった見返りとして、営業利益率を一般に10%以下に抑える。
- 海外から引き合いがあれば、防衛関連企業は兵器システムを海外に販売できる(韓国政府の承認が必要)。製品によるが、輸出する場合の営業利益率は一般に10%を上回る。現行環境下では、ものによっては20%以上、あるいは30%以上の利益率で輸出できる兵器システムさえある。
こうしたビジネスモデルにはいくつか利点があります。
- 韓国軍からいつどのような要請があるか読みやすく、かつ需要が安定的であること(韓国の戦力増強計画に基づく支出は2024年から2028年にかけて年平均12%成長するという試算がある)。
- 最重要要素として、韓国の防衛関連企業は日本のそれと異なり、兵器を積極的に輸出し、より高い利益率を得ることが可能だということ。
- 韓国の防衛関連企業は兵器の種類ごとに専門化が進んでおり、国内プロジェクトに関しては競争がそれほど熾烈でないこと。
LIG Nex1は韓国の防衛関連企業の中でも最大級の研究開発要員を抱えています。2025年第3四半期時点で全従業員の59%以上にあたる約3,200人が研究開発に従事しており、その48%が博士号または修士号を取得していることから、韓国軍から研究開発プロジェクトを獲得する上で有利な立場にあると考えられます。同社の研究開発サービス収益は2021年の約3,780億ウォンから2024年にはおよそ2.5倍の約9,280億ウォンとなっており、開発中の製品は多岐にわたっています。具体的には、自律システム、新型防空システムM-SAM III(中距離地対空ミサイル、いわゆる「韓国版アイアンドーム」)など、将来性の高い案件が複数進行しています。
輸出の可能性
韓国の兵器は世界的に普及しつつあり、その主な例としてはHanwha AerospaceのK9自走砲やHyundai Rotem社のK-2戦車などがあげられます。
LIG Nex1の現行の主力製品はM-SAM IIで、すでにアラブ首長国連邦、イラク、サウジアラビアから発注されています。これはその名の通り、ミサイルや航空機のような飛行物体を攻撃する兵器です。主な競合製品は米国製のPAC-3、別称パトリオット3ですが、M-SAM IIはパトリオットに匹敵する性能を持ちながら、コストはおよそ半分で済むと言われています。
近年の武力紛争においては、部隊を前線に送らずとも高精度な攻撃が可能にするミサイルの重要性が高まっています。一方でミサイルやドローンの使用増加に伴い、対空防衛システムの需要も増しています。当ファンドはLIG Nex1が世界的な市場シェアを獲得できると考えており、M-SAM以外にも長距離防空システムL-SAM(長距離ミサイル)は韓国での配備が始まる見込みで、これも将来的な輸出拡大につながる可能性があります。
2025年第3四半期現在、同社の受注残高は23.4兆ウォンで、これは2025年の推定売上高の約5.7倍に相当します。そのうち50%以上は輸出品で、アジアや北アフリカなど、中東以外の国からも引き合いが多数きていることから、同社が今後も継続的に海外から受注を獲得すると当ファンドは見込んでいます。
ロボティクス
長期的にみると、同社は防衛用電子機器の主要メーカーであることから、無人兵器台頭の恩恵に浴する上で優位な立場にあります。同社は2024年、米国に拠点を置く四足歩行犬型ロボットの主要メーカーGhost Robotics社の株式を60%取得しました。Ghost Robotics社は依然として赤字で(営業利益にして推定十数%分のマイナス要因)、主に米国の政権交代、特に米政府効率化省の施策で昨年の政府支出に上限が設けられたことが原因で、回復が予想より遅れています。しかし、トランプ大統領が国防費の大幅な増額を画策していることから、事業は回復基調に向かうものと思われます。
2025年12月の運用コメント
株式市場の状況
<⽇本の株式市場>
2025年12月、日本株式市場の代表的な指数であるTOPIX(配当込み)は前月末比1.03%上昇し、日経平均株価は同0.17%の上昇となりました。
月前半は、植田日銀総裁の発言を受けて12月会合での利上げ観測が高まり、長期金利が急上昇しました。この影響から銀行株を除く幅広い銘柄が売られ、主要指数は大きく下落しました。その後、米国の利下げ期待や、米政府がロボット産業を支援する方針を示したことを受け、FA(ファクトリーオートメーション)、ロボットなど「フィジカルAI(人工知能)」関連株が急伸し、相場全体をけん引し、TOPIXは史上最高値を更新しました。
月半ばには、米国の利下げ決定後に一時的な調整も見られましたが、米国株が堅調で主要指数が高値を更新するなか、日本市場でも買いが優勢となり、TOPIXは再び最高値を更新しました。しかしその後、米IT大手Oracle社のAIデータセンター完成の遅れや、半導体大手Broadcom社の決算が市場期待に届かなかったことなどから、AI投資の収益性に対する警戒感が高まり、半導体関連株を中心に売りが広がり、相場は調整色を強めました。
月後半は、日銀が利上げを決定したものの、総裁会見がハト派的と受け止められたことから円安が進行し、輸出関連株や半導体株を中心に買いが入りました。ただし、月末にかけては薄商いの影響もあり、相場は方向感を欠く展開となりました。結果として、TOPIXは相対的に底堅く上昇基調を維持し、日経平均株価も小幅ながら前月を上回って当月の取引を終えました。年間を通してみると、年前半に大きな下落に見舞われる場面があったものの、年後半には両指数とも高値更新を続け、高水準での推移となりました。
<アジアの株式市場>
当月、⽇本を除くアジア市場に使⽤される⼀般的な指数であるMSCI AC Asia ex Japan Index(⽶ドル建て)は、前月末比2.75%上昇し、2025年通年では前年比33.02%の上昇となりました。トランプ米大統領が「解放の日」に発表した関税政策をきっかけに未曽有の乱高下が発生したものの、結果として世界の主な株式市場は大幅に上昇して1年を終えました。
アジア市場で上昇幅が大きかったのは、韓国のKOSPI(前年比75.63%上昇)、中国のMSCI China Index(同28.31%上昇)、香港のHSI(同27.77%上昇)、台湾のTAIEX(同25.74%)でした。一方、ASEAN市場は相対的に軟調でした。
韓国市場は今年堅調に推移しましたが、その原動力となったのはSamsung Electronics(前年比126.32%上昇)とSK hynix(同274.93%上昇)でした。AI(人工知能)データセンターで使用される広帯域メモリー(HBM)の需要が旺盛だったことが両社の追い風となりました。加えて、防衛および造船銘柄もKOSPI指数の上昇に大きく貢献しました。
台湾のテクノロジーセクターは、Taiwan Semiconductor Manufacturing Company社(前年比44.19%上昇)を中心に、力強い上昇基調を維持しました。同社は台湾、米国、日本に工場を構え、先端AIチップ向け半導体ファウンドリ分野で揺るぎない地位を維持しています。
中国は米国の関税政策の主要対象となり、また不動産市場が軟調であったにもかかわらず、株式市場は底堅い動きをみせました。これは、Deepseek社をはじめとするテック企業群、EV(電気自動車)、ロボティクスなどの成長分野の活況と、それらの強力な製造能力に支えられたためと考えられます。また、中国政府が国内企業の技術革新と消費を促進する方針を示したことが、投資家心理の改善につながりました。香港市場も、国内外の投資家が有望な投資機会を求めて回帰したことで大きく反発しました。また、2025年の新規株式公開(IPO)件数は117件となり、同市場のIPO資金調達規模は世界トップクラスとなりました。
ASEAN市場は、貿易関税に関する不透明感、国内経済の低迷、政策面での不安定感が投資家心理に影響を及ぼしたことで、通年ではまちまちのパフォーマンスとなりました。インドネシアでは、プラボウォ大統領が打ち出した学校給食無償化政策や低価格住宅支援制度の施行が難航しました。加えて、世界的なコモディティ市場の低迷も、輸出が伸び悩む要因となりました。タイでは政権交代、フィリピンでは洪水対策事業を巡る汚職問題などの政治リスクが、両市場への投資意欲を減退させる要因となりました。インド市場は、企業収益の伸びが鈍化したほか、投資家が韓国と中国・香港に資本を再配分したことから、小幅な伸びにとどまりました。
ファンドの運用状況
当月、当ファンドは前⽉末⽐0.01%下落し、参考指数であるMSCI AC Asia Index(円ベース・配当込み)の同2.21%の上昇を2.22%下回りました。
セクター別では、情報技術セクター、金融セクターなどがプラスに寄与した一方、コミュニケーション・サービスセクター、一般消費財・サービスセクターなどがマイナスに影響しました。
銘柄別では、Samsung Electronics(韓国/テクノロジー・ハードウェアおよび機器)、Taiwan Semiconductor Manufacturing Company(台湾/半導体・半導体製造装置)、Zijin Mining Group(中国/素材)などがプラスに寄与した一方、任天堂(メディア・娯楽)、ソニーグループ(耐久消費財・アパレル)、Samyang Foods(韓国/食品・飲料・タバコ)などがマイナスに影響しました。
1年の振り返り
当ファンドのパフォーマンスは前年末比25.31%の上昇となりました。絶対リターンが堅調だった一方、相対リターンはやや劣後しました。これは前月の運用コメントでも述べた通り、年末にかけて行った組入銘柄の入れ替えにより、相対パフォーマンスが大幅に低下したためです。実際、2025年は世界的に強気相場となり、主要市場の多くが米ドル建てリターンで15%超の堅調なリターンを記録しました。特にMSCI ACWI Indexでは、幅広いセクターが良好なリターンを示しました。こうした市場環境により、指数との差別化が難しい局面となりました。
アジア市場はインドを除き堅調な一年となり、MSCI AC Asia Index(⽶ドル建て)は前年末比30.22%上昇しました。以下は米ドルベースでみた2025年の主要市場のパフォーマンスです。
2025年11月の運用コメント
株式市場の状況
<⽇本の株式市場>
2025年11月、日本株式市場の代表的な指数であるTOPIX(配当込み)は前月末比1.42%上昇し、日経平均株価は同4.12%の下落となりました。
月前半は、AI(人工知能)関連銘柄の前月までの上昇に対する過熱感が意識され、米国株式市場にて関連銘柄が大幅に調整した影響が日本株式市場にも波及しました。一方でバリュー株や内需株等は底堅く推移し、これらのウェイトの差異が指数の変動に大きな影響を与えた結果、日経平均株価の下落が大きくなり、他方TOPIXは相対的に底堅さを維持しました。
月半ばには、日中関係の緊張を背景に中国政府が渡航自粛を要請したことが嫌気され、日経平均株価、TOPIXの両指数とも再び大きく下落し、日経平均株価は節目の5万円を割り込む場面も見られました。その後は、米国株式市場においてNVIDIA社が好決算を受け、時間外取引で同社株が上昇したことが追い風となり、日本株式市場でもアドバンテスト、東京エレクトロン、ソフトバンクグループの3銘柄が日経平均株価を約700円押し上げる場面も見られるなど株価は持ち直しましたが、AI投資の過熱感に対する警戒は根強く、上値の重い展開が続きました。
月後半にかけては、FRB(米連邦準備制度理事会)高官のハト派的発言を受けて12月利下げ観測が再び高まり、米国株の持ち直しとともに日本株式市場も反発しました。結果として、日経平均株価は8か月ぶりの下落となった一方、TOPIXは小幅ながらも上昇を確保し、両指数のパフォーマンスはまちまちとなり、当月の取引を終えました。
<アジアの株式市場>
当⽉、⽇本を除くアジア市場に使⽤される⼀般的な指数であるMSCIアジア指数(⽇本を除く、⽶ドル建て)は、前月末比2.83%下落しました。AI(人工知能)関連銘柄のバリュエーションが割高な水準に達したことに加え、FRB(米連邦準備制度理事会)の金利政策をめぐる不透明感が再燃したことで、企業業績の底堅さが相殺されたことを背景としています。アジアの国別ではパフォーマンスにばらつきが見られ、MSCI香港指数、MSCIフィリピン指数、MSCIインドネシア指数などは上昇した一方、半導体およびAI関連銘柄の比率が高いMSCI韓国指数とMSCI台湾指数は大幅に下落しました。
韓国市場と台湾市場はAI関連銘柄の比率が高いことから、当月は大幅な株価下落となりました。AI事業の業績と見通しが堅調であるにもかかわらず、投資家は関連銘柄の売却を通じて年初来利益の確定に踏み切りました。Taiwan Semiconductor Manufacturing Company社(前月末比4.00%下落)、Samsung Electronics社(同5.76%下落)、SK hynix社(同4.11%下落)などの主要な関連銘柄は、株価上昇の勢いが衰え、前月のピークから下落に転じました。
一方、バリュー株やAI関連以外のセクターは当月堅調に推移しました。香港市場はAIA Group社(同6.83%上昇)を中心に上昇し、インド市場やASEAN市場は、堅調な消費、財政面の支援、サプライチェーンの多様化といった内需主導のファンダメンタルズに支えられて底堅く推移しました。またエネルギー、公益事業、ヘルスケアの各セクターも市場全般を上回るパフォーマンスを示しました。
ファンドの運用状況
当月、当ファンドのパフォーマンスは、前⽉末⽐5.35%の下落となり、参考指数であるMSCI AC Asia Index(円ベース・配当込み)の同0.85%の下落を4.50%下回りました。
セクター別では、金融セクター、生活必需品セクターなどがプラスに寄与した⼀⽅、資本財・サービスセクター、一般消費財・サービスセクターなどがマイナスに影響しました。
当ファンドのパフォーマンスにプラスに寄与した銘柄は、オリックス(金融サービス)、Samyang Foods(韓国/食品・飲料・タバコ)、ソニーグループ(耐久消費財・アパレル)などでした。⼀⽅、マイナスに影響した銘柄は、サンリオ(一般消費財・サービス流通・小売り)、フジクラ(資本財)、Hon Hai Precision Industry(台湾/テクノロジー・ハードウェアおよび機器)などでした。
当月、当ファンドは大幅な下落に見舞われました。残念ながら、その下落幅は市場の下落幅を上回りました。当月のコメントでは、その要因とポートフォリオの現状について説明します。
2025年8月の運用コメントでは、市場がきわめて投機的でモメンタム株主導になっているため、警戒が必要だと指摘しました。しかし残念なことに、当ファンドの運用手法は思い通りにいきませんでした。
第一の理由は、当ファンドは急落局面では市場より下落幅が大きくなる傾向があることです。当ファンドは高成長銘柄と割安銘柄のバランスを意識して運用していますが、実際には高成長銘柄に比重が高くなる傾向があります。さらに、組入銘柄の中で割高な水準まで株価が上昇した銘柄や、ファンダメンタルズ(企業の基礎的収益力)悪化が懸念される銘柄のリスク管理には注力していますが、市場全体の下落を予測したポジションの調整は行っておりません。したがって、ディフェンシブな特性を有するという理由だけで投資先を選定することはほぼありません。当月、組入銘柄の中で最も好調だったのはCTF Services(香港/資本財)でした。同社は中国の有料道路や物流資産といったインフラ資産を所有する香港のコングロマリットで、香港の保険会社も所有しています。配当利回りは7~8%と安定していますが、成長性はほとんどありません。当ファンドが同社を保有しているのは、2026年上期頃に株価上昇材料が出てくると見込んで、配当を受け取りながら保有を続けていますが、このような銘柄を保有するのは例外的です。
AI(人工知能)関連銘柄の動向
第二の理由は、AI関連銘柄が当月急落したことにあります。当ファンドの直接的AI銘柄の組入比率は、半導体や関連ハードウェア銘柄も含めておよそ20%です。三菱重工業(資本財)、日立製作所(資本財)、Contemporary Amperex Technology(中国/資本財、世界有数の電池メーカー)などの発電や電化といった関連テーマの企業まで含めると、合計組入比率はおおよそ20%台後半に達します。当ファンドがAIを前向きにみていることを考えれば、これは許容できる水準だと考えます。なお、MSCI世界株価指数およびMSCI米国指数における情報技術セクターの構成比はそれぞれ約27%、約34%であり、この点から見ても、当ファンドは米国中心のポートフォリオと比べてテクノロジー関連のリスクが高いわけではありません。
当ファンドは急落局面でもテクノロジーセクター全般の組入比率を大きく変えず、電力、メモリ、最先端ファウンドリなど、確信度の高い銘柄に重点を絞りました。
AIの将来については引き続き楽観的にみていますが、市場の一部で投機的な動きが強まっており注意が必要です。AIに関する当ファンドの見解は、本運用コメントの末尾で改めて述べます。
AI以外の銘柄の動向
AI関連銘柄の下落もさることながら、本当の意味で失望したのはAI関連以外の保有銘柄の下落でした。AI関連以外の銘柄は大きく2つのグループに分けられます。
- 株価の連動性を過小評価した銘柄
一つ目のグループは、ファンダメンタルズに問題がないにもかかわらず、市場心理の悪化に伴って下落した銘柄です。例えば、航空エンジン等を手掛けるIHI(資本財)、造船会社であるHD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING(韓国/資本財)、ASEANの配車・フードデリバリープラットフォームを展開するGrab Holdings(シンガポール/運輸)などがこれに相当します。これら企業のファンダメンタルズはAIとは無関係ですが、市場がモメンタム主導になり、株価が一斉に下落する中で、当ファンドは株価の連動性を過小評価してしまいました。
しかしこれら企業のファンダメンタルズは依然堅調で、バリュエーションも妥当と考えています。例えばHD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERINGの株価は12か月予想PER(株価収益率)10倍弱で、今後数年間で収益性改善が見込め、配当利回りも3%強です。また、韓国政府が推進する企業価値向上プログラムによって同社は配当性向を引き上げる可能性もあり、さらに高い配当利回りを提供することも期待されます。市場が回復すれば、株価も再び上昇するというのが当ファンドの見方です。
-
業績が期待外れに終わったために反落した銘柄
二つ目のグループは、きわめて割高な水準まで株価が上昇したものの、その後の業績が期待外れに終わった銘柄です。当ファンドは2025年8月の運用コメントで、このところのモメンタム株の急騰には警戒が必要だと指摘し、一部の銘柄については組入比率を大幅に引き下げました。この判断自体は正しかったものの、やり方が不十分でした。実際、当ファンドが調査対象としている他の企業の多くも、株価チャートを見ると同じような形で推移しています(下図参照)。これは市場全体にモメンタム主導的な特性が現れたためであるというのが当ファンドの見方です。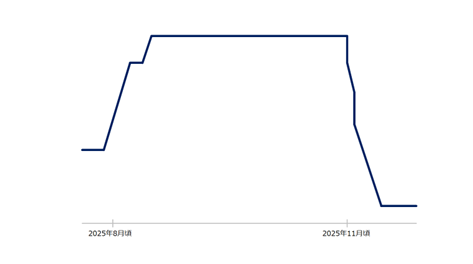
※画像はイメージです。
出所:スパークス・アセット・マネジメント
以下は、当ファンドが下落前に売却し、損失を回避できた主な銘柄です。- MakeMyTrip(インド/消費者サービス、2025年9月に売却済み):インド最大のオンライン旅行代理店(OTA)
バリュエーションが上昇したことから、投資先としてより有望な銘柄が他にあるという考えに至りました。同時に、インドはマクロ経済が減速しており、株価はきわめて弱含みとなっていて、10月から11月にかけて株価は約20%下落しました。ただし長期的なファンダメンタルズは依然として魅力的で、バリュエーションが割安になれば再度組み入れたいと考えて動向を注視しています。
- Sea(シンガポール/メディア・娯楽、2025年9月に売却済み):ASEAN最大のインターネット企業
2024年夏に組み入れを開始して以来、きわめて堅調に推移しました。しかし台湾とブラジルで競争が激化する中で、バリュエーションが高水準に達しました。同社の投資拡大を受け、10月から11月にかけて株価は約20%下落しました。同社は過去の競争局面でも、強固な経営基盤を生かして切り抜け、その基盤を強めてきました。当ファンドは今回も同様の展開を期待しており、状況を慎重に注視しながら、バリュエーションが再び割安になった時点で再度組み入れる意向です。
- Pop Mart International Group(中国/一般消費財・サービス流通・小売り、2025年10月に売却済み)
2025年7月の運用コメントで取り上げた銘柄で、長期的なファンダメンタルズは引き続き良好であるとみていますが、8月の好決算後に市場期待が過度に高まり、8月だけで株価がおよそ30%上昇と短期的な過熱感が見られました。人気キャラクター「LABUBU」への過剰な期待が一時的に株価を押し上げており、今後の業績達成にはリスクがあると判断しました。当ファンドはバリュエーションが再び割安になった時点で再度組み入れたいと考え、動向を注視しています。
以下は11月に発生した株価下落の影響を全面的には回避できず、損失が発生した主要組入銘柄です。
- ヨネックス(耐久消費財・アパレル、2025年11月に売却済み):世界有数のバドミントン用品メーカー
2025年3月期第1四半期決算後に株価が急騰しましたが、当ファンドは利益率の一時的上振れと判断し、組入比率を引き下げました。2026年3月期第2四半期決算は、一過性のものを含めた複数の要因から利益率が低下し割高であると考え、最終的に全て売却しました。売却直後に高市首相の発言がきっかけで日中関係が悪化し、同社の株価はさらに下落しましたが、当ファンドはその下落を回避することができました。同社は中国事業への依存度が高く、今回の関係悪化は懸念材料となり得ます。主要競合先であるLi-Ning Company社(中国)は、バドミントン事業の拡大に強い意欲を示しており、2025年上期の同事業の成長率は30%超に達しました。そのため両国の緊張が長引けば、同社に市場シェアを奪われる可能性があります。売却価格は高水準であったため、当ファンドは利益を確保できました。ヨネックスは年初来のファンド寄与度において、依然として上位に位置しています。 - サンリオ(一般消費財・サービス流通・小売り、引き続き保有中):
サンリオは当ファンドの長期保有銘柄の一つです。2026年3月期第1四半期決算が好調だったことを受けて、8月に組入比率を引き下げました。当月に発表された2026年3月期第2四半期決算では、北米市場およびアジアの一部地域で業績の頭打ちへの懸念をある程度裏付ける内容でした。これは、前年の「ハローキティ50周年」関連イベントの反動が影響したものとみられます。一方で、今年は「クロミ」や「マイメロディ」など他キャラクターのプロモーションを強化していますが、その効果はまだ十分に業績に反映されていません。ただし北米では確かに減速が見られるものの、明るい兆しもあります。北米におけるハローキティ以外のキャラクター(複数キャラクターを含む)の売上構成比は、2025年3月期上期の7%から2026年3月期上期は42.1%に上昇しています。これは他のキャラクターに由来する売上成長が32%に達したことを意味し、キャラクターポートフォリオの多様化戦略は順調に進んでいるように見受けられます。もっとも、同社が前年の高い比較基準を乗り越えるにはまだ時間を要するとみられるため、当ファンドは決算発表後に組入比率をさらに引き下げました。その後、高市首相の発言をきっかけに日中関係が悪化しました。現在、同社の組入比率は当ファンドの中で最も低い部類に入ります。ただし、株価が高水準にあった時期にポジションを削減したため、年初来寄与度は依然としてプラスとなっています。
- MakeMyTrip(インド/消費者サービス、2025年9月に売却済み):インド最大のオンライン旅行代理店(OTA)
振り返ってみれば、過熱感のある銘柄を一部売却していなければ、下落幅はさらに大きかったと考えられます。しかしながら、ポートフォリオの再編成はもっと徹底的に行って、過大評価されていると考えられる銘柄は全面的に売却すべきでした。とはいえ、それは結果論に過ぎません。過去には有望銘柄を早期に手放して機会損失を被った経験もあるからです。
当ファンドは今後も以下のような投資指針に引き続き注力します。
- 強固で持続的な事業基盤を有し、優れた経営陣が率いる企業を選定
- バリュエーションが適正で、株価上昇のきっかけ(カタリスト)となる材料がある場合、または極めて割安な場合に投資
- 魅力的な投資機会に集中するため、ポートフォリオは厳選し、より良い投資先が見つかれば随時入れ替え
AIに関する考察 - 米国の大手テクノロジー企業は中国の大手企業のようになるのか
当ファンドの見方では、米国と中国の大手ハイテク企業には大きな違いが3つあります。
- 米国企業は世界的に優勢だが、中国企業は主に中国国内で活動していること(例外としてByteDance社の「TikTok」やPDD Holdings社の「Temu」などがある)
- 中国企業は規制リスクが大幅に高いこと
- 米国企業は10年以上にわたって比較的緩やかな競争環境の下で事業を展開してきたが、中国企業間の競争は熾烈であること
中国の大手テクノロジー企業の中にはグローバル化を進めているにもかかわらず、依然として現在も主に中国国内向けに事業を展開しています。一方、規制リスクについては少なくとも一時的には当てはまらなくなっています。なぜなら、中国経済が新たな成長の推進役を今すぐ必要としていることから、中国政府がイノベーションを下支えする姿勢に転じており、中国の起業家たちは政府とより協調的な行動をとる方法に習熟してきたからです。
企業間の競争環境については、AIの台頭によって急速に変化してきています。かつては米国の大手テクノロジー企業の間に熾烈な競争はありませんでした。Meta Platforms社(旧Facebook社)は検索事業に参入せず、Alphabet(Google)社はソーシャルネットワークに事業を試みたもののすぐに撤退しました。また、Microsoft社はeコマース(電子商取引)に参入せず、各社はそれぞれ自社が得意とする分野の中で独占的地位を固め、長期にわたってきわめて高いROIC(投下資本利益率)を維持してきました。
しかし現在では、これら大手テクノロジー企業はこぞってAI投資を積極的に進めるようになりました。この流れは、AIによって十分なROI(投資収益率)が得られなくても続く見通しです。なぜなら、AIがこれまで米国の大手テクノロジー企業同士が保っていた棲み分けの境界線が曖昧にし、一部の企業にとっては存続を脅かす脅威となり得るからです。
かつて市場には、Alphabet社の優位がAIによって揺らぐかもしれないという見方が広がった時期もありました(しかし、同社の生成AI「Gemini」の機能改善により市場の見方が変化しました)。
また、AIの進展によって、法人向け業務システムを提供する企業の一部は、既存のソフトウェアが陳腐化するリスクに直面しています。将来的に、もしAIエージェント(AIによる自動対話型アシスタント)がショッピングの主要なインターフェースとなれば、OpenAI社の「ChatGPT」やAlphabet社の「Gemini」などのプラットフォームが、Amazon.com社のような既存の購買経路に取って代わる可能性があります。その場合、Amazon.com社の広告事業にも影響が及ぶかもしれません。また、もしChatGPTが広告収益モデルを採用した場合、Meta Platforms社やAlphabet社の広告事業にも影響を与える可能性があります。このように、AIは米国の大手テック企業にとって、競争と破壊の両方のリスクをもたらしています。米国の大手テクノロジー企業はAIの採用を拡大することで競争し、守りを固めようとしていますが、それには多額の投資が必要です。そうした投資は、たとえROIが低下しても、生き残るために行われるのが常道です。Meta社のMark Elliot Zuckerberg最高経営責任者(CEO)は、「AIへの積極投資を怠るリスクは、過剰投資のリスクよりも大きい」と繰り返し述べています。こうした「勝ち残るしか道はない」という危機感を目にすると、中国の大手テクノロジー企業の姿が思い浮かびます。ここで重要なのは、両国の大手企業がいずれも同様に「勝ち残り」をかけたレースに参戦するしかなくなったということです。かつてソーシャルネットワークはMeta Platforms社にとって「絶対に勝たねばならない」分野でした(そのためInstagramを買収しました)が、Alphabet社にとってはそうではありませんでした。しかしAIは今や、誰にとっても「勝ち残るしかない」分野なのです。
ここまで述べたのは、AIに関する悲観的な見方です。
それでも、AIは依然として社会や経済に大きな価値をもたらす変革的な技術であると考えています。AIが生み出す付加価値の高さが明らかになれば、投資は当然ながら堅調に推移し、その恩恵はアジアのテクノロジー関連サプライチェーンに及ぶことでしょう。仮に多少期待外れに終わったとしても、取り残されることへの不安から、大手テクノロジー企業はAIへの投資を続けるでしょう。しかしその場合、世界有数の優良企業群のROICが構造的に低下することを意味します。いずれにせよ、アジアの半導体関連企業は遠からず順調に事業を展開することになるでしょう。
結論として、当ファンドはAI関連分野への投資を継続しつつ、景気下降の兆しを引き続き慎重に注視してまいります。
2025年10月の運用コメント
株式市場の状況
<⽇本の株式市場>
2025年10月、日本株式市場の代表的な指数であるTOPIX(配当込み)は前月末比6.20%上昇、日経平均株価は同16.64%上昇いたしました。
月前半は、米政府機関の一部閉鎖懸念を背景に軟調なスタートとなりましたが、高市早苗氏が自民党総裁に就任すると、市場では積極財政や成長戦略への期待が高まり、「高市トレード」と呼ばれる株高・円安の動きが急速に進行しました。月半ばにかけては、公明党の連立離脱報道が伝わり、政局不安が広がりました。さらに、米国による対中追加関税発表とそれに対する中国の報復措置が加わり、リスクオフムードが強まったことで、日経平均株価は一時急落しました。その後、一転して日本維新の会との連立協議入り報道を受けて政局の不透明感が後退し、米SOX指数(フィラデルフィア半導体株指数)の上昇も追い風となり、相場は反発に転じました。
月後半には、米中貿易摩擦の再燃や米地銀の信用不安が断続的な重荷となり、短期的な過熱感から一時的な調整局面もみられたものの、20日に自民党と日本維新の会が正式に連立合意に至り、高市新政権の誕生を受けて政策期待が一段と高まったことから市場は再び上昇基調となりました。
月末にかけては、FOMC(米連邦公開市場委員会)で予想通り0.25%の利下げを決定した一方、FRB(米連邦準備制度理事会)議長の発言を受けて12月の追加利下げ観測は後退しました。また、日銀の金融政策決定会合では利上げが見送られ、追加利上げに慎重な姿勢が示されたことで円安基調が継続しました。さらに、米中協議の進展や中国によるレアアース輸出規制延期が好感され、リスク選好姿勢が一段と強まりました。こうした環境下で、アドバンテストの好決算やレーザーテックの大幅株高など、AI(人工知能)・半導体関連株が連日上昇し、日経平均株価も連日で史上最高値を更新しました。結果として、指数間の上昇率の差が広がりながらも、日本株式市場は前月末比で大幅高の水準で10月の取引を終えました。
<アジアの株式市場>
当月、⽇本を除くアジア市場に使⽤される⼀般的な指数であるMSCIアジア指数(⽇本を除く、⽶ドル建て)は、前月末比4.50%上昇しました。韓国市場と台湾市場などが好調に推移した一方、中国市場は軟調に推移しました。パフォーマンスが好調だった要因は、テクノロジーセクターの上昇基調が続いたこと、米中両国の貿易関係が改善したこと、金融政策の方向性が支援材料として働いたことにあります。
AI(人工知能)インフラ投資と半導体需要をめぐる投資意欲の高まりが続いたことが、半導体関連銘柄を新たな高値に押し上げました。韓国では、Samsung Electronics社とSK hynix社が、メモリーチップ、特にAIアクセラレーターやデータセンターで使用される広帯域メモリ(HBM)の好調な需要を背景に、第3四半期の堅調な業績と見通しを示し、韓国のKOSPI(韓国総合株価指数)の上昇に大きく寄与しました。また、Taiwan Semiconductor Manufacturing Company社(台湾)も第3四半期の純利益は前年同期比39%増となり、AI主導で幅広い用途の需要が今後数年間は高水準を維持するという見方から、2025年の売上高見通しを上方修正しました。
当月初旬、中国がレアアースの輸出規制を大幅に強化すると発表したことで、米中両国の貿易をめぐる緊張が高まりました。しかし米国のトランプ大統領と中国の習近平国家主席が韓国で開催されたアジア太平洋経済協力会議(APEC)首脳会議で会談し、これ以上の関係悪化を避け、「1年間休戦」することで合意しました。両国はさらに、対話を継続して双方の溝を埋めていくことでも合意しました。
ASEAN市場では、インドネシアの消費者心理が引き続き弱含みました。Telkom Indonesia社(インドネシア)は決算報告の中で、消費者信頼感が低迷しており、特に中間所得層でその傾向が高いと指摘しました。タイとカンボジアの国境紛争は沈静化した模様ですが、タイは引き続き観光客の減少や個人消費の低迷といった課題に直面しています。
ファンドの運用状況
当月、当ファンドのパフォーマンスは、前⽉末⽐6.16%の上昇となり、参考指数であるMSCI AC Asia Index(円ベース・配当込み)の同8.62%の上昇を2.46%下回りました。
セクター別では、情報技術セクター、資本財・サービスセクターなどがプラスに寄与した⼀⽅、生活必需品セクター、ヘルスケアセクターなどがマイナスに影響しました。
当ファンドのパフォーマンスにプラスに寄与した銘柄は、Taiwan Semiconductor Manufacturing Company(台湾/半導体・半導体製造装置)、ソフトバンクグループ(電気通信サービス)、Samsung Electronics(韓国/テクノロジー・ハードウェアおよび機器)などでした。⼀⽅、マイナスに影響した銘柄は、Samyang Foods(韓国/食品・飲料・タバコ)、WuXi AppTec(中国/医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス)、PUM-TECH KOREA(韓国/素材)などでした。
当ファンドは優良企業を重視する投資家として、強固で持続性のある事業基盤を有する銘柄を探し求めています。優良企業は景気変動の影響を受けにくい事業であるべきと考えられており、主には生活必需品やヘルスケアなどの景気の影響が少ない業界の企業がその代表例とみなされています。しかしながら、当ファンドはそうした見方とは違った考え方を持っています。当ファンドが考える「優良企業」とは、景気循環全体を通じて投下資本に対して適正なリターンを生み出せる企業です。利益率は非常に高い時期があればかなり低い時期もあるでしょうが、平均的に見て健全な水準を維持できることが重要です。例えばTaiwan Semiconductor Manufacturing Company社(台湾)やNVIDIA社(米国)が優良企業であることに異論を唱える人はまずいないと思いますが、両社はいずれも景気循環銘柄です。直近の下降サイクルである2023年1月期では、NVIDIA社の純利益は前年同期比で35%減少し、株価は最高値から60%以上下落しています。したがって、景気循環銘柄であっても、景気サイクル全体を通じて高い資本利益率を実現し、キャッシュを潤沢に創出できるのであれば投資対象として問題はないと考えています。この考え方は当ファンドと他の優良企業重視型投資家の一線を画するもので、そうした投資家の中には優良企業をより厳格に定義している向きもあるかもしれません(より厳格に定義すること自体に問題はありませんが、一長一短があります)。
また、景気循環の影響を受けやすい業界に属する銘柄は比較的業績の振幅が大きいため、柔軟に投資機会を捉える余地があるというメリットもあります。例えば、当ファンドは2022年9月にSamsung Electronics社(韓国)に投資を開始し(2022年10月の運用コメントを参照)、2024年中頃に売却しました。しかしメモリ(HBM、汎用DRAM、NANDを問わず)がまもなく全面的な上昇サイクルに入るという見方から、先日、組み入れを再開しました。
もう一つの例として、表面的には当ファンドの優良企業を重視する投資哲学と矛盾するように見えるかもしれませんが、アジア最大の時価総額を誇る鉱山会社、Zijin Mining Group(中国/素材、以下「Zijin」)があります。一般的に、コモディティ関連企業は優良企業であるはずがないという思い込みがありますが、優良企業を重視する投資家の多くが尊敬しているウォーレン・バフェット氏は、過去複数回石油会社へ投資しています。2025年5月の運用コメントで述べたように、同氏の投資に対する姿勢は非常に柔軟なので、当ファンドもコモディティ企業に対する視点を改める必要があると考えています。コモディティ企業は価格が高水準にある局面では高い資本収益率を実現できます。コモディティ価格を短期的に予測することはほぼ不可能ですが、中長期的観点では合理的な価格レンジを推定することが可能だと考えます。一般的指標となるのは「限界費用」、つまり生産者が供給量を拡大する際にかかる費用です。石油を例にとると、米国のシェールオイルの生産費は1バレルあたり60~70米ドルほどとされています。原油価格がそれを大幅に上回れば、企業は増産して供給量を増やし、価格を下げることができます。価格がそれを大幅に下回れば、多くの企業が生産を中止し、供給を減らして価格を引き上げます。
金属
Zijinは幅広い金属の生産と取引を手がける鉱山会社です。主な取り扱い品目は金と銅で、それぞれ粗利益の40%強を占め、残りを亜鉛、銀、リチウムなどが占めています。したがって、同社の今後の鍵を握っているのは金と銅の動向です。当ファンドはどちらについても見通しは明るいと考えています。
金は現在、各国中央銀行による買い増しや、先進国政府の財政リスク上昇に対するヘッジ需要の高まりという2つの要因から、相場が上昇しています。石油と異なり、金は消費によって目減りするものではなく、これまで採掘された金の大半は依然として流通しています。年間の新規採掘量は既存供給の約1.5%に過ぎず、供給が極めて非弾力的であるため、需要が価格の主な決定要因となります。現在の需要は旺盛で、今後も堅調に推移する見通しです。
銅は送電に不可欠な工業用金属です。再生可能エネルギー、電気自動車(EV)、人工知能(AI)などに関連する電力インフラ投資が進む中で、銅の需要も拡大しています。防衛などその他産業でも消費量が拡大し、需要拡大の一因となっています。そうした要因は、長期的には中国の建設需要の減退を十分に補うと見ています。一方で、主要銅鉱山の枯渇が進み、銅の供給量は低下しています。さらに供給量の拡大に欠かせない採掘のコストも上昇しています。また、銅鉱山の新規開発には通常7年から8年を要するため、銅価格の上昇に即応することは困難です。価格抑制要因としては、価格が一定水準以上に上昇すれば銅スクラップが解決策となり得ることや、用途によってはアルミニウムが銅の代替となり得ることなどが挙げられます。ただし抑制要因が働いたとしても、銅価格は長期的に底堅く推移すると考えます。
アジア最大の鉱山会社
金属価格は企業の今後にとって重要ですが、当ファンドは企業分析に重点を置いています。銅や金を生産する鉱山会社は世界中に多数存在しますが、Zijinが世界的な鉱山会社の中でも傑出していると考える理由は以下の通りです。
- 生産コストの低さ
- 大規模かつ多角的な事業構造
- 有機的成長と優れたM&A実績
- 株主還元の拡大余地
- 生産コストの低さ
コモディティ企業であるからには、競争優位性の決め手となるのはコストの低さです。コストが低いとコモディティ価格が低迷しても会社の利益を維持することができるので、当ファンドはこれを投資基準として重視しています。同社の銅におけるC1コスト(金属を生産する際の直接的な現金コストを測定したもの)は、試算方法によって異なりますが、推定で概ね20~30パーセンタイル(低いほど同業他社と比較してコストが低い)です。金については、同社の総維持コスト(ASIC)は推定20パーセンタイルを下回っています。これは同業他社より利益率が高く、価格低迷に対する耐久力が高いことを意味します。同社は上場後20年以上が経過していますが、一度も年間赤字を出したことがありません。
低コストの背景には、優良鉱山の発掘力に加え、厳格なコスト管理能力があります。同社はまず中国において低品位金山の開発を手がけ、独自の業務運営能力を構築し、他社の追随できないコストとスピードで低品位金山を開発してきました。 - 大規模かつ多角的な事業構造
小規模鉱山会社でも低コスト鉱山であれば複数所有することが可能ですが、それだけでは持続的な事業基盤とは言えません。鉱山は新興国に所在することが多く、政治的リスクが高い場合があり、政府が様々な理由で鉱山を突然閉鎖することも珍しくありません。例えばカナダの鉱山会社First Quantum Minerals社は、2023年秋に環境保護団体の抗議と税金問題を受け、Cobre Panama銅山を閉鎖しました。この鉱山は同社の銅生産量のおよそ半分を占めていたため、同社株価は2か月で30ドル台から10ドル台に下落しました。この例のように鉱業は根本的にリスクが高い事業なので、多角化が欠かせません。
Zijinが保有する銅資源は膨大で、同社は銅生産量で世界の5位以内に入っています。2024年時点で同社最大の銅鉱山はコンゴ民主共和国のKamoa-Kakula銅山で、銅生産量の約22%を占めていました。売上総利益のおよそ40%以上が銅によるものであることから、同銅山が売上総利益に占める割合は約10%に達していた模様です。また、最大の金鉱山はオーストラリアのNorton金山で、金生産量の約13%を占め、売上総利益に占める割合は1桁台半ばであった思われます。 - 有機的成長と優れたM&A実績
高品位鉱石は世界中で枯渇しているため、採掘開始から長年が経過した銅鉱山の大半で、もはや生産量の拡大が望めません。世界大手銅山会社のうちの2社、Southern Copper社(メキシコ)とFreeport-McMoRan社(米国)は、過去10年間にわたって銅の生産量がほぼ横ばいでした。一方で、Zijinは有機的に成長しています。同社は2023年から2028年にかけて銅生産量を大幅に拡大するという目標を掲げ、既存鉱山でそれを実現できるとしています。同社はKamoa-Kakula銅山のように採掘開始から間もなく、生産量拡大の余地がある鉱山を保有している一方で、低品位鉱山の運営能力を高め、さらに自ら資源探査に乗り出して、新規資源の探査能力を培ってきました。2024年には自社探査を通じて獲得した資源の割合が銅で47%、金で50%に達しました。こうした取り組みによって、同社は有機的成長を実現する能力を身につけたのです。
同社はM&Aでも優れた実績を有しています。例えば、Kamoa-Kakula銅山を買収したのは銅価格が大幅に低迷していた2015年末でした。しかし同社が優れたコンソリデーターとして不動の地位を獲得できたのは、なによりも低品位鉱山の開発能力と自社探査能力が優れていたからです。過去に買収したプロジェクトの多くで、プロジェクトの総資源量が買収時の試算より大幅に増加しています。例えば中国の巨龍鉱山はZijinが買収した2020年時点で確認済み銅資源埋蔵量が1,040万トンとされていました。ところが2024年にZijinが探査を実施したところ、総埋蔵量は2,588万トンに達することが判明しました。この探鉱能力が、他社には見えない資産を見抜く力となり、M&Aにおける構造的な優位性をもたらしています。 - 株主還元の拡大強化余地
鉱業はきわめて資本集約的な産業で、大手鉱山会社の多くが借り入れによる資金調達を行っています。Zijinも例外ではありません。しかし、BHP Group社(オーストラリア)やRio Tinto社(英国)のように事業基盤が盤石な鉱山会社の多くはフリーキャッシュフローを潤沢に生成していますが、Zijinのフリーキャッシュフローはごくわずかに留まっています。これは同社がM&Aを積極的に実施し、設備投資を増やして生産量を有機的に拡大したためです。大型M&Aが一巡すれば、フリーキャッシュフローは黒字化に転じる見通しです。現在の配当性向は約30%ですが、キャッシュフローが健全化すれば改善の余地は大きいというのが当ファンドの見方です。例えば中国の国営石油大手であるPetroChina社の配当性向は約50%ですが、2013年から2015年にかけて、Zijinの配当性向は70%を上回っていました。
住友金属鉱山との比較
当ファンドの強みは、日本を含むアジア全域に投資できることです。そこで日本企業とアジア企業を比較してみました。日本で銅と金を扱っている大手鉱山会社の住友金属鉱山は、Zijinと近い企業のように見受けられます。しかし、実際には規模・収益性・成長性・多角化のいずれにおいてもZijinは住友金属鉱山をはるかに上回っています。
*別段の記載がない限り、Zijinのデータは2024年12月期、住友金属鉱山のデータは2025年3月期をもとに記載。
投資対象を日本株式のみとしているファンドの場合、銅と金をテーマに投資するなら住友金属鉱山しか選択肢はありませんが、当ファンドは、日本を含むアジア全域を投資対象としているため、はるかに優良な中国の代替銘柄を組み入れることができるのです。
2025年9月の運用コメント
株式市場の状況
<⽇本の株式市場>
2025年9月、日本株式市場の代表的な指数であるTOPIX(配当込み)は前月末比2.98%上昇、日経平均株価は同5.18%上昇いたしました。
月前半は、Alibaba Group Holding社(中国)による新AI(人工知能)チップ発表をきっかけに米中の技術競争激化が意識され、米国のAI関連株が軟調となり、日本株式市場でもハイテク株中心に下落いたしました。その後、トランプ米大統領が日米間の自動車関税引き下げを盛り込んだ大統領令に署名したことが安心感につながり、相場は持ち直しました。
月半ばにかけては、米国雇用統計が市場予想を下回り、FRB(米連邦準備制度理事会)の利下げ観測が高まったことや、石破茂首相の辞任表明を受けて次期政権への政策期待から日本株式市場は上昇しました。米国株式市場では半導体やAI関連銘柄が市場を牽引し、日本株式市場でも関連株の物色が広がったほか、その他幅広い銘柄に買いが波及しました。日経平均株価やTOPIXは高値更新を続け、相場上昇のモメンタムが継続しました。
月後半は、FOMC(米連邦公開市場委員会)で利下げ再開の決定と年内の継続的な利下げ見通しが示されました。翌日の日銀金融政策決定会合では、政策金利は据え置かれたものの2名の審議委員が利上げを提案し10月の利上げ確率が上昇した他、保有するETF(上場投資信託)の売却を決定したことで指数が一時急落しましたが、売りが一服すると下げ幅を縮め、相場は底堅さを維持しました。
月末にかけては、米国経済指標が堅調だったことから米国の積極的な利下げ期待が後退し、米国株が反落した流れが波及した他、自民党総裁選を控えていることなども重なって日本株式市場は軟調に推移しましたが、月全体としては前月末対比大幅高の水準で当月の取引を終えました。
<アジアの株式市場>
当月、⽇本を除くアジア市場に使⽤される⼀般的な指数であるMSCIアジア指数(⽇本を除く、⽶ドル建て)は、前月末比6.84%上昇しました。国別で見ると、韓国、中国、台湾などが上昇した一方、フィリピンなどは下落しました。韓国のKOSPI(韓国総合株価指数)は前月末比7.49%上昇し、前年末比では42.72%上昇しました。中でも上昇幅が大きかったのがSamsung Electronics社(韓国)で、同社の広帯域メモリ(HBM)がNVIDIA社(米国)の認証試験に合格したと報じられたことが、大幅な再評価につながりました。また、AI投資関連の拡大を背景に、NAND型及びDRAM型メモリに対する世界的な需要が引き続き堅調であることも、投資家が同銘柄を好感する要因となりました。
AI投資の加速は様々な分野に表れています。Taiwan Semiconductor Manufacturing Company社(台湾、以下「TSMC」)は2025年の売上高について30%程度を見込み、2025年中に380~420億米ドルの設備投資を行い、チップ需要の急増に対応する意向を改めて示しました。Alibaba Group Holding社(中国)は最新型のAI言語モデルを公開、NVIDIA社と「フィジカルAI」の強化に向けて戦略的提携を行うと発表し、今後3年間でAI関連インフラに530億米ドルを投資すると明言しました。当月、Samsung Electronics社は前月末比20.4%、TSMCは同12.5%、Alibaba Group Holding社は同53.0%、それぞれ上昇しました。
一方、その他のアジア市場は相対的に軟調でした。インドのITサービスセクターでは、米国がH-1Bビザ(特殊技能を有する外国人向けの就労ビザ)制度を刷新、新規申請に必要な手数料を現在の最低1,000ドル程度から10万米ドルに引き上げると発表したことを受け、株価が下落しました。現在、H-1Bビザ保有者は70%以上がインド人であり、この政策変更は長期的な業績への影響は限定的とみられるものの、短期的には人件費調整などに伴う利益率の不確実性を生じさせました。
ASEAN諸国では、タイの新政権が施政方針を発表し、国内消費の活性化、中小企業支援、観光客誘致、AIやEV(電気自動車)産業への投資に取り組む姿勢を示しました。しかし新政権は4か月以内に議会を解散して総選挙を行う予定で、政策の持続性に懸念が高まっています。
ファンドの運用状況
当月、当ファンドのパフォーマンスは、前⽉末⽐5.20%の上昇となり、参考指数であるMSCI AC Asia Index(円ベース・配当込み)の同5.97%の上昇を0.77%下回りました。
セクター別では、資本財・サービスセクター、情報技術セクターなどがプラスに寄与した⼀⽅、生活必需品セクターがマイナスに影響しました。
当ファンドのパフォーマンスにプラスに寄与した銘柄は、Taiwan Semiconductor Manufacturing Company(台湾/半導体・半導体製造装置)、Contemporary Amperex Technology(中国/資本財)、Zijin Mining Group(中国/素材)などでした。⼀⽅、マイナスに影響した銘柄は、Pop Mart International Group(中国/一般消費財・サービス流通・小売り)、サンリオ(一般消費財・サービス流通・小売り)、富士通(ソフトウェア・サービス)などでした。
当月、中国の大手eコマース(電子商取引)プラットフォームでクラウドベンダー企業でもあるAlibaba Group Holding(中国/⼀般消費財・サービス流通・⼩売り、以下「Alibaba」)を再度組み入れました。当ファンドは長らく同社を前向きには評価しておらず、特にTencent Holdings(中国/メディア・娯楽、以下「Tencent」)と比較すると有望性に乏しいと考えていたため、これは異例のことです。ちょうど3年前にあたる2022年9月の運用コメントでTencentの株価がまもなく底を打つと予測しました。実際に、同社株価は翌月の2022年10月に底を打ち、その後3年間でおよそ250%上昇しました。Alibabaの株価もすでに底を打っているとみられますが、まだ回復の初期段階にあると考えています。地政学的リスクや規制面の観点でよほど特別な出来事が発生しなければ、Tencentと同様に長期保有をする方針です。
業績悪化の背景
ここでひとつ、明確にしておくべきことがあります。多くの人はAlibabaの業績が2021年以降に悪化したのは、中国政府によるAnt Group社(中国)の取り締まりが原因だとは考えていますが、それは主たる要因ではなかったというのが当ファンドの考えです。同社にとって問題なのは規制ではなく、競争の激化です。中国市場における過度な競争は構造的な問題であり、当ファンドが常にTencentを優先的に組み入れ、現在も主要組入銘柄となっているのもそのためです。
Tencentの主力事業であるゲーム事業には、有力な競合先がNetEase社(中国)1社しかありません。同社は収益性を最重視する企業で、積極的に競争を仕掛けてくるような相手ではありません。また、バーチャルアイテムの価格を下げてもゲームのユーザー数は増えないことから、ゲーム事業で何より重要なのはより優れたゲームを開発することであって、他の分野のように価格を下げることではありません。したがって、Tencentの競争環境は非常に健全だと考えています。
対して、Alibabaが置かれた状況は全く異なります。2017年から2018年にかけて、Alibabaの主要な競合先はJD.com社(中国、以下「JD.com」)しかなく、しかもAlibabaの方が優位に立っていました。しかし2021年から2022年にかけて、PDD Holdings社(以下「Pinduoduo」)、Douyin Group社(以下「Douyin」)、Kuaishou Technology社(以下「Kuaishou」)が参入し、主要な競合先は1社から4社に増えました。そのため、Alibabaが運営する「Taobao」と「Tmall」の市場シェア合計は、2021年の推定50%から2024年には同34%に低下しました。ただし市場首位の地位は保っています。一方、新規参入組(Pinduoduo、Douyin、Kuaishou)の市場シェアは同期間に合計28%から46%(Pinduoduoが20%、Douyinが20%、Kuaishouが6%)に伸びました。
当ファンドでは、規制面の問題は経営陣の注意が競争熾烈化への対処に振り向けられるきっかけとなっただけで、Alibabaの業績が悪化した主要因ではないとみています。PinduoduoとDouyin、Kuaishouが参入したのは、Alibabaが初期段階で守りきれなかった2つの未開拓市場です。Pinduoduoが重視したのはきわめて安価なノーブランド商品と中低所得者層のユーザーで、当時はAlibabaが積極的に参入するには収益性が十分ではありませんでした。DouyinとKuaishouは当初、ショート動画アプリ(Douyinは中国版TikTok)で、ライブストリーミング(インターネットを通じてリアルタイムで映像や音声を配信・再生する技術)を利用してeコマースに参入しました。ライブストリーミングは、1)売り手が商品の使い方を実演できること、2)売り手が顧客からの質問にリアルタイムで回答できること、3)時間つぶしに利用するユーザーが多いといった複数の点でeコマースに優位性をもたらします。ライブストリーミングの主な欠点は、買い手が売り手の販売戦術に影響されやすく、衝動買いにつながりやすいということです。また、ライブストリーミングを利用したeコマースでは、顧客定着率が比較的低いのが実情です。いずれにせよ、Alibabaは中低所得者層向けでもライブストリーミングでも後れをとっていました。加えてAlibabaは、ローカルサービス(フードデリバリー)ではMeituan社(中国、以下「Meituan」)に、グローバルマーケットでは当ファンドの組入銘柄であるSea(シンガポール/メディア・娯楽)やTikTokに先を越されていました。そして2021年から2023年にかけて、グループCEO、会長、主要事業部門の責任者に至るまで、経営陣が大幅に入れ替わりました。中国のeコマース最大手であるAlibabaは、手元の切り札を見誤ったことになります。
成長軌道への回帰
Alibabaの主力事業であるeコマース事業は、数四半期前から既に安定化の兆しを見せていました。2024年第1四半期以降、同社の市場シェアは30%台前半で推移しています。重要なのは、顧客管理収益(販売者に課金される手数料と広告収入)が、複数の収益改善施策の効果で、2024年12月期に流通取引総額の伸びを上回るペースで回復したことです。同時に、eコマースに関して収益性を重視する姿勢を強め、他分野に投資する企業が増えたことから、競争の熾烈度もわずかに低下しました。一方で、ショート動画プラットフォームの限界が見え始めました。ショート動画プラットフォームは商品を顧客に初めて紹介する方法としては優れていますが、リピーターにサービスを提供するプラットフォームとしてTaobaoが不可欠であることを、出店者側が再認識し、シェア拡大の勢いは鈍化しました。Pinduoduoはグローバル事業の「Temu」に重点を移しており、その資金源として国内事業の収益を高く保つ必要があります。さらに今年はJD.comがフードデリバリー事業の強化に乗り出し、Meituanへの対抗姿勢を強めています。フードデリバリーは利用頻度がきわめて高いことから、新規ユーザーを獲得して本業に誘導するための戦略であると考えられます。Alibabaは参入が遅れたものの、現状では意外にも勝ち組に入っています。公式な数字ではありませんが、Alibabaの日次注文数は、7月時点でMeituanの3分の2以上に達したとされ、従前の3分の1から大きく拡大しています。
Alibabaの業績は2021年から2023年にかけて惨憺たるものでしたが、何が変わったのでしょうか。Alibabaは5年前ほど強力ではないにしても、まだ切り札を持っています。組織がようやく安定し、カードの切り方がよくなったことが収益改善の要因であると考えます。現会長で創業者の1人である蔡崇信(ジョセフ・ツァイ)氏とCEOの呉永銘(エディー・ウー)氏が就任したのは2023年9月で、同グループはその後、大規模な組織再編を行いました。その一環として、社内で最も尊敬されている若手経営者の一人である蒋凡(ジャン・ファン)氏をeコマース事業グループ全体のリーダーに昇格させ、また組織の簡素化を進めました。
同社はかつて「1+6+N」体制を採用していて、事業が6部門に分かれ、構造的に分散化されていました。現在では、中国eコマース、国際デジタルコマース、クラウドインテリジェンスという3大部門と非主力事業のみという形に簡素化されています。こうした再編成によって、社内体制は安定しました。ここで重要なのは、かつて別々に事業を営んでいたグループが同じ傘下に入り、シナジー効果によって市場で競争力を高められるようになってきたことです。
当ファンドでは、クイックコマース(注文から配達までがごく短時間で完了するサービス)はAlibabaの牽引力、さらには同社独自の強みになり得ると考えています。中国eコマースとローカルサービス(クイックコマースやフードデリバリーが属していた事業部門)は、組織再編までは別々のグループでしたが、現在は同じグループに属しています。これまで同社のフードデリバリー事業は、主にEle.meアプリとAlipayのミニプログラムを通じて運営されていました。同社は今回、「閃購」というタブを主力アプリであるTaobaoのトップ画面に配置しましたが、これは同事業の戦略的重要性を示すものです。その効果は同社の市場シェアが伸びたのをみれば火を見るより明らかです。さらに重要なのは、フードデリバリーとクイックコマースが主力のコマース事業にシナジー効果をもたらすということです。2026年3月期第1四半期決算説明会における同社経営陣のコメントを要約すると以下の通りです。
- クイックコマースの月次アクティブユーザー数が前月に3億人に達した(Meituanに迫る数字と考えられる)
- クイックコマースの寄与で前月にTaobaoアプリの日次アクティブユーザー数が20%増加した
- クイックコマースの利用頻度の高さが寄与し、ユーザー1人当たり平均購入日数が大幅に増加した
- トラフィックが増加したことで、広告収入と顧客管理収入の増加が見込める
- クイックコマースによってユーザーのエンゲージメントが高まったことで、販促およびマーケティング費用を削減できる
- 会社としてはこの傾向が続くと予想している
同社はさらに、自社ローカルサービスの「Amap」への組み込みを強化すると発表しました。Amapは中国最大の地図アプリで、同社が保有するもうひとつの優良資産です。クイックコマースと主力事業のシナジー効果を発揮できれば、同社はクイックコマース事業を手がけていないPinduoduoやDouyin、Kuaishouなど新規参入組に対する優位性を取り戻すことができると考えます。
当ファンドは引き続きAlibabaの事業を注視していきますが、同社は正常な軌道に戻っていると考えています。Alibabaの主力事業は全般的に成長軌道に戻り、クイックコマース投資がまだ収益性改善に寄与していなかった2025年3月期から今後5年間で、セグメント調整後EBITA(利息・税引・無形固定資産減価償却前の当期純利益)の年平均成長率は最低でも5%に達する見通しです(当ファンドの考えでは控えめな数字)。さらに国際事業は黒字化し、クラウド事業も急成長を続ける見込みです。こうした点を総合すると、グループ調整後EBITAの年平均成長率は10%台前半に達するでしょう。加えて、同社は自社株買いを続けて発行済み株式総数を減らし、10%台半ばのEPS(一株当たり純利益)成長率を実現すると考えられます。
したがって今後、同社がクイックコマース、フードデリバリー事業とローカルサービス事業で確固たる地位を築くことに成功すれば、既存事業のeコマースからクイックコマースとフードデリバリー、ローカルサービスにまで広がる事業を大規模に展開し、消費者の日常的ニーズをもれなく充足できる中国で唯一の企業へと脱皮できるということになります。また、将来的には有料会員サービスのバンドルなどを通じてエンゲージメントを強化し、さらなるシナジー効果を生み出すこともできると考えています。
Tencentの辿った道も同じ
Alibabaの有望性に対する自信は、同社がTencentと同じ軌跡を辿るのではないかという考えにも由来しています。2018年から2019年にかけて、Tencentは2つの大問題に直面しました。それは、未成年者保護に関する規制が強化され、業界全体で新規ゲームのライセンス承認が停止されたことや、ショート動画が台頭し(DouyinとKuaishou)、Tencentが完全に乗り遅れたことです。
同社は当時、主力事業における利益確保に注力する一方、様々な投資先(JD.com、Pinduoduo、Meituan、Seaも含む)に資金を投じ、事業展開をその投資先に任せていました。しかし、ショート動画の台頭によって同社の主要メディア資産の利用時間が激減し、広告事業の大幅な減速を招きました。同社のショート動画に対する取り組みは完全に失敗し、士気が低下しました。その後2020年になって、初めて主要資産であるWeChatにショート動画を導入し、WeChat動画アカウントを立ち上げました。コロナ禍の影響で厳しい事業環境が続きましたが、2023年には動画アカウントが軌道に乗り始めました。他は2022年9月の運用コメントに要約してあります。
両社の類似点は2つあります。
- TencentとAlibabaがいずれも、優良資産の有効活用を通じて次なる重要セグメントの成長を促進し、それによって生まれたシナジー効果を優良資産に返す取り組みを始めたこと。
- 組織としての自信を取り戻したこと。両社はいずれも手元に切り札をもっていたにもかかわらず、うまく使いこなせておらず、自信が回復したことで使いこなせるようになったこと。
今回はクラウドとAIビジネスについて触れていませんが、Alibabaの全貌を一度で伝えるのは困難なので、次回以降でさらに詳しくお伝えします。
中国の規制環境
中国の規制環境は国外にいる人の多くが懸念を感じていますが、国外から情勢を眺めている人が見落としがちなのは、中国では規制環境に周期性があるという点です。今のようにマクロ環境が弱含んでいる時、中国政府は緩和的な政策をとる傾向があります。民間部門に経済を支えてもらう必要があることが明らかだからです。政策の支援があれば、対中投資のリスクは国外から情勢を眺めている人の多くが考えているよりかなり小さいものになります。
習近平主席は今年2月、民間企業の経営者と異例の公開会談を行いました。Alibaba創業者の馬雲(ジャック・マー)氏も出席し、習主席と握手を交わしました。これはきわめて心強いシグナルです。民間の企業家が政府の重要な目標を理解し、それに従う限り、規制環境は比較的穏やかなものになると考えられるからです。
当ファンドの中国・香港銘柄の組入比率は2025年2月に合計20%を上回り、現在もその水準を保っています。現時点では、当ファンドは中国と香港に関して引き続き比較的ポジティブな見方をしています。
2025年8月の運用コメント
株式市場の状況
<⽇本の株式市場>
2025年8月、日本株式市場の代表的な指数であるTOPIX(配当込み)は前月末比で4.52%上昇、日経平均株価も同4.01%の上昇となりました。
月前半は、米国の雇用統計で非農業部門雇用者数が市場予想を下回り、労働市場の軟化が意識されたことで米国株が急落しました。その影響を受けて日経平均株価も急落し、一時4万円を割り込む場面もありましたが、雇用統計の弱さが米国利下げ期待を高め、世界的な株高を誘発しました。加えて、国内では主要企業の好決算により企業業績の底堅さが再認識され、日本株式市場は一段と騰勢を強める展開となりました。こうした強い上昇基調のなか、月半ばにはトランプ米大統領が対中相互関税の一部を再び90日間延期すると発表し、投資家心理に安心感を与えたことから株式市場は続伸し、日経平均株価は連日史上最高値を更新しました。
その後、月後半にかけてはジャクソンホール会議を控え様子見ムードが広がり、利益確定売りも重なって調整色が優勢となりました。ジャクソンホール会議では、米連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長の講演が9月の利下げ観測を一段と強めるものとなったほか、米国のNVIDIA社が中国向け輸出に関する不安を残しつつも堅調な決算を発表したことも市場を支え、米国株式市場は堅調に推移し、日本株式市場も底堅い動きを見せ、前月末比で大幅高となって当月を終えました。
<アジアの株式市場>
当月、⽇本を除くアジア市場に使⽤される⼀般的な指数であるMSCIアジア指数(⽇本を除く、⽶ドル建て)は、前月末比1.29%上昇しました。国別で見ると、シンガポール、中国などが上昇した一方、インド、韓国などは下落しました。当月、中国の上海総合指数は10年ぶりの高値に達しました。一方、インドは、米国から50%という想定外の懲罰的関税を課されたことで、市場が低迷しました。
中国市場が上昇したのは、素材セクターと情報技術セクターが好調なパフォーマンスを記録したことによるものです。中国政府の「反内巻政策(中国国内における過度な価格競争や生産過剰の抑制を目指す政策)」によって景気循環銘柄の株価が押し上げられ、AI(人工知能)やロボット関連への設備投資の勢いが底堅かったことが、テクノロジーセクターの株価上昇要因となりました。さらに、香港市場はストックコネクト制度(上海証券取引所と香港証券取引所の相互間で行われる人民元建て上場株式の取引)により、中国本土から記録的な資金が流入したことも追い風となりました。これは中国本土の投資家が香港の上場株式に高い関心を持っていることを示しています。
一方、インド市場では、トランプ米大統領がインドのロシア産石油購入について、インドに対し25%の追加関税を課すという予想外の発表を行ったことで、株価が急落しました。この措置により、インドの対米輸出に課せられる関税率は当月後半から最大50%に拡大しました。これによりインドは他のアジア諸国より不利な立場に置かれ、主要輸出セクター、とりわけ繊維・衣料、資本財、宝石・宝飾品などに影響が及ぶ見通しです。
インドネシアでは当月後半に主要都市で国会議員の住宅手当の引き上げに対する抗議デモが発生しましたが、これは生活費の上昇と所得格差の拡大に対する国民の不満が高まっていることを示しています。この事態を受けて、プラボウォ大統領は議員手当を一部見直すと発表し、国民感情の鎮静化と市場の信頼回復に努めています。
ファンドの運用状況
当月、当ファンドのパフォーマンスは、前⽉末⽐4.90%の上昇となり、参考指数であるMSCI AC Asia Index(円ベース・配当込み)の同0.69%の上昇を4.21%上回りました。
セクター別では、一般消費財・サービスセクター、コミュニケーション・サービスセクターなどがプラスに寄与した⼀⽅、情報技術セクター、ヘルスケアセクターがマイナスに影響しました。
当ファンドのパフォーマンスにプラスに寄与した銘柄は、ソフトバンクグループ(電気通信サービス)、ヨネックス(耐久消費財・アパレル)、サンリオ(一般消費財・サービス流通・小売り)などでした。⼀⽅、マイナスに影響した銘柄は、Taiwan Semiconductor Manufacturing Company(台湾/半導体・半導体製造装置)、GDS Holdings(中国/ソフトウェア・サービス)、日立製作所(資本財)などでした。
当月、当ファンドは好調なパフォーマンスを記録しました。これは、ソフトバンクグループ、サンリオ、Pop Mart International Group(中国/一般消費財・サービス流通・小売り)、ヨネックス、Sea(シンガポール/メディア・娯楽)といった好決算を発表した企業が牽引したことによるものです。しかしそうしたモメンタム株の上昇があまりにも急激だったため、これを機会に利益を確定し、組入比率を引き下げました。とはいえ、当ファンドは当該銘柄の長期的有望性は変わらないと考えており、保有は続けていく予定です。
当ファンドはこのところのモメンタム株の急騰、とりわけ米国とアジアの一部地域における急騰は警戒が必要だと考えています。世界の株式市場が現在の上昇基調に入ったのは2023年ですが、それから現在まで「押し目買い」戦略(株価が上昇トレンドにある際に、一時的に株価が下がったときに株を購入する投資手法)が非常にうまく機能したことで、投資家の間に押し目を拾い続けようという心理が生まれました。これは賢明な戦略となり得ます。なぜなら、投資家が、市場の転換点を早期に認識し、多少の損失を受け入れて撤退するだけの賢明さを持っていれば、投資家が判断を誤るのは一度だけ、つまり市場が本当に転換した時点だけで済むからです。しかし、たいていの投資家は自制心に欠け、市場が反転したことが明らかになっても押し目買いをやめられず、下落相場でナンピン買い(価格が下がった株を買い増し、平均取得単価を下げる手法)を続け、さらに悪いことには、結局はバブルで終わってしまうような急騰株を買い続けたりします。米国とその他の国との貿易協定によって今後の見通しはかなり立ちやすくなったものの、市場の不透明感は依然払拭されていません。当ファンドは米中関係の動向に加え、関税の影響が本格的に表れてきた時点で米国の経済とインフレがどう転ぶかを引き続き見守りたいと考えています。これらの問題は、どちらも市場の行方を大きく左右させうるものです。モメンタム株主体の上昇によって一部保有銘柄のバリュエーションが割高になったことを踏まえ、当ファンドは当月、成長率は低くても事業が強固で耐久性に富み、バリュエーションが割安で、配当の高い銘柄、例えばオリックス(金融サービス)、伊藤忠商事(資本財)、光通信(資本財)、三菱UFJフィナンシャル・グループ(銀行)などにポートフォリオを選択的にシフトしました。
2023年から現在までの実績を振り返ると、当ファンドのパフォーマンスに大きくプラス寄与した銘柄は、Taiwan Semiconductor Manufacturing Company、MakeMyTrip(インド/消費者サービス)、ソシオネクスト(株価が上がり切った時点で売却済み)、サンリオ、Samyang Foods(韓国/食品・飲料・タバコ)といった高成長銘柄でした。一方で、HSBC Holdings(香港/銀行)、三菱UFJフィナンシャル・グループ、Tencent Holdings(中国/メディア・娯楽)といった株主還元が高く、より安定的な銘柄からも堅実なリターンを得ることができました。当ファンドでは、目覚ましいリターンをもたらすのは主に高成長銘柄だと考えています。定義上、利益成長率が一桁台半ばしかない企業は、株価がきわめて割安な時点で購入し、大幅な評価見直しが実現しない限り、株主に目覚ましいリターンをもたらすことはほぼできません。そうした高成長銘柄の好例が既に売却済みの三菱商事(2023年2月の月次報告書を参照)への投資でした。このように目覚ましいリターンをもたらすのが高成長銘柄なら、なぜ高成長銘柄を組み入れないのかと疑問に思う方もおられることでしょう。
現在のような強気相場では、高成長銘柄が最高のリターンをもたらすので、それだけを保有すべきだ、と言うのは簡単です。実際に当ファンドも以前はそうしたアプローチで臨みました。そして2022年に成長株の弱気相場が到来した際に、大幅なアンダーパフォームに苦しむことになったのです。現在はまさに当時と同様の環境なので、あの時に得た教訓を思い出して慎重になるべきなのです。
当ファンドの目標は、適正で比較的安定したリターンを上げることです。まず、私が考える「適正なリターン」とは何かを明確にしたいと思います。米ドルのリスクフリーレート(リスクがほとんどない商品から得られる利回り)がおよそ4%であることを考えると、年間リターンが米ドル建てで10%台半ばというのが適正であると考えます。実際に、年率15%でポートフォリオを複利運用すると、5年後には約2倍になります。当ファンドが組入銘柄で許容できるリターンの最低値は、確実性が高く安全な銘柄であれば10%台前半です。
「 多くの投資家は成長こそが重要だと勘違いしている…だが成長だけで収益を上げられるという保証はない。重要なのは、他者の参入を阻む障壁と持続可能な付加価値である」-クリストファー・ホーン卿
英国の著名なヘッジファンドである「The Children's Investment Fund Management(TCI)」の創設者で、史上最も成功した投資家の一人であるクリス・ホーン卿のこの言葉は、まさに至言です。これは当ファンドのアプローチでもあります。競争優位性がなければ成長できても持続可能ではなく、早晩競争に敗れ去ってしまいます。したがって、当ファンドはどんな時であれ、まず事業の強さに注目し、その上で成長性に目を向けるようにしています。短期的に成長が見込める企業はどこにでもありますが、その成長を持続させる強みを持つ企業かそうでないかを見分けるのが当ファンドの役割です。特にアジアでは、アジアに流入するグローバル資本が通常、成長を求めるため、投資家は成長を追いかける傾向があります。そのため、成長銘柄、特に短期的成長率は高いものの強力な参入障壁を備えていない銘柄が過大評価され、それほど成長しない銘柄は見過ごされて過小評価される傾向があります。そうした銘柄はバリュエーションが相対的に低いため、安定的な優良銘柄で株主還元率が高ければ、トータルリターン(配当と自社株買いの上昇を含む)が10%台半ばに達し、当ファンドの条件を満たす可能性は十分にあります。
また、優良安定銘柄には高成長株との相関性が低い傾向があります。同時に、モメンタム株主体の買いの流れに左右されにくいという傾向もあります。一方で、高成長銘柄は持続不可能な水準まで買われた後で下げに転じ、高値で追った投資家が多額の損失を被るといった事態も高頻度で発生します。景気が後退局面に入ると、投資家はたいてい極度に悲観して冷静さを失い、高成長銘柄を大幅に割安な水準で売却してしまいます。そのため、高成長銘柄には超割高状態と超割安状態の両極端の間で大きく揺れ動く傾向があります。高成長銘柄は優良安定銘柄よりボラティリティが大幅に高いので、安定銘柄は市場低迷期に株価が下落した高成長銘柄を買うための資金源として活用することができます。したがって、目標リターンが10%台半ばの場合であっても、市場低迷期の資金源として活用できるというオプション価値を考えると、安全で確実、かつ安定的な銘柄であれば、リターンが10%台前半でも受け入れることができると考えます。ある意味では、現金はリスクフリーであり、株式市場がどんなに悪化しても(名目上は)価値が下がらないので、オプション価値はさらに高くなります。しかし現金がもたらすリターンはごくわずかであることを考えれば、中長期的な視点では、多額の現金を長期保有するよりも、優良で安定した銘柄でリターン要件を満たすものを保有する方が好ましいでしょう。
当ファンドはアジア全域を対象としたファンドであり、複数市場に分散投資されています。当ファンドの目標の一つは比較的安定したリターンを上げることです。その点、アジア地域の好ましいところは、広大で多様性に富んでいるため、優れたリターンを上げる市場が年によってまったく異なる可能性があることです。例えば2023年は中国市場がきわめて低調でしたが、他の市場は好調でした。2024年は韓国が低調でしたが、中国は好調でした。今年は今のところ、インドがこれまでと一転して大幅に低迷しています。このような特徴があるため、銘柄数を25~40に絞り込んでも十分に分散型のポートフォリオを構築し、比較的安定したリターンを上げることができます。ところがまさに、複数市場に投資するが故に、当ファンドのリターンは、ある特定の年に最も好調だった市場のリターンを下回る可能性はきわめて高くなります。しかしそれぞれの市場に浮き沈みがあるので、当ファンドはポートフォリオのリバランスを積極的に行い、有望な銘柄が多いと考えられる市場の組入比率を高めに設定し、有望な銘柄が少ないと考えられる市場の組入比率を低水準に保っています。長期的にはアジアの各市場でアウトパフォームし、より安定的なパフォーマンスを上げたいと考えています。
以下は当ファンドのパフォーマンスとアジア各国の指数を比較したものです(単純化するためASEANを1つの市場として扱っています)。
2025年7月の運用コメント
株式市場の状況
<⽇本の株式市場>
2025年7月、日本株式市場の代表的な指数であるTOPIX(配当込み)は前月末比3.17%上昇、日経平均株価も同1.44%の上昇となりました。
月前半の日本株式市場は、前月末の急騰を受けた利益確定売りが優勢となるなか、米国による相互関税の動向や参議院議員選挙で与党が苦戦するとの見通しなど、先行きへの不透明感が強まり、株価の動きは限定的となりました。また、米NVIDIAによる中国向けAI半導体の輸出再開報道や、米連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長解任を巡る話題など、強弱入り混じる材料が相次いだこともあり、株式市場は方向感に乏しく、もみ合いが続く展開となりました。
月後半に入ると、20日に実施された参議院議員選挙では、与党が非改選議席と合わせても過半数を獲得できなかったものの、市場では想定内の結果と受け止められたため、連休明けの22日の株式市場への影響は限定的に留まりました。翌23日には、日米通商交渉の合意が報じられたことで株価が一気に押し上げられ、24日のTOPIXは過去最高値を更新し、日経平均株価も急騰する展開となりました。その後は、急ピッチな株価上昇に対する過熱感から一時的な調整が入ったものの、月末には米ハイテク銘柄の好決算の影響などを受けて反発し、日本株式市場は前月末比で大幅高となって当月を終えました。
<アジアの株式市場>
当月、⽇本を除くアジア市場に使⽤される⼀般的な指数であるMSCIアジア指数(⽇本を除く、⽶ドル建て)は、前月末比2.63%上昇しました。国別で見ると、インドやフィリピンを除き概ね上昇しました。米国の貿易政策によって、世界貿易の先行きは依然として不透明です。トランプ米大統領は新たな国別の関税政策を発表しましたが、今後の交渉には引き続き前向きな姿勢を示しました。
中国・香港市場は、中国政府の「反内巻政策(中国国内における過度な価格競争や生産過剰の抑制を目指す政策)」によって企業の収益性が改善し、合理的な競争につながるとの期待感が高まりました。AI(人工知能)セクターやロボティクスセクターは中国の次なる成長ドライバーとして、加速度的な勢いで市場が拡大しています。NVIDIA社(米国)がH20チップ(AI半導体)の対中国向け輸出を再開したことも、AIに対する市場心理のさらなる向上に寄与しました。
韓国市場は李在明(イ・ジェミョン)新大統領が改革路線を打ち出し、家計支出拡大策、コーポレートガバナンスや株主の権利強化策などが公約として掲げられていることが投資家に好感され、年初来の高値を更新しました。一方で、法人税と証券取引税の引き上げが発表されたことで、一部で利益確定売りが見られました。
タイ市場は、タイ・カンボジアの間で長年にわたって続いてきた国境紛争が再燃したにも関わらず、力強く反発しました。停戦合意後も緊張状態は続いていますが、タイ企業に対する影響は限定的に留まると考えています。
インド市場は、米国が発表したインドからの輸入品に対する関税率が25%と予想を上回ったことから、インド市場は月末にかけて急落しました。
ファンドの運用状況
当月、当ファンドのパフォーマンスは、前⽉末⽐3.51%の上昇となり、参考指数であるMSCI AC Asia Index(円ベース・配当込み)の同5.48%の上昇を1.97%下回りました。
セクター別では、金融セクター、資本財・サービスセクターなどがプラスに貢献した⼀⽅、ヘルスケアセクター、一般消費財・サービスセクターがマイナスに影響しました。
当ファンドのパフォーマンスにプラスに寄与した銘柄は、Taiwan Semiconductor Manufacturing Company(台湾/半導体・半導体製造装置)、Futu Holdings(香港/金融サービス)、Tencent Music Entertainment Group(中国/メディア・娯楽)などでした。⼀⽅、マイナスに影響した銘柄は、サンリオ(一般消費財・サービス流通・小売り)、Hugel(韓国/医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス)、Converge Information & Communications Technology Solutions(フィリピン/電気通信サービス)などでした。
「新しい時代を作るのは老人ではない!」
—クワトロ・バジーナ(シャア・アズナブル)(出典:サンライズ 『機動戦士Ζガンダム』第50話より)
2024年12月の運用コメントで、当ファンドが2024年に犯した最大の過ちは「ポップトイ(箱を開封するまで何が入っているかわからない仕様の商品)」を販売している中国企業の組み入れを見送り、同企業の株価が昨年1年間で300%以上も上昇したことだと記しました。サンリオ(一般消費財・サービス流通・小売り)を参考にすれば、この企業の組み入れが必要であることは確実に理解できたにもかかわらず、組み入れに踏み切らなかったのです。実際、当ファンドは同社の店舗を訪問し、感銘を受けていました。組み入れを見送ったのは特に香港や中国市場と比較するとバリュエーションがやや割高に見えると感じたからです。そこで年初に株価が調整したタイミングで、組み入れに踏み切りました。同社の株価が年初来約170%上昇したことで、当ファンドの迅速な対応は報われました。その企業とは、今や世界的な人気を誇るキャラクターとなった「LABUBU」を擁する「Pop Mart International Group(中国/一般消費財・サービス流通・小売り)、以下「Pop Mart」」です。
Pop Martは現在38歳の王寧(ワン・ニン)氏が2010年に設立した企業で、中国における新しいタイプの消費財企業を代表する存在です。同社は一般小売の試みが失敗に終わったあと、ブラインドボックス玩具(日本のガチャガチャのように開けるまで何が出てくるかわからない玩具)の販売に転じ、急成長を遂げました。同社の商品は主に20歳から40歳のいわゆるキダルト(子ども(キッズ)と大人(アダルト)を組み合わせた造語、子ども心を持ち続ける大人を指す)層をターゲットにしています。とりわけ業績を押し上げる要因となったのが「MOLLY(モリー)」というキャラクターの人気で、これは同社が香港のデザイナー、Kenny Wong(王信明)氏から取得したIP(知的財産)です。MOLLYはエメラルドグリーンの大きな瞳をした金髪の少女です。唇をとがらせた表情が特徴的で、可愛らしさの中に少し反抗的なところが感じられ、そうした点が若い世代の共感を呼んでいます。ブラインドボックス玩具には実用性はなく、ベイブレードやNintendo Switchのようにそれ自体で遊ぶことはできません。単なる飾り物として、机の上に置いておくだけです。しかし実用性がなくても、若者が自分らしさを表現する手段のひとつとなっています。同社の最もベーシックなブラインドボックスは、日本ではおよそ1,600円で販売されており、一般的なガチャガチャよりはるかに高価ですが、細部が作り込まれており、品質も優れています。
机の上におもちゃを置いておくことがなぜ自分らしさの表現なのか理解できない人もいるかもしれませんが、日本の女子高生を見ればその理由もわかるでしょう。日本では人形のついたキーホルダーをたくさんバッグにぶら下げて自分らしさを表現している女子高生をよく見かけます。こうした女子高生の行動を理解すれば、LABUBUがなぜ同社を世界的なステージに押し上げたのかを理解するのは難しくありません。LABUBUで最も人気があるのは、まさにキーホルダーになっていてバッグに吊るせる形の商品です。LABUBUの人気が本格化した時期を特定するのは難しいですが、BLACKPINKのリサがSNSで自身のLABUBUコレクションを披露したのがきっかけとされることが多いです。ちなみに、LABUBUの生みの親であるKasing Lung(龍家昇)氏も香港出身です。LABUBUには歯がたくさんあってモンスターのような顔をしています。ハローキティのように昔からいるかわいいタイプと全く異なり、「ブサかわ(不細工だけどかわいい)」なところが若者に人気なのかもしれません。サンリオのハンギョドンが人気なのも、少し「ブサかわ」なところがあるからだと言えるでしょう。LABUBUが瞬く間に世界中に知れ渡ったのは、世界的有名人が紹介したためでもありますが、バッグにぶら下げると非常に目立ち、友人が持っているのを見ると自分も欲しくなるためでもあります。バッグにキーホルダーをぶら下げる習慣が定着している日本でも、従来は日本のキャラクターが強かったものの、最近では女の子がLABUBUをぶら下げているのを見かけるようになりました。
Pop Martの業績成長は著しく、売上高は2019年の16億8,000万人民元から、2024年には130億人民元まで成長しました。2024年の売上高に占める海外売上の比率は約40%を占めており、今年は海外売上が中国本土の売上高を上回る見通しです。同社は海外では一般に現地人を採用して運営を任せ、中国企業からグローバル企業への変革を進めています。さらに重要なのは、玩具会社からIP企業への脱皮を進め、玩具というカテゴリーを超えて成長する体制を整えていることです。例えば、MOLLYはもともとディスプレイ用玩具でしたが、数年前にユニクロとコラボしてTシャツを販売しました。同社はLABUBUに関しても玩具だけでなく、リュックサックなどアクセサリーを販売しています。LABUBUのリュックを購入したい人がいるなら、LABUBUのコップ、LABUBUの水筒、LABUBUのティッシュペーパーを購入したい人もいるかもしれません。だとすると、LABUBUをライセンス化して様々な製品につけることもできるので、LABUBUは正真正銘のIPだということになります。
Pop Martとサンリオには興味深い相違点があります。サンリオのキャラクターはハローキティをはじめとして、まだLABUBUより知名度が高いにもかかわらず、Pop Martの利益はサンリオより多く、時価総額も大きいということです。これはサンリオが主にライセンスモデルを採用しているのに対し、Pop Martは垂直統合型のビジネスモデルを採用しているためだと考えます。こうしたアプローチには、いずれも長所と短所があります。サンリオがライセンスモデルを採用しているのは、リスクを低く抑える戦略をとっているからです。ライセンシー(許諾先)に画像をライセンス供与するだけで、同社の業務はほぼ完了します。ライセンシーが製造、流通、在庫管理などを担当し、サンリオはその見返りとして販売した商品のロイヤリティ(使用料)を受け取ります。一方、Pop Martは直営店を運営するなど、あらゆる業務を自社で行っています。サンリオからキャラクターのライセンス供与を受けたブラインドボックス入り玩具を例にとってみましょう。これが10米ドルで売れた場合、サンリオには60セント(6%)のロイヤリティが入り、サンリオにとってはそのほぼ全額が利益になります。一方、Pop Martは10米ドル全額を売上として回収し、コストをすべて差し引いても2~2.5米ドルの利益を上げることができます。その意味で、同社はバリューチェーンにおいてより多くの価値を獲得しているといえますが、その分リスクも高く、売れなかった場合の在庫リスクや店舗運営費用が発生します。現在の急成長期においては、この戦略が最大の価値獲得を可能にしています。将来的には、サンリオも得られる価値をバリューチェーンに沿って拡大していく試みに乗り出してよいと考えます。
*サンリオ製品およびサンリオキャラクターのライセンス製品の最終市場における総売上高は推定約80億~90億米ドル
2025年6月の運用コメント
株式市場の状況
<⽇本の株式市場>
2025年6月、日本株式市場の代表的な指数であるTOPIX(配当込み)が前月末比1.96%上昇、日経平均株価も同6.64%の上昇となりました。
全体としては、米国の関税政策や地政学的リスクの動向に市場が影響を受ける場面も見られたものの、外部環境の改善や米国金融緩和への期待を背景に、リスク選好姿勢が強まった月となりました。
月前半から月半ばにかけての日本株式市場は、米国の関税政策や景気減速への懸念から軟調に推移しましたが、堅調な米雇用統計や米半導体関連株の上昇を受け、市場は持ち直しました。しかし、イスラエルがイランを攻撃したとの報道によって中東情勢への懸念が高まり、一時的にリスク回避の動きが市場を下押ししました。一方で、日銀が政策金利据え置きと国債買い入れ減額ペースの緩和を示し、米連邦公開市場委員会(FOMC)でも政策金利が据え置かれたことが投資家心理を下支えし、外部要因に振らされながらも市場はもみ合いを続けつつ、徐々にレンジを切り上げる展開となりました。
月後半にかけては、中東情勢の激化や米国によるイラン核施設への空爆報道により、一時的にリスク回避ムードが広がりましたが、その後は地政学的な懸念が早期に沈静化したことや米国株式市場の反発を受けて、日本株式市場も上昇基調に転じました。さらに、トランプ米大統領の停戦に関する発言や米連邦準備制度理事会(FRB)高官による利下げ示唆が投資家心理を押し上げ、リスクオンムードが広がりました。値がさ半導体関連株が相場をけん引し、配当権利落ちに伴う再投資の需要も追い風となり、日経平均株価は年初来高値を更新しました。株式市場全体も前月末比で大幅に上昇して当月を終えました。
<アジアの株式市場>
当月、⽇本を除くアジア市場に使⽤される⼀般的な指数であるMSCIアジア指数(⽇本を除く、⽶ドル建て)は、前月末比6.20%上昇しました。中東地域における地政学的リスクの高まりによって金融市場は一時的に混乱をきたしましたが、イランとイスラエルの停戦合意を受けて急速に回復しました。また、米中両国はジュネーブで貿易協議を行い、貿易規制を一部緩和すること、さらなる交渉を行うことで合意しました。
韓国市場は当月大幅に上昇しましたが、その要因となったのは米国株式市場の記録的な上昇でした。急速な拡大を続けるAI(人工知能)ソリューションの分野では、関連企業を巡って明るいニュースが次々に発表されるなど、良好な展開が続いています。韓国の大統領選挙は李在明(イ・ジェミョン)氏が勝利しましたが、同氏はコーポレートガバナンス改革の推進と国内消費の活性化を公約に掲げています。これを受けて投資家の間に韓国の企業価値向上プログラムが急速に進展する可能性があるという楽観的な見方が広がったことなどから、韓国株式に対する投資家心理が好転しました。
一方、タイ市場とインドネシア市場は軟調な値動きとなりました。タイ市場の重しとなったのは、新たな政治的混乱が発生したことでした。これはペートンタン首相がカンボジアの前首相フン・セン氏との電話の中でタイ軍幹部を批判したとされる音声が流出した問題で、倫理規範に違反したとして職務停止命令を受けたことによるものです。インドネシアではプラボウォ大統領の目玉政策である学校給食無償化制度や低価格住宅支援制度の実施が依然難航しています。低所得者層向けの支援策は遅れる可能性が高く、消費マインドの低下要因となっています。
ファンドの運⽤状況
当月、当ファンドのパフォーマンスは、前⽉末⽐6.73%の上昇となり、参考指数であるMSCI AC Asia Index(円ベース・配当込み)の同4.71%の上昇を2.02%上回りました。
セクター別では、情報技術セクター、資本財・サービスセクターなどがプラスに貢献しました。
当ファンドのパフォーマンスにプラスに寄与した銘柄は、アドバンテスト(半導体・半導体製造装置)、Taiwan Semiconductor Manufacturing Company(台湾/半導体・半導体製造装置)、SK hynix(韓国/半導体・半導体製造装置)などでした。⼀⽅、マイナスに影響した銘柄は、Trip.com Group(中国/消費者サービス)、寿スピリッツ(食品・飲料・タバコ)、BYD Company(中国/自動車・自動車部品)などでした。
当ファンドは前月後半に韓国を訪問し、美容、造船、半導体、製薬、ロボット、インターネット、銀行、オンラインゲームなど幅広い業界の企業を取材しました。2023年に投資方針を転換して以降(詳細は2024年11月の運用コメント参照)、韓国市場は当ファンドのリターンに大きく貢献しています。韓国は事業を世界的に展開するグローバル企業が多いという意味では日本と似ていますが、韓国企業は日本企業と比べてバリュエーションが割安だという点が異なっています。
バリュエーションが割安なのは、コーポレートガバナンスが全般的に脆弱であることからある意味で当然と言えるでしょう(「コリアディスカウント」と韓国の企業価値向上プログラムについては2024年3月の運用コメント参照)。さらに、言語や文化の壁もその原因の一つであると考えられます。例えば、当ファンドの主要組入銘柄の一つであるSamyang Foods(韓国/食品・飲料・タバコ)をはじめ、韓国企業の多くが英語による情報開示を適正な形で行っていません。加えて、K-POP、K-Beauty、さらにはK-Foodといった投資テーマの多くは、韓国文化に対する理解がなければ関連企業の将来性を十分に理解できないという特性を有しています。こうした点から、韓国市場に投資して利益を得るのに最も適した立場にいるのは現地の韓国人ではないかと思う人がいるかもしれません。しかし日本市場と同じで、それは部分的にしか当てはまらないと考えます。当ファンドの経験上、現地人が地元市場で有利というのは、多くの人々が抱いている幻想に過ぎず、誰が有利かというのは企業によって異なります。当ファンドの投資対象の多くはグローバル企業のため、世界的な視点で投資対象を判断する外国人の方が、新たなトレンドを把握しやすいという点で現地人より有利だと考えます。サンリオ(一般消費財・サービス流通・小売り)を例にとると、「クロミ」や「シナモロール」のようなキャラクターが海外市場で人気を得つつあることに気づくのは、日本人よりも外国人の方が早いかもしれません。Samyang Foodsも同様で、売上と成長力の源泉の多くは海外市場です。韓国国内で高いシェアを握っているのはSamyang Foodsより「辛ラーメン」のNongshim社(韓国)ですが、海外でSamyang Foodsの即席麵「ブルダック」の人気が高まっていることに気づくのは、現地の韓国人より海外の投資家の方が早いでしょう。当ファンドは投資先の検討にあたって、必ず「現地人」の目と「外国人」の目という複眼的視点で評価するように心がけています。一方ではその国に関する知識を生かし、他方ではアジア地域全体、時には米国や欧州など他地域の調査で得られた知見を参考にしています。現地に関する知見とアジア地域全体、あるいは世界全体に対する視点を組み合わせるというのは当ファンドならではの優位な手法で、今後もこのアプローチを駆使してアジア全域でリターンの創出を目指してまいります。
当月末現在、当ファンドの韓国株式の組入比率は18.4%で、参考指数であるMSCI AC Asia Indexを大幅に上回っています。以前、韓国市場がそれほど有望ならば、韓国株式の組入比率を60~70%に引き上げてはどうか、と尋ねられたことがあります。それに対する当ファンドの答えは、「ありえない」です。上記の質問は、有望な銘柄があるならその銘柄の投資比率を30~40%に引き上げてはどうかといっているようなものです。当然ながらそんなことはありえません。原則論からいえば、一市場全体の組入比率ですら最大30~40%に抑えるのが当然と考えます。当ファンドの投資理念はリスク管理に最大の比重を置いています。投資にはテールリスク(まれにしか起こらないはずの想定外の暴騰・暴落が実際に発⽣するリスクのこと)や思いがけない問題がつきもので、どれほど将来性のある国でも、どれほど有望な企業であっても、それは変わりません。まったく想定外の問題が発生しても大きな損害を被らないようにするには投資先をある程度分散する必要があり、また投資額を一定以下に抑える手法も欠かすことができません。当ファンドは投資先を分散し、アジア全域に適正比率で配分することで、一市場でテールリスクが発生して壊滅的な損失を被る事態を回避しています。
当月、韓国では2024年末の政治的混乱から半年を経てようやく大統領選挙が行われ、大方の予想通り、革新系政党「共に民主党」の李在明(イ・ジェミョン)氏が第21代大統領に就任しました。政治面の先行き不透明感が解消し、新政権が企業価値向上プログラムに本腰を入れて取り組む姿勢を示したことで、韓国市場は当月、好調なパフォーマンスを記録しました。当ファンドは韓国銘柄の組入比率を高く設定していたため、当月はそうした銘柄がリターンに大きく貢献しました。
以下、今回の韓国取材で得られた知見のうち主なものをご報告します。
K-Beauty - 高い成長率を維持
K-Beauty(韓国コスメ)については2024年6月の運用コメントで取り上げましたが、韓国の化粧品会社は2023年以降、当ファンドの重点分野の一つです。これまでも幾度となく指摘してきた通り、当ファンドが志向するのは、様々な消費財の中でも⽀出額が収入の増加に応じて継続的に増えていくような商品カテゴリーですが、化粧品はその代表例です。2024年に当ファンドの運用コメントで取り上げたK-Beautyのスキンケア製品は、欧米市場における浸透率が高まったこと、意外なことに中国市場において安定化の兆しが見られたことから、引き続き堅調な成長軌道を維持しています。
今回の取材ではスキンケア製品に加え、当ファンドが将来有望と考えている医療用美容機器メーカー(ボツリヌストキシンなど)や家庭用美容機器メーカーとも面談しました。韓国市場で最も有利な点は、同国の美容文化がきわめて根強いものであること、そして業界全体でイノベーションを推進し、手頃な価格で最新の美容製品が購入できる状態を作り出していることだと考えます。ボツリヌストキシンを例にとると、韓国製品は、Allergen社(米国)のオリジナル製品「BOTOX」の3分の2以下の価格でありながら、十分に満足のいく効果が期待できます。韓国は海外からの旅行者に割安で満足度の高い医療美容を提供する国として知られ、医療用美容機器でグローバルな評価を築きつつあります。現在、そうした製品は米国、欧州、中東を含む世界各国に販路を拡大していますが、ここで重要なのは、医療用美容機器は規制の対象となっているため、化粧品より大幅に参入障壁が高いという点です。こうした成長率と参入障壁の高さは投資家に高いリターンをもたらすというのが当ファンドの見方です。
造船 - 10年周期の上昇局面
2025年3月、Financial Times紙に「Why ships are the new chips(造船業界はなぜ新たな半導体業界なのか)」と題する記事が掲載され、造船業の重要性が高まっているという指摘がなされました。数十年にわたる再編と紆余曲折を経て、造船が事業として成り立っている国はもはや中国、韓国、日本の3か国しかありません。現在、米国は国家安全保障の観点から自国の造船能力不足を問題視していますが、中国の造船能力は推計で米国の200倍以上に達しているため、米国は韓国と日本の造船業界に大幅に依存せざるをえなくなるでしょう。
造船業界は景気循環が激しいことで知られており、通常は上昇期が10年程度続くと次の10年程度は下降期に入ります。現在は10年にわたる下降サイクルを脱し、上昇期に入った段階で、とりわけ海軍艦艇やLNG船(液化天然ガス(Liquefied Natural Gas)を運ぶためのタンカー)など、特定の種類の船舶の需要は非常に旺盛です。供給は不足気味で、その一部要因は欧米の一部船舶会社が地政学的要因から中国船の購入を控えていることにあります。一方で、韓国の造船会社は10年にわたる景気低迷期の後であることから、生産能力の拡大に消極的です。韓国の造船会社は設備投資額を抑制しながら堅調に収益をあげることで、財務の健全性と株主還元能力を急速に改善しています。
ピークがいつなのかを予測することは困難ですが、1つの上昇サイクルは10年程度続く傾向があるので、現在はまだこの上昇期の初期段階にいると考えられます。通常の景気循環は別にして、環境負荷に関する要求の高まりも、船主に環境負荷の低い新型船舶への転換を迫る要因となっています。さらに、韓国の造船会社が設備投資に対して慎重姿勢をとっていることから、業績のピークは下がっても、その分だけ上昇期が長く続く可能性が出てきています。当ファンドはHyundai Marine Solution(韓国/資本財)という船舶MRO(メンテナンス(Maintenance)、修理(Repair)、オーバーホール(Overhaul)を指し、船舶の運用を維持し、寿命を延ばすために必要な活動全般のこと)企業を組み入れています。同社は基本的に船舶用エンジンの保守・修理サービスを提供しています。この事業には安定的かつ継続的な受注が見込め、造船業の景気循環の影響を受けにくいという特性があります。当ファンドはこの他に、韓国のLNG船に特化した造船会社の組み入れも開始しました。
金融 - 企業価値向上でマクロ面の不確実性に対応
韓国の企業価値向上プログラムについては2024年3月の運用コメントで取り上げましたが、このプログラムに真っ先に取り組んだのが銀行でした。当ファンドはかつてKB Financial Group社(韓国)を保有していましたが、既に利益を確定しています。
韓国の銀行では、長年にわたって株主還元率が低水準に留まっていました。韓国の銀行には一般にマクロ経済の低迷期に国家と同調して経済の調整役を担う役割が求められており、それが株主還元能力を抑制していたためです。しかし「企業価値向上」という流れの中で、規制当局の姿勢は変わりつつあります。銀行が目標の普通株式等Tier1⽐率(CET1比率、損失吸収力の高い自己資本をリスクアセットで割ったもの。より質の高い自己資本の割合を示した指標)を維持できれば、余剰資本を株主に分配することができます。大手銀行の多くは株主還元率の目標を40~50%としていますが、これは妥当な数字だと考えます。
しかしソウルを訪問して肌で感じたのは、韓国のマクロ環境が厳しさを増しているということです。銀行事業には景気循環に左右されやすい性質があるので、銀行はこれからやってくる試練に耐えられることを証明する必要があります。また企業価値向上プログラムに率先して取り組んだことから、銀行のバリュエーションが割安なのは市場関係者にとって既に周知の事実です。
一方で、企業価値向上プログラム全般は大統領選後に強化されるでしょう。新たに大統領に就任した李在明氏は、商法を改正し、株式市場の下支えを通じて韓国国民の資産を拡大する方針を表明しています。ここで重要なのは、李在明氏が上場企業に自己株式の消却を義務付ける制度を創設するという公約も掲げていることです。韓国のコーポレートガバナンス改革が勢いを保っていることから、過小評価されている銘柄の多くで株価がこれから持続的に上昇していく可能性があるでしょう。
当ファンドは現在、韓国の銀行は保有していませんが、韓国最大級の損害保険会社であるSamsung Fire & Marine(韓国/保険)の優先株を保有しています。保険商品の需要には融資の需要より安定的に推移する傾向があり、同社は銀行より逆境に強いと考えられるためです。また同社は自己資本がきわめて充実しているため、余剰分を株主に還元する余地が多くあります。銀行は力を尽くしてCET1比率を目標水準以上に維持する必要がありますが、同社は総配当性向を50%に設定しても、規制要件を容易に上回ることができます。さらに、当ファンドが投資している優先株は普通株より割安な価格水準にあることから、安全余裕率を広く確保することができます。同社の組み入れについては、来月以降により詳しく取り上げる予定です。
今後の運⽤⽅針
当ファンドは以下3つの基準に基づいて投資を行っています。
- 逆風に強い優良企業で、競争優位性に優れていること
- 経営陣が事業運営に長け、合理的な資本配分を行っていること
- バリュエーションが割安であること
また、一般に以下のような特徴を有する企業を逆風に強い優良企業とみなしています。
- 競争優位性が確立され、業界平均を上回る収益成長を実現していること
- 独自な製品やサービス、あるいは必要不可欠な製品やサービスを提供していて、価格決定力に優れていること
- 営業レバレッジが大きく、事業の成長に伴って利益が経時的に拡大すること
- 優れたコスト構造により、厳しい状況下にあってもフリーキャッシュフロー創出力を維持できること
こうした企業にはアジア経済の成長力を取り込む力がある、あるいはアジア諸国独自の強みを生かして事業を国際展開する力があると考えられます。
当ファンドは日本を含むアジア全域から上記基準に最も合致する企業を選定し、集中的にポートフォリオを構築します。
したがって、国別配分比率はあらかじめ設定せず、各国固有のマクロリスクに注意を払いつつ、ボトムアップで銘柄選定を行ってまいります。
2025年5月の運用コメント
株式市場の状況
<⽇本の株式市場>
2025年5月、日本株式市場の代表指数であるTOPIX(配当込み)が前月末比5.10%の上昇、日経平均株価も同5.33%の上昇となりました。当月の日本株式市場は、月前半に大幅上昇した後、月半ばに調整を挟みつつも月後半にかけて持ち直し、レンジ内での回復基調を維持したまま当月を終えました。
月前半は、前月末から続く米国の関税交渉進展への期待が支援材料となったことや、日銀が展望リポートで実質GDP成長率と物価上昇率の見通しを下方修正し追加利上げに慎重な姿勢を示したことや進行した円安も相まって、株式市場は堅調に推移しました。こうした中、米英貿易協定の合意や米中双方による市場の想定以上の関税率の引き下げを受け、指数は大幅に上昇しました。月半ばには好材料が一巡したことに加え、円高・ドル安の進行や、米国債格下げをきっかけに米国の財政悪化懸念が高まったことも相場の重荷となりました。月後半にかけては、米国による対EU追加関税の延期や、日本国内での超長期国債発行計画の見直し観測による円安の進行等により主力株を中心に買いが入り、日本株式市場は再び上昇に転じました。さらに、28日に米国際貿易裁判所がトランプ政権の関税政策を違法と判断し関税の差し止めを命じたことを受けて円安が加速し、株式市場も大幅高となりました。しかしその後、米連邦巡回区控訴裁判所が関税差し止めの執行を一時的に停止する判断を下したことでドル円相場とともに株式市場は反落しました。
結果として、米国の関税政策をめぐる不透明感に振り回されながらも、日本株式市場は前月末比で上昇して取引を終えました。
<アジアの株式市場>
当月、⽇本を除くアジア市場に使⽤される⼀般的な指数であるMSCIアジア指数(⽇本を除く、⽶ドル建て)は、前月末比5.29%上昇しました。
台湾、韓国、中国・香港市場を中心に、幅広い市場が上昇しました。米中両国が相互関税の発動を部分的に90日間延期したことで、全面的な貿易戦争は回避されるかもしれないという楽観的な見方が生まれたことも、株価上昇に拍車をかけました。中国にとって比較的好ましい状況が長続きするかは不透明ですが、少なくとも両国は話し合いを続けています。また、トランプ大統領は米国際貿易裁判所から、輸入品に対して全面的に関税を課すことは大統領の権限を逸脱しているという判断を突きつけられました。
中国市場と香港市場は関税発動の延期を受けて上昇基調を維持し、そのため多数の企業が貿易関係やサプライチェーンを調整する時間を確保することができました。香港市場については、大手電池メーカーのContemporary Amperex Technology社(中国)をはじめ、大型の新規株式公開(IPO)が数件実施されたことも支援材料となりました。しかし、EV(電気自動車)セクターは月後半以降、逆風にさらされました。これはBYD Company社(中国)が大半の車種で値下げを行うとの発表を受け、競合他社も追随を余儀なくされたためで、価格圧力は利益率に大きな懸念をもたらし、とりわけ小規模EVブランドにはその影響が色濃く現れました。
インド市場は、英国との間で自由貿易協定(FTA)を締結したという発表や、パキスタンとの紛争による緊張緩和、経済全般のモメンタムが改善など、複数の好材料に牽引される形で力強く上昇しました。また、当月は中小型株が大型株をアウトパフォームしました。
一方、台湾市場と韓国市場ではテクノロジーセクターの市場心理が改善し、ASEAN諸国では7月に迫った貿易交渉の期限を前に、引き続き米国との交渉が進められています。
ファンドの運⽤状況
当月、当ファンドのパフォーマンスは、前⽉末⽐10.14%の上昇となり、参考指数であるMSCI AC Asia Index(円ベース・配当込み)の同6.07%の上昇を4.07%上回りました。
セクター別では、資本財・サービスセクター、情報技術セクターなどがプラスに貢献しました。
当ファンドのパフォーマンスにプラスに寄与した銘柄は、Taiwan Semiconductor Manufacturing Company(台湾/半導体・半導体製造装置)、Sea(シンガポール/メディア・娯楽)、LIG Nex1(韓国/資本財)などでした。⼀⽅、マイナスに影響した銘柄は、Hugel(韓国/医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス)、GENDA(消費者サービス)、Indian Hotels(インド/消費者サービス)などでした。
当月開催されたBerkshire Hathaway社(米国)の年次株主総会で、ウォーレン・バフェット氏が年内をもって最高経営責任者(CEO)を退任し、後任をグレッグ・アベル氏に委ねると発表しました。バフェット氏は過去およそ60年間にわたって様々な形で自身の投資哲学を披露してきましたが、当ファンドも含めた多くの世代の投資家に計り知れない影響を与えてきました。そして、その考えはこれからも私たちの指針となり続けることでしょう。
ご存知の方もおられるかもしれませんが、当社の社内勉強会は同氏をはじめとする著名投資家の様々な投資哲学を学んでいることから「バフェット・クラブ」と呼ばれており、当ファンドももちろんバフェット氏が提唱したいくつかの投資指針に基づいてファンドを運用しています。投資家の多くが同氏の戦略を過剰に単純化し、単なるバイ・アンド・ホールド戦略と捉えていますが、同氏の投資に対する姿勢は実は非常に柔軟で、その投資戦略を狭い枠に嵌めて解釈するのは危険だという点には注意が必要です。
バフェット氏は師と仰ぐベンジャミン・グレアム氏(投資理論の古典ともいえる『証券分析』や『賢明なる投資家』の著者)の投資哲学から学び、いわゆる「シケモク投資」と呼ばれる割安株から投資を始めました。事業成績は今一つ(あるいはかなりの低水準)であっても、株価がそれ以上に低迷している銘柄を探し、そして株価が適正水準に戻った時点で、その銘柄を売却して次の投資対象を探すという手法を採用しました。同氏は1950年代から1960年代にかけてBuffett Partnership Limited(BPL)という投資合資会社を運営し、買収合併アービトラージ(企業同士の買収合併が成立することを見込んで関連する企業の株式の裁定取引を行うこと、同氏はこの取引を「work-outs」と命名)やアクティビスト的な動きを伴う投資も行っていました。例えば、同氏は1959年頃にSanborn Map社(米国)へ投資しましたが、その企業価値は同社が保有する多様な株式ポートフォリオの価値を下回っていて、主力事業である地図事業が黒字を計上しているにもかかわらず、その価値は実質的にマイナスと評価されていたのです。そのためバフェット氏は積極的に同社の経営方針に関して提言を行い、企業価値を高めようとしました。興味深いことに、こうした状況は現在の日本市場ではそれほど珍しいことではありません。
ウォーレン・バフェット氏が現在知られる「優良企業を買い、長期保有する」という投資手法に転換したのは、チャーリー・マンガー氏と出会い、バークシャー・ハサウェイの経営権を握った後のことでした(彼自身、この買収を「最大の失敗」と呼んでいます)。Berkshire Hathaway社は実質的に、損害保険事業で手にしたフロートと呼ばれる保険料収入による資金を原資とし、業績が堅調な企業を多数買収することで事業を軌道に乗せました。バフェット氏の初期の戦略はきわめて高い収益率を上げましたが(BPLであげた収益はパーセンテージで見ると同氏の経歴中でも飛び抜けて高水準でした)、投資規模の拡大は不可能でした。しかし優良企業を買収し、それを足がかりにすることで、多額の資本を投じながらまずまずの収益率を維持することに成功したという点では、同氏がよく口にする「規模はパフォーマンスの敵」という言葉が示す通りでした。この戦略の転換は、非常に現実的なものでした。同氏はBerkshire Hathaway社在籍中も、銀の購入(1997年)、米ドル以外の通貨によるバスケット取引(2002年)、買収合併アービトラージ(直近ではMicrosoft社(米国)によるActivision Blizzard社(米国)買収)など、型破りな投資を数多く行いました。投資の基本原則に従いながらも、機会があれば臨機応変に対応するという意味でのバランス感覚が、彼が他の投資家の追随を許さない点だと言えるでしょう。端的に言えば、バフェット氏は多くの人が考える以上に、非常に多才でバランスの取れた投資家なのです。一方で、彼も変わらないと信じる以下のような投資の基本原則が存在し、私たちもそれに従っています。
- 自分の「得意分野(circle of competence)」の範囲内で、自分が理解できるビジネスを展開している企業を買う
- 株式は企業の一側面に過ぎないので、投資家は企業とその本源的価値に目を向ける
- ファンダメンタルズが堅調な企業を注視する
- 株式市場は魅力的な売買価格を提供するための場であって、様々な合図を送って何をすべきかを教えてくれる相手ではない
- 安全余裕率(margin of safety)を確保する
私たちはこれらの原則に基づき、様々な形態で投資を行っています。当ファンドにおいては、組入銘柄のひとつに「光通信(資本財)」という日本企業がありますが、同社もやはりバフェット氏の原則に適合していると考えます。
同社は社名を聞くと通信会社のように聞こえますが、実質的には総合商社より規模がかなり小さいコングロマリットです。同社はアセットライトで経常的にキャッシュフローを生み出せる事業ポートフォリオに加え、様々な銘柄の公開株式も保有しています。光通信といえば、ITバブルの時にソフトバンクグループと並んで2大バブル銘柄と呼ばれていたことを記憶している方もおられるかもしれません。ITバブル崩壊後、ソフトバンクグループが積極的な投資スタイルを維持したのに対し、光通信はバフェット氏の投資原則にならって、より慎重なスタイルに転換しました。
光通信の事業は主力事業と投資(公開株式とM&A)に分けられます。主力事業は様々な品目を扱っているため、何をしているのかわかりにくいかもしれません。例えば、同社は日本の一般家庭や中小企業向けの電力卸売大手の1社です。さらに通信回線サービス、飲料水、損害保険や生命保険なども販売しています。一見関連性がないこれらの事業には、一般にアセットライトで、数年の間経常収益を確保でき、それによって堅調なキャッシュフローを生み出せるという共通点があります。同社は顧客獲得コストに対して生み出される潜在的な利益を見積もり、内部収益率(IRR)を最低15%確保することを目指しています。そしてこの収益基準を達成することに重点を置き、基準を満たせない場合は契約を締結しません。当ファンドが選好するのは、このように規模の追求より投資収益率(ROI)を優先する企業です。
同社は新規顧客獲得に向けて既存事業に再投資するだけでなく、約130万社の法人顧客と約400万人の個人顧客といった大規模な顧客基盤を活用したクロスセルを可能とし、新規事業を積極的に開拓しています。例えば、電力卸売事業は10年前には存在していませんでした。この事業が世に広まったのは、発送電の分離によって電力の小売りが自由化された2016年頃のことです。現在では、電気・ガス事業の規模は同社の主力事業の中で最大となっており、同社がどれほど先見性と起業家精神に富んでいるかがわかります。同社の営業利益の成長率は過去7年間で10.9%に達しています。
主力事業の営業利益が堅調に成長しているなかでで、時に主力事業への再投資に回せる額以上のキャッシュを生み出すため同社はその資金をM&Aや上場株式の購入に活用しています。同社の投資方針は簡単に言えば「安定した事業を行う財務基盤が強固な優良企業を割安な価格で取得」するというもので、これは基本的に当ファンドの運用方針(さらにBerkshire Hathaway社でウォーレン・バフェット氏が実践していると思われる方針)と同じです。同社は2000年代にBerkshire Hathaway社が本社を置くオマハを訪れたことをきっかけに、この手法を身につけたそうです。実際、同社はBerkshire Hathaway社の株主でもあり、保有率も比較的高めです。そうした経緯もあってか、同社はこれまでこれらの運用方針を着実に実践してきました。公開株投資のIRR(税引前)は過去7年間で17%と、まずまずの数字です。営業利益が堅調に伸び、株式投資からも収益が上がっていることから、同社の1株当たり純資産は過去7年間で約23%成長し、配当金支払額は計1,550億円に達しており、非常に堅実な実績を示しています。
当ファンドはかねてから同社のビジネスモデルを把握し、その実績を評価してきました。そして2024年後半の同社経営陣との面談により、同社への確信度が高まり、その直後に投資を決めました。同社の株価から投資ポートフォリオの価値を除いた主力事業の価値は、経常的に利益を生み出す力があり、成長性が高いにもかかわらず、PER(株価収益率)でみてわずか1桁台半ば相当に留まっていると考えられます。また、当ファンドの投資時点の価格からすると、投資ポートフォリオの価値が時間とともに上がっていくのは間違いないと考えます。株価はきわめて割安なうえ、経営陣が今後も企業価値を高めてくれると当ファンドは期待しています。
当ファンドはオリックス(金融サービス)や伊藤忠商事(資本財)などの主に資産配分を主力事業とする日本のコングロマリットを数銘柄組み入れています。こうした企業は規模が大きく、グローバルな事業展開をする能力が高いのが特徴です。事業規模というのはこうした企業にとって欠かせない要素です。規模と人脈がなければ未公開企業に投資できないことから、こうした企業は主に未公開市場で活動しています。しかし、バフェット氏の言う通り、「規模はパフォーマンスの敵」でもあるので、多額の資本を投じながらROIを高水準に維持するのは容易なことではありません。総合商社の場合、時には特定のサプライチェーンで足場を確保するためにROIが妥協される場合もあります。一方、光通信はこうした企業よりはるかに規模が小さく、ROIを高めることだけに事業の重点を絞っていることから、当ファンドは同社がオリックスや伊藤忠商事より早く成長すると予想しています。一方、後者2社についてはバリュエーションの低さと事業が世界的に多角化されている点を引き続き評価しています。これら3社を合わせると、当ファンドにとっては、安定性と耐久性が高く、分散化され、バリュエーションの低いポートフォリオが出来上がることになります。
今後の運⽤⽅針
当ファンドは以下3つの基準に基づいて投資を行っています。
- 逆風に強い優良企業で、競争優位性に優れていること
- 経営陣が事業運営に長け、合理的な資本配分を行っていること
- バリュエーションが割安であること
また、一般に以下のような特徴を有する企業を逆風に強い優良企業とみなしています。
- 競争優位性が確立され、業界平均を上回る収益成長を実現していること
- 独自な製品やサービス、あるいは必要不可欠な製品やサービスを提供していて、価格決定力に優れていること
- 営業レバレッジが大きく、事業の成長に伴って利益が経時的に拡大すること
- 優れたコスト構造により、厳しい状況下にあってもフリーキャッシュフロー創出力を維持できること
こうした企業にはアジア経済の成長力を取り込む力がある、あるいはアジア諸国独自の強みを生かして事業を国際展開する力があると考えられます。
当ファンドは日本を含むアジア全域から上記基準に最も合致する企業を選定し、集中的にポートフォリオを構築します。
したがって、国別配分比率はあらかじめ設定せず、各国固有のマクロリスクに注意を払いつつ、ボトムアップで銘柄選定を行ってまいります。
2025年4月の運用コメント
株式市場の状況
<⽇本の株式市場>
2025年4月、日本株式市場の代表指数であるTOPIX(配当込み)は前月末比0.33%の上昇、日経平均株価は同1.20%の上昇となりました。当月の日本株式市場は、米国の通商・金融政策を巡る不透明感に大きく揺さぶられる展開となりました。
月前半には、米国においてスタグフレーション(景気の後退と物価の上昇が同時進行する経済状況)の懸念が強まる中、トランプ政権が全世界を対象とした最大50%の「相互関税」を発表し、中国やEUが即座に報復措置を講じたことで、世界的にリスク回避の動きが広がりました。これを受けて、日本株式市場は大幅な下落となり、先物市場では「サーキットブレーカー」が発動されるなど、市場の混乱が際立ちました。その後、9日に米政府が一部関税の90日間一時停止を発表すると、過度な悲観ムードが和らぎ、市場は急反発しました。ただし、翌10日には米国が対中関税を累計145%まで引き上げる方針を明らかにしたことで、市場は再び警戒感を強めました。加えて、トランプ米大統領が米連邦準備制度理事会(FRB)に利下げを要求し、パウエル議長の解任懸念が浮上したことにより、FRBの独立性に対する不信感が高まりました。この影響で、米国市場では株式・債券・ドルがそろって下落する「トリプル安」となり、日本株式市場でも上値の重い展開が続きました。
一方、22日にはベッセント米財務長官が「関税は持続不可能」との見解を示したほか、23日にはトランプ米大統領がパウエル議長の解任を否定したとの報道が伝わったことで、市場には安堵感が広がり、日本株式市場も上昇に転じました。さらに、対中国の関税率を見直す旨の報道も好感され、米中対立の緩和への期待からリスクオン姿勢が続き、日本株式市場は前月末比で上昇して当月の取引を終えました。
<アジアの株式市場>
当月、⽇本を除くアジア市場に使⽤される⼀般的な指数であるMSCIアジア指数(⽇本を除く、⽶ドル建て)は、前月末比0.76%上昇しました。しかしこうした良好なパフォーマンスが出ても、株式市場が月内を通じて激しい上下動を繰り返したということの方にどうしても目が向きます。その発端となったのは、トランプ米大統領が「解放の日」に発表した関税の影響が、範囲の面でも規模の面でも市場関係者の予想をはるかに上回ったことでした。対米貿易に対する依存度が大きいアジア諸国のほぼすべてに甚大な影響がおよぶという見方が投資家の間に広がったことから、MSCIアジア指数(⽇本を除く、米ドル建て)は発表後数日で10%以上下落しました。
ところが当初はこれほど大きい衝撃があったにもかかわらず、中国以外の大半の国が報復措置を取らず、90日間の発動一時停止期間中に交渉を行う意欲を示したため、アジアの株式市場は総じて徐々に回復しました。現在は米国とアジア諸国の交渉が進行中で、米国と中国の協議は行き詰まったままです。
輸出と経済成長の鈍化に対する懸念から、アジア諸国の中央銀行は年内に金融緩和を実施し、自国経済の下支えを図る意向を示しています。中国も景気刺激策を通じて家計の消費支出を押し上げ、企業に輸出市場の米国以外への拡大を促すことで、貿易混乱の影響を和らげる措置に乗り出しました。BYD Company社(中国)のように対米輸出に対する依存度が低い企業は、競争力の高いEV(電気自動車)を魅力的な価格設定で供給することで、海外市場でも力強い成長を続けています。
こうした状況の中、インドは比較的有利な立場にあるようです。Apple社(米国)がインドにおけるiPhone生産の拡大を計画しているという報道が流れたことで、これに追随して今後インドで設備投資を行う企業が増え、インドが中国に代わる生産拠点としての位置づけを得る可能性があると考えます。
ファンドの運⽤状況
当月、当ファンドのパフォーマンスは、前⽉末⽐3.45%の下落となり、参考指数であるMSCI AC Asia Index(円ベース・配当込み)の同2.41%の下落を1.04%下回りました。
セクター別では、資本財・サービスセクター、生活必需品セクターなどがプラスに貢献した⼀⽅、金融セクター、一般消費財・サービスセクターなどがマイナスに影響しました。
当ファンドのパフォーマンスにプラスに寄与した銘柄は、Pop Mart International Group(中国/一般消費財・サービス流通・小売り)、LIG Nex1(韓国/資本財)、Hanwha Aerospace(韓国/資本財)などでした。⼀⽅、マイナスに影響した銘柄は、サンリオ(一般消費財・サービス流通・小売り)、三菱UFJフィナンシャル・グループ(銀行)、Tencent Holdings(中国/メディア・娯楽)などでした。
当月は近年でも特にボラティリティの高い月となりました。トランプ米大統領が「解放の日」と命名し、世界各国に相互関税を課すと発表した2025年4月2日以降、世界は一変しました。
当ファンドが解放の日を前にして講じた対策
当ファンドは解放の日にむけた事前対策として、2025年初から解放の日の直前にかけて、米国向け輸出が中心となっている企業のうち、資本財セクター、ハードウェア技術や半導体セクターなど、顧客の設備投資が収益の原動力となっている銘柄の組入比率を引き下げました。その結果、前月末時点で当ファンドの台湾の組入比率は参考指数であるMSCI AC Asia Indexを大幅に下回り、当ファンドが保有する半導体関連銘柄はTaiwan Semiconductor Manufacturing Company(台湾/半導体・半導体製造装置)のみとなりました。また現金保有率も増加し、同時点で7%近い水準に達していました。
解放の日以降の経過
解放の日以降の状況推移は当ファンドや市場の予想をはるかに下回るものでした。いわゆる相互関税の税率は、「X国に対する二国間貿易赤字をX国からの輸入額で割り、それをさらに2で割る」という方法で計算された模様です。その結果、世界の工場であり、一般に対米貿易黒字の多いアジア各国が最大の打撃を受けることになりました。アジア主要国の中で税率が20%を下回ったのはフィリピン(17%)とシンガポール(10%)だけでした。本報告書執筆時点では相互関税の賦課が中国を除いて90日間一時停止されており、2025年7月9日までは基本税率の10%のみが課されることになっています。各国は貿易協定の締結に向けて対米交渉を進めています。
最大のネガティブサプライズとなったのはベトナムで、相互関税は46%でした。対米輸出はベトナムのGDPの約30%を占めています。ベトナムは米国と関税引き下げ協定を締結できなければ、経済に深刻な打撃を受けることになります。なお、当ファンドはベトナム銘柄を組み入れておりません。
一方、やり方が強引すぎたこと、相互関税の計算方法が不可解であること、他国を見下すような発言があったことなどから、米国も深刻な信頼失墜に陥りました。
関税政策がポートフォリオにおよぼす影響(税率が発表済みのもののまま変わらないと想定した場合の弱気シナリオ)
一次的に関税の影響を直接的に被るのは、対米輸出企業でしょう。当ファンドは既にそうしたリスクに晒されている銘柄の組入比率を大幅に削減しています。保有銘柄のうち最も影響を受けると考えられるのは、ソニーグループ(耐久消費財・アパレル)、アシックス(耐久消費財・アパレル)、Samyang Foods(韓国/食品・飲料・タバコ)など、日本と韓国の一部銘柄です。ソニーグループとアシックスの場合、競合他社もアジアのサプライチェーンに依存し、同じ問題に直面しています。したがって、両社の競争上の位置づけは変わらないでしょう。ただし、サプライチェーン全体で値上げが進行し、そのコストを消費者に転嫁せざるを得なくなると考えます。それによって需要が短期的に激減する危険性があります。
Samyang Foodsについては、米国における競合先(東洋水産、日清食品、NongShim社(韓国))が製品を米国内で製造しているため、同社はコスト面で不利な立場に置かれています。しかし即席麺の価格はきわめて安価で、同社が製造する即席麺「ブルダック」の小売価格は100gあたり約1.1米ドルに過ぎません。関税によってコストが15から20セント上昇する可能性があり、小売事業者がそれを価格に全面転化すればその分価格が上昇することになります。しかし、そもそもブルダックは競合他社の製品よりかなり高価であることから、ブルダックの消費者にとって価格はそれほど重要な購買決定要因ではないと考えられ、価格が15から20セント上昇しても、ブルダックの需要が減退することはないとみています。一方、景気が悪化し、インフレが加速すれば、即席麺の需要は逆に増える可能性さえあります。
二次的影響としては、貿易戦争によって世界的な景気後退と米国のインフレ率上昇が発生するという事態が考えられます。しかし変動要素が多すぎるため、その影響を予測するのは不可能です。例えば、サンリオの米国事業はほとんどがライセンス供与であり、関税による直接的影響は軽微です。しかし、そのライセンシーはおそらくアジアから製品を仕入れているため、関税率が大幅に上昇します。
コスト圧力が高まることでサンリオの知財ライセンスを獲得する能力は低下するでしょうか?商品を値上げすることでサンリオに恩恵がもたらされるでしょうか(ロイヤリティは商品価格によって決まるため、価格が高ければ高いほどサンリオのロイヤリティが増える)?値上げによって消費者の需要は減るでしょうか?
正直なところ、事態がどう展開するかまったく予想がつかないので、新たな情報が出てきた時点で対応するしかありません。しかし忘れてはならないのは、ハローキティ、クロミ、シナモロールといったキャラクターに対する消費者のマインドシェアに変化はない、ということです。
当ファンドの投資方針の中心にあるのは、基礎体力があり、耐久力に富むと考えられる銘柄に投資するという考え方です。当ファンドが投資するのは、景気の軟化に対する備えが万全で、その影響に耐えるだけの体力がある銘柄です。そうした銘柄のパフォーマンスはマクロ環境が混迷期にあっても比較的好調に推移すると考えます。
全体的構図
世界各国が米国と交渉中のため、現時点で個々の国についてコメントすることは差し控えます。
関係者の多くが「X国に対する二国間貿易赤字をX国からの輸入額で割り、それをさらに2で割る」という単純かつ不可解な計算式で相互関税率を計算したことを批判していますが、米国の意図は単純明快で、貿易赤字の削減にあるようです。この計算式が他国の対米貿易障壁を適正に反映したものであるか否かは、いわばどうでもよいことなのです。米国は貿易赤字の削減に加え、自国の製造業を復活させたいと考えています。経済と国家安全保障の両面で重要だからです。そのため、米国との交渉は単なる関税の引き下げ要請だけでなく、米国の戦略的優先事項に合致するものでなければなりません。
ここで念頭においておくべきことは、対米貿易黒字を計上している国が必ずしも米国を利用しているわけではないということです。貧困国には、当然ながら米国から多額の商品を購入する資金がありません。そうした国々にできることは、コーヒー豆のような低価格商品や日用品を米国に売り、ドルと交換することです。貧困国が保有するドルの使途は選択の余地が乏しく、米国債を購入して赤字を補填することになるでしょう。そうした場合、常識的に考えて、貧困国が米国を利用しているとは言えないでしょう。
いま何が危険なのかというと、米国の財政赤字に既に注目が集まっているにもかかわらず、米国の世界的信用が失墜しつつあることです。米国は1980年代から「双子の赤字(貿易赤字と財政赤字)」を抱えています(その間に財政黒字期間が短期間だけ存在)。これほど長期にわたって双子の赤字を抱え続けるには、特権的な立場が必要です。ドルは世界の基軸通貨で、世界中の人々がドルを保有しておく必要があります。先行き不透明な状況下では、ドルはしばしば資産の安全な逃避先とみなされます。世界的な基軸通貨としての地位は、技術における米国のリーダーシップといった他要因とあいまって、世界各国から資本を引き寄せ、米国の双子の赤字を維持する要因となっています。
しかし米国の経済力と軍事力をもってしても、双子の赤字がいつまでも続くとは限りません。明確なのは、トランプ政権が貿易赤字と財政赤字という問題を両方解決することの緊急性を理解しているということです。米国が歳入源として関税を課し、政府予算を管理するためにDOGE(政府効率化省)を設置し、同盟国に国防支出を増やすよう圧力をかけているのはこのためです。しかし、政策の先行きが見えないこと、同盟国に対する姿勢が強硬であることから、ドルに対する世界的信頼が損なわれる可能性があります。米国はそれによって債務スパイラルに追い込まれる危険性があります。米国債利回りが上昇し、株式市場が下落する中でドル安が進行したことは、新興国市場ではありがちなことでしょうが、米国のような支配的地位を持つ国では起こりにくい事態です。それは早期警戒のサインだったと言ってよいでしょう。トランプ政権はいわゆる「マールアラーゴ合意」の構想を打ち出しています。ここで考えられる方法は、外国が保有する米国債をより残存期間の長い他の米国債と交換し、実質的に負担を遠い将来に転嫁することです。交換を求められる可能性のある国々は、その前に米国債を売却するかもしれません。幸いなことに、今のところ状況は安定しているようです。しかし対応を誤れば、何らかの形で金融危機に発展するリスクは今や小さくありません。
「米ドルが世界の基軸通貨でいられるのは、米国の市場が開かれていること、経済が堅調であること、法の支配によって財産権が保護されているからだ。それらすべてを保護しているものこそ、米軍である」
「世界経済に対する影響力と基軸通貨の地位を守りたいなら、米国は幅広い人々の信用を勝ち取り、信頼性を高める必要がある」
「同盟関係が強ければ強いほど、基軸通貨の地位も高まる。しかし、その逆もまた真である。歴史を通観すれば、国家が弱体化するとその国の通貨は基軸通貨の地位を失っていくのは明らかである」
- ジェームズ・ダイモン、JP Morgan Chase年次報告書2024年版(2025年4月7日 P25-26)
世界的な貿易不均衡は1つの国だけが原因で発生するものではなく、必ず別の側面があります。中国は世界最大の貿易黒字国であり、最大の債権国でもあります。世界的な貿易不均衡は特段新しい問題ではありませんが、中国が2001年にWTO(世界貿易機構)に加盟して以来、その貿易黒字がかつてない規模で拡大したことがこのところ話題となっています。
理論的に言えば、米国の購買力が低下するなら、中国は国民の消費力を高めて緩やかな人民元高を容認し、世界的な商品の買い手として存在感を増すべきです。それは米国が望んでいることであり、長期的には中国にとって良い結果を招くでしょう。 そうすれば中国は過剰生産能力を世界に安売りし続けるという方法をとらずに、長期的懸案である経済変革を推し進め、国際的イメージを改善することができます。しかしデフレ圧力と過剰生産能力という問題が深刻化する可能性があるため、短期的にはきわめて大きな痛手を被ることになるでしょう。
世界的な貿易不均衡は数十年にわたる問題で、解決には多大な痛みが伴います。たとえ何らかの合意に達したとしても、実際に実行する段になると困難を極める可能性があります。トランプ政権の言う通り、米国は製造業を復活させる必要がありますが、そのためには多くの課題を解決しなければなりません。問題の深刻さと複雑さを考えると、今のように強引なアプローチを続けるなら、その過程で何か非常事態が発生しても不思議ではありません。
解放の日以降にポートフォリオに加えた変更
解放の日以降、先進国市場の金融銘柄、とりわけ2年ほど前に組み入れた三菱UFJフィナンシャル・グループ(銀行)の組入比率を引き下げました。日本のメガバンクのバリュエーションは、市場が日銀の利上げサイクルを織り込んで過去2年間大幅に上昇したことで、相対的に割安感を失っていると判断しました。世界的な先行き不透明感を考慮すると、日銀は利上げを先延ばしする可能性があり、メガバンクの上値余地はさらに限定されると考えます。さらに、新しい世界秩序が米ドルと世界金融システムに与える影響も不透明です。米国の著名投資家レイ・ダリオ氏をはじめ、米国の債務危機が迫っていると指摘する人もいます。グローバル・メガバンクは世界の金融システムと深く結びついており、危機の際には多くのストレスに直面する可能性があります。ただしここで強調したいのは、危機の発生確率が高いということではなく、実際に発生した場合にどのような事態が起きるかわからないということです。幸い最終的に何も悪いことが起きなかったとしても、金融銘柄の株価上昇余地が、同時期に下落した他銘柄と比較して大きいわけではありません。当ファンドはボトムアップ・リサーチを採用しているため、投資決定要因はリスク・リターン特性であって、マクロの予測ではありません。
当ファンドは上記のような組入銘柄の一部売却を行うと同時に、安定した経常収益源と強固なバランスシートを持つと考えられる銘柄の組入比率を拡大しました。例えば、First Pacific(香港/食品・飲料・タバコ)への新規投資を開始しました。同社は香港市場に上場していますが、その資産はASEANの、主にインドネシアとフィリピンにあります。同社は主に世界最大級の即席麺会社であるIndofood CBP Sukses Makmur社(インドネシア)や、フィリピンとインドネシアを中心とした公共事業、有料道路、通信事業者などの重要なインフラ資産を所有しています。これはきわめて安定性の高い事業の集合体で、潤沢なキャッシュフローを創出しています。重要なのは、インドネシアもフィリピンも対米輸出に対する依存度が低く、国内主導型の経済であることです。そのため足元の貿易戦争の影響を受けにくい特性を有しています。同社は配当利回りが5%程度と魅力的な水準であり、累進配当政策を維持しています。さらに、ASEANにおける安定資産のポートフォリオも拡大しています。
もうひとつ組入比率を拡大したのは、対米輸出への依存度が最小で(すなわち一次的影響が最小)、景気低迷に対する耐久力が比較的強い(すなわち二次的影響を抑制可能な)製品を保持している銘柄です。バドミントンとテニス用品の世界的リーダーであるヨネックス(耐久消費財・アパレル)がその一例です。ヨネックスの北米売上はおよそ5%に過ぎず、収益の大半と将来の成長ポテンシャルはアジアからもたらされます。バドミントンのラケットは高額商品ではないため、景気低迷下でも底堅く推移すると思われます。実際、中国と台湾を中心とするアジア部門は、中国が厳しいマクロ環境にあるにもかかわらず、着実に成長しています。
国別では、直近投資していなかったフィリピン銘柄の組み入れを開始しました。フィリピンは人口が多く若年層が厚い国で、経済は国内主導型です。輸出総額はGDPの20%程度で、対米輸出は総輸出額の10%強に過ぎません。フィリピンに賦課される相互関税の税率は比較的低いため、貿易戦争の影響はきわめて軽微と考えます。それどころか、原油価格が下がれば、すでに下降トレンドにあったインフレ率をさらに押し下げる効果もあります。また、ドル安は中央銀行に利下げ余地を与えます。こうした要因によって、同国のマクロ的な状況はより盤石なものとなっています。フィリピンに直近投資していなかったのは、機会費用によるものです。実際、MSCIフィリピン指数は2023年以降、MSCI AC Asia Indexを大幅に下回っています。フィリピン市場もバリュエーションがきわめて低い水準で取引されています。MSCIフィリピン指数の1年後予想PERは約10倍で、コロナ禍の最低時よりさらに低い水準です。世界情勢が一変した現在、他の投資機会と比較して、この国の守備範囲の広さと安定した成長に再び魅力を感じ、インターネット通信関連銘柄と国内大手銀行1行の組み入れを開始しました。
また、資本財セクターやテクノロジー/半導体セクターなど、顧客の設備投資によって収益が左右される企業の組入比率は引き続き低く抑えています。貿易協定が締結されても、企業の大規模投資に対する意欲は著しく損なわれており、回復には時間がかかると思われます。
一方、当ファンドの現金保有比率は株式購入に充当したため低下しました。
幸いなことに、トランプ大統領は当月後半に様々な面で政策を緩和しているようです。しかし、トランプ政権の政策はきわめて予測がつきにくいことから、より安定性と耐久性の高い銘柄でポートフォリオを構築するよう努めています。
今後の運⽤⽅針
当ファンドは以下3つの基準に基づいて投資を行っています。
- 逆風に強い優良企業で、競争優位性に優れていること
- 経営陣が事業運営に長け、合理的な資本配分を行っていること
- バリュエーションが割安であること
また、一般に以下のような特徴を有する企業を逆風に強い優良企業とみなしています。
- 競争優位性が確立され、業界平均を上回る収益成長を実現していること
- 独自な製品やサービス、あるいは必要不可欠な製品やサービスを提供していて、価格決定力に優れていること
- 営業レバレッジが大きく、事業の成長に伴って利益が経時的に拡大すること
- 優れたコスト構造により、厳しい状況下にあってもフリーキャッシュフロー創出力を維持できること
こうした企業にはアジア経済の成長力を取り込む力がある、あるいはアジア諸国独自の強みを生かして事業を国際展開する力があると考えられます。
当ファンドは日本を含むアジア全域から上記基準に最も合致する企業を選定し、集中的にポートフォリオを構築します。
したがって、国別配分比率はあらかじめ設定せず、各国固有のマクロリスクに注意を払いつつ、ボトムアップで銘柄選定を行ってまいります。
2025年3月の運用コメント
株式市場の状況
<⽇本の株式市場>
2025年3月、日本株式市場の代表指数であるTOPIX(配当込み)は前月末比0.22%の上昇、日経平均株価は同4.14%の下落となりました。当月の日本株式市場は、米国の関税政策に対する不安や地政学的リスクの影響を受けて投資家心理が動揺し、荒い値動きが続きました。
月前半にはトランプ米大統領の相次ぐ関税発動によって世界的な景気減速懸念が台頭し、景気敏感株を中心に日本株式市場は大きく下落しました。
月半ばには植田日銀総裁の利上げ継続を示唆する発言、フィラデルフィア半導体株指数(SOX指数)の大幅上昇、ウクライナ情勢を巡る地政学的リスクの後退などに加え、ウォーレン・バフェット氏が率いる米国Berkshire Hathaway社による日本の商社株の保有増が好感されてバリュー株を中心に買いが集まり、日経平均株価が弱含むのに対してTOPIXは底堅く推移し、日経平均株価をTOPIXで除したNT倍率は5年ぶりの低水準となりました。
月後半に入ると、トランプ米大統領が輸入車に対して一律25%の関税を課すと発表したことで自動車株や半導体株が大きく売られ、リスク回避ムードが強まりました。さらに、米国で物価上昇と景気停滞が同時に起きる「スタグフレーション」への懸念が一層強まり主要株価指数が大きく下落したことを受け、日本株式市場もほぼ全面安となり、日経平均株価は約7か月半ぶりの安値で当月の取引を終えました。
<アジアの株式市場>
当月、⽇本を除くアジア市場に使⽤される⼀般的な指数であるMSCIアジア指数(⽇本を除く、⽶ドル建て)は、前月末比0.06%上昇しました。パフォーマンスはアジア各国でまちまちで、関税政策を巡る不透明感、米国の景気後退懸念、AI(人工知能)に関する市場心理の悪化が投資家の信頼感を損なう要因となりました。米トランプ大統領が米国に輸入される自動車に25%の関税を課すと発表し、相互関税の発表も予想されることから、世界的に景況感が悪化しました。
とりわけパフォーマンスが軟調だったのは台湾市場でした。米国の関税政策を巡る不透明感とAIに関する市場心理の悪化がいずれも株価の重しとなりました。また、中国のAI開発企業DeepSeekが従来より大幅に低いコストで高性能のAIを開発したことで、テクノロジー銘柄が高い成長率を維持するという期待感が薄まり、株価が急反落しました。それを受けてAIサーバーや機器の需要が予想を下回るという懸念が広がり、関連企業の業績が下方修正されました。
中国市場と香港市場は、不動産セクターに安定化の兆しが出てきたことやバリュエーションが割安であることから、底堅く推移しました。Alibaba Group Holding社(中国)の蔡崇信(ジョセフ・ツァイ)会長がデータセンター投資におけるバブルの可能性を警戒する発言をしたことが香港ハンセンテック指数の下落材料となりましたが、投資家の関心が再燃したことで、これまでの勢いは保たれました。また、BYD Company社(中国)とXiaomi Corporation社(中国)が生産能力拡張に向けて大規模な資金調達を行ったことは、中国EV(電気自動車)企業の市場シェアと普及率の拡大に対する自信の現れと考えられます。
インドネシア市場は前月の急落から当月は小幅上昇に転じました。新たに設立された政府系投資ファンドにガバナンス上の懸念があることや、国軍法の改正によって現役軍人の政府機関に対する監視を強化する道が開かれたことから、投資家は依然として慎重姿勢を維持しています。1月と2月の税収が低迷したことも、プラボウォ大統領の推進する「学校給食無償化」制度の持続性に関する懸念が高まる要因となりました。
一方、インド市場では、Nifty50指数が5か月連続で下落したあと力強い回復を見せ、当月は6.30%上昇しました。その原動力となったのは、銀行に対する規制緩和、外国機関投資家の投資の再開、民間消費や政府支出の拡大など、経済指標が良好だったことが考えられます。
ファンドの運⽤状況
当月、当ファンドのパフォーマンスは、前⽉末⽐0.41%の上昇となり、参考指数であるMSCI AC Asia Index(円ベース・配当込み)の同0.62%の下落を1.03%上回りました。
セクター別では、一般消費財・サービスセクター、ヘルスケアセクターなどがプラスに貢献した⼀⽅、情報技術セクター、コミュニケーション・サービスセクターなどがマイナスに影響しました。
当ファンドのパフォーマンスにプラスに寄与した銘柄は、Pop Mart International Group(中国/一般消費財・サービス流通・小売り)、三菱重工業(資本財)、サンリオ(一般消費財・サービス流通・小売り)などでした。⼀⽅、マイナスに影響した銘柄は、Taiwan Semiconductor Manufacturing Company(台湾/半導体・半導体製造装置)、LIG Nex1(韓国/資本財)、Futu Holdings(香港/金融サービス)などでした。
過去数か月にわたって今年の世界株式市場は非常に不安定になるだろうと述べてきましたが、実際にあらゆる市場でボラティリティが急上昇しています。当ファンドは選好銘柄のバリュエーション低下を買いの好機と捉えて対応しています。
当月、とりわけ目立ったのはインドネシア市場の月後半にかけての急落で、その要因としては、新たな政府系投資ファンドの発足や現財務相の辞任観測、また学校給食無償化などの政策によって財政悪化懸念が広がったことなど様々なものが考えられます。さらに、インドネシア国会で、政府機関への現役軍人の登用を拡大する改正法案が可決されました。こうした動きがいずれも市場の不安を呼び起こした模様です。当ファンドはかつて一部インドネシア銘柄を組み入れていましたが、いずれも2024年中に利益を確定し、インドネシア銘柄の直接的な組み入れがなかったため、今回の暴落の影響を回避することができました(ただし、Sea(シンガポール/メディア・娯楽)など事業面でインドネシアと関連のある銘柄は引き続き保有しています)。
2024年1月の運用コメントでご説明したように、当ファンドはボトムアップ・リサーチを重視する一方、保有比率の設定にあたり、もちろんマクロ環境の影響も考慮しています。というのは、マクロ環境はいわゆるサーキットブレーカー(株式相場が大きく変動した時に、相場を安定させるために発動される仕組み)の役割を果たしています。当ファンドは投資の規模を、主に投資の確実性という点から判断しています。マクロ経済が弱含み、政治の不確実性が高まると、企業にとっては業績の下振れリスクとなるため、組入比率を低く抑えます。そうした意味では、国別配分に関してマクロ経済分析に基づくトップダウン式のアプローチを採用する投資家と同じ結論に達することもあり得ます。現時点では引き続き状況を注視しており、場合によっては今回下落したインドネシア銘柄を組み入れることがあるかもしれません。
創業160年
2025年3月3日、当ファンドの組入銘柄であるHSBC Holdings(香港/銀行、以下「HSBC」)が創業160周年を迎えました。長期保有を見込む銘柄として、当月は同行について取り上げたいと思います。
もちろん、保有するか否かはバリュエーション次第であり、そして何よりも他に有望な銘柄がないかどうかという点にかかっています。他により有望な銘柄があれば売却して資本を再配分しますので、組入開始時点では長期保有を想定していても、保有期間は想定より短くなる場合があります。
HSBCの社名は母体となった香港上海銀行(The Hongkong and Shanghai Banking Corporation)の略称に由来しています。同行は1865年に当時英国の植民地だった香港を通じて中国と大英帝国の貿易を促進するという目的で設立されました。同行は、第二次世界大戦による混乱など数々の試練を乗り越えて、香港を代表する銀行としての地位を確立し、「The Hong Kong Bank」と呼ばれるまでになりました。香港が単なる港町から国際金融の中心地へと発展したことで、HSBCは多大な恩恵を受けました。香港の中環地区にあるHSBC香港本店ビルは、現在でも香港を代表する建物のひとつです。
HSBCは1990年代に海外進出を積極的に進め、最も重要な取引は1992年のMidland Bank(英国)の買収でした。同行は買収条件を充足させるため、ロンドンにグループの親会社となるHSBC Holdingsを設立しました。その後数十年にわたり、米国のRepublic National Bank of New Yorkや消費者金融会社Household Internationalの買収などを通じて、米国を含む世界各地へ事業を拡大し続けました(ただし2008年の世界金融危機で多額の損失を出し、HSBCは2011年に米国から撤退)。2002年から2016年までの長期間にわたり、同行のブランドスローガンは「The World’s Local Bank(世界の地方銀行)」という当時のグループのポジションを強調するものでした。最盛期には、HSBCは80か国以上で事業を展開していました。
しかし2008年の世界金融危機以降、グローバルバンキング事業は多大な困難に直面しました。銀行事業の収益性はコストの上昇とともに低下し、これほど巨大なグローバルバンキング事業を運営する意味はもはやなくなってしまいました。米国の銀行の中で最も大規模に世界展開を進めていたCitigroupの株価は、金融危機の発生以後、S&P500銀行株指数を大幅にアンダーパフォームしました。そうした事態を受け、HSBCは戦略的優先度の低い市場から撤退して事業構造を簡素化するという長い道のり(同行の160年の歴史と比較すればそれほど長くありませんが)を歩み始めました。現在、同行は58市場で事業を展開していますが、特に力を入れているのはアジア市場と英国市場です。
同行の事業部門は現在、以下のような区分となっています。
- 香港事業部門(2024年税引前利益の28%):香港におけるリテールバンキング業務、商業銀行業務など
- 英国事業部門(同20%):英国におけるリテールバンキング業務、商業銀行業務など
- 法人・機関投資家向け銀行業務(CIB)部門(同35%):主に大企業向けのクロスボーダーバンキング業務、キャピタルマーケット業務など
- 国際資産運用・プレミアバンキング部門(同12%):付加価値の高いリテールバンキング、プライベートバンキング、資産運用など
当ファンドの投資仮説は、事業基盤の強さと耐久力、優れた経営陣、魅力的なバリュエーションという3つの要素に集約されます。この基本要素に加え、カタリスト(きっかけ)があるか、業界は景気循環のどのサイクルにあるか、といった要素に基づいて投資手法を選択し、どのタイミングでどこに投資すれば最も高い利益が見込めるかを判断します。いずれにせよ、当ファンドの投資において3つの基本要素が変わることはありません。
HSBCの事業基盤の強さに関して述べると、同行は世界全体で事業規模を大幅に縮小した後、現在は自社が強みをもつ少数の主力事業に集中しています。同行は香港最大の銀行で、融資、預金、資産運用、生命保険などの分野で首位に立っています。英国では融資残高と預金額でトップ5に入っています。CIB部門では、貿易金融、外国為替、証券サービスなどの分野において、アジアで確固たる地位を築いています。また資産運用部門では、プライベートバンクとしてアジアで第2位につけています。同行は2024年に有形自己資本利益率(RoTE)が16%(一時的項目を除く)に達し、米国連邦準備制度理事会(FRB)の金利引き下げを加味した上で2025年から2027年には10%台半ばを目標としており、普通株式等Tier1⽐率(CET1比率、損失吸収力の高い自己資本をリスクアセットで割ったもの。より質の高い自己資本の割合を示した指標)は14%超ときわめて堅実です。事業基盤の強さは申し分ありません。
同行の経営陣については、2024年9月にGeorges Elhedery氏が新CEOに就任したばかりです。同氏は2005年にHSBCに入社し、グループCFOおよびグローバルバンキング&マーケット部門の共同CEOを務めました。同氏がCFOを務めていた当時、HSBCはすでにグループ構造の簡素化、コストの最適化、主要市場への再集中という戦略的方向性を打ち出していました。当ファンドはそうした方向性が適正で、社内から候補者が出たことで戦略の継続性が保たれると考えています。
今後の展望
事業基盤については前記しましたが、より重要なのは今後がどうなるかという点、バリュエーションが当ファンドにどの程度リターンをもたらすかという点です。HSBCの株価変動要因は以下の通りです。
- 短期的な逆風に直面している融資事業
- 好調な資産運用事業
- 組織再編とコスト削減
- 余剰資本と株主還元
同行は銀行なので、事業の根幹を成しているのは融資事業です。2024年には純受取利息が収益の66%を占めています。また2024年末時点で9,310億米ドルの融資残高のうち、アジアは約4,500億米ドル、その内香港は約2,720億米ドルを占めています。したがって、香港の事業環境はきわめて重要です。しかし短期的には香港経済が弱含み、住宅価格が低迷しているため、状況が好ましいとは言えません。しかし香港と中国の企業不動産(CRE)に大きな課題があるとはいえ、HSBCは優位な立場にあるためにより良い借り手を選ぶことができ、CRE関連の融資も当初は少なかったことから、信用損失の大幅な拡大はありませんでした。香港の他の銀行はこれとは立場が異なるため、多くはCREセクターの信用問題が足枷となっています。HSBCは中期的には融資残高の伸びが1桁台半ばで推移すると見込んでいます。香港については、2026年の融資残高の伸びは横ばいか、あるいはマイナスになる見込みです。一方英国において、HSBCは預金に関しては市場シェアが12%、住宅ローンは8%に過ぎません。資産運用については、市場シェアははるかに低く、成長余地があると考えられます。
香港ドルは対米ドルレートが固定されているため、香港の金利は米国にほぼ追随する形で動きます。米連邦準備制度理事会(FRB)の利下げは純金利マージンにとって逆風ですが、金利ヘッジは別として、定期預金は重要な相殺要因になります。FRBが2022年に利上げに踏み切るまで、定期預金(コストが高い)がHSBC香港の預金に占める割合はわずか一桁でしたが、2024年末時点では、香港における定期預金が預金に占める割合は39%に達しています。香港の6か月定期預金の金利は依然3.0%を上回っており、預金者にとって魅力的な水準です。仮に金利の低下が続いた場合、定期預金のコストにはさらなる低下余地があり、マージン低下分を相殺する効果を発揮することになります。したがって、FRBが利下げを続けたとしても、純金利マージン全体に対する影響は抑制できるものと考えられます。HSBCによると、1%の下落ショックが1年目の純金利マージンにおよぼす影響はマイナス29億米ドル(2024年の資金利益の約6.6%)と試算されています。一方、金利が長期的に上昇するというシナリオでいけば、逆に有利に働くでしょう。したがって、ポートフォリオの観点から、HSBCは長期金利上昇シナリオに対する重要なヘッジ銘柄となり得ると考えています。
資産運用部門は今後に期待できる部門で、HSBCは中期的に年平均成長率二桁という目標を掲げています。利下げ環境下で融資事業が逆風にさらされる中、資産運用事業はその逆風を相殺するという貴重な役割を果たすことでしょう。しかし香港経済が逆風の中、資産運用事業はなぜ堅調なのでしょうか。主な理由の一つは、香港が引き続き資本と人材の集まる場所になっており、とりわけ中国本土からの資本と人材でその傾向が顕著だという点にあります。比較的裕福で高収入な中国本土の人々を呼び込むため、香港は様々な移民制度を設けています。中国が現在低金利環境にあることを踏まえると、中国本土の人々にとって、中国に資本を持ち帰るのではなく、海外に資本を展開する方がはるかに有利です。このことはHSBC(および、当ファンドの保有銘柄であるDBS Group Holdings Ltd(シンガポール/銀行))の資産運用事業に多大な利益をもたらします。2024年には、HSBCは香港で79万9,000人の資産運用顧客を新たに獲得しました。香港の人口が800万人弱であることを考えると、これは非常に大きな数字です。とりわけ重要なのは、その成長要因が構造的なものであり、株式市場全般の動向とは関係ないと考えられることです。また、同行は香港以外にもシンガポールやアラブ首長国連邦といった主要事業拠点で資産運用事業を拡大しています。
同行はコスト削減を続ける見通しで、2024年のコスト基盤の約4.5%に相当する15億米ドルの削減を目標としています。しかし短期的には解雇に伴う退職金が増加する見込みで、2025年の支払額は約18億米ドルに上ります。このコスト削減の効果は2026年から2027年にかけて徐々に反映されることになるでしょう。コスト削減は収益に影響を与えず、すべて利益に転嫁されます。
これらの要因を総合的に考慮すると、HSBCの収益は利下げという逆風があっても安定を保ち、逆風が正常化した後に再び成長を取り戻す見通しです。
最後に、当ファンドの投資仮説の核心部分となる点でもありますが、HSBCは多額の資金を株主に還元できる形で生み出しています。同行のCET1比率は現在14.9%で、目標の14~14.5%を大幅に上回っています。前述ように、香港では融資残高の伸び悩みが予想されていますが、これは一見マイナス材料のように聞こえるものの、HSBC株式の現行バリュエーションでは融資残高の伸び悩みは必ずしもマイナス材料とは見なされていません。銀行にとって、融資残高の拡大ほど簡単に実現できるものはありません。銀行が低金利で質の低い借り手に積極的に貸し出せば、借り手は無制限に増えるからです。しかしそうした融資を行うと、銀行は損失を出すことになります。したがって、銀行業では融資残高が伸びることはが必ずしも好ましいものであるとは限りません。融資残高を拡大する場合、リスク加重資産(RWA)が増加するので、銀行は追加資本を確保して自己資本比率を維持する必要があります。一方、RWAがほぼ安定しており、リスク加重資産利益率(RoRWA)が適正であれば、銀行は長期的に余剰資本を蓄積できます。これらは銀行特有のものですが、再投資も配当も行わない一般企業が余剰資本を蓄積するのと本質的には変わりません。HSBCは短期的には、融資残高が拡大する見込みがないことから、余剰資本を株主に還元しています。実際、これはシンガポールや韓国などアジア先進国の銀行が軒並み実施していることです。2024年の1株当たり有形純資産価値(TEV)が8.61米ドルで、2025年末には約9.2米ドルに伸びる見込みであることから、HSBCはP/TEVがおよそ1.2倍強の水準で取引されていることになります。RoTEは10%台半ばで、HSBCが自社株買いを行うのに魅力的なバリュエーションであると考えます。同行は2025年の配当性向について、50%を目標としています。現在四半期あたり20億米ドルの自社株買いを行っていることを踏まえると、現行価格での総株主還元利回りは約10%に達し、アジア主要先進国の銀行の中で最も魅力的な水準になります。注目すべきは、HSBCがアジアで最も堅固な銀行フランチャイズの1つを保持していることです。
長期的にみると、HSBCは香港には中国本土の顧客を中心にして資産運用の一大拠点に発展できる可能性があるというのが当ファンドの見方です。香港市場に対する悲観的な見方がある中、スイスの金融大手UBS GroupのCEOであるSergio Ermotti氏は2024年半ばのイベントで、香港の富裕層向け資産運用業界は年平均7.6%成長しており、2027年にはスイスを抜いて世界最大になると述べました。当ファンドは、HSBCが最もこの発展の恩恵を受ける企業になり得ると考えます。HSBCの香港事業と国際資産運用事業はいずれも、グループ平均を上回るリスク加重資産利益率を実現しています。当ファンドは同行が資産運用事業の急速な拡大を続け、グループにより高い利益をもたらすと考えます。
ポートフォリオのバランス
当ファンドの投資において、「成長」は投資仮説の主要部分を占めています。しかし、「成長」だけが利益を生む方法ではありません。利益を確保するには企業の実態価値より低い価格で株式を購入するしかないのです。企業は株主還元を通じてそうした実態価値を市場の価格に反映することができ、HSBCはその好例と言ってよいでしょう。この種の銘柄には高成長株との相関性が低い傾向があり、ポートフォリオのバランスを保つ銘柄として重要な役割を果たします。
当ファンドは2024年に、アジア先進国の銀行で一部銘柄の入れ替えを行いました。2024年3月には韓国の企業価値向上プログラムで株主還元が向上するという仮説に基づいて、韓国のKB Financial Groupへ投資を開始しましたが、韓国の経済環境に対して慎重的な見方へ改めたことから、12月前半に売却しました。その分の資金はDBS Group Holdingsの買い増しおよびHSBCに乗り換えました。韓国の銀行銘柄はPBRが0.5倍以下ときわめて割安に見えますが、堅実なファンダメンタルズがなければ株主還元は実現しないため、その観点で懸念を抱いています。一方、HSBCとDBS Group Holdingsのファンダメンタルズははるかに強固で、株主還元は現行バリュエーション下でさらに拡大しています。
このように、当ファンドは特定のスタイルに固執することなく、バランスの取れたポートフォリオを構築することで、不安定な市場環境を柔軟に乗り切る力をつけることを目指しています。
今後の運⽤⽅針
当ファンドは以下3つの基準に基づいて投資を行っています。
- 逆風に強い優良企業で、競争優位性に優れていること
- 経営陣が事業運営に長け、合理的な資本配分を行っていること
- バリュエーションが割安であること
また、一般に以下のような特徴を有する企業を逆風に強い優良企業とみなしています。
- 競争優位性が確立され、業界平均を上回る収益成長を実現していること
- 独自な製品やサービス、あるいは必要不可欠な製品やサービスを提供していて、価格決定力に優れていること
- 営業レバレッジが大きく、事業の成長に伴って利益が経時的に拡大すること
- 優れたコスト構造により、厳しい状況下にあってもフリーキャッシュフロー創出力を維持できること
こうした企業にはアジア経済の成長力を取り込む力がある、あるいはアジア諸国独自の強みを生かして事業を国際展開する力があると考えられます。
当ファンドは日本を含むアジア全域から上記基準に最も合致する企業を選定し、集中的にポートフォリオを構築します。
したがって、国別配分比率はあらかじめ設定せず、各国固有のマクロリスクに注意を払いつつ、ボトムアップで銘柄選定を行ってまいります。
2025年2月の運用コメント
株式市場の状況
<⽇本の株式市場>
2025年2月、日本株式市場の代表指数であるTOPIX(配当込み)は前月末比3.79%の下落、日経平均株価は同6.11%の下落となりました。当月の日本株式市場は、トランプ米大統領の関税政策に関する言動に振り回され、月後半にかけて大幅な下落となりました。
月前半にトランプ米大統領がメキシコ、カナダ、中国に対する追加関税の検討を表明したことを受けて日本株式市場は急落しましたが、その後メキシコとカナダの関税発効が延期され株式市場は一時的に回復しました。しかし、複数の米国経済指標の結果からスタグフレーション(景気の後退と物価の上昇が同時進行する経済状況)懸念が再浮上する中で投資家は慎重な姿勢を保ち、日本株式市場も方向感のない、上値の重い相場が続きました。
月後半には、日銀の追加利上げ観測が高まり国内長期金利は一時約15年ぶりの高水準まで上昇しました。また、米国の消費者信頼感指数や購買担当者景気指数(PMI)が予想を下回る結果となり、米国経済の先行きに対する懸念が強まりました。これを受けて、為替市場では円高ドル安が進行し、日本株式市場の重石となりました。さらに、トランプ米政権による対中半導体規制強化の観測や、米国ハイテク株の下落、米国の関税政策を巡る不透明感などが影響し、日本株式市場は大幅に下落し当月の取引を終えました。
<アジアの株式市場>
当月、⽇本を除くアジア市場に使⽤される⼀般的な指数であるMSCIアジア指数(⽇本を除く、⽶ドル建て)は、前月末比1.05%上昇しました。パフォーマンスはアジア各国でまちまちで、中国、香港などの上昇幅が大きかった一方、インドネシア、タイ、インドなどは大きく下落しました。トランプ米大統領の関税政策を巡る不透明感の高まりが続いており、とりわけ新興国市場の先行きが不透明となっています。
米国が関税引き上げの姿勢をみせているにもかかわらず、中国市場と香港市場は当月に入って大幅に上昇しました。これは当月に習近平国家主席が民間企業のトップと会談したことを受け、今後を楽観する見方が改めて広がったことによるものです。中国政府は長年にわたって各業界の取り締まりを続けてきましたが、今回の会談によって、民間企業、とりわけテクノロジー企業の活動を明確に下支えする方針が打ち出されたという解釈が広がり、香港の代表的な株価指数であるハンセン指数は13.43%上昇して月を終えました。恩恵に浴したのは主に中国のテクノロジー関連銘柄で、Alibaba Group Holding社、Tencent Holdings社、Xiaomi Corporation社、BYD Company社などの株価が大きく上昇し、ハンセンテック指数は3年ぶりの高水準に達しました。
中国のAI(人工知能)開発企業DeepSeekが前月に話題をさらったことで、中国市場ではAI関連銘柄の上昇が続きました。大手テクノロジー企業であるAlibaba Group Holding社とTencent Holdings社はAI分野で大胆な動きを見せています。Alibaba Group Holding社はクラウドコンピューティングとAIインフラに3,800億元(約7兆8,400億円)を投資すると発表し、Tencent Holdings社は同社が運営するメッセージングアプリ「Weixin(微信)」に対するDeepSeekのAIモデルの試験導入を開始しました。
中国のテクノロジーセクターが好調だった一方で、台湾の半導体セクターは主にAIへの過剰投資に対する懸念から、米国市場に追随する形で下落しました。NVIDIA社(米国)の2025年1月期第4四半期決算発表後に発生した下落によって、とりわけその傾向が強まりました。
インド市場は海外投資家による売りが続いたこと、企業業績がふるわなかったこと、国内市場の成長に関する懸念が広がったことなどから大きく下落しました。政府が予算案に減税を盛り込み、インド準備銀行が利下げと流動資金の注入に踏み切るなど緩和的措置をとっているにもかかわらず、市場心理は全般的に弱含んだままでした。
ファンドの運⽤状況
当月、当ファンドのパフォーマンスは、前⽉末⽐1.75%の下落となり、参考指数であるMSCI AC Asia Index(円ベース・配当込み)の同2.49%の下落を0.74%上回りました。
セクター別では、コミュニケーション・サービスセクター、一般消費財・サービスセクターなどがプラスに貢献した⼀⽅、資本財・サービスセクター、情報技術セクターがマイナスに影響しました。
当ファンドのパフォーマンスにプラスに寄与した銘柄は、Tencent Holdings(中国/メディア・娯楽)、Samyang Foods(韓国/食品・飲料・タバコ)、LIG Nex1(韓国/資本財)などでした。⼀⽅、マイナスに影響した銘柄は、Taiwan Semiconductor Manufacturing Company(台湾/半導体・半導体製造装置)、リクルートホールディングス(商業・専門サービス)、Trip.com Group(中国/消費者サービス)などでした。
当月は前月取り上げたテーマの続編です。韓国の即席麺「ブルダック」を製造するSamyang Foods(韓国/食品・飲料・タバコ)が発表した2024年第4四半期決算はきわめて好調な内容でした。同四半期の売上高は前年同期比47%増、営業利益は同約142%増となりました。需要は非常に旺盛で、同社はその充足に必要な生産能力を何とか確保することができましたが、利益率の低い国内市場に対する供給を減らし、利益率の高い海外市場への供給に振り向ける必要がありました。そのため海外売上高は前年同期比78%増加しましたが、国内売上高は同18%減少しました。同社は2025年6月に韓国の密陽で新工場を立ち上げる予定のため、生産能力の逼迫は一時的に解消される見込みです。同社の業績が好調だったのと対照的に、日本の東洋水産と日清食品の業績はいずれも軟調でした。両社はともに北米市場で販売が低迷しています。日清食品の高価格帯商品は米国の主要小売店で韓国企業に棚スペースを奪われている模様です。日本株に投資する際、アジア市場に関して十分に理解しておかないと自らリスクを負うこととなります。その観点において日本を含むアジア全域に投資できることは、当ファンドの大きな強みだと考えます。
インドでは市場の下落が続きました。前月の運用コメントでインド銘柄の組入比率を10%程度に引き下げたとお伝えしましたが、当月前半にさらに引き下げ、約7%で月を終えました。当ファンドは過去2年間にわたってインドから高いリターンを得てきましたが、現状は成長局面の踊り場に相当すると考えています。過去2年間の大幅上昇の一部はバリュエーションの再評価によるもので、特に中型株でその傾向が顕著でした。MSCIインド中型株指数の予想PER(株価収益率)は2023年の約25倍から2024年下期には40倍に達して低下に転じ、足元の調整を経ても約33倍を維持しています。インド株の多くはバリュエーションが高く、とりわけインドがリスクフリーレート(リスクがほとんどない商品から得られる利回りのこと)の高い市場であることを踏まえると、なおさらそれが当てはまります。多数の銘柄がモメンタムを重視する買い手に支えられて上昇しましたが、上昇基調が反転したことで、モメンタム重視の買い手が売り手へと変わり、株価は自己破壊的な局面に陥る可能性があります。ここで重要なのは、インド経済が減速すると多数の企業で成長率が低下し、高い期待値に応えることがますます難しくなることです。当ファンドはインド銘柄の組入比率をこれ以上引き下げることは考えておらず、確信度の高い銘柄は保有を続ける方針です。しかし、アジアにはインド以外にも有望な投資先があるというのが現時点での所感です。
また、当月前半に、DeepSeekに関連するAI(人工知能)アプリケーション関連銘柄および中国銘柄の組み入れを決定しました。その資金を賄うため、台湾のハードウェア関連銘柄の一部について、組入比率を引き下げました。
ただし、これは当ファンドがハードウェアに対して全面的に弱気だということではありません。DeepSeekのような安価なAIモデルによってAIの普及が促進され、最終的にはAI半導体やハードウェアの需要が高まると考えています。しかし、AIハードウェア関連銘柄への投資の有望性は投資家の間で共通認識となっていることから、好材料の多くは既に株価に織り込まれていると考えます。株価は一次派生的な材料(既に変化しているもの)ではなく、二次派生的な材料(これから変化するもの)に反応する傾向があります。したがって、AIアプリケーション隆盛の恩恵を受ける企業に注目することで、より多くの投資機会を見出せると考えています。
AIアプリケーションに関しては、既保有銘柄であるTencent Holdings(中国/メディア・娯楽)、ソフトバンクグループ(電気通信サービス)、日立製作所(資本財)の組入比率を引き上げ、富士通(ソフトウェア・サービス)を新たに組み入れました。ソフトバンクグループは2024年後半に新規投資を開始した銘柄で、今後改めて詳しく取り上げるかもしれません。要するに、より安価で簡便なAIモデルが登場するとエッジAIの採用が加速する可能性があるというのが当ファンドの考えです。現在の市場価値からすると、ソフトバンクグループの価値の大部分は英国の半導体設計会社ARM社を保有していることに由来しています。エッジコンピューティングが軌道に乗れば様々な場面でARMチップの採用が増えるため、ARM社はその主要な受益者となると考えられます。
日立製作所と富士通は、いずれも日本を代表するITサービス企業です。当ファンドはより安価なAIモデルが登場すれば企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)が進むと考えています。AIは従来型のローエンドなITサービスの一部に壊滅的な打撃を与える可能性もありますが、代わりに新たな需要も生み出します。ここで必ず念頭に置いておいていただきたいのは、AIは単なる企業向けソフトウェアではなく、企業のあり方を根本的に変える可能性を持っているということです。
Accenture社(アイルランド)の報告書「Technology Vision 2025」に以下のような記述があります。「リーダーが十分に理解しておかなければならないのは、AIの最も重要な特徴は学習能力にあるということである。AIが普及し、企業がAIを事業のあらゆる分野で活用し、人々がそれを生活に取り入れるようになれば、AIは単に新しい機能や能力を提供する技術以上の存在に転化する可能性がある。企業はAIを活用することで、労働力を強化し、顧客サービスの新しいチャネルを作り、業務の一部を自動化するだけではない。一般知識を幅広く備え、学習能力があることを本質的な特徴とするテクノロジーを採用して、それに自社事業の一部を覚え込ませるのだ。さらに人々がそれを使う時には、さらに自分の好みや嗜好、ニーズを教え込むことになる」
企業はAIを企業戦略全体にどう組み込むかを検討するにあたって他社の力を借りる必要があるため、強力な技術力とコンサルティング能力を持つITサービス企業が恩恵を受けることになるでしょう。
最後に、当ファンドは2024年第4四半期に開始した取り組みの一環として、中国銘柄の組入比率を大幅に引き上げました。当月は中国・香港株の組入比率はインデックスの構成比に近い約22%で月を終えました。
DeepSeekの事例から、中国が米国から半導体規制を課されても引き続きAI開発競争に参加していることがわかります。AI開発は中国における新たなイノベーションの原動力となるでしょう。Tencent HoldingsはDeepSeekをはじめとするAIモデルをWeChatサービスに組み込んでいます。そうしたモデルはこれから汎用商品化していくと考えます。その理由の1つは、Meta Platforms社(米国)の「Llama」や「DeepSeek」に代表される先進的モデルの多くがオープンソースであることです。本当の意味で勝者となるのは、複数のモデルをまとめ、消費者にとって有用なアプリケーションに作り替えることができる企業でしょう。Tencent Holdingsはチャットアプリ「WeChat」や「QQ」といったサービスを幅広く手がけ、中国の消費者との接点が他社とは比較にならないほど豊富であることから、それを活用する上で最適な立場にあると考えられます。消費者だけでなく、様々な企業がAIの導入に関心を示していることが、クラウドビジネスの成長を後押しするでしょう。足元の株価上昇は、2024年第4四半期にみられた短期的上昇局面とは明らかに異なると考えます。2024年の上昇は純粋に政府の景気刺激策への期待によるもので、最終的には期待外れに終わりました。しかし今回の上昇は、中国の民間企業が自前のイノベーション能力を生かした何らかの成果への熱い期待が原動力となっています。そうした期待感の方がはるかに持続可能性が高いと考えられるため、香港・中国市場は年間を通じて持続的な上昇を遂げる可能性があると判断しています。
過去4年間に中国市場の障害となってきたのは、主に国内の規制リスクでした。インターネット業界や教育業界も含む様々な業界が一連の規制強化によって深刻な打撃を被りましたが、ついに転換点が訪れたようです。当月には習近平主席がAlibaba Group Holding社(中国)の馬雲(ジャック・マー)氏ら民間企業のトップと異例の公開会談を行いました。ここで重要なのは、かつて提唱されていた「共同富裕」というイデオロギーに回帰する動きが見て取れることです。習主席は会談で民間企業に対し、「まず豊かになり、それから繁栄を分かち合う(先富促共富)」ように促しました。これは1980年代に進められた改革開放政策を彷彿とさせる動きです。当時中国の指導者であった鄧小平氏は、先に一部の人を豊かにし(讓一部份人先富來)、そうした人々の力で他の人々を牽引し、最終的に国民全員で豊かになるべきだと提唱しました。過去40年にわたって中国経済を奇跡的成長に導いたのが、こうした発想だったのです。今回の会談は、これまでの規制強化のサイクルに終止符を打つ大きな転換点になると考えます。少なくとも今後2~3年間については規制の見通しが明らかになり、企業はイノベーションと成長再開に向けて体制を整えたということができるでしょう。
ところで、中国について語るなら、地政学的リスクを無視することはできません。これまでのところ、トランプ米大統領の出方は中国にとってプラスに働いています。まず、トランプ氏は選挙期間中に提示した一律関税に加えて中国からの輸入品に60%の関税を課すという案に代えて、相互関税を提案しています。同氏は「きわめてシンプルだ。我々に関税を課す国には、我々も関税を課す」と述べていますが、アジアには相互関税によってより大きな打撃を被る国が複数あり、中国は両国間の関税差が少ない(中国が米国からの輸入品に課す関税は、米国が中国からの輸入品に課す関税と同程度)ため、比較的影響が軽微とされています。
次に、トランプ大統領はカナダやEUといった米国の古くからの同盟国と距離を置きつつあります。米国はカナダとメキシコに25%の関税を課すと発表しましたが、現時点では課税を延期しています。同氏はさらにグリーンランド、カナダ、パナマ運河を領有したいという意向も示しています。同氏の立場からすれば、この3か所の領有には重要な貿易的・軍事的合理性があるのでしょうが、そうした発言は他国をひどく不安にさせるものです。
最後にEUに関しては、トランプ氏はウクライナとの和平交渉について、EUを介さずにロシアと直接行いたい意向を示しています。同氏のこうした行動によって、他国は対米関係の今後についてますます疑心暗鬼になっており、その結果、各国は米国との関係に100%依存するのではなく、中国と米国の間でよりバランスの取れた関係を持とうとする可能性があります。市場は米中関係の改善について一切期待していない模様ですが、中国が様々な国と関係を改善する可能性についても、株価には十分に織り込まれていないというのが当ファンドの見方です。
当ファンドは中国が直面している多くの経済的課題を無視しようとしているわけではありません。しかし、そうした課題の多くはすでに広く知られているものです。投資おいて重要なのは、まだ株価に十分に織り込まれていない二次派生的な材料です。足元で最大のリスクは、政府が現状に満足し、さらなる景気刺激策の推進を怠ることだと考えます。中国は依然としてバランスシート不況に陥っており、沈静化の兆しはあるものの、全体的なマクロ環境は軟調なままで、財政刺激策が不可欠です。日本は失われた数十年の間に複数回にわたって財政刺激策を縮小させましたが、その結果、経済をデフレに逆戻りさせただけでした。こうした教訓を無視してよいはずはありません。
今後の運⽤⽅針
当ファンドは以下3つの基準に基づいて投資を行っています。
- 逆風に強い優良企業で、競争優位性に優れていること
- 経営陣が事業運営に長け、合理的な資本配分を行っていること
- バリュエーションが割安であること
また、一般に以下のような特徴を有する企業を逆風に強い優良企業とみなしています。
- 競争優位性が確立され、業界平均を上回る収益成長を実現していること
- 独自な製品やサービス、あるいは必要不可欠な製品やサービスを提供していて、価格決定力に優れていること
- 営業レバレッジが大きく、事業の成長に伴って利益が経時的に拡大すること
- 優れたコスト構造により、厳しい状況下にあってもフリーキャッシュフロー創出力を維持できること
こうした企業にはアジア経済の成長力を取り込む力がある、あるいはアジア諸国独自の強みを生かして事業を国際展開する力があると考えられます。
当ファンドは日本を含むアジア全域から上記基準に最も合致する企業を選定し、集中的にポートフォリオを構築します。
したがって、国別配分比率はあらかじめ設定せず、各国固有のマクロリスクに注意を払いつつ、ボトムアップで銘柄選定を行ってまいります。
2025年1月の運用コメント
株式市場の状況
<⽇本の株式市場>
2025年1月、日本株式市場の代表指数であるTOPIX(配当込み)は前月末比0.14%の上昇、日経平均株価は同0.81%の下落となりました。
月前半は、米国の堅調な景況感指数や雇用統計の結果を受け、米国の利下げ期待の後退から日米長期金利が上昇したことや、米バイデン政権がAI(人工知能)向け半導体の輸出規制を強化する計画であると報じられたこと、その後当規制案が発表されたこと等を受け、株式市場は下落しました。
月半ばには、日銀総裁および副総裁から当月の金融政策決定会合で「利上げを行うかどうか議論して判断する」と、利上げを行う可能性が示唆されたことで円高が進行し株式市場の重しとなりました。しかし、昨秋からのレンジ下限として意識されている水準に近づくと下げ止まりの動きを見せ、株式市場は一転して上昇いたしました。
月後半は、トランプ米大統領が公約に掲げてきた対中関税の即時発動を見送ったことや、ソフトバンクグループ、OpenAI(米国)、Oracle社(米国)等が今後4年間で米国のAI開発事業に最大5,000億米ドルを投資すると発表し、AI・半導体関連銘柄が上昇をけん引したことなどにより、株式市場は堅調に推移しました。
一方、月の終盤にかけては、中国のAI開発企業DeepSeekが、米国製競合モデルを上回る性能を持った大規模言語モデルを低コストで開発したと公表したことで、米半導体企業の独占的地位が揺らぐとの警戒感から日米のAI・半導体関連銘柄が大幅に下落し、株式市場全体を下押しする局面がありました。しかし、月末にかけては揺り戻しの動きが見られ、前月末と概ね同水準で当月の取引を終えました。
当月もしばらく続くレンジ内での推移に終始した格好となりました。また、月中に日銀は政策金利の0.25%の引き上げを実施いたしましたが、事前の日銀総裁および副総裁の発言や、利上げ観測報道で市場への織り込みが進んでいたことから、影響は限定的なものとなりました。
<アジアの株式市場>
当月、⽇本を除くアジア市場に使⽤される⼀般的な指数であるMSCIアジア指数(⽇本を除く、⽶ドル建て)は、前月末比0.76%上昇しました。パフォーマンスはアジア各国でまちまちで、韓国、シンガポールなどの上昇幅が大きかった一方、ASEAN諸国、インドなどは出遅れました。韓国のKOSPI(韓国総合株価指数)は、前月の政情不安によるパニック売りから、当月は反発に転じました。
中国と香港市場は国内経済の低迷やトランプ氏の米大統領就任後の関税政策の不透明感が、引き続き投資家の懸念材料となって市場心理が弱含んだ状態で年明けを迎えました。しかし意外にも、トランプ米大統領が対中関税の即時発動を見送ったため、米中間で何らかの交渉や合意の可能性への期待感が高まりました。これを受け、中国・香港市場は春節(旧正⽉)休暇を前にして反発に転じました。
当月後半は、世界各国でテクノロジー・セクターが急落しました。そのきっかけとなったのは、中国のAI(人工知能)開発企業DeepSeekが生成AIモデル「DeepSeek- R1」を発表したことでした。この中国製AIは他のAIモデルの大半と同等以上の性能をきわめて低コストで実現したとされており、今後のAI関連投資の先行きに対する懸念が高まっています。この主張が事実なら、AIに対する設備投資、とりわけデータセンターとAI用ハードウェアの需要に大きな影響が及ぶことになります。そのためAI技術における米国の優位が揺らぐのではないかという懸念が投資家の間に沸き起こり、米国S&P500種株価指数は急落しました。またASEAN市場、特にマレーシアのデータセンター関連銘柄が大幅な下落に見舞われました。インド市場は、国内経済の成長に関する懸念と海外資金の流出が主な原因で、引き続き軟調に推移しました。
ファンドの運⽤状況
当月、当ファンドのパフォーマンスは、前⽉末⽐2.49%の下落となり、参考指数であるMSCI AC Asia Index(円ベース・配当込み)の同0.67%の下落を1.82%下回りました。
セクター別では、コミュニケーション・サービスセクターがプラスに貢献し、⼀⽅、一般消費財・サービスセクター、生活必需品セクターなどがマイナスに影響しました。
当ファンドのパフォーマンスにプラスに寄与した銘柄は、Sea(シンガポール/メディア・娯楽)、Futu Holdings(香港/金融サービス)、任天堂(メディア・娯楽)などでした。⼀⽅、マイナスに影響した銘柄は、Indian Hotels(インド/消費者サービス)、Zomato(インド/消費者サービス)、Varun Beverages(インド/食品・飲料・タバコ)などでした。
2024年12月の運用コメントの末尾でも触れましたが、2024年12月の「BofAグローバルファンドマネージャー調査」によると、ファンドマネージャー達は異例なほど株式に強気で、米国株式への投資比率が過去最高水準となり、ボラティリティの高い相場となる構図を作り出しています。当ファンドはトランプ米大統領の政策や米連邦準備制度理事会(FRB)の利下げ路線の不透明感から、このような相場が長期間にわたって続くと予想しています。これはあまりに慎重すぎる見方だと思われるかもしれませんが、決して市場が今後下落すると予想しているわけではありません。株式市場が一筋縄ではいかないものだからこそ、当ファンドは常々慎重姿勢を心がけています。当ファンドは2024年も慎重姿勢でしたが、最終的なパフォーマンスは予想を上回るものとなりました。当ファンドは基本姿勢が慎重なので、基礎体力があり、耐久力に富むと考えられる企業でポートフォリオを構成するように日頃から努めており、地域的にも株価上昇要因の面でもバランスを重視してポートフォリオを構築しています。当月は2024年に好調だった銘柄の多くが反落し、アンダーパフォームしました。そこでこれを機に、確信度の高い既存保有銘柄に加え、購入のタイミングを見計らっていた銘柄をいくつか新たに組み入れました。
インドは景気減速に直面していますが、当ファンドはこれを景気循環によるものだと考えています。インドの2024年度第2四半期のGDP成長率は前年同期比5.4%増と減速し、直近数四半期の中ではかなりの低水準となりました。同時に、生活必需品企業の多くで成長率が弱含んでいます。当ファンドが組入上位で保有するインド銘柄は、旅行関連企業のMakeMyTrip(インド/消費者サービス)、Indian Hotels(インド/消費者サービス)などですが、両社の業績は引き続き好調です。MakeMyTripの予約総額(米ドルベース)は、10月から12月までの3か月についてみると前年同期比約25%増、調整後営業利益は同約38%増となりました。Indian Hotelsは、RevPAR(利用可能な客室1室あたりの売上高、ホテル業界における既存店売上高に相当)が同15%と大幅に伸びたことで、10月から12月までの四半期売上高が前年同期比29%増、EBITDAは同32%増となりました。しかし、同社の株価は市場全体の急落による影響を免れることができませんでした。インド市場で問題なのは、バリュエーションが高いこと、そして当ファンドの感覚でいうと株価動向にモメンタム主導的な傾向が色濃くみられることだと考えます。インド株の多くが前回の上昇局面であまりにも上昇し過ぎたため、上昇基調が衰え、市場参加者が取引を手仕舞いしたことで、自己破壊的な局面に入ったというのが当ファンドの見立てです。これはバリュエーションが大幅に切り下がってファンダメンタルを重視する投資家がインド株へ投資するようになるまで、多くのインド株にとって苦境は解消されないということなのかもしれません。好材料とみなせるのは、モメンタム主導の下降局面に入れば、株価が最終的に本来の水準以上に下落し、割安な状態になる可能性があるという点です。それがいつになるかは不明ですが、バリュエーションはまだ心から安心できる範囲には入っていないというのが当ファンドの感覚です。当ファンドはインド銘柄の組入比率が約14%程度で当月を迎えましたが、月半ばから同比率の削減を始め、最終的に約10%程度で月を終えました。
テクノロジーに関しては、中国のAI研究所であるDeepSeek社が開発したオープンソース推論モデル「DeepSeek-R1」が当月後半に公開され、世界の半導体セクターに衝撃が走りました。DeepSeekはきわめて高性能で、しかもAIモデルの構築に要した費用は同社報告によるとわずか560万米ドルであるとされており、他のモデルが一般に数億ドル以上を費やしているのと比較すると格段の違いです。そのため、現状のようにデータ処理基盤に何十億ドルも投資しなくてもAIは開発でき、NVIDIA社(米国)のGPUのようなAI向け半導体の供給過剰が深刻化するのではないかという懸念が沸き起こりました。しかし、DeepSeekは現行の大規模言語モデルを基盤にして最適化されたもので、業界全体で行われた何十億ドルもの投資の恩恵を受けていることに留意すべきです。正直なところ、その衝撃の大きさを本当に理解している者はまだ誰もいません。ただし、AIモデルの構築や推論にかかるコストを大幅に引き下げることが可能なら、AIの技術革新や応用が促されることになるでしょう。それによって、最終的には計算能力、特にエッジコンピューティングの需要が高まるかもしれません。そのため、テクノロジー関連銘柄の組入比率に大幅な変更を加えることは見送りました。当ファンドは引き続き状況を注視し、先入観を持たずに対応していく意向です。
当ファンドの特徴は、日本の銘柄とアジアの銘柄をポートフォリオに組み入れているという点にあります。従来、多くの投資家は日本と日本以外のアジアへは別々に投資してきました。しかし、日本とアジア各国は経済的な結びつきが強いことから、多くの日本企業とアジア企業は密接な協力関係にあったり、競合相手だったり、同一バリューチェーンの各部分を棲み分ける運命共同体のような関係だったりします。アジア各国の調査を通じて得られた知見は日本の銘柄を組み入れる際の投資判断に役立ちますし、その逆も同様です。当ファンドはアジア全域にわたる知見を活用し、日本とアジアという範囲の中で最適な投資テーマを選定します。その最良の例が即席麺です。即席麵が最初に広まったのは日本ですが、今ではアジア各国に現地の即席麺メーカーがあります。当ファンドは2024年12月の運用コメントで、韓国で2024年最もパフォーマンスに寄与した銘柄であるSamyang Foods(韓国/食品・飲料・タバコ)を簡単にご紹介しました。当月は同社についてさらに詳しくご紹介したいと思います。
台頭する新世代の主食
「いつもこの小さなソースを持ち歩いて、何か食べる時は必ず入れるようにしているんです」 - ロゼ(BLACKPINK)※
当ファンドではこれまで幾度となくご説明してきた通り、消費者の所得が増えるにつれて⽀出額が継続的に拡⼤していくことから、エンターテインメント、旅行、美容、利便性といった消費関連カテゴリーを選好しています。即席麺は「利便性」のカテゴリーに入りますが、消費者の所得が増えたからといって即席麺に対する支出額が増えるわけではありません。それどころか、おそらく所得が増えると即席麺の消費量は減るでしょう。しかし、当ファンドはSamyang Foodsにはまだまだ成長の余地があると考えています。
即席麺をカテゴリー全体でみると、足元の環境は確かに追い風となっています。安価な食品であることから、インフレ率の上昇が有利に働きます。例えば米国のような市場では、人件費の高騰やチップ文化(食事代金の20%程を上乗せする)によって、外食やデリバリーが非常に高額になってしまい、手が届きにくいものになっています。米国では日清食品の高価格帯の即席麺でも1.00~1.20米ドル程度で売られているので、カロリーの割には非常に手頃な値段です。そのため、米国の即席麺市場はコロナ禍以降、堅調に成長しました。このように即席麺は不況やインフレに強いため、当ファンドは選好しています。このカテゴリーに属する企業は幅広い環境下で耐久力を発揮できると考えます。
思わしくないのは、即席麺市場全般の成長速度が速くないことです。アジア諸国を中心とする主要市場の多くでは、1人当たり消費量が既に高水準に達しています。しかしそうした中で、Samyang Foodsは2021年から2024年にかけて売上高を150%以上伸ばしたと推定されます。同社の売上高の約80%は韓国以外の市場であげたものです。2024年上期は総売上に占める中国の比率が約17%、米国が約22%、アジア(中国と韓国を除く)が約17%、欧州が約15%に達しました。成長の主な原動力は、即席麺市場としては歴史が浅いため浸透率がまだ低水準に留まっている米国と欧州です。特に両地域はインフレ率と物価が高いため、同社は自社製品をより高い価格で販売し高い利益率を上げられるということです。成長率が高い上に不況とインフレに強いのですから、これほど心強いことはありません。
米国市場で優位に立っているのは日本の東洋水産で、市場シェアが40%台半ば(売上高ベース)に達しています。同社の主要ブランドである「マルちゃん」の定番の袋麺はおよそ0.4~0.5米ドルで販売されています。米国民が好んで食べるのは単に価格が安いからです。東洋水産の米国事業が成長しているのは、主として一般に低所得者層である移民が増加しているためだと考えます。韓国の即席麺はそうした状況下で市場に参入しました。韓流ブームのおかげで世界中の消費者が韓国食品に興味を持ち始め、Nongshim社の「辛ラーメン」は韓国食品を代表する商品となりました。人々が韓国の即席麺を食べるのは、単に安いからではなく、韓流ブームの影響でもあるのでしょう。米国におけるNongshim社の市場シェア(売上高ベース)は、推定で2017年の約20%から2023年には20%台半ばまで上昇したとされています。しかし辛ラーメンは古参ブランドです。一方Samyang Foodsの「ブルダック」は新しいブランドで、若年層の心を急速に掴みつつあり、新世代の主食として台頭してくる可能性があると考えられます。
ブルダックはまずアジア諸国で人気を勝ち得ました。その理由は以下のようにいくつかあります。
- 独特の味わい:ブルダックには独特の甘辛い味わいがあります。実は、同社はソース(冒頭のK-POPグループ、BLACKPINKメンバーのロゼの言葉にもある小さなソース)を別商品として販売しています。ソースを別売りにできるということからも、この味の人気の高さがわかります。他の即席麺ブランドで、調味料だけを別売りできるものは見たことがありません。
- 魅力的なパッケージ:ブルダックのパッケージには火を吹くニワトリが描かれており、他の即席麺多数と並べても一目で判別できます。Nongshim社の辛ラーメンのパッケージには「辛」という文字が書かれていますが、漢字が読めない人には意味がわからないでしょう。
- デジタル・マーケティング戦略:ブルダックはソーシャルメディアでブルダックのラーメンの完食に挑戦する様子を投稿する「ファイヤー・ヌードル・チャレンジ」が流行ったことで人気に火がつきました。サンリオを取り上げた際に知財ビジネスについてご紹介しましたが、それと同様、現在の消費財企業には効果的なデジタル戦略が必要だというのが当ファンドの考えです。その点、Samyang Foodsは他の即席麺メーカーよりデジタルの活用方法に長けていると考えます。
当ファンドはブルダックの人気が高まっていることを知り、長期にわたってSamyang Foodsを注視してきました。2024年12月の運用コメントでお伝えしたように、当ファンドはブルダックのオリジナル味(黒いパッケージのもの)はアジア以外の国の人にとっては辛すぎると考えています。アジア人であっても、あまりに辛いので高頻度で食べるのは不可能でしょう。当ファンドが同社の組み入れを開始したのは、新たに登場したカルボナーラ味(ピンク色のパッケージのもの)の人気が世界的に高まってきてからです。この味はネットユーザーがオリジナル味の麺にクリームとチーズを加えて辛さを和らげていたことに着想を得て誕生したものだと言われています。カルボナーラ味は世界的なヒット商品となり、TikTokには昨年、テキサス州の少女が誕生日プレゼントにピンク色をしたカルボナーラ味のブルダックをもらって嬉し涙を流している口コミ動画が投稿されました。Samyang Foodsはそれを知って少女にカルボナーラ味のブルダックを1年分プレゼントしたそうです。ここからも、同社がソーシャルメディアをマーケティングに活用する方法を熟知していることがわかります。カルボナーラ味ブルダックの売上高は2023年上期の約600億ウォンから2024年上期には約1,570億ウォンに急増し、売上貢献度はオリジナル味のブルダックに匹敵するほどでした。
カルボナーラ味のブルダックが世界的人気を博している理由は、前記した3点以外にもう一つあります。大多数の即席麺がスープ麺であるのに対し、カルボナーラ味のブルダックはスープのない炒麺であるということです。正確なデータはありませんが、米国や欧州のような先進国市場では、麺類はスープのないもの(パスタを含む)の方が一般的だと思われます。日本の即席麺メーカーも焼きそばのような炒麺商品を出していますが、味はきわめて日本的で、欧米市場には合いません。一方、「カルボナーラ」味は洋風そのものですが、Samyang Foodsはクリーミーな食感と韓国風のスパイシーな風味を組み合わせることで、独特の味に仕上げています。さらに、炒麺にはスープ麺にはない柔軟性があり、ネギやチーズ、卵などを自由にトッピングして混ぜ合わせることができます。スープ麺だとこれほど自由にアレンジするのは困難です。
ではSamyang Foodsは現状の優位性を維持できるのでしょうか。当ファンドはできると考えます。
まず、即席麺の競争環境が安定的で、競合他社がほんの一握りに限られていることです。模倣品もあることはあります。例えば日清食品もカルボナーラ味の韓国風炒麺を発売しました。しかし、まったく同じ味を作ることは不可能です。業界全体を見渡しても、人気の即席麺が模倣品に取って代わられたのを見たことはありません。また、違う味の商品であっても、根強い人気がある商品に取って代わるのは困難です。特定の市場で優位に立った味は、その後も優位に立ち続ける傾向があります。例えば、ブルダックが人気だとはいえ、韓国市場で辛ラーメンの人気を脅かすほど売れているわけではありません。香港では、日清食品の「出前一丁(ごまラー油味)」が今も即席麺の代表格で、高い人気を誇っています。消費者には味覚の一貫性とでも言うべきものがあり、一度「ハマる」とずっと同じ味を選ぶようになる傾向があると考えます。ブルダックのカルボナーラ味は、欧米先進国市場の新興消費者層の需要に応えていると考えられます。ブルダックはそうした新興消費者層の心をしっかりとつかむことができれば、長期的な優位性を確保できる可能性があります。
次に、Samyang Foodsは製品開発のペースが非常に速いということです。同社が2024年上期にブルダックの輸出であげた売上高のうち、ブルダックオリジナル味、カルボナーラ味、その他の味が占める割合はそれぞれ約3分の1ずつでした。ブルダックには他にもトマトパスタ、クアトロチーズ、カレー、ハバネロ&ライムなど様々な味があります。これほどまでの製品開発の速さは、他の即席麺メーカーではほとんど見られません。同社は海外市場の成長を取り込むため、2023年下期に即席パスタの新ブランド「tangle(テングル)」を立ち上げました。tangleは便利な即席麺ですが、パスタ麺は冷風乾燥したもので、油で揚げたものではありません。そのためカロリーが一般的な即席麺の1食あたり500kcal以上なのに比べ、400kcal未満と低いのが特徴です。これにより従来と全く異なる消費者層を惹きつけ、長期的にもう一つの成長の原動力になる可能性があるとみています。また同社はデジタルチャネルを通じて顧客と効果的にエンゲージメントを図る能力(ブルダックのInstagramのフォロワー数は24万人以上)とイノベーション能力を兼ね備えていることから、同社は世界の消費者を獲得する上で、他の即席麺メーカーよりはるかに有利な立場にあるというのが当ファンドの考えです。
当ファンドがよく受ける質問に、どこから投資アイデアを得るのかというものがありますが、最も一般的な方法は「市場を知る」ことです。市場や業界をよく知っていれば、どこに投資機会があるのかは自ずと見えてきます。当ファンドは業界に関する予備知識と背景情報を既に保持しているので、それが投資アイデアを生み出す最も安全な方法だと考えます。エンターテインメントに詳しい人なら、ハローキティやK-POPの人気の高さは当然知っていることでしょう。即席麺を食べる人々は、ブルダックの人気が高まってきたのを無視することはできません。当ファンドは今後もボトムアップ・リサーチと市場に関する広範な知識を生かして、知見とアイデアを生み出してまいります。
※ 出典:VOGUE Taiwan.“[KOR SUB]打開BlackPink Rosé(로제)超大Saint Laurent隨身包包:痘痘貼也要很可愛、只用蘋果有線耳機|In The Bag|Vogue Taiwan“. Youtube, 2023/05/25,https://www.youtube.com/watch?v=LCmYJR5mnXg&t=335s(参照:2025/01/31)
今後の運⽤⽅針
当ファンドは以下3つの基準に基づいて投資を行っています。
- 逆風に強い優良企業で、競争優位性に優れていること
- 経営陣が事業運営に長け、合理的な資本配分を行っていること
- バリュエーションが割安であること
また、一般に以下のような特徴を有する企業を逆風に強い優良企業とみなしています。
- 競争優位性が確立され、業界平均を上回る収益成長を実現していること
- 独自な製品やサービス、あるいは必要不可欠な製品やサービスを提供していて、価格決定力に優れていること
- 営業レバレッジが大きく、事業の成長に伴って利益が経時的に拡大すること
- 優れたコスト構造により、厳しい状況下にあってもフリーキャッシュフロー創出力を維持できること
こうした企業にはアジア経済の成長力を取り込む力がある、あるいはアジア諸国独自の強みを生かして事業を国際展開する力があると考えられます。
当ファンドは日本を含むアジア全域から上記基準に最も合致する企業を選定し、集中的にポートフォリオを構築します。
したがって、国別配分比率はあらかじめ設定せず、各国固有のマクロリスクに注意を払いつつ、ボトムアップで銘柄選定を行ってまいります。
2024年12月の運用コメント
株式市場の状況
<⽇本の株式市場>
2024年12月、日本株式市場の代表指数であるTOPIX(配当込み)は前月末比4.02%の上昇、日経平均株価は同4.41%の上昇となりました。年間では両指数とも2年連続で上昇し、年末終値としては日経平均株価が最高値を更新しました。
月前半には、厚生労働省が年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)を通じて運用する資産の利回り目標を引き上げる方針を明らかにしたことで、日本株式の資産配分比率が高まるとの思惑が高まったことや、好調なハイテク株に支えられた堅調な米国株式市場、さらには米国の利下げ鈍化懸念からの円安進行等が日本株式市場の上昇につながりました。
月後半には、18日に米連邦準備制度理事会(FRB)は米連邦公開市場委員会(FOMC)において予想通り政策金利の引き下げを決定し、2025年については2回の利下げに留まることを示唆しました。これを受けて米国長期債利回りは上昇し、米国株式市場は調整に転じ、その影響で日本株式市場も軟調に推移しました。しかしながら19日には日銀は金融政策決定会合にて金利を据え置くことを決定し、その後の記者会見で植田日銀総裁がハト派的な発言を行ったことで為替市場では円安ドル高が進みました。その後は好調な米国の半導体株及びさらなる円安に支えられ、日本株式市場は再び上昇に転じ、27日には日経平均株価は4万円の大台を回復しました。
<アジアの株式市場>
当月、⽇本を除くアジア市場に使⽤される⼀般的な指数であるMSCIアジア指数(⽇本を除く、⽶ドル建て)は、前月末比0.19%上昇しました。パフォーマンスはアジア各国でまちまちで、韓国、オーストラリア、インドなどの下落幅が大きかった一方、台湾、香港、中国などは上昇しました。通年でみると、MSCIアジア指数(⽇本を除く、⽶ドル建て)は前年末比12.51%上昇しました。
当月はKOSPI(韓国総合株価指数)が前月末比2.30%下落しました。韓国大統領が戒厳令を発令したことで、市場ではパニック売りが発生しました。政情不安と統治問題に対する懸念は、もともと軟調だった韓国経済に追い打ちをかける形となっています。KOSPIは通年で前年末比9.63%下落し、2024年のパフォーマンスはアジア市場の中で最低となりました。
中国市場は景気低迷と対米貿易摩擦の激化に対する懸念が拭えない中で、2024年通年のリターンがプラスとなりました。これは中国政府が景気刺激策の発動を示唆したことを受け、9月に入って株価が急騰したことによるものです。しかし、より具体的な対策が打ち出されなければ消費需要の低迷や不動産市場の苦境からの立ち直りはおぼつかないことから、投資家は慎重姿勢を崩しませんでした。
台湾のテクノロジーセクターは年間を通じて堅調なパフォーマンスを見せました。Taiwan Semiconductor Manufacturing Company社(台湾)やMediaTek社(台湾)といった企業が、半導体やAI(人工知能)技術に対する世界的な需要拡大の恩恵に浴しました。
当月、ASEAN市場のパフォーマンスはまちまちでした。インドネシア市場は通貨安と消費支出低迷の影響で、とりわけ軟調に推移しました。一方、マレーシアの株式市場は、半導体やデータセンターを中心に海外投資の流入が続いたことが支援材料となり、堅調に推移しました。
ファンドの運⽤状況
当月、当ファンドのパフォーマンスは、前⽉末⽐4.55%の上昇となり、参考指数であるMSCI AC Asia Index(円ベース・配当込み)の同4.90%の上昇を0.35%下回りました。
セクター別では、一般消費財・サービスセクター、情報技術セクターなどがプラスに貢献しました。
当ファンドのパフォーマンスにプラスに寄与した銘柄は、Taiwan Semiconductor Manufacturing Company(台湾/半導体・半導体製造装置)、サンリオ(一般消費財・サービス流通・小売り)、Hyundai Marine Solution(韓国/資本財)などでした。⼀⽅、マイナスに影響した銘柄は、Hanwha Aerospace(韓国/資本財)、セブン&アイ・ホールディングス(生活必需品流通・小売り)、Asia Vital Components(台湾/テクノロジー・ハードウェアおよび機器)などでした
2024年はアジア各国にとって驚きと動揺に満ちた一年となりました。そうした中で、当ファンドは比較的好調なパフォーマンスを達成しました。通年でみると、当ファンドが前年末比40.85%上昇した一方で、参考指数であるMSCI AC Asia Index(円ベース・配当込み)は同24.16%の上昇でした。2024年11月の運用コメントで2023年に実施した投資方針の転換について触れましたが、2年連続で絶対リターンがプラスとなり、市場平均を上回るパフォーマンスを達成できたことは喜ばしい限りです。
2024年のパフォーマンスが良好なものとなった要因は様々なものが考えられます。市場を日本、インド、韓国、台湾、香港・中国、ASEANに分けてみると、全ての市場がプラスのリターンに貢献しました。当ファンドはボトムアップ・リサーチを用いて投資機会を見出し、それに基づいて様々な市場に資本を配分していますが、同時にアジア各地域で組入銘柄のバランスを保つことも心がけています。そのため、特定の国が他の地域と比べて非常に良好なパフォーマンスを示した場合、当ファンドのパフォーマンスは単年ではその国の市場に劣後する可能性が高くなります。例えば日本株式市場は、2023年はきわめて好調でしたが、2024年は他地域と比べてまずまずのパフォーマンスでした。そのため、当ファンドは2023年にはなかなかTOPIX(配当込み)に追いつけませんでしたが、2024年は大幅にアウトパフォームし、2年間でみるとTOPIX(配当込み)を大幅に上回ることができました。これは意図的にそうなるようにしたのであって、偶然ではありません。ポートフォリオ内の銘柄がそれぞれ異なるタイミングで上昇・下落することこそが分散投資を行う上で肝心な点であり、そうした銘柄全体を3~5年という長期間でみた場合に十分なリターンが生まれている限りは、理想的な状態であると言えるでしょう。もしも仮にポートフォリオ全体が同時に上下するのなら、分散投資を行う意味はありません。たとえ株価が堅調に推移している国でも長期にわたって不調に転じる可能性もあり、また、これから株価が上昇する国がどこなのかを言い当てられる人はあまりいないでしょう。だからこそ、組入銘柄を地域的に分散させることは決して無意味なことではないのです。当ファンドはアジアにおける投資機会を一括で捉えることができるワンストップ・ソリューションを提供しています。
株式市場は全体でみると過去2年間で上昇しており、それが絶対リターンの追い風となりました。そうなると当然ながら、市場が軟調に転じるとどうなるのかという疑問が湧いてきます。「There is always a bull market somewhere(強気相場は常にどこかにある)」という格言がありますが、当ファンドもこの考えに賛同します。当ファンドはボトムアップ・リサーチを採用しており、保有銘柄はそれほど多くありません。投資対象地域はアジア全域で、保有銘柄数は25銘柄から35銘柄です。こうした集中的なアプローチをとることで、各市場にごく少数しかない最有望銘柄に集中することができます。適正な銘柄をごく少数選定すれば、市場全体が軟調な時でもプラスのパフォーマンスを上げることは可能です。その好例が後述する2024年の韓国の状況です。こうした背景から、当ファンドは2025年の市場動向について楽観的な見方を維持していますが、一部の市場では注視すべき兆候が見られることも確認しています。
日本:コーポレート・ガバナンス改革
日本は当ファンドの国・地域別構成比率が最大であることから、2024年の絶対リターンに対する寄与度が最も大きな市場となりました。本コメントをお読みの方ならおわかりかもしれませんが、日本企業で2024年の当ファンドのパフォーマンスに最も寄与した銘柄はサンリオでした(2024年2月と2024年10月の月次報告書を参照)。しかしながら、2024年はサンリオだけでなく、幅広い銘柄が値上がりました。
日本市場について何か一つ書くとすれば、「コーポレート・ガバナンス改革」についてでしょう。コーポレート・ガバナンス改革は単なるスローガンではなく、実際に株式のパフォーマンスを向上させる力をもっています。その効力で一定水準のリターンを上げたセクターの一つに、日本の損害保険会社があります。
日本の損害保険会社はこれまで、いわゆる政策保有株式の上にあぐらをかいており、その金額は数兆円に達していました。保険会社がこうした株式(トヨタ自動車㈱など、上場企業数百社の株式)を購入したのは1960年代で、企業保険の取引関係を構築、維持するためでした。何十年も株式を保有し続けていると、巨額の含み益が積み上がります。しかし、そうしたこれらの株式は長らく「活用されていない資産」として放置され、非効率的な資本管理を象徴する存在となっていました。そこで2024年初頭に金融庁が保険会社に対し、業務改善計画の一環として政策保有株式の売却を加速するよう要請し、改善計画の提出期限を2024年2月に設定しました。各社はこれを受け、当該株式を今後6~7年間ですべて売却すると表明しました。この発表は市場で好意的に受け止められ、その結果、株価は年内に大きく上昇しました。当ファンドはMS&ADホールディングス(保険)については、短期間で目標価格に達したことから、既に利益を確定しました。一方、東京海上ホールディングス(保険)については保有を継続しています。当ファンドは東京海上ホールディングスの事業運営と過去のM&Aにおける優れた実績を高く評価しており、株価は未だ割安な水準にあると考えています。
日本に関してよく受ける質問の一つに、「日本の上昇余地はどこにあるのか。円安局面が終わればEPS(1株当たり純利益)の伸びも見込めなくなるはずだ。」というものがあります。日本は30年以上も低成長が続いているため、EPSは伸びないという印象が広がっています。しかし日本の素晴らしいところは、市場が多様性に富んでいて、個別に見ていけばEPSを十分なペースで伸ばすことができると考えられる優良銘柄(サンリオなど)が多数あるということです。したがって、「There is always a bull market somewhere」という格言は日本市場を最もよく言い表した言葉だということができます。当ファンドがなすべきことは、ボトムアップ型のアプローチでそうした銘柄を発掘することです。
一方で、コーポレート・ガバナンス改革はEPS成長の貴重な原動力です。その例として一般的なのが、自社株買いの増加です。日本ではよくあることですが、バリュエーションが低い状態で株式が買われると、自社株買い自体がEPSの成長を促すことがあります。有機的成長(オーガニックグロース:企業自身が収益を拡大し、成長すること)の観点では、日本の大企業の多くは優れた技術力や製造能力を有しており、半導体、エネルギー転換、ヘルスケアなどの世界的成長を取り込む上で有利な立場にあります。しかし多数の企業が事業領域を多角化しており、その多くが収益性の低いセグメントです。企業が資本効率を重視し始めると、そうした非効率部門を整理し、資本を再利用して、自社に強みがあり高成長が見込める分野に投資するようになります。そのため、当該企業の有機的成長が促進されます。また事業構造の複雑さに由来する非効率が軽減されることで、事業のどこが有望なのかが外部の投資家から見えやすくなるという効果も生まれます。当ファンドは特定分野で世界トップクラスの競争力を持つコングロマリットを多数組み入れています。
インド:一般消費財銘柄が躍進
市場別ではインドの寄与度が2番目で、中でも寄与度が最も大きかったのがMakeMyTrip(インド/消費者サービス)でした(2023年8月の月次報告書参照)。インドは経済成長率が高い上に人口がきわめて多く、若年層が厚く、教育水準が上昇していることから、消費財セクターに有望な投資対象があることは想像に難くありません。インドの消費関連企業で投資家がよく思い浮かべるものに、Hindustan Unilever社(インド)やNestle India社(インド)のような生活必需品企業があります。確かに、消費者の基本的なニーズを満たすこうした企業は、過去20年にわたって投資家に大きなリターンをもたらしてきました。しかし、当ファンドが選好するのは消費者サービスセクターの銘柄です。理由は以下2点です。
1)インドは裁量支出がこれから大幅に拡大する状況にあると考えられること。
国⺠⼀⼈当たりGDPは通常2,000米ドルが転換点と見られています。中国は2006年に、インドは2019年に初めてその転換点を超えました。
2)2023年8月の運用コメントで述べた通り、当ファンドが消費関連銘柄への投資に際し、支出額の上限が高いカテゴリー、すなわち消費者の所得が増えるにつれて⽀出額が継続的に拡⼤していくと考えられるカテゴリーを選好していること。同様に、商品よりもサービスを提供する企業を選好していること。
当ファンドが選好する消費関連カテゴリーには、娯楽、旅行、美容、利便性(所得が増えると時間を買うためにお金を使う傾向があるため)などがあります。
インドの一般消費財市場の成長余地は莫大です。ホテル業界を例にとると、組入銘柄の一つにインド最大の上場ホテル運営企業であるIndian Hotels Company(インド/消費者サービス、以下「IHCL」)の運営客室数はおよそ2.5万室(2024年10月末現在)です。もう一つの上場ホテル運営企業Lemon Tree Hotels(インド/消費者サービス)の運営客室数はおよそ1万室(2024年9月末現在)です。中国との比較でみると、大手ホテル運営企業であるH World Group社(中国)の中国国内における運営客室数はおよそ100万室(2024年9月末現在)で、その数は今も増え続けています。当ファンドは旅行や利便性といった分野に注力する消費者サービス銘柄を多数組み入れています。
今後は、インド銘柄の多くで短期的にバリュエーションが高まり、特に中小型株にその傾向が顕著であることから、状況の推移を慎重に注視しています。一方、インド銘柄が大幅なプレミアムに値すると考える理由もあります。当ファンドが調査したインド企業の多くは、同地域の中でも最も資本利益率(ROC)に対する意識の高いと考えられる企業です。多くの企業が、100年以上とは言わないまでも、何十年もの間危機を乗り越えてきた歴史を有し、長期的な視野を持った経営者によって運営されています。IHCLの主要ホテルブランドである「Taj(タージ)」は1903年に最初のホテルを開業しており、IHCLの親会社であるTata Group社(インド)は1868年に設立されています。インドは急速に成長しており、若年層が多く、国民の教育水準の高さも十分です。当ファンドは楽観的な見方を維持していますが、銘柄選定にあたっては慎重なスタンスをとっています。
韓国:韓流ブームは継続
韓国は2024年、アジアで群を抜いてパフォーマンスが軟調な市場となりました。しかし貢献度の点では、日本、インドに次いで3番目につけました。まさに「There is always a bull market somewhere」という格言を体現したことになります。
韓国といえば、たいていの方が半導体やSamsungグループを思い浮かべるでしょう。しかし当ファンドが注目するのはそこではありません。当ファンドは2024年中頃にSamsung Electronics(韓国/テクノロジー・ハードウェアおよび機器)を売却し(2024年9月の運用コメント参照)、その後の累積利益の減少を回避しました。韓国には半導体より興味深い分野が豊富にあると考えます。2024年10月の月次報告書で述べた通り、当ファンドは戦略的投資を通じ、一時はK-POP企業からかなりの利益を上げました。韓流はK-POPに留まらず、K-Beauty、K-Food、K-Dramaなど、広い裾野を有しています。
韓国で2024年最もパフォーマンスに寄与した銘柄は、Samyang Foods(韓国/食品・飲料・タバコ)という即席麺メーカーです。同社は「ブルダック炒め麺」(ブルダックは韓国語で「火のように辛い鶏」の意)という、スープのない激辛の即席麺を販売しており、そのオリジナル味はアジアで高い人気を博しています。しかし、この味はおそらくアジア以外の国の人にとっては辛すぎるでしょう。同社はその後、辛さを抑えたカルボナーラ味の麺を発売しました。これはネットユーザーがオリジナル味の麺にクリームとチーズを加えて辛さを和らげていることから着想を得たと言われています。カルボナーラ味はTikTokなどのソーシャルメディアやK-Foodの人気上昇も手伝って、世界的なヒット商品となりました。当ファンドはカルボナーラ味が世界市場の嗜好に合うと考えたこと、成長の勢いが加速している模様であることから同銘柄を組み入れました。
今後について述べると、韓国は関税リスクに晒されていることから、今一つ楽観視できない市場です。韓国はアジア諸国の中でも対米輸出がきわめて多い国で、米国の現地メーカーと競合している企業が多数に上ります。Hyundai Motor(韓国/自動車・自動車部品)を例にとると、米国における販売台数のうち、現地生産分は40%弱に過ぎず、残りは韓国からの輸入に頼っています。もう一つの注目点は韓国の「企業価値向上プログラム」で、これは東京証券取引所の改革にならって株主還元を向上させる取り組みです(2024年3月の運用コメント参照)。銀行など一部セクターでは、株主還元の改善について市場関係者と積極的にコミュニケーションを図っている様子が確かに見られました。当ファンドは韓国の銀行を組み入れておりましたが、株価が急上昇したことから既に売却し、利益を確定しています。しかし、それでも財閥を中心に、依然多数の企業が変革に抵抗しています。2024年には財閥持株会社の再編が行われましたが、その中には未だに他の株主を犠牲にして大株主に利益を供与しようとするところがありました。一方、多くの企業が「企業価値向上」計画を発表しましたが、大多数は期待外れに終わりました。その要因は、少なくとも部分的には、マクロ環境の厳しさ、あるいは中国をはじめとする他国との競争の熾烈さにあると考えています。韓国の課題はファンダメンタルズ(経済の基礎的条件)にあります。ファンダメンタルズが脆弱だと、株主還元の意義が十分に残存しません。
とはいえ、当ファンドの組入銘柄は25から35銘柄に過ぎません。つまり、韓国で必要なのは2つか3つのテーマだけで、極言すれば韓国に投資する必要はまったくないのです。しかし優れたテーマを今後も個別に探し出すことができれば、市場のパフォーマンスとは無関係にリターンを得ることができると考えます。
台湾:AI(人工知能)がすべて
韓国と同様、台湾といえば思い浮かぶのは半導体でしょう。Taiwan Semiconductor Manufacturing Companyは別にしても、台湾には設計から製造まで、半導体サプライチェーンのエコシステムが驚くほどしっかり整備されています。驚くべきは、台湾には複雑な技術をわかりやすく説明した記事やYouTube動画が無数にあることです。Advanced Micro Devices社(米国)のCEOを務めるLisa Su氏が述べている通り、「CoWoS(高性能パッケージング技術)とは何かを説明せずとも誰もが知っているのは、おそらく世界中で台湾だけ」です。そのため、当ファンドにとっては定期的に台湾を訪問し、最新トレンドを把握しておくことが重要だと考えています。
当ファンドの半導体に対する楽観的な見方は、2024年の中頃に後退に転じました。米国のハイパースケーラー(巨大なサーバーリソースを保有する企業の総称)が2025年、2026年と設備投資を増やし続けると予想されることから、AI半導体は今後も成長を続けると考えていますが、変化の速度はますます遅くなる可能性があります。AIアプリケーションの飛躍的進化を別にすれば、AI半導体に関わる好材料の多くは既に織り込み済みです。もちろんテクノロジーの進歩は速いので、必要ならいつでも見方を変えることができます。
ASEAN:見過ごされているが価値は莫大
現在の世界の投資環境は、パッシブ投資とETF(上場投資信託)によって形作られています。通常、これは大規模市場にとって有利な状況です。米国株ETFや日本株ETFを買う場合、たいていはS&P 500 ETFやTOPIX ETFといった大型株中心のETFが対象になります。大型株と中小型株のバリュエーションギャップが拡大している理由の一つはここにあると考えられます。アジアでは、日本株ETFやインド株ETFを買う人はいても、ASEAN ETFを買う人は稀でしょう。ASEANはアジアでは小規模な市場なので、目に入らないことが多いのです。
ASEANはかつて、有望と言われながら期待に応えられない市場でした。何が有望なのかというと、人口が多く、若年層が厚いために、中産階級が台頭してくるという点です。しかし投資家は10年以上にわたって、ASEANでは期待よりはるかに少ないリターンしか上げることができませんでした。2014年以降に進んだコモディティの下降サイクルと米ドル高は、ASEAN諸国の多くにとって大きな足枷となりました。さらに、コロナ禍とそれに続く物価上昇率の高止まりで大打撃を受けた国もあり、その影響はまだ消え去ったわけではありません。
一方で明るい材料は、ASEANがサプライチェーン移行による恩恵を最も受ける地域のひとつであることです。マレーシア市場は長期にわたってマイナスリターンを記録した後、2024年は半導体、データセンターなどへの投資が拡大したことで、力強い上昇を見せました。域内で産業の革新が進んでいることは、株価上昇の重要な原動力となるでしょう。さらにASEAN企業の多くが、経営が順調でありながら、かなり割安なバリュエーションで取引されています。
ASEANは見過ごされている市場なので、たとえ割安であったとしても、それを再評価する動きがすぐに起こるとは期待していません。そのため、当ファンドは配当という形で企業から直接利益を還元してもらえる銘柄に投資する必要があります。当ファンドの中では、ASEAN銘柄の配当利回りが最高水準です。
後述しますが、当ファンドは世界市場の一部、とりわけ米国市場でバリュエーションが高まっていることを憂慮しています。市場心理によって予測不可能な程にバリュエーションが乱高下し、時に非現実的なものになることがあります。そうした環境下では、ASEAN諸国のバリュエーションの低さと配当利回りの高さは最も「現実的」な選択肢のように感じられます。
中国:2024年最大の過ち
中国はおそらく、アジア地域で最も驚きに満ちた市場でした。9月後半に発表された景気刺激策の効果により、香港と中国のパフォーマンスはアジア域内の他国を上回りました。中国では金利が大幅に低下し、30年国債利回りは今や日本のそれを下回っています。低金利によって市場は安定的に収益を生み出す資産を探すようになっており、その傾向は長期的に継続する見込みです。
中国は強力な財政刺激策を継続的に行ってバランスシート不況に対処する必要があることから、経済環境は依然厳しいと言えるでしょう。バランスシート不況への対処が長期戦となるのは、日本が不況からの脱却に30年以上かかったのを見れば明らかです。景気刺激策を十分に続けなければ、経済はデフレスパイラルに逆戻りするでしょう。市場心理は今後も財政刺激策を巡るニュースに左右されることになります。もう一つの注目点としては米中関係が挙げられますが、米中関係のさらなる悪化を巡る懸念材料の多くは、既に株価に織り込まれているというのが当ファンドの見方です。
2024年における当ファンド最大の過ちは、銘柄選定を誤ったこと(株式を購入して損失を出したこと)ではなく、材料を見誤ったこと(株価の上がる株式を購入しなかったこと)です。当ファンドは「ポップトイ(箱を開封するまで何が入っているかわからない仕様の商品)」を販売しているある企業の組み入れを見送りましたが、同企業の株価は2024年に300%以上上昇しました。サンリオを参考にすれば、この企業の組み入れが必要であることは確実に理解できたはずです。実をいうと、当ファンドは同社の店舗を一部訪問し、感銘を受けていました。組み入れを見送ったのはバリュエーションがやや割高に見え、特に香港や中国市場と比較するとその傾向が顕著だと感じたからです。同社の知財は、K-POPの世界的スターを含む有名人がおもちゃを購入したこともあって、世界的な人気を博しました。同社の商品は「おもちゃ」と呼ぶよりコレクターズアイテムと呼ぶ方が正確でしょう。ガチャガチャと同様に一種の中毒性があり、全種類集めたくなるような仕掛けが施されているのです。同社をみれば明らかなように、中国には経済環境が軟調であっても生き残る方法を見つけ出す力を持った企業が複数存在します。消費財セクターはきわめて有望なセクターで、景気がよければ恩恵を受ける企業があるのはもちろんのこと、景気が悪くても成長する企業があるのも事実です。それを見極めるには、消費者の行動を注意深く観察し、財布の中身の行き先を把握するしかありません。幸いなことに、当ファンドは旅行やクイックサービス・レストランといった不況に強いカテゴリーからも恩恵を受けました。
2024年5月の運用コメントで述べた通り、中国企業の多くは経営陣が自社の株価が割安であることを認識し、自社株買いや配当の増額によってそれに対処しようとしています。当ファンドは景気低迷下にあっても耐久力を発揮し、株主利益を十分にもたらしてくれる企業を探し出したいと考えています。
結論:ボトムアップ・リサーチ
当ファンドは現在、市場の一部について慎重姿勢をとっています。ポジションの構築には警戒が必要です。前月の「BofAグローバルファンドマネージャー調査」によると、ファンドマネージャーは異例なほど株式に強気で、米国株式への配分比率は過去最高となっています。さらに、米国ではバリュエーションがピークに近づいています。両要因が同時発生していることから、2025年の世界市場は大幅に乱高下すると考えられます。
アジアにはきわめて多様な機会が揃っています。当ファンドは引き続き一般市場との相関関係がそれほど高くないと考えられる投資テーマを探ります。韓国のポートフォリオや当ファンドが組み入れを見送った中国のポップトイ企業を見れば明らかなように、市況が厳しくても高いパフォーマンスを上げられる銘柄は存在します。2024年11月の運用コメントで紹介した通り、アジアはそうした高パフォーマンス銘柄が世界で最も多い地域と考えております。強気相場はどんな時でも必ずどこかにあるもので、厳しい環境下にあっても、ボトムアップ・リサーチによってそうした強気相場を探し当てることは可能だというのが当ファンドの考えです。
最後に、2024年末時点における当ファンドの状況は以下の通りです。
今後の運⽤⽅針
当ファンドは以下3つの基準に基づいて投資を行っています。
- 逆風に強い優良企業で、競争優位性に優れていること
- 経営陣が事業運営に長け、合理的な資本配分を行っていること
- バリュエーションが割安であること
また、一般に以下のような特徴を有する企業を逆風に強い優良企業とみなしています。
- 競争優位性が確立され、業界平均を上回る収益成長を実現していること
- 独自な製品やサービス、あるいは必要不可欠な製品やサービスを提供していて、価格決定力に優れていること
- 営業レバレッジが大きく、事業の成長に伴って利益が経時的に拡大すること
- 優れたコスト構造により、厳しい状況下にあってもフリーキャッシュフロー創出力を維持できること
こうした企業にはアジア経済の成長力を取り込む力がある、あるいはアジア諸国独自の強みを生かして事業を国際展開する力があると考えられます。
当ファンドは日本を含むアジア全域から上記基準に最も合致する企業を選定し、集中的にポートフォリオを構築します。
したがって、国別配分比率はあらかじめ設定せず、各国固有のマクロリスクに注意を払いつつ、ボトムアップで銘柄選定を行ってまいります。
2024年11月の運用コメント
株式市場の状況
<⽇本の株式市場>
2024年11月、日本株式市場の代表指数であるTOPIX(配当込み)は前月末比0.51%の下落、日経平均株価は同2.23%の下落となりました。
月前半は一進一退の展開となりました。5日に実施された米大統領選挙で共和党のトランプ前大統領が優勢と伝わったことから日経平均株価は大幅に上昇し、7日には40,000円に迫る場面もありました。しかしその後、トランプ次期米大統領が政権人事で対中強硬派の人物を起用する方針が報じられ、次期政権が掲げる関税強化策への警戒感が強まったことで半導体関連株に売り圧力がかかり、株式市場は下落に転じました。一方、14日には米連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長が「利下げを急ぐ必要はない」旨の発言をしたことで円安が進行し輸出関連株が買われ、半導体関連株の反発もあって株式市場の連日の下落が一服しました。
月後半は狭いレンジで推移し、米国の金融政策の先行き不透明感や米国半導体株の動向に一喜一憂する動きが続きました。また、トランプ次期米大統領が中国、メキシコ、カナダに対する関税措置を発表したことを受け、相場は軟調な動きが続き、前月末比で下落して当月の取引を終えました。
<アジアの株式市場>
当月、⽇本を除くアジア市場に使⽤される⼀般的な指数であるMSCIアジア指数(⽇本を除く、⽶ドル建て)は、米国大統領選挙でトランプ氏が勝利し、アジア株式市場が軒並み軟調に推移したことから、前⽉末⽐3.28%下落しました。トランプ氏が勝利したことで、関税の引き上げや中国への技術移転防止策の強化に対する懸念が高まり、投資家の間で今後の混乱に対する警戒感が広がりました。
MSCI中国指数(⽶ドル建て)は4.43%の大幅下落となり、MSCI香港指数(⽶ドル建て)も3.61%下落しました。その主な要因は、トランプ氏が中国からの輸入品に60%の関税を課すという公約を掲げたことで、貿易摩擦の激化を懸念する声が高まったことにあります。さらに中国のテクノロジーセクターに対する規制の強化が予想されることも、市場の変動幅が高まる要因となっています。予期していたこととはいえ、貿易摩擦激化の公算が高まったことで、アジア各国でリスク選好度が低下しました。
世界貿易量の減少や市場のボラティリティ上昇を予想する向きが増えてきたことで、FRB(⽶国連邦準備制度理事会)が来年の利下げ幅を縮小するのではないかという憶測が広がっています。アジア諸国、特にASEAN諸国をはじめとする新興国の経済は資本流出やバリュエーションリスクの影響を受けやすいため、そうした国々ではこの事態が否定的に受け止められています。
台湾と韓国のテクノロジーセクターも、人工知能(AI)サーバーの需要が2025年下期から先細りになるとの懸念が浮上したことから、当月は重い値動きとなりました。特にSamsung Electronics社(韓国)はファウンドリー事業とメモリー事業の両方で大きな競争圧力にさらされており、両国市場が全般的に低迷する要因となっています。
ファンドの運⽤状況
当月、当ファンドのパフォーマンスは、前⽉末⽐1.22%の下落となり、参考指数であるMSCI AC Asia Index(円ベース・配当込み)の同3.28%の下落を2.06%上回りました。
セクター別では、一般消費財・サービスセクター、生活必需品セクターなどがプラスに貢献し、⼀⽅、情報技術セクター、ヘルスケアセクターなどがマイナスに影響しました。
当ファンドのパフォーマンスにプラスに寄与した銘柄は、サンリオ(一般消費財・サービス流通・小売り)、Sea(シンガポール/メディア・娯楽)、オルガノ(資本財)などでした。⼀⽅、マイナスに影響した銘柄は、LIG Nex1(韓国/資本財)、Taiwan Semiconductor Manufacturing Company(台湾/半導体・半導体製造装置)、Hanwha Aerospace(韓国/資本財)などでした。
当月前半、米国のトランプ前大統領のホワイトハウス復帰が決定しました。さらに議会でも共和党が上下両院で過半数の議席を獲得したことを受けて市場は乱高下しました。トランプ氏は政策について明確な方向性を打ち出しており、再任後に貿易と移民の制限強化、新たな減税策の導入、規制緩和が行われることは間違いないでしょう。そうした政策の中には経済に対して相反的な影響を与えるものもあるため、今後の見通しがまったく立ちません。例えば関税の引き上げはトランプ氏が望む米ドル安とは逆の効果をもたらします。同時に予期せぬ結果を招くことも少なからずあるでしょう。トランプ氏がパリ協定からの再離脱をちらつかせ、化石燃料の利用を後押しする姿勢をみせていることは、足元の事業環境への影響だけでなく、長期的に重大な気候変動リスクをもたらします。
アジア諸国おいて、トランプ氏の言葉通りに中国製品に最大60%の関税が課されれば、最も直接的な影響を受けるのは中国と考えられます。すべての商品に一律に関税が課される可能性は低いものの、中国に対する依存度に応じて様々な税率が課されるでしょう。一方、中国経済の成長鈍化は短期的にアジア全域に影を落としかねません。また、人民元の下落が予想されることから、その連鎖反応でアジア全域に通貨安が広がる可能性があります。ただし、中国の政策対応、特に国内経済を刺激するための政策次第で状況は変わるでしょう。短期的な地域経済への影響を乗り越えた先には、米中貿易戦争の再燃が「チャイナ・プラスワン」(海外拠点を中国へ集中させることによるリスクを回避し、中国以外の国・地域へも分散して投資する経営戦略)を加速させ、長期的には他のアジア諸国に恩恵をもたらすと考えられます。実際、2018年に発生した前回の米中貿易摩擦以降、ASEAN諸国は外国直接投資(FDI)の流入において明確な恩恵を受けており、この流れがさらに加速する可能性があります。
しかしながら、最終的には各国の政策対応に大きく依存するため、予測は困難です。明確な見通しが得られるまで、景況感は弱含むと見られますが、不透明感がなくなれば力強い回復が期待できると考えます。当ファンドはマクロ経済の問題を乗り越えられる強固な事業基盤を持つ銘柄へ投資するという戦略にしたがって、アジア全域に分散投資を行っています。同時に状況を慎重に注視し、可能な限り機動的に対応しています。現時点では慎重な姿勢を維持し、国内事業に軸足を置いた企業を優先的に組み入れています。
アジアにおける一連の機会
アジアにはどんな時でも投資機会が潤沢に存在していると考えています。当ファンドは株式への投資にあたり、米ドルベースで年率15%以上のリターンを目指しています(保有期間3年、5年、10年でほぼ50%、100%、300%のリターンに相当)。そこで以下の分析を実施し、各市場に5年間で100%以上のリターン(米ドルベース)を上げた銘柄がどれだけあるか確認しました。さらにもう一つ、時価総額5億米ドル以上という基準も追加しました。これはその規模以下の銘柄に投資する可能性が低いためです。
出所:各種資料を基にスパークス・アセット・マネジメント作成
*1 2024年は11月末日現在、その他の年は原則1月1日から12月31日まで
*2 アジアはパキスタンなど現時点で組み入れていない小規模市場を除外
*3 ASEAN諸国はインドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナムに限定
例えば2019年から2023年までの期間で、時価総額が5億米ドル以上、米ドルベースで100%以上のリターンを記録した銘柄は世界全体で2,186銘柄です。このうち、642銘柄は米国、313銘柄は西ヨーロッパ、868銘柄はアジアの企業でした。上表が示すとおり、少なくとも過去7年間の統計を見る限り、アジアには当ファンドが求めるリターンを生み出せる投資先が潤沢に存在していることが分かります。ボトムアップ型の投資家である当ファンドにとって重要なのは、指数の動向ではなく、上表にある銘柄を探し出して投資できるかどうかという点です。
しかし、アジアは課題の多い市場でもあり、インデックスに追従するパッシブ運用では高いリターンを得るのは難しいと考えます。また、上表からわかるように、アジアは情勢変化の激しい市場でもあります。時期によって勝ち組となる市場が異なるのです。アジアで高い利益を上げるには積極的な投資姿勢が必要となります。加えて地政学的リスクが大幅に拡大したことも、域内に勝ち組と負け組が生まれる要因となっていると考えます。
過去2年間の振り返り
当ファンドはアジア域内各国の浮沈の激しさと情勢の変化を踏まえ、2023年中に環境適応力を高めるための方針転換を行いました。それから約2年が経過しましたが、結果は今のところ満足のいくものです。以下は当ファンドが行った方針転換の概要をまとめたもので、それらの変更が持続的にポジティブな効果をもたらすと考えています。
1.カタリスト(株価上昇のきっかけ)を重視する姿勢を一段と強め、即時対応すること
2.組入銘柄のバランスと多様性をより重視すること
3.テクノロジーを重視する姿勢を一段と強めること
カタリスト
アジアはダイナミックでチャンスに満ちていますが、そのために当然ながら機会費用(選択行動において、ある選択を行うことで得られたであろう価値)が高くなります。カタリストがなく、パフォーマンス向上が期待できない銘柄を長期にわたって組み入れたままにしておくと、1)利益が得られず、2)アジアに潤沢に存在する他の投資機会を逃すことになります。期待度の低い株式を売却すれば、他の有望な銘柄に資金を投じることができます。
当社の投資哲学において、カタリストは常に重要な役割を果たしています(当社ウェブサイト「スパークスの投資哲学」参照)。当ファンドは企業の実態価値と市場価格(株価)の差、すなわちバリュー・ギャップを投資機会と捉えていますが、カタリストはそのバリュー・ギャップの解消を促す重要な要素です。カタリストとは、本質的に言えば市場の株式に対する認識が変わるきっかけに他なりません。カタリストとは一般に以下のようなものです。
- 市場予想と大幅に異なる業績の発表
- 急激な業績回復
- 株主還元や事業再編など、近年よく見られるコーポレート・ガバナンス改革の関連事項
アジア各国の激しい情勢変化に対応するには、カタリストを探ることで規律的に投資を行う必要があるというのが当ファンドの認識です。当ファンドでは、カタリストとは、今後12か月内に発生が予想される事象のうち、組入銘柄のバリュー・ギャップを大幅に縮小させるものと定義しています。ある組入銘柄のカタリストが出尽くした場合、利益を確定して他の投資機会を探ります。例えば当ファンドは2023年にセブン&アイ・ホールディングス(生活必需品流通・小売り)を売却しました。これは同社が持続的にバリュー・ギャップの大きい状態にあったにもかかわらず、米国事業の低迷が続いたため、すぐにはカタリストが発生しないと判断したためです。しかし当ファンドは2024年8月に同銘柄を買い戻しました。売却から再投資までの間に他の銘柄を組み入れ(セブン&アイ・ホールディングスを2023年10月に売却し、11月に東京海上ホールディングス(保険)を組み入れ)、好ましいパフォーマンスを上げたことを考えると、この決定は正しかったと言えるでしょう。
ただし、これは当ファンドの投資分析期間が12か月になったということではありません。上記のような手法をとる第一の理由は、当ファンドが必ず企業の実態価値を分析してから、カタリストについて検討しているという点にあります(「スパークスの投資哲学」3つの着眼点を参照)。その際、長期的な観点に立って、経営者の質、企業収益の質、市場の成長性を分析します。何よりもまず長期的な観点から基礎体力と耐久性の高い企業を探し、その上でカタリストを探るのです。第二の理由は、カタリストが単なる好業績で終わってしまうケースが多いことです。優れた企業は往々にして想定外の好業績を叩き出しますが、バリュー・ギャップがある限り、次のカタリストを期待し続けることができます。
以上を総括すると、当ファンドが長期的な有望銘柄を探ることに変わりはありませんが、カタリストに関してより厳格な要件を設定し、より短期間で利益を実現できるようにしたということです。これによりポートフォリオの運用が機動的になり、長期にわたってパフォーマンスの上がらない銘柄でポートフォリオが占められるという事態を避けることができると考えます。これは変化の激しいアジア市場でリターンを最大化し、リスクを管理する上できわめて重要なことです。
バランスと多様性を重視したポートフォリオ構成
かつて当ファンドのポートフォリオの構成銘柄は主として高成長銘柄(グロース株)だったため、2022年に米国が利上げに踏み切ったことでバリュエーションが切り下がり、大幅なアンダーパフォームを記録しました。そのため当ファンドは世界情勢の変化を踏まえ、よりバランスの取れたポートフォリオが必要だと考え、多数のバリュー株、とりわけ日本銘柄の組み入れを開始しました。しかしながら、これは大きな戦略転換ではありません。当ファンドはどんな時でも必ず、基礎体力がしっかりした質の高い企業に注目しています。しかし質が高いにもかかわらず、様々な要因のために成長率がそれほど高くないために「バリュー株」というレッテルを張られた企業が多数存在します。
バリュー株への投資は一般的に難しいものです。基本的なリターンの計算式を考えてみてください。リターン=配当利回り+1株当たり利益(EPS)の伸び+株価収益率(PER)の増減です(銘柄の種類やバリュエーション(企業の利益・資産などの企業価値評価のこと)指標によっては、リターン=配当利回り+1株当たり純資産(BPS)の伸び+株価純資産倍率(PBR)の増減になることがあります。例えば総合商社の場合、時間の経過に伴うBPSの増減を調べます)。バリュー株は本質的にEPSやBPSの成長率が低いため、投資家がリターンを上げるにはバリュエーションの上昇か配当利回りの高さに頼らざるを得ません。バリュエーションは理由もなく突然上昇することはないので、一般的に前の2つの要因、すなわち配当利回りとEPSの伸びに対する期待の変化と連動することになります。したがって、バリュー株に投資するには、株価の再評価につながるカタリストと高い配当利回りのうち、いずれかが必要です。どちらもなければ、典型的な「バリュートラップ」(割安のわな)銘柄でしかありません。
2023年以降、ある構造的変化がカタリストとして作用し始めたことから、当ファンドは質の高いバリュー株をより安心して保有できるようになりました。その変化の一つに日本のコーポレート・ガバナンス改革があります。詳細は省きますが、その一般的成果として、多くの企業が1)事業の再編、2)株主還元の拡大と資本効率の向上に着手しています。そうした企業のEPS成長率は本当の意味での高成長企業(MakeMyTrip(インド/消費者サービス)、サンリオ(一般消費財・サービス流通・小売り)、Sea(シンガポール/メディア・娯楽)など)には及びませんが、配当利回りが高く、EPSの伸びも多少高めであることから、リターンが十分に見込めると判断し、当ファンドは質の高いバリュー株の組み入れを開始しました。2024年3月(韓国の企業価値向上プログラム)と2024年5月(中国の企業価値向上施策)の月次報告書でも取り上げたように、アジアの他の国々も日本に追随する形で企業改革を進めています。こうした一連の変革によって、質の高いバリュー株を組み入れる機会が一段と豊富になりました。
実際、日本株式市場がこの2年間上昇しているのはバリュー株の上昇が大きく寄与しています。TOPIXバリュー指数は2022年末から2024年11月末にかけて50.9%上昇し、TOPIXグロース指数の32.4%の上昇を大幅に上回っています。
当ファンドのポートフォリオは現在、質の高いグロース株と質の高いバリュー株で構成されています。当ファンドはバランスと多様性を重視してポートフォリオを構成することで、インフレや金利といったマクロ要因の変化に耐えられるようになったと考えています。
テクノロジー
過去2年の間に幾度か述べた通り、テクノロジーは当ファンドにとって欠かせない投資テーマであり、その重要性は今後ますます高まっていくと考えます。重要なのは、テクノロジーセクターには当ファンドの品質基準に適合する企業が多いということです(例えば2024年9月の月次報告書にあるGudeng Precision Industrial(半導体・半導体製造装置)の項を参照)。
当ファンドは2022年後半からテクノロジーセクターを注視する姿勢を大幅に強めていますが、これは1)その頃がサイクルの底にあると考えたこと(2022年10月の月次報告書にあるSamsung Electronicsの項を参照)、2)テクノロジーに対する調査体制を強化するという基本方針を定めたことによります。
結論
当ファンドが2年前に実施した投資方針の変更は、今のところ満足のいく結果を得ていると考えています。アジア市場にはチャンスが潤沢に存在しますが、それを物にするには足元の逆境を乗り切る必要があると考えます。当ファンドが行った投資方針の変更は、これから諸課題を解決し、良好なリターンを生み出していくための柔軟性と耐久力を与えてくれることでしょう。高いリターンを上げることができれば、特に米国株式やグローバル株式(MSCI ACWI Indexに占める米国の割合が65%程度であることを考えると、やはり米国株式が中心)への投資から分散を図りたい投資家にとって、当ファンドは価値ある選択肢となれると考えています。
来月は年末になるため、2024年の当ファンドと市場の総括する予定です。
今後の運⽤⽅針
当ファンドは以下3つの基準に基づいて投資を行っています。
- 逆風に強い優良企業で、競争優位性に優れていること
- 経営陣が事業運営に長け、合理的な資本配分を行っていること
- バリュエーションが割安であること
また、一般に以下のような特徴を有する企業を逆風に強い優良企業とみなしています。
- 競争優位性が確立され、業界平均を上回る収益成長を実現していること
- 独自な製品やサービス、あるいは必要不可欠な製品やサービスを提供していて、価格決定力に優れていること
- 営業レバレッジが大きく、事業の成長に伴って利益が経時的に拡大すること
- 優れたコスト構造により、厳しい状況下にあってもフリーキャッシュフロー創出力を維持できること
こうした企業にはアジア経済の成長力を取り込む力がある、あるいはアジア諸国独自の強みを生かして事業を国際展開する力があると考えられます。
当ファンドは日本を含むアジア全域から上記基準に最も合致する企業を選定し、集中的にポートフォリオを構築します。
したがって、国別配分比率はあらかじめ設定せず、各国固有のマクロリスクに注意を払いつつ、ボトムアップで銘柄選定を行ってまいります。
2024年10月の運用コメント
株式市場の状況
<⽇本の株式市場>
2024年10月、日本株式市場の代表指数であるTOPIX(配当込み)は前月末比1.88%の上昇、日経平均株価は同3.06%の上昇となりました。
月前半は、全米企業エコノミスト協会の年次総会に登壇したパウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長が今後の利下げについて「急ぐ必要はない」と強調したことや、米国雇用統計が市場予想を大幅に上回ったこと等から利下げ観測が後退したこと、石破茂首相から日銀の早期の追加利上げに否定的な見解が示されたこと等からドル高円安が進行しました。また、中東情勢の悪化により株価が一時的に下落する局面もありましたが、前述のように円安の進行や米国経済の底堅さ、石破政権が岸田前政権の経済政策を継承するとの方針が確認されたこと等から株式市場は上昇いたしました。
月半ばから後半にかけては、オランダの半導体製造装置大手ASML Holding社の決算発表で2025年12月期の業績見通しが引き下げられたことで半導体関連株に売りが広がったことや、日米長期金利の上昇基調の継続が意識されたこと、27日投開票の衆議院選挙で与党自民・公明両党が過半数議席の確保が微妙な状況と報じられたこと等から株式市場は軟調な推移となりました。
衆議院選挙では連立与党が2009年以来15年ぶりに過半数を割り込む結果となり、今後の政権の枠組みは少数与党が政策や法案ごとに野党に協力を求める「パーシャル(部分)連合」になるのではないかという見方が強まりました。財政拡張的な政策を掲げる野党との協力により景気刺激的な政策が実行される可能性が意識されたことや、リスクイベント通過に伴う先物の買戻し等から株式市場は衆議院選挙を境に一転し、前月末比で上昇して当月の取引を終えました。
<アジアの株式市場>
当月、⽇本を除くアジア市場に使⽤される⼀般的な指数であるMSCIアジア(⽇本を除く、⽶ドル建て)指数は、前月末比4.46%下落しました。台湾市場はAI(人工知能)需要が予想を上回り、台湾半導体企業の株価が上昇したことから堅調に推移しました。しかし、米国経済が好調であることや、米国大統領選挙の先行きが見通せないことなどから投資家は新興国市場への投資を控え、アジア株式市場の多くで海外資金が流出しました。
中国政府は追加刺激策を示唆して景気の下支えを図りましたが、具体的な内容が明らかにされなかったため、前月の急騰から当月は下落基調に転じました。大統領選挙後に米国の対中輸出(特にバイオテクノロジーやハイテク分野)規制が強化されるのではないかという懸念も投資家のリスク選好度の低下要因となり、選挙が終わるまで様子見の姿勢が広がりました。
インド市場のパフォーマンスは年初から好調を維持してきましたが、当月は一服感をみせました。その一因は、都市部における消費低迷のあおりで消費関連企業の業績が予想を下回ったことにあります。ASEAN市場も投資家の利益確定によって資本が流出し、総じて軟調に推移しました。
ファンドの運⽤状況
当月、当ファンドのパフォーマンスは、前⽉末⽐2.82%の上昇となり、参考指数であるMSCI AC Asia Index(円ベース・配当込み)の同1.95%の上昇を0.87%上回りました。
セクター別では、資本財・サービスセクター、情報技術セクターなどがプラスに貢献し、⼀⽅、ヘルスケアセクターがマイナスに影響しました。
当ファンドのパフォーマンスにプラスに寄与した銘柄は、LIG Nex1(韓国/資本財)、Taiwan Semiconductor Manufacturing Company(台湾/半導体・半導体製造装置)、MakeMyTrip(インド/消費者サービス)などでした。⼀⽅、マイナスに影響した銘柄は、AIA Group(香港/保険)、ベイカレント(商業・専門サービス)、ICICI Lombard General Insurance(インド/保険)などでした。
前月の月次報告書で当月は香港の状況について取り上げる可能性をお伝えしましたが、状況が流動的であることから、香港と中国に関する報告は延期させていただきます。中国に対するネガティブな見方は総体的にみると多少後退しましたが、経済面に関しても地政学的リスクと同様に大きな課題が残されているという見方に変わりはありません。当ファンドの目標は適正な絶対リターンを長期的に上げることにあり、中国の組入比率を相対的に低く保つことが妥当であると考えます。香港・中国銘柄の組入比率は現在14%程度で、当ファンドの参考指数より低く抑えています。
50歳の小さな女のコ
2024年11月1日はサンリオのメインキャラクター、ハローキティの50回目の誕生日です。2024年2月の月次報告書でサンリオについて取り上げました。それ以来、年間を通じて当ファンドのパフォーマンスにプラスに貢献した銘柄のひとつとなりました。当月はハローキティ誕生50周年を記念して、同銘柄についてお伝えしたいと思います。
2月の月次報告書では、サンリオが魅力的な投資先であると考える理由を以下の通り説明しました。
- ユニークで時代を超越したIP(知的財産)ポートフォリオを持つ素晴らしいビジネスである
- 新しい経営陣の経営の⼤転換により、企業文化を良い方向に変えた
- デジタル社会において、IPは単なる物理的な商品から、常に消費者と関わりあうことができるコンテンツへと変化している
- キャラクターの多様化が、より安定した持続可能な成長を促進する
サンリオは2024年5月、新たな中期経営計画(MTP)を発表しました。MTPで、同社は上記3と4の点について言及しています。過去のサンリオについて、同社の激しいボラティリティの歴史を1)海外でのハローキティ構成比の高さ、2)「グッズ中心」という価値提供の狭さ、と総括しています。同社はキャラクター多様化の進捗状況を公表しており、2014年3月期は海外売上高の93%をハローキティが占めていましたが、2024年3月期は、ハローキティ、ハローキティとのコラボ、その他のキャラクターがそれぞれ50%、19%、31%となりました。
新たなMTPでサンリオは、今後数年間に向けて、成長戦略として「3本の矢」を掲げています。
- 外的要因に依拠したブームに左右されることからの脱却を目指し、“ブランディングを変える”
- ブームを一過性で終わらせない仕組みがないことから脱却するため、“組織基盤を強固にする”
- 価値提供の狭さから脱却するため、「IPポートフォリオ拡充」・「グッズ活用以外の価値創造」の2つに投資する
同社の成長戦略は、地域やキャラクター、顧客との関わり方を広げる、という当ファンドの望む方向に向かっていると考えます。特に「第3の矢」は、ゲーム、デジタル、リアル体験などを通じて、顧客とのタッチポイントを強化する計画です。同社の豊富な知的財産ポートフォリオは、適切なデジタル戦略の助けを借りて、これらすべての面で成果を上げる強さを備えていると見ています。
サンリオは今後3年間で、グローバルコンテンツ開発、ゲーム開発、デジタルエンターテインメントなどに300億円の投資を計画しています。また、同社はM&Aや資本提携等の機会に備えて500億円を確保しています。デジタルゲームやアニメへの進出についてはより多くの投資を必要とするため、同社の投資規律が失われるのではないかという懸念が株式市場から出ていますが、当ファンドは経営陣と面談を行い、同社がこのような懸念を十分に認識していることを確認しました。当ファンドは、同社の大半の取り組みがパートナーによってサポートされているため、同社が大きな投資をする必要はないと考えています。例えば、Alibaba Group Holding社(中国)傘下の動画共有サービス「Youku」と提携してアニメを制作していることなどが挙げられます。一方、アニメはサンリオが取り戻すべき重要な機会でもあります。2000年代には、サンリオには「おねがいマイメロディ」のような人気アニメがありました。「おねがいマイメロディ」の登場キャラクターであるクロミの根強い人気は、彼女のユニークな個性(例えば、乱暴者に見えるけれど、実はとっても乙女チック!?イケメンがだ〜い好き。)が貢献していると考えます。よくできたアニメシリーズは、キャラクターを宣伝するのに非常に効果的なツールであり、サンリオにとって実績のある流れです。しかし、サンリオのキャラクターにはシリアスなストーリーがないことを考えると、映画に向いているのかどうかということについては懐疑的です。一方、当ファンドの保有銘柄でもあるバンダイナムコホールディングス(耐久消費財・アパレル)のガンダムシリーズは、ロボットを「モビルスーツ」という「兵器」として扱ったリアルな戦争描写や緻密な科学考証、複雑に織り成す深い人間ドラマがとても深く、映画に向いています。
同社はMTPの中で、成長戦略のほかにも財務力と株主還元にも触れています。1つの重要な目標は、事業のボラティリティを低減し、どんなに厳しい環境下でもROE(株主資本利益率)15%以上を維持することです。また、サンリオは配当性向30%以上を目標に掲げており、余剰があれば株主還元を上乗せする可能性もあります。事業のボラティリティを低減させるというコミットメントは当ファンドが期待した方向に進んでいますが、配当性向が30%というのは、キャッシュフローを生み出す事業であることを考えると十分とは言えないため、当ファンドは同社に提言を続けていく予定です。
全体として、同社のMTPは様々な面で正しい方向に進んでいると考えます。同社はこれまで当ファンドに素晴らしい結果をもたらしてくれましたが、問題は株価が上場来高値を更新している現在でも魅力的な投資先であるかどうか、ということです。まず、同社はMTPで2027年3月期までに営業利益400億円以上と目標を掲げています。しかし、2025年3月期第2四半期決算で、同社は2025年3月期の営業利益の見通しをすでに410億円に上方修正しています。また同社は、年間計画を提示する際に保守的な数値を出す傾向があることから、営業利益410億円を超えることができると当ファンドでは考えています。現在の時価総額は約1兆円で、予想PERは30倍を超える水準となります。これは見た目には安くはありませんが、当ファンドは多くの優れた企業がグローバルに拡大する際にこうした状況を見てきました。ファーストリテイリング社やアシックス社を例にとれば、株価は決して安くはありませんが、好業績を背景に堅調に推移しています。株式市場はこれらの本当に優れた企業の可能性を一貫して過小評価してきました。当ファンドはサンリオの可能性について次のように考えています。
- サンリオの収益はすべて現金であり、設備投資はほとんど必要ありません。同時に、営業レバレッジは非常に大きくなっています。
- サンリオの世界的なポテンシャルは、ファーストリテイリング社やアシックス社に勝るとも劣らないと考えます。市場シェアは世界的に見てもまだ非常に小さいのです。
- 世界最大の知財商品市場である米国におけるサンリオのビジネスは、依然としてハローキティに大きく依存していると見ています。しかし、毎年行われている同社キャラクターの投票イベント「サンリオキャラクター大賞」のランキングが示すように、シナモロールやポムポムプリンなどのキャラクターの人気が高く、マネタイズで追いつく余地があると考えます。
- 更なる伸びしろとして、サンリオが長年変更していないロイヤリティ料率を引き上げる余地があると考えます。ロイヤリティの引き上げによる増収分はすべて会社の利益にそのまま反映されるため、営業レバレッジは非常に大きくなります。
短期的には、ハローキティの50周年が、来年の成長にとって高いハードルとなる懸念があります。一方で、他のキャラクターたちも来年アニバーサリーを迎えます(リトルツインスターズ(キキ&ララ)が50周年、マイメロディが50周年、クロミが20周年)。今こそ同社の多角化に向けた取り組みが試される時です。
K-POP - スローダウンの必要性
2024年2月の月次報告書では、防弾少年団(BTS)、NewJeans、LE SSERAFIMなどのグループを運営し、4月に若干の損失で売却したHYBE社(韓国)についても取り上げました。2023年に売却したJYP Entertainment社(韓国)とSM ENTERTAINMENT社(韓国)を加えると、当ファンドはK-POP関連企業から全体的に多くのリターンを得てきましたが、現在そのポジションは解消しています。
HYBE社から撤退したきっかけは、NewJeansを管理している子会社ADOR社とHYBE社との対立です。当ファンドはこのニュースが入ったと同時に「売却」ボタンを押しました。取引時間内にこのニュースを見て即売却を決断したのは衝動的だったようにも思われるかもしれませんが、株価はその日の水準まで回復することはありませんでした。当ファンドは、通常25〜35銘柄の非常に集中したポートフォリオで運用しているため、リソースと時間を集中させ、保有銘柄について弱みも含めて深く理解することができます。これにより、当ファンドは株価が不安点な時期にも保有を継続する自信を持つことができ、さらに本当に悪いことが起こったときに迅速に行動することができます。なぜなら、常に状況を把握していれば結論に達するのに何日もかける必要がないからです。
NewJeansに何が起こったのでしょうか?HYBE社に関する当ファンドの初期の投資仮説は、同社が「マルチレーベルシステム」に進化した、ということです。マルチレーベルシステムとは、本社が才能のあるプロデューサーにリソースを提供し、プロデューサーが自身のレーベルを立ち上げ、独自の練習生を募集し、K-POPアイドルとしてデビューさせる、という仕組みです。プロデューサーには自主性が与えられ、本社はマーケティング支援などのリソースを提供します。これにより、HYBE社はBTSへの依存度を下げ、多角的で持続可能なビジネスへと進化することができます。NewJeansはまさにマルチレーベルシステムの成功例です。NewJeansのプロデューサーであるミン・ヒジン氏は、SM ENTERTAINMENT社のクリエイティブ・ディレクターとして活躍し、Red VelvetやSHINeeといったグループのブランディング・コンセプトを数多く成功させた人物です。ミン・ヒジン氏は2019年にCBO(Chief Branding Officer)としてHYBE社に移籍、2021年には翌年のNewJeansのデビューに備え、新しい子会社ADOR社を設立するための資本を与えられました。新鮮で差別化されたスタイルで、NewJeansは瞬く間にK-POPガールズグループのトップに躍り出ました。その後、2024年4月22日、HYBE社はADOR社の経営権を掌握しようとした疑いで同氏に対する内部監査を開始し、ADOR社のCEOとしての辞任を公に要求しました。取引時間中には正確な理由はわかっていませんでしたが、マルチレーベルシステムに深刻な亀裂が入り、すでに投資仮説が崩れたとの結論に至り、当ファンドは速やかに同銘柄を売却しました。これに対し、ミン・ヒジン氏は後に記者会見を開き、別のHYBE社のレーベル、BELIFT LAB社から今年デビューしたガールズグループ、ILLITによる盗作疑惑について苦言を呈しました。ILLITがデビューしたとき、当ファンドはNewJeansとILLITの類似点に気づいていました。当ファンドは年初にHYBE社と面談の機会がありましたが、その場で新人アーティストのカニバリゼーション(自社やグループ内の商品・サービス等が互いに競合して、顧客や売り上げを侵食しあう)問題について話し合いました。ここ数年で大きな成功を収めたK-POP関連各社は、成長を追い求めるために新グループを積極的に展開するようになり、大手各社は毎年新しいグループを送り出しています。当ファンドは、熾烈な競争を引き起こすことなく、市場の成長がこれほど多くのアーティストの供給を支えることができるのか疑問に思っていました。JYP Entertainment社の若手ガールズグループ、ITZYとNMIXXの人気が低迷しているのは熾烈な競争の結果だと見ていました。ADOR社とHYBE社の争いは、当ファンドが懸念していたことの現れに過ぎません。マルチレーベルシステムの初期の仮説はもはや成立せず、内部競争にしかならないからです。
K-POPの歴史は常に周期的です。2010年代初頭、少女時代、EXO、BIGBANGなどのグループは、アジアで強力なファン層を開拓していました。その後、一時的な閑散期を経て、2010年代後半にはTWICEやBTSといった新しいグループによってアジアでのK-POP人気がさらに高まりました。2019年のBIGBANGのスキャンダルによってK-POPのイメージは幾分損なわれましたが、コロナ禍中はBTSやBLACKPINKのようなグループに支えられ、K-POP業界は再び盛り上がりを見せて世界的な存在となりました。K-POPは今後も存続すると思われますが、K-POP関連各社は新しいグループを頻繁に出すのではなく、ペースを落としてクオリティに集中する必要があると考えます。このダウンサイクルは長いものになるとみています。音楽、ゲーム、ドラマ、リアリティショーなど、韓国がエンターテインメントビジネスにおいて多くの創造性を持っていることは世界的に認められています。創造的な精神が残っている限り、新たな投資機会はあるでしょう。
皮肉なことに、2024年2月の月次報告書では、人間の有名人への投資がハローキティのようなキャラクターほど優れていない理由を説明しました。人的リスクは常に存在し、ついにHYBE社で現実のものとなりました。年齢を重ねることなく、仕事を選ばず、賃上げを求めないセレブリティを抱えるサンリオは稀有な存在であるという確信を更に強めました。
エンターテインメントビジネスは、人々の幸福への要求に応えるものです。人々は幸せになりたいし、そのためには喜んでお金を払います。アジアは全体的に人口が多く、豊かになりつつあり、エンターテイメントに対する需要も増えていくでしょう。当ファンドでは、エンターテインメントはアジアにおける持続性の高い投資テーマだと考えており、この分野での調査を継続していきます。
今後の運⽤⽅針
当ファンドは以下3つの基準に基づいて投資を行っています。
- 逆風に強い優良企業で、競争優位性に優れていること
- 経営陣が事業運営に長け、合理的な資本配分を行っていること
- バリュエーションが割安であること
また、一般に以下のような特徴を有する企業を逆風に強い優良企業とみなしています。
- 競争優位性が確立され、業界平均を上回る収益成長を実現していること
- 独自な製品やサービス、あるいは必要不可欠な製品やサービスを提供していて、価格決定力に優れていること
- 営業レバレッジが大きく、事業の成長に伴って利益が経時的に拡大すること
- 優れたコスト構造により、厳しい状況下にあってもフリーキャッシュフロー創出力を維持できること
こうした企業にはアジア経済の成長力を取り込む力がある、あるいはアジア諸国独自の強みを生かして事業を国際展開する力があると考えられます。
当ファンドは日本を含むアジア全域から上記基準に最も合致する企業を選定し、集中的にポートフォリオを構築します。
したがって、国別配分比率はあらかじめ設定せず、各国固有のマクロリスクに注意を払いつつ、ボトムアップで銘柄選定を行ってまいります。
2024年9月の運用コメント
株式市場の状況
<⽇本の株式市場>
2024年9月、日本株式市場の代表指数であるTOPIX(配当込み)は前月末比1.53%の下落、日経平均株価は同1.88%の下落となりました。
月前半は米国のISM製造業景況感指数や雇用統計が予想を下回ったことで、米国経済の減速懸念が高まり市場心理に影響を与えました。さらに米連邦公開市場委員会(FOMC)による利下げ期待と日銀の利上げ期待の高まりにより、月半ばにかけて円高が進行しました。このような状況の中、株式市場は一時的に下落した後、反発が見られたものの上値は重く、投資家は慎重な姿勢を維持しました。
月後半はFOMCが0.5%の利下げを決定した後、パウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長が緩和を急がない姿勢を示したことや、日銀が金融政策を現状維持したことから円高が一服し、輸出関連株や半導体関連株の買い戻しが進みました。また、自民党総裁選挙で高市早苗氏が当選し、金融緩和が再開されるとの見通しが高まったことで日経平均株価は26日から27日にかけて大きく上昇しました。しかし、最終的には石破茂氏が勝利し、経済政策への警戒感が高まったことなどから30日の日本株式市場は全面安の展開となり、前月末比で下落して当月の取引を終えました。
<アジアの株式市場>
当月、⽇本を除くアジア市場に使⽤される⼀般的な指数であるMSCIアジア(⽇本を除く、⽶ドル建て)指数は、米国が利下げに踏み切ったことや、中国政府が不動産市場の下支えと国内消費の活性化を狙って景気刺激策を導入したことを受け、前月末比8.47%上昇しました。米中両国の施策が好感されてMSCI中国指数(⽶ドル建て)は前⽉末⽐23.90%、MSCI香港指数(⽶ドル建て)は同17.08%上昇し、前月までの軟調なパフォーマンスが一転しました。
中国では、預金準備率(RRR)と金利の引き下げ、住宅ローンの頭金比率の引き下げ、銀行に対する流動性供給による企業向け貸し出しの促進などの追加刺激策が発表されました。また、今後は低所得者層の支援を図るため、さらなる財政刺激策が導入される見込みです。
台湾市場と韓国市場では、このところテクノロジーセクターが堅調に推移していましたが、その後上昇が一服しました。一方、ASEAN市場はタイ、シンガポール、フィリピンを中心に、堅調に推移しました。
ファンドの運⽤状況
当⽉、当ファンドのパフォーマンスは前⽉末⽐1.77%の上昇、参考指数のMSCI AC Asia Index(円ベース・配当込み)は同3.31%の上昇となりました。
当⽉パフォーマンスにプラスに貢献した銘柄は、Tencent Holdings(中国/メディア・娯楽)、Taiwan Semiconductor Manufacturing Company(台湾/半導体・半導体製造装置)、三菱重工業(資本財)などでした。一方、ASPEED Technology(台湾/半導体・半導体製造装置)、オリックス(金融サービス)、Lemon Tree Hotels(インド/消費者サービス)などがマイナスに影響しました。
台湾訪問
今回の月次報告書では、前月の台湾出張について取り上げたいと思います。
台湾の輸出において、半導体関連が全体の30%以上を占めています。つまり半導体が好調であれば、台湾経済は総じて堅調であると言えます。台湾の2024年第2四半期の実質GDP成長率(速報値)は前年同期比5.06%増となりました。株式市場も堅調に推移しており、当月末時点のMSCI台湾指数(米ドル換算)は年初来で約31%の上昇と、2023年と同程度の上昇となっています。このように経済全般と株式市場が堅調であることを受け、住宅市場もきわめて好調に推移しています。
当ファンドは7月に半導体に対する楽観的な見方を多少改めましたが、それでも長期的には依然として重要なセクターであると考え、引き続き投資を続けています。今回の出張ではデータセンター用チップの設計を手がけるチップ設計会社、データセンターの液冷ソリューション事業者、半導体製造時に使用する消耗品の製造会社、スマートフォン部品メーカー、PCメーカーなど、複数のテクノロジー企業を訪問しました。全体的に、データセンター関連企業はきわめて好調ですが、スマートフォンやPCなど他のセグメントは依然低調です。世界経済の減速が鮮明になってきていることから、ますます高価になりつつあるスマートフォンやPCを消費者に購入してもらう上で、エッジAI(ネットワークの端末機器(エッジデバイス)上でAI(人工知能)処理を実⾏するシステムの総称)の搭載だけでは訴求力が不十分です。したがって、エッジAIのトレンド化はまだ先になるかもしれません。
小規模でも将来性の高い企業を探索
今回の出張で、今後も調査価値があると判断した企業が多数見つかりました。当ファンドが組み入れているのは一般に中型株と大型株です。なぜなら、当ファンドが最も重要視しているのが事業の健全性であり、企業規模が大きいほど事業の健全性が高い傾向にあるからです。しかし、規模が小さくても健全性が高く、将来性が期待できる企業がないわけではありません。そうした企業に出会った場合、当ファンドはもちろん躊躇なく投資対象に加えます。例えばGudeng Precision Industrial(台湾/半導体・半導体製造装置)というかなり小規模(時価総額20億米ドル未満)な企業を、当ファンドは以前から調査対象としていましたが、今回の経営陣と面談を通じ新規投資を決定いたしました。
当ファンドと他のテクノロジーセクターを扱う投資家との大きな違いは、特定製品の景気サイクルではなく、事業の質を重視している点だと考えています(ただし前者でもうまくいけば高収益の確保が可能です)。前月の月次報告書でお伝えした通り、このところマーケット・ニュートラル戦略をとるヘッジファンドで半導体セクターに投資するものが増えているため、この違いがますます際立っていくと考えます。ビジネスモデルが弱ければ、たとえ取り扱い製品の景気サイクルが上昇期にあっても、当ファンドは殆どの場合、その銘柄を組み入れません。その好例がiPhoneの部品サプライヤーです。Apple社(米国)は強大な交渉力を持ち、これまで容赦なくサプライヤーに圧力を加えてきました。そのため、Apple社の部品サプライヤーはたいてい事業の質がかなり劣っています。成長率の高い企業は多くありますが、競合他社の攻勢を防ぐ手立てのないままで成長を続けることはできないと当ファンドは考えます。そうした企業は、いずれ他社が参入すると収益性が低下する可能性があるためです。したがって当ファンドが魅力を感じるのは、強力な参入障壁を備えていて、かつ成長力の高い企業です。
Gudeng Precision Industrial社はフォトマスク(電子部品の製造工程で使用されるパターン原版をガラスや石英等に形成した透明な板。電子部品の回路パターン等を被転写対象に転写する際の原版となるもの)やシリコンウエハーの搬送に使用する専用キャリアを専門的に手がけています。先端半導体ではトランジスタ1個の大きさが数ナノメートル(nm)しかなく、インフルエンザウイルスの約100nmよりさらに微小です。先端半導体は人類がこれまで作り上げた製品の中でも複雑性の高さが突出していて、あらゆる事象をナノメートル単位で測定するため、この上なく繊細で、欠陥が発生しやすいという特徴があります。フォトマスクを搬送する容器でさえ、環境中の微粒子によるフォトマスクの損傷の防止やフォトマスクへの電荷蓄積による静電気放電障害を防止といった対策が必要で、専門化が進んでいます。これらの要件を満たすことがあまりに困難なため、同社はEUV(極端紫外線)フォトマスク搬送用EUVポッドで市場シェアの約85%を占めています。同社はさらに独自の精密加工技術を活用し、航空宇宙用材料分野やデータセンター冷却ソリューション分野にも進出しています。以下の点を鑑みれば、同社は強い参入障壁と成長力を兼備するという当ファンドの投資基準に合致した企業だと言えるでしょう。
- 同社はフォトマスクとウェハーキャリア分野で競争力に優れ、高い市場シェアを確保している。主な競争先は米国企業だが、同社は台湾企業なので、世界最大のEUVリソグラフィ装置ユーザーであるTaiwan Semiconductor Manufacturing Company社と距離的に近い。
- 同社は優位性を生かし高い利益率を得ている(粗利益率は約46%と、製造業としてはかなりの高水準)。
- 先端半導体製造においてEUVプロセスの採用が拡大しているため、同社は成長力が強い。
- 同社は新たな成長の原動力を確立しつつある。同社の航空宇宙用部品は既に世界的な大手航空宇宙用材料メーカー数社の審査を通過し、急成長を遂げている。同セグメントは参入障壁が高い。
- 同社は台湾の半導体サプライチェーンにおいて、ニッチだが有望な投資先を探している。そうした投資先企業の製品は同社製品と組み合わせる形で顧客に販売されているため、シナジー効果が発生する。投資先企業が単独販売に成功したとしても、同社は投資自体から十分なリターンを得ることができる。
当ファンドは以前から同社が主力事業のフォトマスクとウェハーキャリアで優位性があることを認識しておりましたが、今回経営陣と面談を通じて、歴史の浅い航空宇宙事業の現状と今後の資本配分計画について知り、同社への確信度が得られたため、新規投資を決定しました。
投資先の企業調査以外の成果
台湾は半導体製造の最前線に位置していることから、バリューチェーンに対してどのような影響力を有しているのか見ておきたいと思います。例えば、今回の出張ではCPO(Co-Packaged Optics、光学部品と半導体チップを同じパッケージ内に組み込み、電子に変わって光をデータ送受信に使うことで、データセンターや高性能コンピューティング環境などでのデータ転送速度の向上と、電力消費の削減に対応する技術)に関する知識を深めることができました。データセンターでは、着脱可能な光トランシーバーをサーバーに接続してデータを出し入れします。信号は光ファイバーを通して外部から光トランシーバーに送られ、光トランシーバーは光信号を電気信号に変換します。その後、電気信号は銅線を通してチップに伝送されます。銅線は信号の伝送効率があまり高くなく、特に光ファイバーと比較するとその差が歴然としています。CPOというのは、光学部品をスイッチチップ上に直接組み込むことで、チップと光学部品の物理的な距離を短縮する手法です。そうすることで、銅線を短縮し、帯域幅を高め、消費電力を抑えて性能を大幅に向上できるようになります。この手法は考え方としては新しいものではありませんが、克服すべき課題がまだまだ残されています。しかし当ファンドは今回の企業調査を通じて、2025年末から2026年にかけてCPOの供給量が拡大する可能性のあることが確認できました。CPOの採用が進むことによって、着脱可能な光トランシーバーモジュールが不要になっていくと考えられます。当ファンドが調査を続けている日本企業の中には光トランシーバーの部品を製造している企業があることから、CPOの実用化が実現した場合の影響を今後検討する必要があると考えています。
今回はハイテク企業以外にも、スキンケア製品メーカー、製薬CDMO(医薬品の開発・製造受託機関)、自転車メーカーなど、他セクターの企業を多数訪問しました。その結果、台湾市場で有望なのはハイテク企業だけではないという考えがますます強くなりました。ただし、その多くはニッチ銘柄で、台湾への投資を検討していてもほぼ検討対象に入ってこないような企業です。だからこそ、現地を訪問してそうした企業を探し出す必要があるのです。
いい思い出、ただし過去の話
テクノロジー銘柄でもうひとつ触れておきたいのは、当ファンドが保有していたメモリー企業のSamsung Electronics社(韓国)とSK hynix社(韓国)です。当ファンドは半導体に対する楽観的な見方を改めた後、両銘柄を売却しました。2022年10月の月次報告書でSamsung Electronics社の組み入れについて述べましたが、それはメモリーのサイクルが底を打つと確信していたからです。それから現在まで、当ファンドはSamsung Electronics社かSK hynix社(あるいは両方)の保有を継続していました。両銘柄を売却した理由はいくつかありますが、具体的には以下のようなものです。
- メモリーは全般的にコモディティ化した製品で、メーカーは資本集約度が高いという特徴があることや、大手3社(Samsung Electronics社、SK hynix社、Micron Technology社(米国))間の差は極めて狭く、競争が熾烈であること等の特徴があることから、メモリー事業のビジネスモデルはそれほど優れているとは言えません。2022年は、奇しくも投資家心理が異例の落ち込みをみせていたことから、メモリー企業を組み入れるには絶好の機会だと判断しました。当ファンドはよほどの理由がなければ、優れたビジネスモデルと競争上の優位性を備えた企業を重点的に組み込みたいと考えています。メモリー企業を完全に排除するわけではありませんが、事業の質という観点から見ると、優先度はかなり低い位置に置かざるを得ません。半導体業界にはより優れたビジネスモデルと競争力を備えた企業が他にも多数存在していると考えます。したがって、景気回復局面が完全に過ぎ去ったことから、メモリー企業に対する関心が薄れたというのが実情です。
- SK hynix社はAIデータセンターに不可欠な高帯域幅メモリー(HBM)の圧倒的なリーダーとしてかなりの好業績を上げてきたものの、NVIDIA社(米国)との間にHBM3Eの認証で一時的な問題が発生してから、Samsung Electronics社の追い上げに直面しています。
Samsung Electronics社は高い生産能力を備えていますが、NVIDIA社から認証を得られておらず、また歩留まりの低さに苦しんでいます。Samsung Electronics社がNVIDIA社の認証を取得し、業界全体の歩留まりの低さが改善されれば、HBMの生産量が大幅に改善し、供給過剰が発生するリスクは低くありません。しかしながら、HBMがやがてコモディティ化し、SK hynix社のSamsung Electronics社に対する優位性が実質的に失われれば、現状のバリュエーションに付加されているプレミアムは持続できなくなる可能性があります。皮肉なことに、Samsung Electronics社が増産に成功してHBMがコモディティ化した場合、HBMの収益性が低下する可能性があるため、Samsung Electronics社もそれほど利益を上げられないでしょう(それでも低価格製品よりははるかに高水準)。これは「同じ場所に留まるために必死に走っている」状況の典型で、競合他社に対して実質的な優位に立っていない場合に発生する問題です。 - 2022年10月の月次報告書で米国が先端半導体技術に対する規制を強化して中国のメモリー企業の締め出しを図ったことが韓国企業にとって優位に働くと述べましたが、これが正反対の方向に進み始めた模様であること。中国企業がEUVリソグラフィ装置を導入できなければ、先進的なDRAM製品を製造できないのは確かです。しかし米国が規制を強化したことで、中国の半導体企業は規制対象がいずれ成熟技術にまで広がることを見越して、成熟ノード用の半導体装置を可能な限り早期に購入するようになりました。中国の大手DRAM企業であるChangXin Memory Technologies社はウェハー生産能力が2025年末までに月産30万枚に達する見込みで、これはMicron Technology社の生産能力に比肩する量です。HBMやDDR5メモリーのようなハイエンド市場は依然として世界3大メーカーの手にしっかりと握られていますが、中国企業はローエンドからミドルエンドのメモリー市場に革新的な変化をもたらし始めています。成熟ノード技術における中国企業の急成長は、メモリーにとどまらず、広範囲に影響を及ぼしています。成熟ノード・ロジックとアナログ半導体を手がける企業には危機が迫っています。
当ファンドの投資プロセスの中心にあるのは各企業の競争優位性と業界における競争の動向です。メモリーについては動向が好ましくないため、両銘柄の全売却を決定しました。
中国市場について - あらゆる手立てを尽くすなら
当月末にかけて、香港・中国市場で株式が急騰しました。これはひとえに中国の政策支援に関して楽観的な見方が出てきたことが要因と考えます。以下は中国人民銀行が主導する主な金融政策ですが、政府も財政政策を通じて景気支援を行うという主旨の声明を出しています。
- 銀行の預金準備率(RRR)引き下げ
- 政策金利、預金金利、住宅ローン金利など複数金利の引き下げ
- 2軒目の住宅購入時における最低頭金比率の引き下げ
- 市場関係者を驚かせたのは、中国人民銀行が株式市場に対する直接的な流動性支援に乗り出し、証券会社、ファンド、保険会社を対象に5,000億元の融資枠を設定するなどして株式購入資金の提供に取り組み始め、さらに銀行にも3,000億元の再貸出枠を設定し、上場企業や主要株主による自社株式の購入の支援に乗り出したこと
もし中国がすでに「バランスシート不況」に突入したと考えるなら(2023年7月の月次報告書参照)、経済にこれ以上流動性を注入してもほとんど効果はありません。なぜなら、企業も家計も疲弊し過ぎていて、再び借り入れを増やす余裕がないからです。将来的な収入に不安があることや住宅投資で損失を出したことで、消費者心理はきわめて弱含んでいます。過去数年の間に、比較的高収入の従業員を多く雇用していた業界、例えばインターネット、金融サービス、教育といった業界はいずれも規制措置によって勢いを削がれました。そうした業界で働く人々は、売れ筋商品の高価格化に中心的な役割を担っていました。しかし今ではその多くが職を失い、不動産投資で損失を被って、生活を維持することさえままならない状況に陥っています。中国には「寝そべり族」(躺平族)という流行語がありますが、これは頑張って成功しようという意欲(さらに働こうという意欲)を喪失した人々を指します。そして「バランスシート不況」という用語を提唱した野村総合研究所のリチャード・クー氏によれば、その解決策は財政政策にあるようです。
本報告書執筆時点では、どのような財政政策が発表されるのかはまだ不明です。Reuters社(英国)の報道によると、中央政府は特別債を2兆元分発行し、消費の刺激と投資の促進、子どもが複数いる家庭への手当支給、地方政府の負債対応に充当する予定だということです。これまでのところ、政府は問題解決にあたって自らがもつリソースを十分に活用していないと批判されています。もしも中央政府がそうしたリソースをうまく活用できるなら、中国はあらゆる手立てを尽くして経済の停滞を食い止めようとしていると言ってよいでしょう。
当ファンドは中国銘柄の組み入れを低めに抑えており、そのために当月末にかけて相対的にパフォーマンスが低下しました。その後中国銘柄の組入比率を引き上げましたが、それほど大幅なものではありません。
当ファンドが目指しているのは、損失を出すリスクを極力抑えながら、適正な長期的絶対リターンを上げることです。したがって、中国株が急騰したからといって、過剰なリスクを冒してまでその動きに追随しようとは思いません。そうしたなか、Tencent Holdings社については、消費者心理が弱含んでいるものの、同社のファンダメンタルズが強固であることを踏まえ、組入比率を引き上げました。
2022年9月の月次報告書で同社について取り上げましたが、そこで論じた内容の妥当性は今も変わっていません。それどころか、同報告書で同社の業績が底を打つと述べて以来、過去2年間、同社の株価は当ファンドの参考指数(MSCI AC Asia Index(円ベース・配当込み))とTOPIXをいずれも大幅にアウトパフォームしています。中国の株式をTOPIXと比較するのはおかしいと思われるかもしれません。しかし当ファンドは日本にも他のアジア市場を投資対象としていますが、2024年1月の月次報告書で述べた通り、日本は政治的に安定した法治国家であることから、投資先の選択肢としては日本を最優先に考えています。もちろん日本の保有銘柄がTOPIXをアウトパフォームすることは期待していますが、アジアの他市場の株価がTOPIXを上回る期待がなければ、日本を捨ててまでアジアの他市場に投資する必要はないと考えています。
中国市場に関する主な問題点は、経済が長期的なデフレに陥るリスクがあることです。デフレ環境下にあっては、企業の名目成長率が恒常的に逆風にさらされるため、中国株式のファンダメンタルズをインフレ率が低い状態にある域内の他市場と比較するのが困難になります。しかし中国政府があらゆる手立てを尽くしてデフレ圧力を抑制しようという姿勢を見せてくれるなら、中国株の有望性を見極めやすくなります。例えば主要インターネットプラットフォームの多くは、株価急騰後も引き続きPER(株価収益率)が10倍台前半、フリーキャッシュフロー利回りが1桁台後半の状態で取引されていて、全力で株主還元に取り組む姿勢を保っています。こうした企業はいずれもキャッシュフロー生成能力が高く、過去4~5年間で中国の景気が減速するまでは世界屈指の優良企業でした。そうした観点に立って、改めてこう考えてみたいと思います。こうした銘柄の中には日本の「割安」銘柄より有望なものが多いのではないか、と。
当ファンドは今後も高い基準を掲げて、アジア地域における長期投資を模索してまいります。
香港とハローキティ
当月は香港に出張しました。香港は大きな課題に直面していることを受けて、当ファンドは関連銘柄の組み入れをごく低水準に抑えています。しかしFRBが利下げサイクルに入れば、状況はわずかに改善する可能性があると考えています。来月は香港の状況について取り上げるかもしれません。
さらに、11月1日はハローキティの誕生日ですが、ハローキティは当ファンドの組入銘柄であるサンリオ(一般消費財・サービス流通・小売り)の主要キャラクターです。この少女(ハローキティは猫ではありません)の50歳の誕生日を祝って、来月は同社の最新情報をお伝えする予定です。
2024年8月の運用コメント
株式市場の状況
<⽇本の株式市場>
2024年8月、日本株式市場の代表指標であるTOPIX(配当込み)は前月末比2.90%下落し、日経平均株価は前月末比1.16%下落しました。
当月の日本株式市場は歴史的な乱高下を演じ、日経平均株価の月間値幅(高値と安値の差、終値ベース)がバブル経済崩壊時期を超えて過去最大となりました。
7月31日の日銀金融政策決定会合での追加利上げが円高を呼び、さらに市場予想を下回った7月の米ISM製造業景気指数で米国景気減速懸念が台頭し円高が一層進行したことで、月前半の日本株式市場はリスク回避の流れが強まり暴落しました。5日には米国経済や雇用の減速への警戒などから円高が大幅に進み、午後には日経平均先物でサーキットブレーカーが13年ぶりに1日に2回発動され、日経平均株価は前日比4,451円の下落と過去最大の値下がりを記録しました。しかしながら翌6日には為替市場がいったん落ち着いたことで日本株式市場も落ち着きを取り戻し、TOPIXおよび日経平均株価は史上最大の上げ幅となりました。加えて、翌7日の内田日銀副総裁のハト派発言も投資家の安心感につながり、月半ばにかけて日本株式市場は急反発しました。
月後半は米国経済への先行きに対する警戒感がひとまず和らぎ、日本株式市場は緩やかなペースで回復し、月前半の急落分の大半を取り戻して当月の取引を終えました。
<アジアの株式市場>
当⽉、アジア株式市場は様々な値動きとなりました。⽇本を除くアジア市場に使⽤される⼀般的な指数であるMSCIアジア(⽇本を除く、⽶ドル建て)指数は、前月末比1.98%上昇しました。月前半は円キャリー取引の巻き戻しと米国の景気後退に対する懸念を受けて株価が急落しましたが、その後は反動で回復に向かいました。FRB(⽶国連邦準備制度理事会)のパウエル議長がジャクソンホール会議で近い将来に利下げに踏み切るという主旨の発言をしたことから、市場心理が改善しました。
フィリピン、マレーシア、インドネシア、タイなどアジア新興諸国の当月のパフォーマンスは北アジア諸国やインドを上回り、中でもMSCIフィリピン指数(⽶ドル建て)は前月末比10.37%と高い上昇を示しました。インドネシア市場も同国政府が規律ある次期予算を示したことから、堅調に推移しました。プラボウォ次期大統領が公約に掲げた「学校給食無料提供」制度の予算はGDP比0.3%程度と、当初懸念されていた同2%程度よりはるかに低水準でした。その他補助金やインフラ支出もほぼ横ばいに据え置かれました。
香港の前月の小売売上は数量ベースで前年同月比13.3%減と予想を下回り、13か月にわたって下降傾向が続いています。小売売上の低迷は広範囲にわたり、大半の消費カテゴリーに及んでいます。住宅価格も引き続き低迷し、オフィスの空室率は未だに高水準に留まっています。
ファンドの運⽤状況
当⽉、当ファンドのパフォーマンスは前⽉末⽐4.09%の下落、参考指数のMSCI AC Asia Index(円ベース・配当込み)は同1.85%の下落となりました。
当⽉パフォーマンスにプラスに貢献した銘柄は、サンリオ(一般消費財・サービス流通・小売り)、三菱重工業(資本財)、日立製作所(資本財)などでした。一方、Samyang Foods(韓国/食品・飲料・タバコ)、ルネサスエレクトロニクス(半導体・半導体製造装置)、丸紅(資本財)などがマイナスに影響しました。
当月に入って、日本の株式市場では史上最大の暴落が発生しました。これは日銀が前月末に今後も緩和基調の政策を続ける姿勢を示し、円高が進んだことによるものです。円高の進行をきっかけに、円キャリー取引と呼ばれる日本円の投機的な売り持ちを解消しようという動きが加速し、その余波を受けて日本の株式市場が大暴落しました。キャリー取引とは幅広く行われている取引手法で、低金利国の通貨で資金を調達しておいて、利幅の大きい海外のリスク資産に投資するというものです。最も一般的なのは、日本円の資金調達コストの低さを利用して金利の高い米ドルを購入する、あるいは日本円を借り入れて日本の株式を購入するという手法です。この手法のリスクは、資金調達通貨に大幅上昇の可能性があるという点にあります。その意味では、ウォーレン・バフェット氏が日本円を借りて日本の総合商社5社に投資したのは、キャリー取引と言えるかもしれません。(ただし、同氏には長期社債を発行してこの取引を行うだけの余裕があるので、為替相場が短期的に円高に振れても気にする必要はありません。)
ここ数年は円安が着実に進んできたことから、キャリー取引は全般的に収益性の高い取引手法だったといえるでしょう。しかし価格動向が安定的に上向きであれば、当然ながら短期的売買で利益を上げようと投機筋(短期的な値動きの変化から利益を獲得することを目的に取引を行う投資家のこと)が群がってきます。当初は資産価格が安定しているため、「安定的」な利益を求めて投機筋が集まってきますが、それが逆に資産価格の不安定化をもたらします。価格動向が安定的な上昇基調を描かなくなると、こうした短期的動向を追う投機筋の目論見は崩れ、短期的取引の解消が発生します。そのため、当ファンドは組入先の選定にあたって株価が安定しているかどうかをあまり考慮しません。市場には変動が付き物で、変動を回避するのは困難だからです。変動を回避するよりも、あまり気にしないようにするか、あるいは逆に利用してしまおうというのが当ファンドの考え方です。
投機筋について言えば、市場にはさまざまなタイプの参加者がいるので、誰もがファンダメンタルズ(経済の基礎的条件)の観点から投資先を検討していると考えるのは間違っています。クオンツ運用派、マクロ運用派、パッシブ運用派など、参加者のタイプは数え上げればきりがありません。そうした投資家は多くの場合、ファンダメンタルズの観点から割安・割高を考えるというより、特定のセグメントに投資したいという理由で株式を売買します。例えば誰かが半導体ETF(上場投資信託)を購入したとしても、それは単に半導体セクターに投資したいだけで、必ずしも時間をかけて組入銘柄のバリュエーションを検討するとは限りません。またファンダメンタル投資家であっても、マーケット・ニュートラル戦略を採用し、厳格なリスク制限の下で運用を行うヘッジファンドが増えています。こうした投資家は市場の変動幅が拡大すると既存の持ち高を解消してしまう場合があります。このように当ファンドとまったく異なる方法で取引を行う市場参加者が多いため、そうした状況下では優良銘柄を割安な価格で購入する機会が生まれます。そうした理由もあって、当ファンドは多数のアナリストが注視している大型株にも引き続き投資機会があると考えています。中小型株については、流動性の制約から、クオンツ運用、マクロ運用、パッシブ運用、マーケット・ニュートラル運用の投資家が参加する可能性は低いと考えます。したがって当ファンドの競合先はファンダメンタル投資家である可能性が高く、相手より優れた判断力を持っていなければ投資で収益を上げることができません。そうした意味から、中小型株にさえ投資すれば何もしなくても優位に立てるとは考えられません。最終的には大型株にも中小型株にもチャンスがあると考えられるので、常にケースバイケースで投資先を検討しています。ところで付言しておきますが、マクロ戦略やマーケット・ニュートラル戦略をとるヘッジファンドが市場の混乱を受けて保有株を手放したからと言って、その運用手法が間違っていたということにはなりません。戦略が違えば目標も違うというだけのことです。そうしたファンドの目標は変動の少ない環境下でその日その日の収益を得ることであり、市場の変動が拡大した時点で持ち高を減らすのは当然なのです。当ファンドの目標は、市場の短期的変動をあまり注視せず、複数年(できれば数十年)にわたって市場全般より高い投資収益を生み出すことにあります。
当ファンドは日本株式市場を依然ポジティブに捉えているため、当月の下落を機に、日本銘柄の組入比率を大幅拡大しました。先行きに確信の持てない保有株の一部を売却し、オリックス、サンリオ、日立製作所など、日本の主要組入銘柄を集中的に買い増しました。
セブン&アイ・ホールディングス(生活必需品流通・小売り)
当月は上記以外にも、昨年売却したセブン&アイ・ホールディングスを再度組み入れました。同銘柄を売却したのは米国事業の進展に満足できず、事業の再加速にはかなりの時間がかかると考えたためです。これまでのところ、その判断は正解でした。しかし、当ファンドは同社の今後について弱気だったわけではありません。コンビニエンスストア事業は資本収益率とキャッシュフロー創出力が高い有望な小売事業で、生活必需品を販売しているため、需要も安定しています。「セブン-イレブン」の比類ないブランド力と規模を考えれば再加速は時間の問題だと考え、再投資の時期を待っていました。同社は当月19日付のプレスリリースで、コンビニエンスストアチェーン「Circle K」を運営するAlimentation Couche-Tard社(カナダ)から買収提案を受けたと発表しました。この協議はまだ初期段階にあり、資金調達と規制の両面から大きな障害に直面しています。提案については現在、セブン&アイ・ホールディングス社内に設置された特別委員会が検討中です。
当ファンドでは、買収交渉の結果にかかわらず今回の提案は好材料だと考えています。セブン&アイ・ホールディングスは規模が大きいため、Alimentation Couche-Tard社が全額現金で買収することはほぼ考えられません。両社が合併するのなら、合併後にできる超巨大コンビニエンスストア運営会社の株式をぜひとも所有したいと考えています。もし今回の提案が何の成果ももたらさなかったとしても、セブン&アイ・ホールディングスには世界的にみてきわめて長期的な成長余地があります。重要なのは、同社の価値を戦略的投資家が認めているということが今回の提案によって世界に示されたことです。同社の株価は現状を起点として底堅く推移することになるでしょう。また、今回の提案は公表されたため(2020年に同社が「海外の小売企業」から買収提案を受けたという噂が流れたが公表されなかった時と異なる)、経営陣は自らの決定について説明責任を負うことになります。提案を拒否した場合、経営陣は現在進行中の戦略的施策を加速し、事業の本質的価値を急速に高める以外に選択の余地がありません。総体的にみて、同社の株価が現状(のれん償却前EPS(2025年2月期予想163.62円)を前提とすると、現在の株価では実質的にPER(株価収益率)12倍台)より大幅に下落する可能性はかなり低くなったと考えます。事業の長期的成長力が高いこと、株価が大幅に下落する可能性が低いことから、当ファンドは同社の再度組み入れに踏み切りました。
日本銘柄の組入比率拡大にかかる資金は、韓国銘柄の組入比率を縮小することで調達しました。今年は韓国銘柄から多くの収益を得ましたが、ファンダメンタルズの面で逆風が強まっていることから一部組入銘柄のバリュエーションは割安でなくなっていると考えます。対米ドルで円高が進むことは一般に日本市場にとってあまり好ましくありませんが、ウォン高が韓国企業におよぼす悪影響はその比ではありません。海外に大規模な生産拠点を持つ一部日本企業と異なり、韓国企業は韓国からの輸出というビジネスモデルへの依存度が高いためです。韓国ウォンが上昇すると、競合先がどの国の企業なのか次第で、そうした企業の競争力が低下する可能性があります。当ファンドは組入銘柄の長所と短所を十分に認識しており、保有する韓国銘柄の一部について、組入比率を若干修正しました。
台湾訪問
当月は台湾を再訪問し、調査を行いました。台湾銘柄の組入比率はそれほど高くありませんが、テクノロジーセクター全体でみるとかなり高水準に達しています。台湾はAI(人工知能)関連製品の製造拠点で、サプライチェーンがきわめてよく整っています。例えば、世界のAIサーバーの90%は台湾で生産されていると言われています。したがって、台湾を訪問するとテクノロジーの動向に関してきわめて貴重な知見が得られます。紙面を割くべき突発的な事態が株式市場で発生しなければ、次回の月次報告書で台湾出張の成果についてお知らせする予定です。
2024年7月の運用コメント
株式市場の状況
<⽇本の株式市場>
2024年7月、日本株式市場の代表指数であるTOPIX(配当込み)は前月末比0.54%下落し、日経平均株価は前月末比1.22%下落しました。
当月の日本株式市場はボラティリティの大きい相場展開となりました。月前半は、前月からの好調な流れを引き継ぎ堅調に推移しました。米国の雇用統計で労働需給の逼迫が緩和される兆しが見られ、FRB(米連邦準備制度理事会)の年内利下げ観測が高まったことで、長期金利が低下し、米国のハイテク株が上昇しました。日本でも半導体関連銘柄が相場を支え、日経平均株価は連日で史上最高値を更新し、11日には4万2,000円台に到達しました。しかしながら米国消費者物価指数が想定以上に軟化し、米国ハイテク株に利益確定売りが入ったことやドル円が円高方向に振れたことなどから、日本株式市場は下落に転じました。そして月後半に入ると下げが一層加速しました。トランプ氏が大統領選で優勢と伝わると、米中対立の深刻化やドル高是正などの自国優位政策が懸念され、半導体関連株に売りが膨らみ、日本株にも影響が及びました。さらに日銀の追加利上げやFRBの利下げ観測から「円キャリー取引」の巻き戻しが発生し、ドル円は一時151円台を付け、日本株式市場も幅広く売りが広がり、日経平均株価は3万8,000円を割り込む水準まで大幅に下落しました。
31日に日銀は金融政策決定会合で政策金利を0.25%程度に引き上げることを決定し、国債買い入れの減額計画も明らかにしました。また、米国政府が対中国の半導体輸出規制で日本などを除外すると報じられると、半導体関連株が反発し日本株式市場は下げ幅を縮小して当月の取引を終えました。
<アジアの株式市場>
当⽉、アジア株式市場は様々な値動きとなりました。⽇本を除くアジア市場に使⽤される⼀般的な指数であるMSCIアジア(⽇本を除く、⽶ドル建て)指数は、前月末比0.06%下落しました。パフォーマンスで上位につけたのはタイ、シンガポール、フィリピン、インドなどで、株価が堅調に推移しました。台湾と中国は遅れをとり、全般的にみて株価指数の低迷要因となりました。
米国では、カマラ・ハリス副大統領がバイデン大統領に代わって民主党候補に指名され、秋の大統領選挙でトランプ前大統領と対決することになりそうです。一方、FRB(⽶国連邦準備制度理事会)が9月に利下げに踏み切るという観測が広がっています。米国株式市場、特にマグニフィセント・セブン(米国株式市場を牽引する超大手テクノロジー企業7社)の株価の振れ幅が拡大したことも、アジア市場の投資家心理が弱含む原因となりました。AI(人工知能)と米国テクノロジーセクターの低迷は、テクノロジーセクターへの依存度が高い台湾株式市場にとって大打撃となっています。
中国では三中全会(中国共産党の「中央委員会第3回全体会議」の略称)が開催され、政策がいくつか発表されたものの、市場に大きな反応を引き起こすと考えられるものではなく、市場関係者からはあまり材料視されませんでした。一方、香港は依然経済面の課題を抱えており、不動産価格が下落し、小売売上高が低迷しています。6月の小売売上高は、本土に出かけてグレーターベイエリア(大湾区)で買い物をする住民が増えたことで、前年同月比9.7%減少し、4か月連続の減少となりました。
インド市場は幅広い構造改革と良好な事業環境が好材料となって当月も好調を維持し、経済は力強い成長軌道を保ちました。ASEAN諸国は総じて好調で、マレーシアのデータセンター、半導体、観光セクターに引き続き大きな関心が集まっています。インドネシアも景気底打ちの兆しを見せており、投資家は10月に就任する新大統領が政策を明確に打ち出してくれることを期待しています。
ファンドの運⽤状況
当⽉、当ファンドのパフォーマンスは前⽉末⽐6.11%の下落、参考指数のMSCI AC Asia Index(円ベース・配当込み)は同4.53%の下落となりました。
当⽉パフォーマンスにプラスに貢献した銘柄は、KB Financial Group(韓国/銀行)、MakeMyTrip(インド/消費者サービス)、サンリオ(一般消費財・サービス流通・小売り)などでした。一方、SK hynix(韓国/半導体・半導体製造装置)、COSMAX(韓国/家庭用品・パーソナル用品)、Taiwan Semiconductor Manufacturing Company(台湾/半導体・半導体製造装置)などがマイナスに影響しました。
当月の株式市場は振幅の大きい値動きとなりました。
一つ目の要因は月内に円高が進んだことにあります。当ファンドのパフォーマンスは円高の進行を受けて下落し、特に日銀が当月末に追加利上げを発表し、さらなる金融引き締めの姿勢を示したことで、その傾向は一段と顕著になりました。円高は、海外株式に投資する他の円建てファンドと同様に、当ファンドが組み入れている海外株式に直接的な影響を与えました。また、日本企業はグローバル企業が多く、円高は一般的に収益悪化要因となります。しかし、多くの日本企業は為替相場が円高に振れることを想定して通期計画を発表しているため、現行水準の円高で見通しが悪化することはないでしょう。当ファンドが保有する日本企業は内需企業が多く円高の影響をあまり受けないと考えられますが、円高は当ファンドのパフォーマンス悪化要因となる可能性があります。
二つ目の要因は、米国大統領選でトランプ氏が勝利するという見方が市場関係者の間に広がったためです。思い起こせば、同氏が2016年に選挙に勝利したときもやはり同様の変動がありました。同氏が台湾に関して「台湾は米国から半導体ビジネスを奪った」、「台湾は米国に防衛費を支払うべきだ」などと発言したことが、地政学的懸念の拡大につながりました。一方、トランプ氏が再びホワイトハウス入りした場合、中国にとっても好ましい事態とは言えません。なぜなら、同氏が再選した場合には海外からの輸入品すべてに一律10%、中国からの輸入品には同60%の関税を課すという意向を示しているからです。
トランプ氏が勝利するとどうなるかは、同氏が実際に勝利し、より具体的な政策が発表されるまでは何とも言えません。当ファンドに関して言えば、中国関連銘柄の組入比率はきわめて低く、対米輸出への依存度の高い銘柄はありません。その他組入銘柄については、全般的に競争力が高く、10%の関税を課された程度では成長軌道を逸脱しないと考えられる銘柄を選択しています。米国で現地生産を行っているような企業の中にはトランプ氏勝利の恩恵を受けるものもあるかもしれません。さらに、競合先によっても影響は異なります。競合先が中国企業であれば、相手に60%の関税が課せられることになるため、たとえ関税を10%課されても結局的には有利に働く可能性があるでしょう。一方、競合先が米国企業なら、トランプ氏の勝利は不利に働きます。また、同氏はNATO(北大西洋条約機構)加盟国など同盟国に国防費増額を迫る可能性が高いため、一部産業、例えば防衛産業がその恩恵を受けるのは確実です。当ファンドは三菱重工、LIG Nex1社(韓国)といった防衛関連銘柄を保有しています。しかし副次的効果で世界貿易の広範な減速や景気後退が起こる可能性もあることから、最終的にどのような影響が及ぶかはやはり不明です。ところが当月、バイデン大統領が米大統領選からの撤退を表明し、カマラ・ハリス現副大統領が正式に民主党の後継候補に選ばれるという見方が濃厚になりました。そのためトランプ氏の勝利に対する期待感は薄れ、月末にかけて「トランプトレード」が一部後退しました。
当ファンドの揺るぎない信念のひとつに、「ニュースを追いかけ、ニュースに基づいて相場の方向性を判断するのは無意味だ」というものがあります。いつの時代であれ、新聞に書いてあるのは市場の動きを説明するための物語であり、つまりは過去の出来事の話に過ぎません。そうした点を踏まえると、いま当ファンドにできることは、毎回述べている通り、足腰が強く、回復力に富んだ銘柄にこだわるということしかないでしょう。
当月は一部のセクターにおいて、組入比率の調整を行いました。
第一に、半導体銘柄、とりわけAI(人工知能)データセンターに直接的に関わる銘柄で、バリュエーションの高い企業の組入比率を引き下げました。これはトランプ氏の発言を受けたものではなく、AIの投資サイクルの中でもデータセンター関連のものは間もなくピークを迎えるのではないかという懸念を抱いたためです。そうした企業がこれまで市場の寵児ともいうべき存在であり続けてきたことを踏まえると、より慎重にならざるを得ません。Taiwan Semiconductor Manufacturing Company(台湾/半導体・半導体製造装置)が発表した2024年第2四半期決算と第3四半期業績予想はいずれもきわめて好調で、CEOを務める魏哲家氏は、CoWoS(Chip on Wafer on Substrate、GPUが使用する半導体パッケージの一種)の生産能力確保は難航しており、顧客の需要を満たせるだけの供給体制が整うのは早くても2025年か2026年頃になるだろうと述べました。こうした企業のファンダメンタルズは引き続き堅調ですが、忘れてはならないのは、株式市場というものは将来を見据えて動くものだということです。今後数年以内にピークを迎える可能性があるということがバリュエーションに影響し、上値余地は限定されるでしょう。当ファンドの半導体セクターに対する見方がポジティブになったのは2022年後半からで(2022年10月の月次報告書(https://www.sparx.co.jp/mutual/jag_202210.pdf)、Samsung Electronics社(韓国)の組み入れに関する項を参照)、同セクターはそこで底を打ち、以後7四半期にわたって好調を維持してきました。
AIは今後数年にわたって市場の牽引役となることは言うまでもありませんが、当ファンドではクラウド・コンピューティング(インターネット上でサーバー、ストレージ、データベースなどのサービスを利用すること)も同様に考えています。10年程前にクラウドがMicrosoft社(米国)やAmazon社(米国)といった米国巨大テクノロジー企業の成長の原動力になってから、両社のクラウド事業(それぞれAzure、Amazon Web Services)の売上高は前年比で減少したことがありません。しかし、だからといってその間に設備投資が一度も鈍らなかったわけではありません。AIをいち早く導入したこれらの企業が、莫大なコストと比較して生産性の面でどれだけのメリットを得たのかについては、まだ議論の余地があると考えます。Meta社(米国)は4月に今年の資本支出を350億ドル~400億ドル(事前計画では300億~370億ドル)に引き上げる計画を発表したところ、株価が下落しました。ここから判断すると、AI投資からどれだけ利益を上げられるのかという意味で、巨大テクノロジー企業に対する圧力が高まっているようです。ChatGPTを運用するOpenAI(米国)の年商は34億ドルとされています。巨大テクノロジー企業の設備投資額を合計すると年間1,000億ドル以上に達することから、今後数年間でAIの売上を1,000億ドルとは言わないまでも数百億ドル規模に拡大できなければ、莫大な投資を正当化することはできないでしょう。
Meta社(米国)のCEOを務めるマーク・ザッカーバーグ氏はBloombergのインタビューで次のように語っています。
「現状では企業の多くが過剰設備を抱えている可能性が高いと思う。あとから振り返って、しまった、何十億ドルも無駄遣いしてしまったと感じるのではないか。(中略)その一方で、実は投資を行っている企業はすべて合理的な判断をしているのではないか、とも思う。他社に後れを取ると、最重要テクノロジーでこれから10年も15年も存在感を失うという失態を演じることになるからだ。」
ザッカーバーグ氏はAIの今後について、次のような道筋を示していると当ファンドは考えます。
「AIが将来的に最強のツールになるなら、巨大テクノロジー企業は他社に後れをとるわけにはいかないので投資額を高水準に保ち、過剰投資のリスクを冒すことも厭わない。だが過剰投資に気づいたその時こそ、AI半導体が破綻する瞬間になるだろう。」
半導体産業に景気循環的な性質があることは常に念頭に置いておく必要があります。つまるところ、半導体産業の収益とは顧客の設備投資に他なりません。顧客の設備投資を収益とする事業には、一般的にきわめて循環的な性質があります。例えば消費者からみると、家電製品の購入費は一種の「設備投資」ですが、スキンケア製品の購入費は「営業費用」です。したがって、家電製品の購入は一般的に先延ばしできることから、家電製品はスキンケア製品よりも循環的な性質を帯びることになります。半導体も例外ではありません。景気後退局面が突然やってきて、何の備えもしていなかったら、どれほど痛手を被るかわかりません。当ファンドは半導体に対して全面的に弱気になっているわけではありませんが、このセクターはファンダメンタルズの強固さに対する信頼感と、現状の好況がいつピークを迎えるのかという不安が拮抗する段階に移行したと考えています。そうした点を念頭に置いて、リスクリワード特性が好ましくないと判断し、利益を一部確定することにしました。
一方、近い将来AIにまだ次の波がくるなら、それはエッジAI(ネットワークの端末機器(エッジデバイス)上でAI処理を実行するシステムの総称)ではないかと考えています。Apple社(米国)は次世代機iPhone 16と現在発売中のiPhone 15 Pro/Pro MaxにオンデバイスAIの機能を搭載したApple Intelligenceのリリースを発表しました。iPhone16が消費者の手元に届いてからでないとわかりませんが、Apple Intelligenceの機能のすばらしさが評判になれば、スマートフォンの買い替えが一気に進むことになるかもしれません。スマートフォンの購入は2021年に急増しましたが、端末は永遠に使えるものではなく、買い替えが必要です。Morgan Stanley社(米国)によると、iPhoneの買い替え周期は現状4年から5年ということなので、買い替えの時期が近づいていることになります。以上のことから、当ファンドはスマートフォン関連銘柄を比較的楽観的にみています。
第二に、日本とインドへの投資比率を拡大しました。これはテクノロジーセクターのバランスを見直したことをきっかけに、アジア地域においてテクノロジー以外の投資機会を探ることができたためです。当ファンドは日本とインドはいずれも経済大国であり、多様な産業を擁しているためアジア地域の中でもより有望な投資機会があると考えています。また、両国は域内の他の国と比べて地政学的リスクが低いということも、魅力の一つです。日本企業の多くが5月に発表した業績予想はかなり慎重なものでした。そのため、それらの企業の株価の重荷となりましたが、会計計画が保守的だったことが分かれば株価は回復する可能性があります。そのため当ファンドは日本市場にはまだまだチャンスがあると考えています。インドは、問題はバリュエーションの高さにあると考えています。消費財関連の大型株でも成長率が10%未満でありながら、PER(株価収益率)が50~60倍に達している銘柄が多数存在します。そのため、割安な優良企業を探し出すにはかなりの時間が必要です。当ファンドでは人工関節置換術に注力するインドの病院を新たに組み入れました。
短期的な状況は依然不安定ですが、株価を長期的に左右するのは企業業績だということを念頭に置いておくべきでしょう。2016年の選挙でトランプ氏が勝利すると、株式市場は一時的に下落しましたが、その後は減税や半導体の需要回復など様々な要因によって、新たな上昇局面に入りました。結局のところ、当ファンドのなすべきことは業績を継続的に伸ばせると考えられる企業を探し出し、割安な価格で購入すること以外にありません。アジアにはそうした企業を発掘する機会が十分にあると考えています。
2024年6月の運用コメント
株式市場の状況
<⽇本の株式市場>
2024年6月、日本株式市場の代表指数であるTOPIX(配当込み)は前月末比1.45%上昇し、日経平均株価も前月末比2.85%上昇しました。
当月の日本株式市場は、日米の金融政策の動向に注目が集まるなかレンジ内でもみ合いの推移となった後、円安の進行とともに月末にかけて上昇しました。月前半は、米国金融政策の動向を巡り米国マクロ経済指標に注目が集まるなか、雇用・物価関連指標等の結果を受けインフレ鈍化の見方が支持され、目先のFRB(米連邦準備制度理事会)の利下げ観測の高まりから米国長期金利が大幅に低下し、米国株式市場は半導体・ハイテク株中心に上昇しました。この流れを受けて、日本株式市場も上昇しました。月半ばには、日銀金融政策決定会合で、日銀が国債買い入れ減額の方針を固めたものの、具体策については公表が見送られ、円安の進行とともに日本株式市場は上昇しました。その後は、会合後の記者会見にて日銀総裁より買い入れ減額規模について「相応の規模になる」との発言があったことや、7月の会合で利上げを行う可能性も否定しない主旨の発言があったこと、また、フランス政治不安が改めて意識され下落した欧州市場の影響などいくつかの材料が出るなか、日本株式市場は下落する場面がありましたが、月後半にかけて株価は持ち直しました。月後半は、ドル円レートが一時161円台まで下落し、1986年12月以来およそ37年ぶりの安値を更新しました。円安が支えとなったほか、日本長期金利の上昇を受けた銀行株などの上昇も相場をけん引し、月末にかけては配当金の再投資の観測もあるなかで日本株式市場は前月末対比で上昇し、当月の取引を終えました。
<アジアの株式市場>
当⽉、アジア株式市場はまちまちの値動きとなりました。⽇本を除くアジア市場に使⽤される⼀般的な指数であるMSCIアジア(⽇本を除く、⽶ドル建て)指数は、台湾、韓国、インドなどを中心に株価が上昇し、前月末比4.32%上昇しました。
台湾市場と韓国市場は、テクノロジーセクターの上昇基調が引き続き追い風となりました。台湾で毎年開催されるCOMPUTEX TAIPEI(台北国際コンピュータ見本市)では、AI(人工知能)の能力が急速に向上し、速いペースで導入が進んでいることが明らかになりました。両国の企業はAIサプライチェーンの中で戦略的な立ち位置をとり、今後数年にわたって続くAIの進化の流れに乗ろうとしていると考えられます。
インド市場では総選挙後しばらくの間、変動幅の大きい状態が続きました。モディ首相率いる国民民主同盟(NDA)は下院で293議席を獲得し、予想より少ないながらも、過半数を確保しました。株価はモディ政権発足直後こそ下落したものの、現行政策が継続されるという見方が投資家の間に広がったことで、力強く反発しました。
中国市場と香港市場は4月と5月には好調なパフォーマンスを記録しましたが、当月は上昇基調が一服しました。これは中国政府が7月に開催される長期的な経済政策運営の方針を決める重要会議「三中全会」の後に大規模景気刺激策を打ち出すという見方が薄れ、景気回復のペースをより慎重に見定めようという姿勢が強まったためと考えられます。一方、香港の不動産セクターは引き続き業績が低迷しており、中古住宅価格の指標となる中原城市領先指数(CCL)は2016年以来の低水準に達しました。オフィス市場も苦戦しており、英不動産コンサルティング会社Knight Frank社は香港の空室率は過去最高の12.2%に上ると発表しました。また、ハンセン不動産指数の年初来の下落幅は約19%に達しました。
ASEAN諸国は内需と外需がいずれも低迷したことで、経済成長が総体的に鈍化しました。米ドル高によって新興国通貨にさらなる下落圧力がかかり、新興国経済の直面する課題がまた一つ増えた形となりました。
ファンドの運⽤状況
当⽉、当ファンドのパフォーマンスは前⽉末⽐9.07%の上昇、参考指数のMSCI AC Asia Index(円ベース・配当込み)は同4.87%の上昇となりました。
当⽉パフォーマンスにプラスに貢献した銘柄は、Taiwan Semiconductor Manufacturing Company(台湾/半導体・半導体製造装置)、Samyang Foods(韓国/食品・飲料・タバコ)、ASPEED Technology(台湾/半導体・半導体製造装置)などでした。一方、MINISO Group Holding(中国/一般消費財・サービス流通・小売り)、オルガノ(資本財)、New Oriental Education & Technology Group(中国/消費者サービス)などがマイナスに影響しました。
ウォーレン・バフェット氏は前月開催されたBerkshire Hathaway社(米国)の年次株主総会で、消費者行動を理解することがいかに迅速な投資判断を可能にし、最終的にApple社(米国)への投資に繋がったかを語りました。当ファンドも消費者行動についてバフェット氏と同様に関心を持っています。当ファンドの調査手法は、世の中を理解することにあります。経済というものは突き詰めれば消費者の欲求を満たすことを中心に構築されています。つまり、消費者の行動と動向を理解することが世の中を理解する上で欠かせないことであり、ひいては当ファンドの調査の中核を成すものです。そのため、これまで幾度となく述べてきた通り、当ファンドは消費者関連セクターを柱の一つとしています。
現在、世界の人口の約60%をアジア諸国が占めており、その文化や発展段階は国によって異なります。アジアには中国という世界的な大消費国があり、将来的にはインドもそれに追随することになるでしょう。一方で日本や韓国のように、世界トップクラスの消費財を世界に輸出している国もあります。消費者関連の投資機会を探るのにこれほど最適な環境が果たしてあるでしょうか。
当ファンドが志向するのは、様々な消費財の中でも、人々が果てしなく追い求め、それに対する支出額が収入の増加に応じて継続的に増えていくような商品カテゴリーです。例えば乳製品について考えると、収入が増えたからといって乳製品に対する支出額を一定額以上に増やすことはおそらくないでしょう。つまり、乳製品という商品カテゴリーは支出額の上限が比較的低いということになります。一方、当ファンドがとりわけ注目している商品カテゴリーは旅行と美容です。当ファンドは2023年4月の月次報告書で、韓国の大手医療用美容機器メーカーであるClassys(韓国/ヘルスケア機器・サービス)について取り上げました。人間が美とアンチエイジングを限りなく追求する存在であることは、美容というものが極めて息の長い成長過程をたどる業界だということです。様々な指標から明らかなように、アジアの中では日本と韓国が世界の中でも美に対するこだわりの強い国で、革新的な商品を多数生み出してきた国でもあります。両国は美容関連の投資機会を探るのに適していると考えています。
世界へはばたくK-beauty(韓国コスメ)
2024年2月、㈱資生堂が日本国内における大規模な早期退職募集を行うと発表しました。アジアの化粧品会社は中国への依存度が高く、この数年は中国経済の減速、地域ブランドとの競争激化、時折起こる政治的イベントのために、苦戦を強いられていました。一方、韓国ブランドは日本ブランドよりかなり早い時期から苦境に立たされていました。
2010年初頭、中国では韓国の化粧品ブランドが全盛期を迎えていました。「星から来たあなた」を筆頭に韓国ドラマが人気を博し、韓国化粧品に対する関心が一気に高まりました。「星から来たあなた」の公式スポンサーでもあった韓国の大手化粧品会社Amorepacific社は、2010年から2016年にかけて売上高が大きく拡大しました。しかし韓国が2017年に米国のTHAADミサイル(終末高高度防衛ミサイル)システムを配備したために中韓関係が悪化し、中国で韓国製品の大規模な不買運動が起きたことで、同社の収益は次第に減少していきました。
しかし、収益の減少を政治的な出来事だけに求めるのは誤りだと考えます。Amorepacific社の大衆向けブランドである「InnisFree」は、より安価な中国の現地ブランドと熾烈な競争を繰り広げていました。また、中国では2016年から2017年にかけてeコマース(電⼦商取引)が普及し始めましたが、同社はオンライン化の流れに対応できませんでした。これらの問題は同社にとって重い足枷となりました。同社は採算の取れない実店舗を大量に閉鎖するなど、中国事業を数年かけて再編しました。
また同社のプレミアムブランド「Sulwhasoo(雪花秀)」は、「代購」と呼ばれる外国から仕入れた商品を転売する業者によって韓国の免税店で安く大量に購入、中国において高値(それでも定価よりかなり安価)で転売されたことにより、その価格とブランド価値が傷つけられました。なおこの問題は「Sulwhasoo」だけではなく、他社の高級スキンケアブランドでも同様に起こっていました。加えて高麗人参を主成分とする「Sulwhasoo」は独自の韓国的なブランドイメージを誇っていましたが、中国における韓国文化の人気低下とともに、その人気も衰えてしまいました。
中国経済が低迷していることから、韓国の化粧品ブランドは他の市場に活路を見出す必要があります。世界的な高インフレ環境は彼らに絶好の機会を与えてくれました。韓国化粧品の強みは技術革新の速さと、コストパフォーマンスの良さにあると考えます。今後消費者が物価高への対処を迫られるなかで、費用対効果の高い商品に対する需要が世界的に拡大していくでしょうが、韓国化粧品はそうした需要を満たすと考えます。
また、当ファンドが日頃から述べている通り、テクノロジーによって消費者の行動に変化が起こりました。米国で実店舗の棚に食い込むにはSKU(Stock Keeping Unit、在庫管理における最小の管理単位)の数と強力なブランド力が必要となるため、商品を置いてもらうのは非常に困難です。ところがeコマースとソーシャルメディアの登場によってこうした状況が変わり、韓国の化粧品にチャンスが訪れました。韓国の化粧品ブランドはTikTokのようなソーシャルプラットフォームでプロモーションを行い、Amazonのようなeコマースプラットフォームを製品販売に活用し、人気を博しています。
以下は2019年から2023年にかけての化粧品輸入総額に占める韓国化粧品の割合を地域別に比較したものです。
2024年5月の運用コメント
株式市場の状況
<⽇本の株式市場>
2024年5月、日本株式市場の代表指数であるTOPIX(配当込み)は前月末比1.16%上昇し、日経平均株価も前月末比で0.21%上昇しました。
当月の日本株式市場は、月前半は4月の米国雇用者数が市場予想を下回り、米利下げ観測が強まったことから日米株式市場ともに上昇しましたが、日銀の金融政策正常化観測などから上値が抑えられました。月半ばには米消費者物価指数や米小売売上高など予想を下回る指標が発表され、金融引き締めの長期化への懸念が後退しました。その結果、米国の主要3株価指数が史上最高値を更新し、日経平均株価も一時39,000円を回復しました。さらに、NVIDIA社(米国)が市場予想を上回る好決算を発表し、半導体株が軒並み上昇して相場を支えました。月後半は、米景気の底堅さを背景とする利下げ動向への懸念や、日銀総裁の追加金融引き締めを示唆する講演が再び注目されて日米長期金利の上昇により株価が下落しましたが、最終的には金利上昇がひとまず一服したとの見方が買い戻しにつながり、前月末を上回る水準で月を終えました。
<アジアの株式市場>
当月、アジア株式市場はまちまちの値動きとなりました。⽇本を除くアジア市場に使⽤される⼀般的な指数であるMSCIアジア(⽇本を除く、⽶ドル建て)指数は、台湾、シンガポールなどに牽引される形で前月末比1.58%上昇しました。当⽉パフォーマンスが振るわなかった市場は、インドネシア、フィリピン、韓国などでした。中国市場と香港市場は前月以降の堅調な上昇基調を維持しました。中国政府は当月、不動産セクターに対する政策支援を発表し、地方政府の支援を通じて落ち込んだ不動産市場の安定化を図る意向を示しました。一部投資家の間に中国の不動産セクターは最悪期を脱した可能性があるという見方があることから、MSCI中国不動産指数は過去2か月でおよそ17%上昇しました。
AI(人工知能)関連銘柄は前月に一時的な調整局面に入りましたが、当月は堅調な上昇基調を取り戻しました。NVIDIA社(米国)が好調な業績と見通しを発表したことは、アジアのAIサプライチェーン全体、とりわけ台湾と韓国のハイテク銘柄に恩恵をもたらしました。アジア地域でデータセンターの需要が旺盛であることから、Microsoft社(米国)、Alphabet社(米国)、Amazon.com社(米国)、NVIDIA社などはASEAN諸国に多額の投資を行い、域内の有能なエンジニアと低い運営コストを最大限に生かそうとしています。
インド市場は小幅な値動きで推移しましたが、これは投資家が選挙の行方を見定めようとして待ちの姿勢をとったためだと考えられます。モディ首相が続投して3期目に突入し、現行政策を継続して経済成長を推進するというのが大方の予想となっています。
インドネシア市場は企業業績やマクロデータの低迷や前月に発表された予想外の利上げの影響で軟調なパフォーマンスに終わりました。
ファンドの運⽤状況
当⽉、当ファンドのパフォーマンスは前⽉末⽐4.66%の上昇、参考指数のMSCI AC Asia Index(円ベース・配当込み)は同1.35%の上昇となりました。
当⽉パフォーマンスにプラスに貢献した銘柄は、Samyang Foods(韓国/食品・飲料・タバコ)、MakeMyTrip(インド/消費者サービス)、COSMAX(韓国/家庭用品・パーソナル用品)などでした。一方、Lemon Tree Hotels(インド/消費者サービス)、サンリオ(一般消費財・サービス流通・小売り)、Hanwha Aerospace(韓国/資本財)などがマイナスに影響しました。
2024年3月の月次報告書で韓国の企業価値向上プログラムについて取り上げました。一方、2021年以降パフォーマンスが大幅に落ち込んでいる中国も、「企業価値向上」に取り組んでいます。
中国も企業価値向上に取り組み
前月、中国国務院(中国の最高行政機関)は資本市場改革に関して「資本市場の監督強化、リスク防止、質の高い発展を促進する意見」、いわゆる新『国家九条』を発表しました。これは同政策としては3回目となり、1回目と2回目はそれぞれ2004年と2014年に発表されました。
「監督」という言葉がありますが、中国政府がこの言葉を発したからといって慌てる必要はありません。実際のところ、資本市場には監督を強化すべき側面がたくさんあるからです。中国のオンショア(上海と深センを含むA株)市場が長年にわたって市場の「資金調達機能」を重視してきたことは、企業が資金を調達し、中国の産業を発展させる上で欠かせない基盤となっています。市場のパフォーマンスは非常に軟調であるにもかかわらず、中国A株(上海証券取引所と深圳証券取引所に上場している⼈⺠元建ての中国株式)市場は2022年から2023年にかけて世界最大のIPO市場となり、資金調達額は米国を上回りました。しかし、市場の「投資機能」に十分な焦点が当てられず、市場関係者はコーポレートガバナンスの不備と投資家保護の手薄さに悩まされてきました。Goldman Sachs社(米国)のデータによると、中国A株市場に対する機関投資家の参加率はおよそ15%で、インドの約33%、韓国・台湾の約50%と比較すると著しく低水準にとどまっており、総体的にみると中国A株市場は個人投資家が主導する市場であり、また多くの人は単なるカジノと見ています。こうした状況を受けて、中国政府は市場を改革し金融機能と投資機能を両立させたいと考えています。このことは中国政府が投資主導型経済から消費主導型経済への変革を志向する一環と考えますが、こうした移行をうまく進めるには、個人投資家が資本市場で着実に利益を積み上げられるようにする必要があると考えます。
新『国家九条』の要点をまとめると、以下のようになります。
- 上場基準を引き上げ、出資者の責任を強化することでIPOの基準を厳格化する。
- 上場企業に対する監督を強化することで、コーポレートガバナンスと情報開示を改善、大株主による株式売却を規制し、配当支払いを促進する。
- 黒字でありながら低配当または無配当を続けている企業にはリスク警告を発する可能性がある。配当の予測可能性を高めるため、企業には年に複数回の配当を行うことを奨励する。
- 上場廃止の監視を強化し、業績不振で財務的に不安定な企業を排除する。
- A株市場に対する保険会社や年金といった中長期資金の流入を促進する。
さらに当月には、本土投資家を対象として上海・香港ストックコネクト(上海証券取引所と香港証券取引所の相互間で行われる人民元建て上場株式の取引)を通じて購入した香港上場株式の配当金の20%課税免除を検討しているという報道が流れました。
中国株の多くは割安なバリュエーションで取引されていますが、バリュエーションを高める上で障害となる要因には、主として規制や地政学的リスクや株主還元の少なさなどがあります。株主還元が最小限に留まっているなら、そうした企業は数年前の日本企業のような典型的なバリュートラップ(割安のわな)銘柄でしかありません。実際、中国の高配当銘柄は過去2年間でみてもパフォーマンスがきわめて好調です。また、すべての企業が規制や地政学的リスクにさらされているわけではなく、大半は重大な地政学的リスクはないというのが当ファンドの考えです。新たな施策によって企業の株主還元に対する意識を高めることができれば、バリュエーションが低い中国市場において、再び潤沢な投資機会が訪れると考えます。また、新『国家九条』はオンショア市場に関するものですが、オフショア市場(香港)もその恩恵を受けることができると考えます。ストックコネクトという制度があるため、香港株とA株は同じような投資資金の奪い合いが起こっています。よって、香港に上場する企業が株主還元を強化しなければ、投資家の関心はA株企業に奪われてしまうことでしょう。重要なのは、香港上場企業の多くは規制当局の後押しがなくても、すでに株主還元の強化を積極的に進めているということです。
誤った判断は景気上昇期に下され、正しい判断は景気下落期に下される
ここで世界最大級のモバイルゲーム会社であり、中国のメッセンジャーアプリ「WeChat(微信)」を運営しているTencent Holdings(中国/メディア・娯楽)を取り上げたいと思います。当ファンドは2022年9月の月次報告書で同社について、「最悪期はまもなく過ぎ去る」と述べました。この予測通り、同社の株価は2022年10月に底を打ち、業績は2022年以降全事業部門において着実に回復しています。さらに注目すべきなのは、利益率の大幅な改善です。2024年第1四半期の売上高は前年同期比6%増でしたが、非IFRS営業利益(株式報酬と若干の調整を除いた営業利益)は前年同期比30%増の約580億人民元となりました。これは強力なコスト削減努力に加え、WeChat動画アカウント(視頻号)の広告、動画アカウントでのライブストリーミングを通じた電子商取引の手数料、企業向けSaaS(サービスとしてのソフトウェア)製品など、より高い収益を生み出す事業に注力したためと考えられます。同社は2024年3月に、2024年の配当目標を前年同月比42%増の320億香港ドルに設定し、自社株買いも1,000億香港ドルに倍増すると発表しました。3月末時点の同社の時価総額に基づくと、総株主還元利回りは約5%となり、日本企業の現状と比較してもまずまずの数字です。
ではなぜ同社の収益性と株主還元はこれほど大幅に改善したのでしょうか。その答えはこの段落の表題の通り、誤った判断は景気上昇期に下され、正しい判断は景気下降期に下されるからです。あらゆるものが素晴らしく見える強気市場では、企業は貪欲になり、どんなコストをかけてでも成長のための投資を行います。そのため判断を誤り、資本配分が不適切になることもあります。しかし景気下落期に入ると、それまでの誤った資本配分が裏目に出てしまい、企業は過剰な従業員、採算性の低いプロジェクト、余剰在庫、低稼働の工場、さらに悪いことに、多額の負債を抱えてしまうことがあります。企業がこうした状況を乗り切るためには、解雇、不採算プロジェクトの削減、在庫の一掃、資産の売却、債務返済など、痛みを伴う対策を選択しなければなりません。そうすると一部の企業、特に債務比率の高い企業は生き残ることができません。このような局面では、企業は収益性とキャッシュフローによく注意を払うようになるため、生き残ることができた企業は、より収益性の高い体質とより優位な立場を手にすることになります。これがまさにTencent Holdingsに起きたことなのです。実は、当ファンドの保有銘柄であるMakeMyTrip、Trip.com Group(中国/消費者サービス)といった旅行関連企業もコロナ禍期間とその後に、すでにそうした停滞期を経ています。多くの中国企業は、これからがそうした期間を経験する番だと考えます。中国企業の多くは長年にわたって誤った資本配分を行っており、とりわけ不動産セクターはその傾向が著しいため、今こそ気を引き締めて軌道を修正し、効率性改善に注力する時だと考えます。
2月から当月にかけて、調査対象企業のファンダメンタルズが安定し、効率性と株主還元を重視する姿勢が強まったと判断したことから、当ファンドは香港・中国銘柄の組入比率を継続的に引き上げました。中国経済は減速していますが、企業の多くは引き続き一桁台後半以上の売上成長が可能だと考えています。過去の中国経済の成長率と比べるとかなり低いように思えますが、経済が一定程度成熟し、成長が鈍化しているので、ある程度の低下は避けられません。市場ではバリュエーションの大幅な見直しが進み、今では新たな現実を反映した状態となっています。企業の売上成長率がたとえ「わずか」10%でも、効率と利益率の一貫した改善、適正な自社株買いの効力を利用すれば、利益の成長率は10%より高く保つことが可能だと考えます。こうした取り組みの状況とバリュエーションの妥当性を組み合わせてみれば、長期的には非常に優れたリターンを生み出すことができます。
年初来でみると、MSCI中国指数のリターンは日本円換算で18.6%の上昇となり、TOPIXを上回っています。当ファンドにとって、香港・中国銘柄の組み入れは、2023年はパフォーマンスに対してマイナス要因だったのが、2024年はプラス要因に変わっており、とりわけ日本市場が横ばい推移に移行し始めた前月以降はその傾向が顕著になっています。市場が異なれば時期によってパフォーマンスも異なるため、当ファンドは投資対象国を分散し、リレーのように順次入れ替えています。短期的にみると、こうした手法によって国ごとの弱みが相殺され、パフォーマンスが安定します。こうした手法を一貫して採用することで、当ファンドは長期的に平均以上のパフォーマンスを上げるよう努めています。
2024年4月の運用コメント
株式市場の状況
<⽇本の株式市場>
2024年4月、日本株式市場の代表指数であるTOPIX(配当込み)は前月末比0.91%下落し、日経平均株価は前月末比4.86%の大幅下落となりました。
月前半は利益確定売りや、⽶連邦準備制度理事会(FRB)高官の年内利下げ先送り示唆に伴い米長期金利上昇が懸念され、米国株式市場の下落を招き、日本株式市場は上値を抑えられました。月半ばには米CPI(消費者物価指数)の市場予想を超える上昇や半導体関連企業の大幅下落、また中東情勢の悪化などから日経平均株価は一時37,000円を割り込みました。月後半には中東情勢の落ち着きから買い戻しの動きが見られ、日経平均株価は38,000円台を回復しました。26日まで開かれた日銀金融政策決定会合では緩和的な金融政策の維持が決定され、日本が祝日だった29日にドル円相場は一時160円台へ急伸し約34年ぶりの高値を更新しました。しかしながら、その後一転して154円台まで大きく円高に振れ、市場では政府による為替介入が行われたとの観測が広がりました。
<アジアの株式市場>
当月、アジア株式市場はまちまちの値動きとなりました。⽇本を除くアジア市場に使⽤される⼀般的な指数であるMSCIアジア(⽇本を除く、米ドル建て)指数は、中国、香港、シンガポールなどに牽引される形で前月末比1.26%上昇しました。当月パフォーマンスが振るわなかった市場は、インドネシア、韓国、フィリピンなどでした。米国のインフレ率が予想を上回ったことで、米国の金利に対する投資家の見方は「高金利の長期化」シナリオにシフトし、成長株を中心に下落しました。
ナスダック総合指数は4.41%下落し、アジアのテクノロジーセクターにも大きな影響を与えました。韓国市場はテクノロジーセクターに対するエクスポージャーが高いことから、低調に推移しました。
ASEAN市場はインドネシア、フィリピン、タイを中心に全般的に低迷しました。米ドル高の影響から、これらの市場で為替変動とインフレ圧力に対する懸念が高まりました。インドネシアは自国通貨の下支えを狙って唐突に政策金利を0.25%引き上げ、6.25%としました。
一方、中国市場と香港市場は、政策支援、業績回復期待、割安なバリュエーションに後押しされ、堅調に推移しました。不動産セクターとインターネットセクターに投資家の関心が集まりました。
インド市場は前月の調整後、中小型株の力強い反発に牽引され、上昇基調を取り戻しました。インドの国政選挙は当月半ばに始まり、6月前半の開票まで1か月半あまり続きます。
ファンドの運⽤状況
当⽉、当ファンドのパフォーマンスは前⽉末⽐3.39%の上昇、参考指数のMSCI AC Asia Index(円ベース・配当込み)は同2.79%の上昇となりました。
当⽉パフォーマンスにプラスに貢献した銘柄は、Lemon Tree Hotels(インド/消費者サービス)、Tencent Holdings(中国/メディア・娯楽)、Hanwha Aerospace(韓国/資本財)などでした。一方、サンリオ(一般消費財・サービス流通・小売り)、MediaTek(台湾/半導体・半導体製造装置)、アシックス(耐久消費財・アパレル)などがマイナスに影響しました。
当月に入って、マクロリスクが再び注目されるようになりました。米国経済の底堅さとインフレの常態化によってFRBが利下げに転じる可能性が低下する一方で、イランがイスラエルとの戦闘に直接関与するなど、中東の紛争がエスカレートしました。この状況を2022年の市場低迷期と似ていると見る向きもありますが、当ファンドの見方は少し違います。
- 2022年のインフレ率が非常に高かったのは、コロナ禍でスタグフレーション(高インフレ下の景気低迷)を主因とするサプライチェーンの混乱や、またロシアが突如ウクライナに侵攻したことが原因であること。
現在、インフレ率は米国経済の底堅さを背景に、FRBの目標値である2%を依然上回っているものの、沈静化してきているのが実情です。 - 2022年は金利がほぼゼロの状態から急激に引き上げられたのに対し、現在は比較的高い水準で推移していること。
2022年の金利ショックは現在よりはるかに甚大でした。 - 2022年は多くの業界が在庫サイクルの底にありました。コロナ禍のサプライチェーンの混乱は、2022年に新型コロナウイルス感染症が収束の兆しを見せたことで、過剰発注を引き起こし、最終的には在庫積み上がりの要因となったこと。
当時は多くの企業が業績の大幅悪化に苦しんでいましたが、現在は在庫がほぼ正常化し、企業の収益も改善しています。
アジアに限って言えば、2022年には見られなかった好材料がいくつかみられます。
- 日本がコーポレート・ガバナンス改革を加速させており、韓国や中国など他国も追随の姿勢を見せていること。
- 半導体業界が2022年には景気循環の後退期にあったが、現在は回復初期にあること。
AI(人工知能)投資がまだ初期段階にあるため、このアップサイクルは数年にわたって続くと考えます。 - 総体的にみると環境は依然芳しくないものの、中国経済が継続的にロックダウンを実施していた2022年と違って経済活動を再開していること。
現状で最大のテールリスク(まれにしか起こらないはずの想定外の暴騰・暴落が実際に発生するリスクのこと)は、中東の紛争が拡大し、世界の石油の約3割、世界の液化天然ガス(LNG)の約2割が通過するホルムズ海峡の交通が寸断されることです。
しかし、イランも含む湾岸諸国はいずれも同海峡を通じて石油を輸出していることから、影響は甚大であるにしても発生確率はきわめて低いと考えられます。イランはホルムズ海峡経由で主要顧客である中国に石油を輸出しているので、単純にみて本格参戦のリスクは大き過ぎるでしょう。
では現状のリスクにどう対処していけばよいのでしょうか。当ファンドの戦略は決して変わりません。強靭で耐久力に富み、経営者が効率的に資本配分を行っている企業を探し出し、バリュエーションが割安な機会を見計らって企業へ投資します。最高の銘柄を探して最も割安な価格で購入することが、日々の目標です。逆境に耐える力があり収益性の高い銘柄をバリュエーションの割安な時点で購入できれば、どんな外的ショックでも乗り切ることができると考えます。そのために何よりも大切なのは銘柄の選定であり、銘柄選びを誤れば、他の方法で埋め合わせることは不可能です。銘柄選定についてはこれまで幾度となく取り上げているので、今回はリスク管理の他の側面、ポートフォリオの構成とポートフォリオの組み換えの2点について触れたいと思います。
ポートフォリオの構成
当ファンドは25~40社という比較的少数の銘柄を厳選してポートフォリオを構築しています。日本とアジアへ投資する主な利点は、その投資対象の広さです。多くのアジア市場で事業を展開しているグローバル企業だけではなく現地企業も組み入れているため、25~40銘柄程度でも十分に分散投資が可能であると考えます。さらに銘柄の選定にあたっては、互いの相関性が低く、他社の動向から影響を受けにくい投資先を選ぶようにしています。投資対象となる銘柄はきわめて幅広く、必要なのは25~40銘柄と少ないため、選別は容易です。また、保有銘柄を増やしても、必ずしもリスクが減るわけではないと考えます。なぜなら、保有銘柄が増えれば増えるほど、それぞれの銘柄に関する調査の時間が少なくなりますし、ポートフォリオをシンプルに保ち、リスク要因や銘柄間の相関性を理解しやすくした方が良いと考えるためです。2023年12月の月次報告書で取り上げた通り、当ファンドの保有銘柄は大まかに以下のように分類できます。
- 新興国銘柄 – インドとインドネシアは世界の新興国の中でも最も有望な市場であると考え、MakeMyTrip(インド/消費者サービス)、Bank Mandiri(インドネシア/銀行)などを組み⼊れています。
- テクノロジー関連銘柄 – 世界の主要な製造拠点として、アジアにはテクノロジー関連銘柄について新たな投資機会があると考え、半導体銘柄だけでなく、富士フイルムホールディングス(テクノロジー・ハードウェアおよび機器)、SK hynix(韓国/半導体・半導体製造装置)といったヘルスケア、ファクトリーオートメーション、再生可能エネルギー関連銘柄も組み入れています。
- 消費者動向関連銘柄 – 日本や韓国といった国々は数十年にわたって国際競争力のある消費財を作り続けてきたことから、今後はアジア諸国の文化発信力の拡大に伴って音楽やアニメキャラクターといった文化関連商品の輸出を拡大すると考え、アシックス(耐久消費財・アパレル)、サンリオ(一般消費財・サービス流通・小売り)といった銘柄を組み入れています。
- インフレ受益銘柄 – 日本ではインフレが進行しており、インフレと金利が引き続き世界的なリスクとなる見込みであることから、こうした動向から恩恵を受ける銘柄、例えば三菱商事(資本財)や三菱UFJフィナンシャル・グループ(銀行)などを組み入れています。
現状の中東における地政学的リスクに関しては、2023年10月の月次報告書で取り上げた通り、⽯油開発・⽣産関連銘柄を組み⼊れ、さらに総合商社を通じて幅広いコモディティへの投資も⾏っています。金利の影響に関しては、銀行、保険会社など、日本の名目金利上昇の恩恵を受ける企業の組入比率を高めに設定しています。バランスの取れたポートフォリオを構成し、国内外の幅広い株価上昇要因を捉えることが、高いリスク調整後リターンを長期にわたって確保することに役立つというのが当ファンドの考えです。
当ファンドが最優先で取り組んでいるのは資本の保全です。したがって、ポートフォリオを組む際に最も重視しているのは、リスクを低く保ったままでリターンを上げられる確度はどの程度かということです。アップサイドが大きいと予想されるもののリスクが高い銘柄の組入比率は低く設定しています。確実性を重視する姿勢は、当ファンドの銘柄選定の理念、すなわち競争に負けない強力な企業を選定するという考え方と軌を一にしています。そのため組入上位銘柄は、業界を代表する大企業が多いです。とはいえ、中小型株も組み入れていないわけではないので、それについては今後の月次報告書で取り上げる予定です。
ポートフォリオの組み換え
当ファンドの日々の目標は、最高の銘柄を探して最も割安な価格で購入することです。そのため保有銘柄と組入候補銘柄の比較を定期的に行い、ポートフォリオの組み換えを行っています。ポートフォリオを随時更新することで、深刻なリスクを回避することができると考えます。当ファンドは2023年1月の月次報告書で、中国のエクスポージャーを抑えているとお伝えしました。経済再開に対する期待が現実化したあと、保有する中国銘柄の魅力が相対的に低下すると考えたからです。それは結果的に正しい判断でした。当ファンドはマーケット・タイミングではなく、最良の銘柄を割安な価格で投資することを重視しています。さらに先日は他社に先駆けて株価が上昇し、これ以上は上昇が望めなくなった銘柄を数社売却し、利益を確定しました。その1社がアドバンテストです。株価が大幅に上昇していましたが、他の保有銘柄と比較すると投資魅力が低下したと判断し、2月後半に売却に踏み切りました。一方、日本の不動産セクターに対するエクスポージャーを増やしましたが、これは日本の実質金利が引き続きマイナスで推移するため、同業界にとって有利であると考えたためです。同業界はますます不安定化する国際情勢の中にあって、しっかりと対応できるだけの耐久性を備えていると考えます。当月の半導体関連銘柄のように株価の上昇余地が減ると下振れリスクに目が向きやすくなるのは当然と考えます。ポートフォリオを随時更新することで、割安なバリュエーションで投資し続け、底堅いパフォーマンスを維持したいというのが当ファンドの意向です。
割高な水準まで上昇した銘柄の売却による利益確定は別として、時には見込み違いで失敗することもないわけではありません。もちろん間違いに気づいた場合、その時点で売却します。不安を感じたために売却して他の銘柄に切り替えることもよくあり、その一例が2023年5月に売却したオリンパスです。当ファンドは同社が内視鏡分野で主導的地位につけていることを好感していましたが、同社は米食品医薬品局(FDA)から複数回にわたって警告を受け、2023年には想定外のFDA関連対応費用が発生すると発表しました。同社の強みが消えたわけではないというのが当ファンドの見方でしたが、問題の深さや解決に要する期間について確信が持てないと感じました。一般に、保有銘柄が短期的に下落することは避けられないことなので、それほど心配はしていません。しかし、下落度合いとその期間については見通しを立てたいと思っています。投資先は無数にあり、ファンドの保有銘柄数も限られているため、どの銘柄を保有するにしても、機会費用は相当なものになります。オリンパスについては十分な見通しが立たなかったため、売却して他の銘柄と入れ替えました。
総括すると、当ファンドは以下の方法でリスクを管理しています。
- 適正な銘柄選定
- 相関性の低い銘柄の選定による少数精鋭型のポートフォリオ構成と、それを通じたリスク要因の明確化
- 銘柄の随時入れ替えることにより魅力的なバリュエーションの銘柄によるポートフォリオ構成
当ファンドは⽇本・アジアの株式と投資対象が広く、前述のリスク管理措置を効果的に実行することができると考えます。
2024年3月の運用コメント
株式市場の状況
<⽇本の株式市場>
2024年3月、日本株式市場の代表指数であるTOPIX(配当込み)は前月末比4.44%上昇し、日経平均株価は前月末比3.07%の上昇となりました。
当月の日本株式市場は、月前半は前月から引き続き半導体関連銘柄の上昇などが相場をけん引し、日経平均は史上初となる4万円台に到達するなど堅調な推移となりましたが、月半ばにかけては米国半導体関連銘柄が下落した影響や、日銀のマイナス金利政策解除を示唆する報道、春季労使交渉(春闘)での高い賃上げ実現への期待の高まりなどから日銀の金融政策正常化への思惑が広がって円高が進行したことなどが重しとなり、下落しました。月後半にかけては、日銀が金融政策決定会合でマイナス金利政策の解除や長短金利操作の撤廃、上場投資信託(ETF)の買い入れ終了などを決定したものの、当面は緩和的な金融環境が継続するとの見通しが示されたことなどを受けて円安進行とともに上昇し、最終的に前月末を上回る水準で取引を終えました。
<アジアの株式市場>
当月、アジア株式市場はまちまちの値動きとなりました。⽇本を除くアジア市場に使⽤される⼀般的な指数であるMSCIアジア(⽇本を除く、⽶ドル建て)指数は、台湾、韓国、シンガポールなどに牽引される形で前月末比2.58%上昇しました。テクノロジーセクターは引き続き堅調な値動きを見せ、代表的な銘柄であるTaiwan Semiconductor Manufacturing Company(台湾/半導体・半導体製造装置)の株価は過去最高水準に達しました。AI(人工知能)に対する投資家の期待感は、NVIDIA社(米国)がGPU(Graphics Processing Unit、画像処理装置)技術に関するカンファレンス「GPU Technology Conference 2024」で最新GPU「Blackwell GPU」を発表したことでさらに高まり、AI関連事業を展開するアジアのテクノロジー企業、特に台湾銘柄と韓国銘柄の株価を押し上げました。
韓国市場ではテクノロジーやAIに対する期待感に加え、政府の「企業価値向上プログラム」が投資家の関心を集めたことも追い風となりました。同プログラムには企業経営陣にコーポレートガバナンス、ROE(株主資本利益率)、株主還元の改善を促すことで、最終的に韓国企業の評価を向上させる効力があるというのが一部投資家の見方です。
中国政府が発表したマクロデータは予想を上回る内容でしたが、市場が景気回復の持続性に対して慎重姿勢をとったことから、当月中の株式の上昇は小幅に留まりました。香港市場の当月のパフォーマンスはアジア市場の中で最低水準でしたが、これは不動産セクターとヘルスケアセクターの低迷が原因と考えます。
インドでは、規制当局が中小型銘柄の流動性とバリュエーションに懸念を示したことを受け、当該銘柄の株価が調整しました。しかし同国の大型銘柄はアウトパフォームし、中小型銘柄の低迷を相殺する形となりました。
ファンドの運⽤状況
当⽉、当ファンドのパフォーマンスは前⽉末⽐5.80%の上昇、参考指数のMSCI AC Asia Index(円ベース・配当込み)は同3.96%の上昇となりました。
当⽉パフォーマンスにプラスに貢献した銘柄は、MakeMyTrip(インド/消費者サービス)、Taiwan Semiconductor Manufacturing Company、三菱商事(資本財)などでした。一方、Lemon Tree Hotels(インド/消費者サービス)、KB Financial Group(韓国/銀行)、Indofood CBP Sukses Makmur(インドネシア/⾷品・飲料・タバコ)などがマイナスに影響しました。
当ファンドは日本とアジア各国の株式を投資対象としているため、世界屈指の急成長を遂げているアジアという地域ならではの多様な投資機会を柔軟に捉えられるという強みがあります。いくつか例を挙げるだけでも、AI需要拡大の恩恵を受ける半導体企業から、日本独自の総合商社、世界的な人気を誇るエンターテインメント関連企業、インドでの旅行需要拡大の恩恵を受ける予約プラットフォームやホテル、資金調達コストがきわめて低いインドネシアの大手銀行まで多岐にわたります。また、投資対象が広いため、見込みの少ないと考えられる市場から撤退し、有望と考えられる投資対象に集中できるという利点もあります。当ファンドは新規銘柄の組み入れにあたり、1) ポートフォリオの潜在リターンを拡大する、2) 全体的なリターン特性を著しく悪化させることなくポートフォリオのリスク全般を分散するという目標のうち、最低でもどちらか、できれば両方を達成したいと考えています。互いの相関性が低く、他社の動向から影響を受けにくい投資先を選定し、ファンドのパフォーマンスを着実に向上させたいというのが当ファンドの意向です。さて、韓国は2023年、当ファンドのパフォーマンスに大きく貢献した市場であることから、運用担当者数名が当月に同国へ出張し企業調査を行いました。韓国は半導体の製造拠点として重要ですが、当ファンドでは半導体関連銘柄の投資機会は日本や台湾の方が潤沢であるという考えから、韓国の半導体銘柄にそれほど重点を置いていません。それよりはむしろ、半導体市場との相関性が少ない他の投資対象に注目しています。しかしこのところ、韓国ではこれまで調査してきたテーマとまったく異なる投資機会をもたらす可能性のある事態が起きています。
韓国の企業価値向上プログラム
韓国の尹錫悦大統領は2024年1月、韓国取引所の開場式に出席し、韓国株式市場はきわめて過小評価されていると述べました。また2月には韓国金融委員会(FSC)が日本の東京証券取引所の改革と同様に、上場企業のバリュエーション向上を目的とした「企業価値向上プログラム」の概要を公表しました。
ここ数年、韓国の個人投資家による株式市場への参加が大幅に増加しています。個人投資家の数は2019年の約600万人から2022年には約1,400万人に増加しており、これは韓国の有権者数のおよそ3分の1に相当します。一方、2021年には家計資産全体に占める不動産など非金融資産の比率が60%を上回りました。ちなみに、この比率は日本ではわずか39%、米国では29%に過ぎません。資産が非金融資産に集中すると、家計は物件価格の変動といったシステミック・リスクにさらされます。そのため、韓国政府には韓国市場のパフォーマンスを改善し、家計資産をより多く金融資産に振り向けたいという意向もあると考えます。
韓国市場のパフォーマンス低迷は、「コリアディスカウント」と呼ばれる慢性的なバリュエーションの低さに起因しています。Goldman Sachs社(米国)によると、2024年2月上旬の時点で韓国株の70%近くがPBR(株価純資産倍率)1倍を下回る水準で取引されています。当ファンドは、1) 韓国企業の多くが景気循環の影響を受けやすい業界に属していて、特に中国との熾烈な競争に直面していること、2) 地政学的リスクにさらされていること、3) コーポレートガバナンスが全般的に好ましくなく、株主還元率が低いことが、こうしたバリュエーションの低さの要因となっていると考えます。政府が取り組もうとしているのは、このうち3番目の問題です。企業価値向上プログラムが発表される前も、アクティビストが経営陣に積極的に提言を行う事例は増加していました。そうした提言が通る場合もあり、例えばSM Entertainment社(韓国)では創業者の李秀満氏が退任を余儀なくされるなど、市場ではコーポレートガバナンスの改善に向けた機運が高まっています。
しかし、「コリアディスカウント」の根幹に横たわっている問題はきわめて複雑なものです。例えば、韓国は相続税率が非常に高く、最も高い場合は60%に上ります。Samsung Electronics社(韓国)の李健煕元会長が亡くなったあと、相続人が総額12兆ウォン以上の相続税を支払うことになったという報道が2021年に流れました。課税額が多額に上るため、支配株主には株価を低水準に保ち、相続税評価額を下げることで納税額をできるだけ抑えたいという気持ちが働きます。多くの場合、支配株主は配当を通じて現金を受け取る代わりに、別の方法で上場企業から現金を持ち出し、他の株主の利益を著しく損なっています。例えば「サービス」を提供する別会社を設立し、上場会社に料金を請求することもあり、その一例がSM Entertainment社です。このように、問題は証券取引所の改革だけで解決するほど単純なものではなく、政府が様々な側面から首尾一貫した取り組みを行わなければ決して解決できないものと考えます。実は、相続税改革は尹大統領の選挙公約の一つです。そして相続税以外にも、改革を通じて根本的に解決しなければならない問題が別にあると考えます。
企業価値向上プログラムが発表されたあと、自動車メーカー、銀行、コングロマリットといったPBRの低い銘柄の多くで、株主還元改善に対する期待感から株価が上昇しましたが、この試みはすぐに頓挫しました。Samsung Electronics社とSamsung Biologics社(韓国)の株式を保有し、Samsungグループの事実上の持ち株会社であるSamsung C&T社(韓国)は、3月に開催された株主総会でアクティビストから出された株主還元の大幅拡大要求を拒否しました。Samsung C&T社も韓国の他のコングロマリットも、保有株式の税引き後市場価値に大幅なディスカウントを適用した水準で取引されています。これは「コリアディスカウント」の典型例です。アクティビストはSamsung C&T社に株主還元率の引き上げを求めましたが、この要求は行き過ぎとみなされ、国民年金機構を含む株主の大多数が反対票を投じました。これは企業価値向上プログラムにとっては残念な出来事だというしかありません。当ファンドは韓国コングロマリットのバリュエーションの低さに注目していましたが、問題の複雑さを認識していたため、組み入れを行っていませんでした。そうした企業の持株会社は後継問題や財閥の利害と直結しており、政府の改革だけですぐに状況が変わると期待するのは非現実的です。日本の株式市場は現在大きく改善していますが、その発端は10年以上前のアベノミクスにあると考えられ、そこから上昇基調に乗るまでにはかなりの時間を要しました。当ファンドは韓国市場で有望なのはK-POPや美容製品といった革新的な製品やサービスを提供する高成長企業であると考えていたため、PBRの低い銘柄にはあまり目を向けてきませんでした。企業価値向上プログラムが進展すれば、PBRの低い銘柄の一部に投資機会が広がるでしょう。重要なのは、当ファンドの現在の保有銘柄と相関性が低いところに機会が生まれるということです。当ファンドは今後も調査を続け、状況を注視しながら投資を行っていく所存です。
日本では日銀が方向転換
日本銀行は大方の予想通り、当月の金融政策決定会合でマイナス金利政策を解除しましたが、緩和的な金融環境を維持すると表明しました。当ファンドはこれを日本経済の正常化の始まりと捉えています。名目金利はここから上昇に転じるかもしれませんが、日本が最終的にインフレ局面に入れば、実質金利はマイナスに留まります。したがって当ファンドでは、日本市場に対する楽観的な見方を維持しています。
2024年2月の運用コメント
株式市場の状況
<⽇本の株式市場>
2024年2月、日本株式市場の代表指数であるTOPIX(配当込み)は前月末比4.93%上昇し、日経平均株価は前月末比7.94%の大幅上昇となりました。
当月の日本株式市場は、月前半はFOMC(⽶連邦公開市場委員会)の内容を受け早期の米利下げ期待が後退し一進一退の動きで推移しましたが、月半ばから後半にかけては内田日銀副総裁がマイナス金利解除後も日銀は緩和的な金融環境を維持するとの認識を示したことや、生成AI(人工知能)向け半導体需要の増加が期待される米国で半導体関連企業の株価上昇が続き、日本の半導体関連企業にも資金が集中したことから、続伸しました。22日には日経平均株価は39,098.68円で終え、約34年ぶりに最高値を更新しました。その後の日本株式市場の推移は緩やかだったものの、月末まで日経平均株価は3万9,000円台を維持したまま当月の取引を終えました。
<アジアの株式市場>
当⽉、アジア株式市場は力強く反発しました。⽇本を除くアジア市場に使⽤される⼀般的な指数であるMSCIアジア(⽇本を除く、⽶ドル建て)指数は、中国、韓国、台湾などに牽引される形で前⽉末⽐5.62%上昇しました。中国市場が堅調に推移したのは、マクロデータが市場予想を上回ったことや、旧正月の国内観光収入がコロナ禍前の水準を上回ったことなどによるものでした。バリュエーションの割安感と政府系ファンドによる買い支えも、中国株式市場の底打ちに対する信頼感の増大要因となりました。
韓国では、政府が「企業価値向上プログラム」を導入し、PBR(株価純資産倍率)の低い企業に対策を講じるよう促したことを受けて、株式市場が上昇しました。同プログラムは日本で東京証券取引所などが進める市場改革と同様、企業経営陣にコーポレートガバナンス、ROE(株主資本利益率)、株主還元の改善を促すことで、企業のバリュエーション向上を狙ったものです。
また、当月はインドネシアで大統領選挙が行われました。過半数の票を獲得する候補がなく、6月に2回目の投票が実施されると予想されていましたが、世論調査機関4社の集計によると、プラボウォ・スビアント氏が初回投票で約58%の票を獲得し、過半数に到達して当選を確実にしました。新政権の正式発足は10月ですが、短期的には現行の政策方針に大きな変更はないというのが大半の投資家の見方です。
ファンドの運⽤状況
当⽉、当ファンドのパフォーマンスは前⽉末⽐9.74%の上昇、参考指数のMSCI AC Asia Index(円ベース・配当込み)は同7.08%の上昇となりました。
当⽉パフォーマンスにプラスに貢献した銘柄は、Hanwha Aerospace(韓国/資本財)、三菱商事(資本財)、サンリオ(一般消費財・サービス流通・小売り)などでした。一方、ソニーグループ(耐久消費財・アパレル)、丸紅(資本財)、Control Print(インド/テクノロジー・ハードウェアおよび機器)などがマイナスに影響しました。
2023年12月、山本由伸投手のロサンゼルス・ドジャースへの移籍が発表されました。オリックスへの譲渡金は5,062万5千ドル(約72億円=為替レートは入団合意時)になる見通しです。12年で総額3億2,500万ドル(約465億円)という契約金は、おそらく投手としての最高額でしょう。スポーツビジネスは基本的にセレブリティ、すなわち有名人の人気にあやかったビジネスです。ファンたちは競い合ってチケットやグッズなどを購入し、売り上げに大きく貢献します。2023年9月の月次報告書でお話しした通り、インターネットでコンテンツを配信できるようになったことで、世界中の人に情報を届けることがこれまでよりはるかに容易になりました。よって、こうしたビジネスの収益力は大幅に拡大していると考えます。有名になることはいつの時代でも素晴らしいことですが、今はこれまでにない最高なタイミングと言えるでしょう。
ではどうすればセレブリティに投資できるのでしょうか。さらに言えば、有名人の収益力を生かせる優良企業はどうすれば見つかるのでしょうか。当ファンドは防弾少年団(BTS)、SEVENTEEN、LE SSERAFIM、NewJeansといったK-POPグループが所属し、さらに2021年にはジャスティン・ビーバーやアリアナ・グランデが所属しているIthaca Holdings社(米国)の買収した、HYBE(韓国/メディア・娯楽)に投資してきました。しかしセレブリティたちは有名になると交渉力を得て、より高い給与を要求したり、また仕事を選り好みしたり、働く意欲が低下する可能性があります。そしてやがては年を取り、引退していきます。したがって、そうした心配のない有名人を抱えるほうがはるかに良いということになります。その最たる例が2023年10月に組み入れを開始したサンリオで、同社は「ハローキティ」、「シナモロール」、「クロミ」、「ポムポムプリン」、その他知財を多数所有しています。
理想的なセレブリティ
ハローキティは素晴らしいセレブリティです。いつまでも老いることがなく、誕生から50年にわたって世界中の幅広い年齢層の消費者から愛され続けています。また、「ハローキティは仕事を選ばない」ことでも有名です。アルコールやタバコのような不健康なイメージがある商品を除けば、ほとんどどんな商品ともコラボレーションできます。ティッシュペーパーやビスケット、機動戦士ガンダム、米国のプロ野球チームとのコラボ、さらにTVアニメ「クレヨンしんちゃん」への出演など、その守備範囲の広さは驚くばかりです。もちろん、ハローキティが賃上げを要求することもありません。
理想的なビジネス
サンリオのビジネスモデルはきわめてシンプルです。玩具など一部商品を直接販売し、さらに他社からキャラクターの知財を自社製品に使用したいという要請を受けた場合はライセンスを供与し、当該商品の売上の一部から使用料を徴収しています。例えばティッシュペーパーの場合、箱にハローキティが描かれていても、ティッシュペーパーの品質とは全く関係がありません。しかし消費者はハローキティがついているからその商品を購入するので、メーカーは自ら進んでサンリオにキャラクター使用料を支払い、箱にハローキティを印刷するのです。同社は以下の点で当ファンドが考える優れたビジネスモデルの基準を満たしています。
- 多額の資本を必要とせず、労働力もそれほど必要ではないこと。
- 最小限の投資で事業を拡大できること。ほぼハローキティや他のキャラクターのデザインをライセンス商品に合わせてデザインし直すだけでよい。
- 消費者のハローキティやその他キャラクターに対する思い入れが、きわめてユニークな資産であること。サンリオの二次元キャラクターほど描きやすいものはおそらく他になく、誰もが同じような二次元のキャラクターを描けそうな気がする。人々はそれでもサンリオのキャラクターを愛しているのであって、そうした意味から考えると、サンリオが保有している無数の資産は決してまねのできないものである。
とはいえ、サンリオの歴史に苦難がなかったわけではありません。欧米では2000年代後半にハローキティブームが巻き起こり、同社の営業利益は2014年3月期に過去最高を記録しました。ところがThe Walt Disney社(米国)が2013年に『アナと雪の女王』を発表して大成功を収めると、米国の小売店ではハローキティの棚の大半がアナと雪の女王に取って代わられました。また当時はサンリオの他のキャラクターの知名度が低く、同社の米国事業はハローキティが大黒柱でした。さらに折悪しく、創業者である辻信太郎氏の息子で当時最高執行責任者を務めていた辻邦彦氏が、会社が逆境の只中にあった2013年11月に死去されたのです。競争と非効率な経営によって、同社の営業利益は2021年3月期まで連続で減少しました。そのような中、2020年夏に辻信太郎氏の孫で当時31歳だった辻朋邦氏が社長兼CEOに就任し、「組織⾵⼟改⾰」、「構造改革の完遂」、「再成長の種まき」を3本柱として、経営の⼤転換に着手しました。例えば、若くとも幅広い経験を持つ上級管理職を外部から採用し、業績をより重視する企業文化を醸成したのです。事業面では商品の品目数を削減し、世界共通商品の数を増やしたことで、商品販売の収益性が大幅に改善しました。方向転換はいつでも難しいものですが、企業文化や構造改革の方向転換にはとりわけ困難が伴います。ですが、同社はそれをうまくやり遂げ、再建に成功しました。では、このような稀代の再建を成し遂げることができたのは何故なのでしょうか。それは、再建された事業が根本的に優れたものだったのか、それとも凡庸なものだったのかという点にあると考えます。過去10年にわたって事業が低迷していたとはいえ、サンリオのキャラクターは世界中の人々に愛されていました。そうした根本的な強みがあったからこそ、問題解決に伴う痛みは凡庸な事業を立て直すより場合よりはるかに少なくて済んだのです。同社の事業には現在、力強い勢いがあり、今後の成長が期待できると考えます。2023年4月から12月までの9ヵ月間において、売上高は前年同期比40.3%増加、営業利益率は29.5%に達しています。ここで重要なのは、成長率が世界のどの地域でみても堅調であることです。景気低迷中の中国でさえ、同社は同時期に前年同期比53%の増収を達成しています。
ハローキティは今年、誕生から50年を迎えます。世界中のファンが祝福するので、収益は堅調に拡大する見通しです。2010年代初頭のブームが一時的なものに終わってしまったことを忘れてはなりませんが、これからは好不況の波は小さくなっていくと当ファンドは考えています。これは2023年9月の月次報告書でお話した点にも通じますが、エンターテインメント知財ビジネスのあり方がインターネットの普及によって大きく変わったからです。インターネット登場以前の世界では、消費者に知財を届ける手段は、主に新聞、雑誌、小売店、テレビ、ラジオくらいしかありませんでした。一日の新聞の掲載スペースに限りがあるように、これらの媒体はすべて枠に限りがあります。そのため媒体側の交渉力が強大になり、掲載や放送を断られれば、企業は消費者との接点が完全に失われてしまいます。ハローキティは小売店でアナと雪の女王に取って代わられたことで、消費者との接点を失いました。しかし、世界は変わりました。現在では、YouTube、Instagram、X(旧Twitter)、TikTok、Netflix等を通じて知財が消費者に届けられ、eコマース(電⼦商取引)で商品が販売されます。こうしたチャネルは事実上、キャパシティに制限がありません。企業はSNS上で新しいコンテンツを発表し続けることができ、消費者はいつでも好きな時にそのコンテンツを消費することができます。したがって、知財は物理的な商品から、常に消費者と関わりあうことができるコンテンツへと変化したのです。多くの場合、他の有名人もサンリオのキャラクターを無償で宣伝しています。例えば、韓国のガールズグループBLACKPINKのジスはハローキティのファンとして有名で、自身のSNSアカウントにハローキティの商品とともに映っている写真を投稿しています。言い換えると、SNS上でファン層を開拓し、維持することがはるかに容易になったのです。当ファンドはインターネットがサンリオの世界的なファン層の拡大に大きく貢献したと考えています。同社は毎年「サンリオキャラクター大賞」というキャラクターの人気投票を行っていますが、以下はその過去6年間の総得票数の推移です。
サンリオはハローキティだけでは終わらない
サンリオの今後の成長は、世界的なファン層の拡大もさることながら、ハローキティ以外のキャラクターにも懸かっています。10年前と比較すると大幅に減少しているとはいえ、同社の収益面でのハローキティに対する依存度は未だに高いと考えます。しかし同社の収益基盤は他のキャラクターによって多様化できる可能性が高いというのが当ファンドの見方です。実際、ここ数年のサンリオキャラクター大賞の結果を見ると、シナモロール、クロミ、ポムポムプリンといったキャラクターが、ハローキティに勝るとも劣らない人気を誇っています。街を歩けば、シナモロールやクロミが特に若年層に人気であることは一目瞭然です。重要なのは、これらのキャラクターはハローキティと全く異なる特徴を持っているため、ハローキティとは別のファン層を獲得できるということです。サンリオは他キャラクターのプロモーションにも積極的に取り組んでおり、現在はハローキティを中心として他キャラクターのプロモーションする「ハローキティとなかまたち」というコンセプトを展開しています。当ファンドはこうした他キャラクターには未開拓の需要が大いにあり、同社はこのチャンスを逃さないだろうと考えています。同社のビジネスモデルは本性的に質が高く、収益源が多様化してきていることを踏まえると、同社は今後さらなる進化を遂げ、安定的に利益を生み出せる企業へと進化していくと考えています。
日本には人気キャラクターを生み出してきた長い歴史があります。スーパーマリオからハローキティ、さらに最近のすみっコぐらしやちいかわに至るまで、数えれば切りがありません。キャラクタービジネスには日本独自の文化があり、アジアの他の国々が同じような商品を作るのはきわめて困難だというのが当ファンドの見方です。またこれはK-POPにも同じことが言えると考えています。当ファンドは⽇本とアジアの株式を扱っているため、ハローキティとBTSに同時に投資できる柔軟性を備えています。当ファンドは今後も引き続き、日本と他のアジア諸国に固有の投資機会を発掘し、投資ポートフォリオに組み入れてまいります。
2024年1月の運用コメント
株式市場の状況
<⽇本の株式市場>
2024年1⽉、⽇本株式市場の代表指数であるTOPIX(配当込み)は前⽉末⽐7.81%の上昇となりました。
当⽉の⽇本株式市場は、能登半島地震の影響精査のため⽇銀が利上げを⾒送るとの⾒⽅が⾼まったことや、⽶連邦準備制度理事会(FRB)⾼官のタカ派な発⾔を受けた⽶⻑期⾦利の上昇を背景に円安が進み、⽉前半は⼤きく上昇しました。また、新NISA制度の開始による個⼈投資家の買い需要や、東京証券取引所の市場改⾰への期待感から海外投資家の資⾦も多く流⼊しました。⽉半ばから後半にかけては、利益確定の売り圧⼒や、⽶国半導体⼤⼿の業績⾒通しが市場予想を下回ったことから半導体関連銘柄を中⼼に⼀時下落基調に転じる場⾯もあったものの、最終的に前⽉末を上回る⽔準で⽉を終えました。
<アジアの株式市場>
アジア株式市場は軟調な値動きで年明けを迎えました。⽇本を除くアジア市場に使⽤される⼀般的な指数であるMSCIアジア(⽇本を除く、⽶ドル建て)指数は、前⽉末⽐5.44%下落しました。中国政府が⾦融緩和や景気刺激策などで政策的⽀援を⾏ったにもかかわらず、中国市場と⾹港市場に対する投資家⼼理は冷え込んだままでした。国内要因(不動産危機、消費低迷、⼀貫性のない規制)と国外要因(中国に対する⽶国の規制強化、紅海の海運混乱など)が、中国に対する投資意欲をさらに減退させました。
⼀⽅、台湾では、AI(⼈⼯知能)投資の加速とスマートフォン回復への期待から、テクノロジーセクターが好調な勢いを維持しました。台湾総選挙は想定内の結果で決着し、現政権を担う⺠主進歩党(⺠進党)が総統選を制した⼀⽅で、野党の台湾国⺠党(国⺠党)が議席を伸ばしました。また、第三党の台湾⺠衆党(⺠衆党)は獲得議席数こそ少ないものの、今後数年間の政策の⽅向性を左右しうる新たな政治勢⼒として台頭しました。
インドは強⼒な政府、若年層⼈⼝の多さ、⻑期的成⻑⼒といった⽀援材料に恵まれ、引き続き投資対象として投資家の注⽬を集めています。インドネシア市場では消費⽀出に若⼲陰りが⾒られ、とりわけ低価格帯商品にその傾向が⾊濃く表れました。同国では間もなく⼤統領選挙が⾏われる予定で、次期政権発⾜まで⼀時的に投資家の関⼼が向かなくなる可能性があると考えます。
ファンドの運⽤状況
当⽉、当ファンドのパフォーマンスは前⽉末⽐5.63%の上昇、参考指数のMSCI AC Asia Index(円ベース・配当込み)は同1.95%の上昇となりました。
当⽉パフォーマンスにプラスに貢献した銘柄は、MakeMyTrip(インド/消費者サービス)、Lemon Tree Hotels(インド/消費者サービス)、アドバンテスト(半導体・半導体製造装置)などでした。⼀⽅、Shenzhou International Group Holdings(中国/耐久消費財・アパレル)、Samsung Electronics(韓国/テクノロジー・ハードウェアおよび機器)、Classys(韓国/ヘルスケア機器・サービス)などがマイナスに影響しました。
2024年は史上まれに⾒る選挙の多い年で、50か国・地域で20億⼈以上の有権者が投票所に⾜を運ぶとされています。アジアでは1⽉の台湾から選挙が始まり、⼤⽅の予想通り頼清徳⽒率いる⺠進党が史上初めて3期連続で政権を担うことになりましたが、同党の獲得議席は過半数に達しませんでした。今回の台湾総統選挙は従来と様相が異なり、⺠進党と国⺠党という⼆⼤政党の争いではなくなりました。⺠衆党の柯⽂哲⽒が約360万票という無視できない数の票を獲得したのです(⺠進党の頼清徳⽒は約550万票、国⺠党の侯友宜⽒は約460万票)。単純化しすぎだと⾮難されるのを承知の上で⾔えば、中国本⼟との関係で正反対の⽴場をとる⺠進党と国⺠党と異なり、⺠衆党はより中⽴的な⽴場をとっています。この⼤きな変化は、台湾の⼈々、特に若年層が、選挙期間になるといつも話題を独占してしまう中台関係に関する論争に飽き飽きしていることを⽰しているのかもしれません。台湾の⼈々はむしろ、地域経済の改善と価格⾼騰に起因する住宅難の解消を望んでいるものと思われます。国会がねじれ状態となっていることを踏まえると、⺠衆党の姿勢は来期の政策決定に⼤きな影響を与える可能性があります。とはいえ、当ファンドの台湾における投資先は主にテクノロジー企業で、地域経済や政治は通常、そうした事業の将来を⾒通す上でそれほど⼤きな役割を果たしません。⼀⽅で、地政学は台湾では常に重要なトピックです。頼清徳⽒はかつて⾃らを「台湾独⽴のための現実的な働き⼿(務實的台獨⼯作者)」と表現しており、中国本⼟と距離を置くことに積極的であると受け取られています。しかし台湾が中国本⼟の怒りを呼び覚ますようなことをする動機はあまりなく、現状が維持されるだろうというのが当ファンドの考えです。
アジア株式市場は、⽇本市場の⼤幅な上昇と中国市場の急落で新年の幕を開けました。当ファンドは中国へのエクスポージャーをわずか5%程度に抑えて新年を迎えたため、中国市場急落の影響をほぼ回避することができました。当ファンドは⽇本を含むアジア株式に投資するファンドで、単⼀国に投資するファンドと異なり、国別配分は避けて通れない課題です。
スパークスの投資哲学は、「マクロはミクロの集積である。」というものです。当ファンドはボトムアップ・リサーチで企業調査を⾏っており、その過程でマクロデータを読むだけでは得られない広範な経済に関する貴重な知⾒を得ることができます。当ファンドではGDP成⻑率や輸出データなどを予測してどの国の組み⼊れを拡⼤するかを決めることはせず、主として個別の銘柄選定の結果として国の⽐率が決まります。
しかし、マクロデータに全く注⽬していないわけではありません。マクロデータは当ファンドにとってサーキットブレーカーの役割を果たしています。特定の国で重⼤かつネガティブなマクロイベントや政治的事件が発⽣すれば、投資縮⼩の理由となり得ます。ここで⾔うネガティブなマクロイベントとは、1〜2四半期程度の短期的な経済の低迷ではなく、危機的な出来事、とりわけ多額の負債を伴い、下落スパイラルの原因となるような出来事のことです。こうした危機の後には投資機会が多数到来することがよくありますが、経済の低迷と資産価格の下落は通貨安をもたらす可能性が⾼く、外国⼈投資家にとって、下落スパイラルは⾮常に⼿痛いものになりがちです。1997年のアジア通貨危機がその典型例です。
政治的事件が投資縮⼩の理由になることもあります。政治リスクはどの国にも存在しており、投資家はそれを乗り切らなければなりません。投資とは資本家と市場で構成されたシステムに基盤を置く活動なので、法の⽀配、政治的安定による投資の保護、事業環境の整備がいずれも重要になります。さらに、これらがどの程度満たされているかという点ばかりでなく、その⽅向性も同じように重要になります。当ファンドは、こうした点が改善している国、あるいは少なくとも悪化していない国に投資したいと考えています。その観点ではシンガポールという⾮常に⼩規模な市場を除いた場合、アジアで最⾼の法の⽀配と政治的安定性を備えているのは⽇本だと考えているため、当ファンドの第⼀の選択肢は⽇本です。また、⽇本にはグローバル企業が多数存在し、世界各地で事業を⼿がけているため、当然ながら特定の国の政治リスクが軽減されます。アジアの他の国々では政治リスクやマクロ⾯のリスクが各国各様で、それぞれが独⾃の問題を抱えています。しかし多く場合、当ファンドが選好するアジア企業の有望性は、マクロ⾯のリスクや政治リスクを上回る場合が多いというのが当ファンドの判断です。当ファンドはバランスの取れた柔軟なアプローチを採し、先進国市場と新興国市場の両⽅に投資しています。
台湾に話を戻すと、当ファンドの組⼊銘柄であるTaiwan Semiconductor Manufacturing Company(台湾/半導体・半導体製造装置)が2023年の決算を発表し、堅調なAI(⼈⼯知能)需要を受けて2024年の売上⾼は最⼤25%増を⾒込んでいるとしました。また、AI関連の収益は2027年までに収益の10%台後半を占めるところまで拡⼤し、年平均成⻑率は50%に達するという予想も発表されました。当ファンドは少し前から半導体銘柄を積極的に組み⼊れてきましたが、この発表を受けて同セクターは⼤幅に上昇しました。また、Samsung Electronics(韓国/テクノロジー・ハードウェアおよび機器)は、最上級のAIを内蔵した新型スマートフォン「ギャラクシーS24」シリーズを発表しました。その機能の⼀例を挙げると、同機種は端末に内蔵されたAIを利⽤して⾳声通話の内容を即時翻訳し、テキストとして表⽰することができます。現状AI普及の恩恵を受けているのは主に半導体企業ですが、これはインターネット黎明期ように、当該技術に不可⽋な物理的インフラの構築を担っている存在だからです。インフラ以外にも、AIは既に⼀部企業のソフトウェアや⼤テクノロジープラットフォームのバックエンドに組み込まれています。誰もが所有し、⻑時間使⽤しているスマートフォンに端末内蔵型AIが浸透し始めると、産業界に⼤変⾰が訪れ、アプリケーションやコンテンツの分野で新たな恩恵を⽣み出すかもしれません。当ファンドの組⼊柄の⼀つにMediaTek(台湾/半導体・半導体製造装置)がありますが、同社の主⼒事業はスマートフォン向けアプリケーションプロセッサの製造で、これはスマートフォンの端末内蔵型AIを動作させる上で⽋かせない部品です。Apple社(⽶国)以外のスマートフォン向けアプリケーションプロセッサ市場はMediaTekとQualcomm社(⽶国)による寡占状態にあります。またMediaTekは近年、ハイエンドスマートフォン向けのアプリケーションプロセッサ市場への参⼊を続けています。当ファンドは、同社が端末内蔵型AI普及の恩恵を初期に受ける企業の⼀⾓を占めると考えています。同社はスマートフォン以外にも幅広い製品群を⼿がけており、Wi-Fi 7や⽶国のクラウドコンピューティング企業から引き合いがきているデータセンター⽤ASICチップ設計事業などを通じて製品アップグレードの恩恵に浴することができる⽴場にあります。同社については、今後の⽉次報告書で詳しく取り上げたいと考えています。全般的に、AIは未だ普及の初期段階にある技術であることから、半導体セクターの有望性が失われることは当⾯ないと考えます。したがって問題となるのは、アジアには多種多様な半導体サプライチェーン企業が存在しており、最も恩恵を受けるのはどのサブセグメントなのかという点です。当ファンドは今後も引き続き、⽇本とアジア各国でAI普及の恩恵を受ける銘柄を発掘してまいります。
2023年12月の運用コメント
株式市場の状況
<日本の株式市場>
2023年12⽉、⽇本株式市場の代表指数であるTOPIX(配当込み)は前⽉末⽐0.23%の下落となりました。
当⽉の⽇本株式市場は、⽉前半は⽇銀の植⽥総裁と氷⾒野副総裁両名の発⾔を受けて⾦融政策修正の思惑が⾼まったことや、FOMC(⽶連邦公開市場委員会)のハト派の内容を受けて⽶⻑期⾦利が低下したことで、円⾼が進み下落しました。⽉後半は、⽇銀⾦融政策決定会合における⾦融緩和維持の決定が好感される場⾯もありましたが、年末の閑散相場もあって円⾼基調が継続する展開が重しとなり、最終的に前⽉末を下回る⽔準で⽉を終えました。
<アジアの株式市場>
当⽉、アジア株式市場は中国を除いて概ね堅調に推移しました。⽇本を除くアジア市場に使⽤される⼀般的な指数であるMSCIアジア(⽇本を除く、⽶ドル建て)指数は、前⽉末⽐3.55%上昇しました。中国市場のリターンはマイナスとなりましたが、これは中国経済の成⻑に関する懸念が拭えないためと考えます。⽉後半に中国でオンラインゲームに関する包括的な規制案が公表されたことを受け、今後こうした規制が消費者の⾏動全体に及ぶのではないかという懸念が投資家の間に広がり、その影響はオンラインゲーム関連のセクターに留まらず幅広い分野に及びました。
中国以外のアジア株式市場は、インフレと⾦利の圧⼒が緩和したことで、前⽉以上に好調に推移しました。インド市場は当⽉、企業のファンダメンタルズの底堅さ、安定政権、⻑期的な構造的成⻑のポテンシャルが好材料とみなされて市場への資⾦流⼊が続き、史上最⾼値を更新しました。
台湾市場は⽣成AI(⼈⼯知能)に対する期待感の⾼まり、スマートフォンの需要回復、データセンターの成⻑によって半導体セクターが堅調に推移したことで、2023年通年ではまずまずのパフォーマンスをみせました。
ASEAN各国市場は、国内経済の成⻑と「チャイナ・プラス・ワン(中国のみに⼯場を構えるリスクを回避するため、他のアジアの国に製造拠点を展開すること)」関連の投資に⽀えられ、底堅く推移しました。インドネシアでは2023年、海外直接投資(FDI)が増加、とりわけ鉱物セクターの川下にあたる製造業でその傾向が顕著にみられました。またマレーシアでも⽶国企業や中国企業を含む⼤⼿グローバル企業から半導体産業に対するFDI増加の動きが継続しました。
ファンドの運用状況
当⽉、当ファンドのパフォーマンスは前⽉末⽐1.96%の下落、参考指数のMSCI AC Asia Index(円ベース・配当込み)は同0.96%の下落となりました。
当⽉パフォーマンスにプラスに貢献した銘柄は、Varun Beverages(インド/⾷品・飲料・タバコ)、MakeMyTrip(インド/消費者サービス)、MediaTek(台湾/半導体・半導体製造装置)などでした。⼀⽅、NetEase(中国/メディア・娯楽)、アシックス(耐久消費財・アパレル)、Tencent Holdings(中国/メディア・娯楽)などがマイナスに影響しました。2023年のアジア株式市場は、市場によってパフォーマンスが⼆極化したことが特徴的な⼀年でした。⽶ドルベースでパフォーマンスが⾼かった市場の⼀つは台湾で、MSCI台湾指数は前年⽐31.33%上昇しました。⼀⽅、パフォーマンスが低かった市場の⼀つは中国で、MSCI中国指数は同11.20%下落しました。このように市場によって⼤きな差があったため、国別組⼊⽐率がパフォーマンスに多⼤な影響を及ぼしました。
当ファンドの2023年のパフォーマンスを決定づけたのは主に以下の要因です。
- 台湾銘柄の組⼊⽐率はそれほど⾼くありませんでしたが、同市場の主な上昇要因が半導体銘柄にあり、当ファンドが市場を問わず半導体関連銘柄の組⼊⽐率を⾼めに設定していたことがプラスに貢献しました。当ファンド組⼊銘柄のSamsung Electronics(韓国/テクノロジー・ハードウェアおよび機器)については2022年10⽉の⽉次報告書、ソシオネクスト(半導体・半導体製造装置)については2023年6⽉の⽉次報告書をご参照ください。
- インド銘柄の組⼊⽐率は2023年上半期を通してほぼ変わりませんでしたが、下半期から銘柄構成をパフォーマンスが相対的に低下した⾦融セクターから消費関連セクターに⼤幅変更したことがプラスに貢献しました。当ファンドの組⼊銘柄のMakeMyTripについては2023年8⽉の⽉次報告書をご参照ください。
- ⽇本市場(総合商社、メガバンク)と韓国市場(K-POP、メディカル・ビューティー)で個別テーマの関連銘柄がプラスに貢献しました。
- 中国銘柄が全般的にマイナスに影響しました。当ファンドは2023年1⽉時点で中国銘柄の組⼊⽐率は18.6%でしたが、同年6⽉には9.2%に縮⼩し、当⽉は5.8%となっています。
今後の運用方針
「投資の成否を左右するのは、ある業界が社会にどれほど影響を与えるか、あるいはどれほど成⻑するかを⾒極める⼒ではなく、ある企業の競争優位性、そして何よりもその優位性の持続性がどの程度かを⾒極める⼒である。」- ウォーレン・バフェット
当ファンドは強固な事業基盤を有していて、かつ経営者が効率的に資本配分を⾏っている企業を探し出し、バリュエーションが割安な時機を⾒計らい投資しています。前述のバフェット⽒の⾔葉にあるように、当ファンドは成⻑性よりも企業としての耐久⼒や競争優位性を重視しています。耐久⼒に富んだ企業であれば、たとえ企業成⻑の⾒込みが低くても、経営陣がそれを認識し、適切な資本分配を⾏っている限り、問題は無いと考えます。そうした企業は優れた買収先を探したり、割安な価格で⾃社株を買い戻すことができます。こうした点を重視することで、バリュー株やグロース株といった⾒⽅にとらわれた他の市場関係者とは⼀線を画することができるというのが当ファンドの考えです。
新興国市場
過去10年間(2014年〜2023年)を振り返ると、アジア各国市場のパフォーマンスには⼤きなばらつきがみられます。
中国は2021年まで好調でしたが、この2年でこれまでのリターンは無に帰しました。インドネシアとフィリピンはいずれも⼈⼝に占める若年層の割合が⾼く、様々な商品やサービスの普及率が低いため、リターンがいまひとつでした。しかしながら、当ファンドは新興国市場に対して慎重ながらも楽観的なスタンスを保持しています。楽観的に⾒ているのは、新興国市場が発展の初期段階にあるからで、慎重なのは中国のように事態が急変する可能性があり、さらにはGDP成⻑率の⾼さが必ずしもROE(株主資本利益率)の⾼さに結びつかないからです。株主リターンの⼤きさは、GDPや売上の伸び以外にも、収益性、コーポレートガバナンス、政治的ガバナンスといった様々な要因によって決まります。また経済成⻑の初期段階にあるからといって、その後の成⻑が⾃動的に進むわけではありません。当ファンドは新興国市場が投資家に⼤きなリターンをもたらすのはかなり稀であって、⼀般的ではないと考えています。それどころか、中国を別にしても、過去10年間で投資家に⼤きなリターンをもたらした新興国はありません。
とはいえ、アジア新興国は今後その稀有な例になり得ると当ファンドは考えています。株式投資を⾏う際に重要なのは株価上昇の起爆剤で、それは新興国市場の場合でも同様です。中国とインドの国⺠⼀⼈当たりGDPは1960年から1990年まで同程度でしたが、今では中国の⼀⼈当たりGDPはインドの数倍に成⻑しています。中国は2001年にWTO(世界貿易機関)に加盟し、世界の製造業の⼀⼤拠点へと成⻑しました。⼀⼈当たりGDPはその後10倍以上に増え、MSCI中国指数の2001年末から2021年末までのトータルリターンは約740%に達しています。株価上昇の起爆剤は起動⼨前で、特にインドにそれが当てはまるというのが当ファンドの⾒⽅です。⻑年にわたって経済改⾰を進めてきたこと、中国から他国へサプライチェーンを移⾏する必要性が⾼まっていることから、インドは中国から世界の製造業の拠点としての地位を引き継ぐ国にふさわしい⼒を持っていると考えます。ここで重要なのは、市場で資本を⼗分に調達できないため、企業経営陣の多くが資本をどう配分すれば合理的かという点を強く意識していることです。インドはこの機会を⽣かすことができれば、今後数⼗年にわたって⼒強い経済成⻑を成し遂げ、投資家にも⼤きなリターンをもたらすことでしょう。
サプライチェーンの移⾏はインドばかりでなく、インドネシアやマレーシアといった他のアジア新興国にとっても株価上昇の起爆剤になると考えます。アジア新興国市場における投資機会については今後の報告書で改めて取り上げる予定です。
当ファンドのポートフォリオ
アジアには有望な新興国市場に投資する機会がありますが、それだけではありません。先程の表からもわかるように、台湾はテクノロジーへの投資が急拡⼤したことで、過去10年のトータルリターンがすばらしい数字になりました。このことから、アジアには多種多様なテクノロジー、消費者サービス、ヘルスケア関連企業が存在し、優れた製品やサービスを世界中に販売しているということが改めて確認できます。当ファンドは⽇本を含むアジアの株式に例外なく投資できるという優位な⽴場にあり、より広い投資先候補の中から最も優れたグローバル企業を選定することができます。当ファンドが現在組み⼊れている銘柄は以下のように⼤別できます。
- 新興国銘柄- インドとインドネシアは世界の新興国の中でも最も有望な市場であると考え、MakeMyTrip、Indofood CBP Sukses Makmur(インドネシア/⾷品・飲料・タバコ)などを組み⼊れています。
- テクノロジー関連銘柄– 世界の主要な製造拠点として、アジアにはテクノロジー関連銘柄について新たな投資機会があると考え、半導体銘柄だけでなく、MediaTek、アドバンテスト(半導体・半導体製造装置)といったヘルスケア、ファクトリーオートメーション、再⽣可能エネルギー関連銘柄も組み⼊れています。
- 消費者動向関連銘柄- ⽇本や韓国といった国々は数⼗年にわたって国際競争⼒のある消費財を作り続けてきたことから、今後はアジア諸国の⽂化発信⼒の拡⼤に伴って⾳楽やアニメキャラクターといった⽂化関連商品の輸出を拡⼤すると考え、アシックス、HYBE(韓国/メディア・娯楽)といった銘柄を組み⼊れています。
- インフレ受益銘柄- ⽇本ではインフレが進⾏しており、インフレと⾦利が引き続き世界的なリスクとなる⾒込みであることから、こうした動向から恩恵を受ける銘柄、例えば三菱商事(資本財)や三菱UFJフィナンシャル・グループ(銀⾏)などを組み⼊れています。
バランスの取れたポートフォリオを構成し、国内外の幅広い株価上昇要因を捉えることが、⾼いリスク調整後リターンを⻑期にわたって確保することに役⽴つというのが当ファンドの考えです。
⾃分の得意な⼿法からの脱却
2023年は中国経済の冷え込みが予想以上に早く進んだため、中国銘柄を⼤量に⼊れ替えました。その⼀⽅で、これまで⾼く評価して組み⼊れていた銘柄を売却しました。その⼀例が、ある⼤⼿K-POP企業で、創業者が⾳楽に情熱を傾けていて、当ファンドはそれを⾼く評価していました。同社はコロナ禍後の経済再開のおかげでアルバムでもコンサートでも売上を順調に伸ばし、パフォーマンスは年間を通じて堅調でした。しかし、ある問題に気づいたことで、当ファンドは不安を感じるようになりました。同社はK-POPの成⻑の恩恵を受けていましたが、新たに結成したガールズグループのパフォーマンスが期待したほどでなく、特に同業他社と⽐較すると⾒劣りするのです。同社がコンテンツ制作や傘下グループのコンセプト作りに⼗分な投資をしていないのではないかというのが当ファンドの感触です。今⽇では、アーティストに必要なのは才能だけではありません。所属会社がコンセプト、コンテンツ制作、マーケティングなどに関してアーティストをどうサポートするかという点も同様に重要なのです。
同社はきわめて⾼い収益を上げており、市場関係者はそれを評価して競うように株式を購⼊しました。⼀⽅、当ファンドはある企業に投資する場合、その企業がどのような問題に直⾯する可能性があるかという点をしっかり意識するよう努めており、そうした問題が発⽣する兆しが現れ、解決が困難であると判断した場合には株式を売却する意向です。今回の場合、投資額を抑えて直ちに⾼収益を上げようという⼿法は⾮効率な資本配分以外の何物でもなく、事業の持続可能性が損なわれます。市場は経常利益の⾼さを評価していますが、それは同社に誤ったシグナルを送ることになります。当ファンドは同社が戦略を変えることはないと感じたため、⼀旦全売却いたしました。
さて、本報告書の締めくくりにあたって、当ファンドの偉⼤な先達で、11⽉に亡くなったチャーリー・マンガー⽒の⾔葉をご紹介しておきたいと思います。
「バークシャー・ハサウェイがささやかな前進を遂げたとすれば、その推進⼒の⼤部分は、ウォーレン・バフェットと私が⾃分たちの最も得意なやり⽅をきれいさっぱり捨て去ってきたことにある。⾃分の得意なやり⽅を何から何まで踏襲したとしたら、その年はおそらく無駄な1年になるだろう。」- チャーリー・マンガー
2024年はおそらく当ファンドの得意な投資⼿法を⼀部捨て去ることになるでしょうが、それと置き換わる投資⼿法がすばらしい効⼒を発揮してくれることを願ってやみません。
2023年11月の運用コメント
株式市場の状況
<日本の株式市場>
2023年11⽉、⽇本株式市場の代表指数であるTOPIX(配当込み)は前⽉末⽐5.42%の上昇となりました。
当⽉の⽇本株式市場は、⽉前半はFOMC(⽶連邦公開市場委員会)での政策⾦利の据え置きや、市場予想を下回る⽶雇⽤統計を受けての⽶⻑期⾦利の低下を背景に上昇しました。⽉半ばは、⽇本企業の良好な決算や、市場予想を下回る⽶国のCPI(消費者物価指数)を受けた⽶追加利上げ観測の後退などから、⽉中⾼値をつけました。⽉後半に⼊ると、中東情勢の地政学リスクの後退や⽶⻑期⾦利低下等を好材料に上昇した後、⼀時1ドル=146円台後半まで進⾏した円⾼が重しとなって下落基調に転じましたが、最終的に前⽉末を上回る⽔準で⽉を終えました。
<アジアの株式市場>
当⽉、アジア株式市場は反発しました。⽇本を除くアジア市場に使⽤される⼀般的な指数であるMSCIアジア(⽇本を除く、⽶ドル建て)指数は、韓国と台湾に牽引される形で前⽉末⽐6.96%上昇しました。⽶国の労働市場とインフレに関するデータが軟化したことで、市場関係者の⾒⽅は2024年に利下げが⾏われ、低いとはいえ妥当な⽔準の経済成⻑が続くという⽅向に変化しました。これは⽶国市場のソフトランディングシナリオと⾔ってよいでしょう。こうした変化を受けて、テクノロジー関連やインターネット関連セクターなどの成⻑株、とりわけ韓国と台湾の銘柄が底堅く推移しました。
⼀⽅、中国市場は当⽉も引き続き低迷しました。政府の緩和政策にもかかわらず、不動産セクターの状況にはほとんど改善が⾒られませんでした。経済成⻑率の低迷も消費⽀出の抑制要因となり、消費者の間に低価格志向が広がっています。
インドは引き続きアジア諸国の中で⾼い成⻑率を保っている数少ない市場の⼀つで、2023年第3四半期GDP成⻑率は前年同期⽐7.6%上昇しました。構造的な⻑期成⻑が⾒込める市場は、新事業に果敢に取り組もうという気概のある企業に時流に乗じる機会を与えます。政府の⽀援策も効⼒を発揮しており、特に様々な優遇措置を通じて国内の製造業を下⽀えし、海外直接投資を誘致することで、成⻑に寄与していると考えます。
ファンドの運用状況
当⽉、当ファンドのパフォーマンスは前⽉末⽐2.74%の上昇、参考指数のMSCI AC Asia Index(円ベース・配当込み)は同4.99%の上昇となりました。
当⽉パフォーマンスにプラスに貢献した銘柄は、ルネサスエレクトロニクス(半導体・半導体製造装置)、Samsung Electronics(韓国/テクノロジー・ハードウェアおよび機器)、Taiwan Semiconductor Manufacturing Company(台湾/半導体・半導体製造装置)などでした。⼀⽅、ANTA Sports Products(中国/耐久消費財・アパレル)、SamsoniteInternational(⾹港/耐久消費財・アパレル)、ヨネックス(耐久消費財・アパレル)などがマイナスに影響しました。
7⽉の⽉次報告書で、中国が「バランスシート不況」に追い込まれる可能性について取り上げました。中国のCPI(消費者物価指数)は7⽉にマイナス圏に落ち込み、その後持ち直しましたが、10⽉には再びマイナス圏に戻りました。⼀⽅、PPI(⽣産者物価指数)は年間を通じてマイナス圏にあり、中国が過酷なデフレ圧⼒に直⾯していることは明らかです。当ファンドは中国の不動産や⾦融などの⼤きな問題を抱えているセクターには投資していませんが、⼤⼿消費者ブランドやプラットフォームには引き続き関⼼を持っています。消費関連セクターが直⾯している最⼤の課題は、消費者の多くが低価格商品を志向する傾向が⾼まっていることです。そこで今回はマクロ的なデータを提⽰する代わりに、個別銘柄の状況を取り上げます。
当ファンドの過去の組⼊銘柄のうち、Li Ning Company社(中国)とYum China Holdings社(中国)の2銘柄は2023年第3四半期決算発表をうけて株価がいずれも⼤きく下落しました。Li Ning Company社を組み⼊れたのは2020年8⽉で、2020年8⽉と2022年8⽉の⽉次報告書で同社について取り上げています。当ファンドは2023年初頭、中国市場で株価が急騰したことから、割安感のなくなったと判断し同社を売却しました。とはいえ、これほど状況が悪化するとは想定していませんでした。同社は前⽉後半に通年の売上成⻑率予想を10%台半ばから1桁台に引き下げました。同社は中国を代表するブランドという強⼒なイメージを通じて、過去数年間で確かにブランド⼒を⾼めてきました。そうしたブランド⼒の向上と製品の品質改善により、同社はNIKEやadidasに⽐肩する価格設定の⾼価格帯商品を積極的に発売し、市場シェアを⼤幅に落としたadidasを尻⽬に、この2年間はかなりの好業績を残してきました。しかし消費者の多くが低価格商品を志向している中で中⾼価格帯商品への移⾏戦略を採⽤したことが、最終的に裏⽬に出たことになります。
さて、次にYum China Holdings社に話題を移しますが、同社は当ファンドが2022年組み⼊れを開始した銘柄で、当時は中国のロックダウンに対する懸念が市場で⾼まっていた時期でした。同社は中国でケンタッキーフライドチキン(KFC)とPizza Hutのフランチャイズ店を展開しています。KFCは中国最⼤級の外⾷チェーンで、中国内の店舗数はマクドナルドのおよそ2倍に達しています。先進国ではファストフードは安い⾷べ物だと思われていますが、中国ではKFCの商品が必ずしも低価格だとはいえず、⼀線都市(北京、上海、広州、深セン)ではバーガーコンボ(ハンバーガー+フライドポテト+ドリンク)が30〜40⼈⺠元(約630円〜840円)で販売されています。当ファンドは低価格レストランとの競争が熾烈化する可能性を考慮し、前⽉に同銘柄を売却しましたが、残念ながらその懸念は現実のものとなりました。同社の2023年第3四半期決算ではレストランの利益率が前年同期⽐で減少していますが、同社はその要因を、来店客数を伸ばすために値引きを増やしたためであるとしています。当ファンドの⾒⽅では、KFCは規模が⼤きく、サプライチェーンと運営能⼒が優れていて、価格に⾒合った価値を提供してはいますが、必ずしも消費者に最安値で商品を販売しているわけではありません。低価格レストランは以前から存在していましたが、これまでは消費者がより⾼価格な商品を志向していたために、同社は低価格レストランとの競争を回避できると当ファンドは考えていました。しかし消費者の志向が低価格帯商品に移ってきたことで、低価格レストランが次第に優位に⽴ちつつあります。例えば、サイゼリヤは料⾦の割に質のよい料理が楽しめることで知られる⽇本のレストランチェーンですが、中国で順調に業績を伸ばしています。⽐較のために述べておくと、サイゼリヤの⼀線都市における販売価格はパスタが9⼈⺠元(約190円)、8インチピザが22⼈⺠元(約460円)からラインナップされています。
当⽉は⼤規模セールで有名な「独⾝の⽇」がある⽉でもありました。今年の全eコマース(電⼦商取引)プラットフォームのキーワードは「ネット最安値」です。セール期間中、プラットフォームが加盟店に最安値を提⽰するよう圧⼒をかけているというニュースが絶えず流れていました。これはまさに、恐るべき「底辺への競争」です。
こうした低価格帯商品志向が構造的なトレンドなのかどうかはまだわかりません。しかしデフレサイクルのリスクが⾼まっているのは間違いないと考えています。中国の⼀般家庭は貯蓄率が⾼く、資⾦的に潤っているのは確かです。政府は景気刺激策によってデフレの連鎖を⽌める必要があり、⻑期的には社会的セーフティネットを改善し、⼀般家庭が貯蓄を減らして⽀出を増やせるようにしなければなりません。不本意ではありますが、これが構造的な傾向だとしたら、投資家としては何ができるでしょうか。当ファンドは⽇本を含むアジアを投資対象とするファンドであり、投資対象となる銘柄はきわめて幅広い範囲に広がっています。投資機会は⼗分にあるので、好ましくない状況に陥った市場からは躊躇なく⼿を引くことができます。アジアには当ファンドが現在投資していない市場が複数あります。しかし中国は巨⼤市場で、多種多様な事業が展開されているので、投資機会が尽きることはないと考えます。
スポーツウェアに話を移すと、前述の話には別の側⾯があります。アシックスやDESCENTE(中国のDESCENTEはANTASports Productsが運営)といった⾼級専⾨ブランドの業績が好調なのです。2023年第3四半期にアシックスは中華圏の売上が前年同期⽐11%増(為替の影響を除く)、DESCENTEは同40〜45%増を記録しました。また⾼級品と考えられているヨガ・アパレル・ブランドのLululemonは、独⾝の⽇のセール期間中に⼤幅に売上を伸ばしました。
総括すると、低価格商品志向があるのは確かですが、⾼級品志向もなくなったわけではないと考えられます。消費者はどのような商品で⾼価格帯のものを購⼊するかという点で、より慎重かつ選別的になっており、不要と思われる商品では低価格帯へと移⾏しているのです。KFCが35⼈⺠元で販売している⾷事に価格に⾒合った価値がなければ、消費者はより安いレストランに移るでしょう。アシックスの製品が優れていて⼗分差別化されているなら、消費者は対価を惜しまないはずです。消費者の財布の中⾝が⾏き着く場所は、これから⼤きく変わることでしょう。マクロデータからは消費者の動向は今⼀つ掴めないため、ボトムアップ⽅式で⾒ていく必要があると考えています。
投資に関して現状で抑えておきたいのは以下のような点です。
- 熾烈な価格競争のあるセグメント、特に中国企業との価格競争が激しいセグメントは投資を回避します。これは当ファンドが⽇頃から注意している点です。中国企業は世界的に⾒てコスト⾯で強い優位性を持っており、その多くが成⻑のために収益性を犠牲にする傾向があります。アジアの別の国の企業に投資する場合でも、コストが最⼤の差別化要因となっている製品で中国企業と真っ向勝負している企業への投資は避けたいと考えています。
- 前項と関連して、価格競争が問題にならないセグメントを探したいと思います。その⼀例がオンラインゲームです。モバイルゲームはそもそも無料なので、ゲーム内アイテムの価格を下げたところで、プレイヤーの消費需要を刺激することはできても、他のゲームから乗り換える魅⼒にはなりえないと考えます。差別化要因は主として優れたゲームを作ることであり、値下げではありません。
- 低価格志向がトレンドなら、低価格商品を販売する企業に投資するのは素晴らしいことではないか、という考え⽅もあるかもしれません。そうした企業が⼀時的に有望かもしれません。しかし、コスト⾯の優位性だけでは持続可能な優位性とは⾔い難く、とりわけ中国ではその傾向が顕著です。当ファンドは常に低コストの企業を選好していますが、低コスト以外の強みも持っている企業を探したいと考えています。
- 製品の差別化要因については、さらなる分析が必要です。消費者があらゆる分野で⾼級品を求める時代は過ぎ去りました。企業にとって必要なのは、消費者に消費を惜しませない強⼒な価値提案を⾏うことです。乳製品、スナック菓⼦、⽇⽤⾐料品といった基礎的品⽬は⼗分な差別化が難しいため、これから逆⾵に直⾯すると考えます。
- 複数のブランドや製品を持っていて、低価格志向と⾼級志向の両⽅に対応できる企業を探します。その⼀例が、NetEase(中国/メディア・娯楽、当ファンド保有銘柄)をはじめとする⼤⼿モバイルゲーム会社です。ゲームの中には、MMORPG(⼤規模多⼈数同時参加型オンラインRPG)のように消費者が⽐較的価格に無頓着で、時間とお⾦を⼤量に費やすものがあります。また⼀⽅で、ユーザー数が多く、ユーザー1⼈あたり⽀出額がきわめて少ないジャンルもあります。ANTA Sports Products もそうした企業の⼀例で、同社の⼤衆ブランド「ANTA」は、低価格トレンドに強いと考えます。⼀⽅、FILA、DESCENTE、ARCʼTERYX(ANTA Sports Products が2019年に買収したAmer Sports Corporation社(フィンランド)傘下のブランド)といった⾼級ブランドは、消費者の⾼価格帯商品需要を取り込めるだけの、きわめて強⼒な価値提案を⾏っています。
短期的な⾒通しは依然厳しいですが、当ファンドは構造改⾰の兆しを探りたいと考えています。政府が構造改⾰について正しい決断を下し、⼈々に消費拡⼤の⾃信を与え、中国経済を投資主導型経済から消費主導型経済へと移⾏してくれれば、中国には投資機会の新しい波が到来するというのが当ファンドの⾒⽅です。
2023年10月の運用コメント
株式市場の状況
<日本の株式市場>
2023年10⽉、⽇本株式市場の代表指数であるTOPIX(配当込み)は前⽉末⽐2.99%の下落となりました。
当⽉の⽇本株式市場は、⽉前半は堅調な⽶雇⽤統計を受けての⽶⻑期⾦利の変動や、中東情勢の緊迫化などを受け乱⾼下の展開となりました。⽉後半に⼊ると、中国の景気刺激策が好感される場⾯があったものの、⽇銀の政策再修正への思惑や⽶テクノロジー企業の低調な決算への失望が株式市場の重しとなり、最終的に前⽉末を下回る⽔準で⽉を終えました。
<アジアの株式市場>
当⽉、アジア株式市場は前⽉に引き続き軟調に推移しました。⽇本を除くアジア市場に使⽤される⼀般的な指数であるMSCIアジア(⽇本を除く、⽶ドル建て)指数は、前⽉末⽐3.86%下落し、3か⽉連続の下落となりました。世界的な景気減速が進⾏していること、FRB(⽶国連邦準備制度理事会)が「より⾼く、より⻑期に」という偏った政策を続けていることが世界の株式市場の下落につながりました。また、イスラエルとハマスの紛争が地政学的リスクの新たな震源となりました。
中国政府は1兆⼈⺠元の特別国債発⾏を決議し、各種インフラプロジェクトに資⾦を充当するなどの複数の景気⽀援策を発表しましたが、消費者⼼理は依然弱含みで、市場は引き続き下⽅圧⼒にさらされています。また、⽶国はAI(⼈⼯知能)半導体の対中国への輸出規制をさらに強化し、中国におけるAI能⼒の急速な発展を抑制しようとしています。
韓国市場もEV(電気⾃動⾞)⽤電池とEV⽤素材セクターが調整したことで、アンダーパフォームしました。EV需要の鈍化に対する懸念、Tesla社(⽶国)をはじめとするEVメーカーの値下げが投資家⼼理の重荷となったと考えます。⼀⽅、台湾市場では、5G(第5世代移動通信システム)に対する楽観的⾒⽅とスマートフォン需要の底打ちが要因で、MediaTek(台湾/情報技術、当ファンド組⼊銘柄)などのハイテク部品銘柄の株価が上昇しました。
ファンドの運用状況
当⽉、当ファンドのパフォーマンスは前⽉末⽐4.07%の下落、参考指数のMSCI AC Asia Index(円ベース・配当込み)は同2.67%の下落となりました。
当⽉パフォーマンスにプラスに貢献した銘柄は、NetEase(中国/メディア・娯楽)、ANTA Sports Products(中国/耐久消費財・アパレル)、ソニーグループ(耐久消費財・アパレル)などでした。⼀⽅、ルネサスエレクトロニクス(半導体・半導体製造装置)、BFI Finance Indonesia(インドネシア/⾦融サービス)、アシックス(耐久消費財・アパレル)などがマイナスに影響しました。
10⽉に⼊ってイスラエルとパレスチナの間で痛ましい軍事衝突が起こり、本報告書執筆時点でも停戦のめどは⽴っていません。株式市場はこの事態にあまり反応を⽰さず、むしろ⽶国のインフレと雇⽤統計の⽅に注⽬が集まりました。⼀⽅、原油価格は10⽉前半に急落しましたが、その後は急反発しました。原油はおそらく最も地政学的な影響を受けやすいコモディティ(エネルギー類(原油・天然ガス等)、貴⾦属類(⾦、プラチナ等)、農産物類(トウモロコシ・⼤⾖等)等の「商品」のこと)であり、⼤局的にみて世界情勢の形成要因となっています。中東が地政学的に危険なのは、狭い範囲の中で資源を巡る利権と様々なイデオロギーが複雑に絡み合い、典型的な軍事衝突の背景となっているためです。こうした軍事衝突は、時に当事国以外の国々にも多⼤な影響を及ぼします。原油の純輸⼊⼤国であるアジア諸国は、とりわけそうした危険にさらされています。アジアの原油純輸⼊量は2021年に⽇量2,200万バレルを上回りました。原油価格の⾼騰はインフレ圧⼒と消費者の負担を増⼤させるため、経済にとってマイナスに作⽤します。政府から燃料補助⾦が⽀給されている国では、原油価格の⾼騰によって政府の財政状態が悪化します。企業にとっては、原油価格の⾼騰はコストの押し上げ要因であり、とりわけ世界的な製造拠点となっているアジア諸国ではその傾向が顕著です。原油価格の⾼騰にドル⾼が重なって、現地通貨建ての原油価格はさらに⾼騰しているため、このところ負担がより⼤きくなっています。⽇本は国家安全保障の観点から原油の⼤部分を中東諸国から輸⼊しており、中東地域で紛争が発⽣すれば、どのようなものであれ、国家にとってエネルギー安全保障上の重⼤な脅威となります。
1970年代に⽶国で発⽣したハイパーインフレの⼀因は⽯油危機にあり、当時もイスラエルは紛争の当事国でした。1973年にエジプトやシリアとイスラエルの間で戦争が勃発しました。現在ではヨム・キプール戦争(第四次中東戦争)と呼ばれている戦争です。当時、⽶国のイスラエル⽀援に対抗するため、アラブ⽯油輸出国機構(OAPEC)は⽶国に対する⽯油の禁輸措置を発動しました。そのため原油価格は措置発動前の1バレル3ドル前後から1974年1⽉には1バレル10ドル前後に上昇し、その後禁輸措置が解除されてからも⾼⽌まりしました。原油価格はその後、1980年代から1990年代にかけて低落傾向に転じました。そして2000年代に⼊って中国が世界貿易機構(WTO)に加盟し、新興国市場が成⻑したことで、2008年には1バレル140ドル近い最⾼値を記録しました。
2010年代に⼊ると⽶国でシェールブームが起きて原油情勢が⼤きく変化し、⽯油輸出国機構(OPEC)の価格決定⼒は⼤幅に低下しました。⽔圧破砕と⽔平掘削技術の進歩により、堅い岩⽯に閉じ込められていて従来は取り出せなかった原油を採算ライン以下のコストで⼤量に取り出すことが可能になったのです。⽶国の原油⽣産量は、2011年の⽇量約790万バレルから、2021年には⽇量1,700万バレル以上に増加しました。2011年から2021年までの⽶国における原油⽣産量の増加幅は、同時期の世界全体における⽣産量増加分の総計を上回っています。原油市場は2014年から⼤幅に落ち込み、原油価格は2021年まで⻑期にわたり低迷しました。
原油市場は転換期を迎えたようです。数年にわたるダウンサイクルとESG投資の台頭によって⽯油会社は資本不⾜に陥り、設備投資はここ数年で急減しています。The Goldman Sachs Group社(⽶国)の試算によると、⽶国の原油⽣産会社による設備投資の⽐率は営業キャッシュフローの35%未満に過ぎません。2014年から2015年ごろにかけて100%以上だったことを踏まえると⼤幅な下落です。投資不⾜のため、原油供給の途絶対策としての供給バッファが世界的に不⾜しています。ロシアとウクライナの戦争が続いていることも、状況をより複雑にしています。例えば、OPECはこのところ価格決定⼒を取り戻しつつあり、原油価格が⾼いという認識が広がっているにもかかわらず、減産体制を維持しています。また、先⽇⼤⼿⽯油会社による⼤規模なM&Aが発表され、同セクターの資本規律がさらに強化される可能性が出てきました。
「市場が堅調で、原油価格が⾼く、ガソリン価格が⾼ければ、我が社は⽂字通り現⾦⾃動預払機となる」
- BP社(英国)前CEO、バーナード・ルーニー
当ファンドは以前から⽯油開発・⽣産関連銘柄を直接組み⼊れ、さらに総合商社を通じて幅広いコモディティへの投資も⾏っています。地政学的情勢がきわめて複雑化している状況下において、アジアは⾔うまでもなく原油の純輸⼊国なので、こうしたコモディティ関連企業の⼀部に割安なバリュエーションで投資することは、当ファンドにとってきわめて魅⼒的なヘッジ⼿法になると考えます。
ところでコモディティ銘柄への投資全般について、いくつか取り上げたい問題があります。
- 当ファンドは⽯油銘柄を組み⼊れていませんが、これは原油価格が短期的に上昇すると予測しているからです。OPECが価格決定⼒を取り戻したことで、原油価格が⾼⽌まりする可能性は⼗分にあると考えます。当ファンドの⾒⽅では、コモディティのスポット価格の変動を予測して株式投資を⾏うのは好ましくない⽅法と考えています。株価というのは企業が将来的に⼿にするフリーキャッシュフローの総額を現在価値まで割り引いたものであるため、⻑期平均コモディティ価格の⽅がスポット価格よりはるかに重要です。短期的なコモディティ価格の変動に賭けるなら、短期先物取引の⽅がはるかに優れた投資⼿段です。先物取引と株式投資の違いは、先物の買い⼿はスポット価格が動かなければ儲からないということです。ただしバックワーデーション(先物価格がスポット価格より低い状態)の場合は例外で、買い⼿はロールイールドを得ることができます。⼀⽅、株式投資の場合、スポット価格が動かなくてもそれほど問題はありません。バリュエーションが⼗分に割安な状態で株式を購⼊し、原油価格が⼗分に⾼く、企業が⼗分なキャッシュフローを⽣み出す限り、株式所有者は配当と⾃社株買いによってリターンを得ることができます。株式への投資は短期的なコモディティ価格に賭けることとは全く異なる⾏為だと考えます。
- 不況に⾒舞われると、需要が減退するため原油価格は下落します。循環性が⾼く、コモディティ化した産業にあっては、⻑期投資家にとって最も重要なのは供給と資本規律であり、それらは景気循環によって浮き沈みする需要よりはるかに⻑期的な効果をもたらすと考えます。2022年10⽉の⽉次報告書でSamsung Electronics(韓国/テクノロジー・ハードウェアおよび機器)への投資について取り上げて説明したような、供給規律が⽯油業界にも備わっているというのが当ファンドの考えです。
- コモディティ化した製品を販売する企業は質の低い企業だと⾒なされていますが、当ファンドは概してこの⾒⽅に賛成で、前⽉取り上げたエンターテインメント企業のように、独⾃性があり簡単に複製できない資産の保有企業の⽅が断然投資にふさわしいと考えます。しかし商品価格が⾼く、企業のコストが低ければ、それも事業として成⽴すると考えます。重要なのは品質と将来性に適切な価格を⽀払うということです。コモディティ銘柄の中には、バリュエーションが割安で、その将来性にふさわしい取引ができる銘柄があると考えます。
- いずれ、エネルギー転換によって⽯油は時代遅れとなることでしょう。それは間違いありません。しかし、こういった考えはESG投資の推進とともに近年エネルギー企業が資本不⾜に陥っている原因の⼀つとなっています。⽯油がやがて使われなくなるという考えが、いま、⽣産能⼒への投資にブレーキをかけているのです。しかし、数年でエネルギー転換を完了させることは不可能であり、世界で今後数年間にわたってこれまでと同様に⼤量の⽯油が必要とされるのは間違いありません。エネルギー転換にはきわめて多額の資本が必要で、現在の⾦利環境とインフレはエネルギー転換の進展にとって⼤きな障害です。この問題については、今後の報告書で再度取り上げるかもしれません。
ESG投資を考えるなら、コモディティ銘柄の組み⼊れは避けるべきなのでしょうか。しかし世界中の投資家がコモディティ銘柄への投資を⽌めたとしても、コモディティ企業は存続し、⼈々はそのコモディティを毎⽇消費するのです。コモディティ銘柄を避けることや、無視することが正しい解決策だとは思えません。⽯油会社はもれなくポートフォリオの変⾰に取り組んでおり、世界の⼤⼿⽯油会社は数千億ドルもの資産をバランスシート上に計上し、エネルギー転換に重要な役割を果たすリソースを莫⼤に保有しています。将来的に⽯油資産を⼿放し、事業転換を図る場合、その資本をより持続可能な事業に再投資するか、株主還元を通じて分配すると考えます。いずれにせよ、数千億ドルもの資本を再配分する必要があるので、資本市場はそれを無視するのではなく、そのプロセスに積極的に参加し、関与していくべきでしょう。
2023年9月の運用コメント
株式市場の状況
<日本の株式市場>
2023年9⽉、⽇本株式市場の代表指数であるTOPIX(配当込み)は前⽉末⽐0.51%の上昇となりました。
当⽉の⽇本株式市場は、⽉前半は中国製造業購買担当者景気指数(PMI)の改善により中国の景気後退不安が⼀時的に後退したほか、国内では早期衆院解散・総選挙への期待感が⾼まったことを受け、上昇基調となりました。⼀⽅⽉後半は、FOMC(⽶連邦公開市場委員会)で⾦融引き締めの⻑期化が⽰唆されたことや、⽶議会の予算協議が難航し政府機関閉鎖への警戒感が⾼まったことから、市場⼼理が悪化し値を戻す展開となり、最終的に前⽉末を若⼲上回る⽔準で⽉を終えました。
<アジアの株式市場>
当⽉、アジア株式市場は前⽉に引き続き軟調に推移しました。⽇本を除くアジア市場に使⽤される⼀般的な指数であるMSCIアジア(⽇本を除く、⽶ドル建て)指数は、前⽉末⽐2.65%下落し、フィリピンとインドを除くアジア市場全体が軒並み下落して⽉を終えました。
原油価格の上昇、景気の減速、各国中央銀⾏が「より⾼く、より⻑期に」という偏った政策を続けていることなどから、世界各国の株式市場と債券市場が下落しました。
中国の不動産セクターは当⽉も中国と⾹港の株式市場の重しとなりました。過剰債務をかかえる不動産開発業者は依然として流動性問題の解決を迫られており、政府が住宅ローンの融資条件緩和という⽀援策に踏み切ったにもかかわらず、不動産販売件数に⼤幅な改善は⾒られませんでした。⼀⽅、鉱⼯業⽣産や⼩売売上⾼など、中国の8⽉の経済指標が⼀部プラス成⻑を⽰す数値となったことは好材料と考えます。
インドのNifty50指数は当⽉に最⾼値を更新しました。その要因としては、⽣産年齢⼈⼝の割合増加に由来する経済成⻑、都市化、インフラ投資、「チャイナ・プラス・ワン(中国のみに⼯場を構えるリスクを回避するため、他のアジアの国に製造拠点を展開すること)」の動きが同国経済の⻑期的成⻑を後押しするという⾒⽅が投資家の間に根づいてきたことがあげられます。また、タイの株式市場は観光客数の多さと新政権による景気刺激策にもかかわらず、下落幅がASEAN諸国中で最⼤となりました。
ファンドの運用状況
当⽉、当ファンドのパフォーマンスは前⽉末⽐1.06%の下落、参考指数のMSCI AC Asia Index(円ベース・配当込み)は同0.05%の上昇となりました。
当⽉パフォーマンスにプラスに貢献した銘柄は、MakeMyTrip(インド/消費者サービス)、三菱UFJフィナンシャル・グループ(銀⾏)、Lemon Tree Hotels(インド/消費者サービス)などでした。⼀⽅、ソシオネクスト(半導体・半導体製造装置)、ルネサスエレクトロニクス(半導体・半導体製造装置)、Mitra Adiperkasa(インドネシア/⼀般消費財・サービス流通・⼩売り)などがマイナスに影響しました。
当ファンドは当⽉、世界的に有名なアニメキャラクターを制作する⽇本企業や、韓国のK-POP企業など、複数のエンターテインメント企業の経営陣と⾯談を⾏いました。エンターテインメント事業とは、端的に⾔えば、知的財産(知財)の販売に他なりません。知財には様々な種類がありますが、例えば、あるテクノロジーを他社にライセンス供与して使⽤を認める場合も知財に含まれます。ソフトバンクグループ㈱が株式の過半数を保有し、先⽇⽶国で上場したArm Holdings社(英国)は、プロセッサアーキテクチャ(コンピュータの中央処理装置(CPU)の設計と構造)を知財として半導体チップ設計事業者に販売しています。⼈々が毎⽇使っているスマートフォンのプロセッサは、同社のアーキテクチャの⼒で動いているのです。⼀⽅、当ファンドの⾯談先企業が販売しているのは、⾳楽やアニメキャラクターといったエンターテインメント関連の知財です。当ファンドはこれまで数社のエンターテインメント企業に投資を⾏ってきましたが、その理由は1) 知財はコモディティや⼯業製品と違って模倣が困難であるという点、2) 当該企業が最⼩限の資産で事業を運営できるという点、3) 知財を⼤量に複製することで、多額の利益が得られる可能性があるという点にあります。エンターテインメント知財を売るということは、いわば「幸福感」を売るということです。ハローキティが描かれたカップがよく売れるのは、何も描かれていない真っ⽩なカップよりハッピーな気分になれるからです。⼈々は幸福感を感じられるもの、持っているだけで嬉しい気持ちになれるものにはためらわずにお⾦を払います。そのため⼈気キャラクターの知財を保有する企業は、強⼒な価格決定⼒を⼿にすることになります。
アジアでエンターテインメント知財関連の投資機会が⾒られるのは主に⽇本と韓国ですが、中国にも⼀部存在していると考えます。⽇本はアニメ、ゲーム、マンガの制作能⼒の⾼さが群を抜いており、ポケモン、スーパーマリオ、ガンダム、ハローキティといったキャラクターが世界的に⼈気を博しています。過去10年間でそれに迫ってきたのが韓国だと当ファンドは考えており、K-POP、韓国ドラマ、ウェブトゥーン(縦スクロールのフルカラーマンガ)は世界中で⼈気を集めています。
テクノロジーの進歩はエンターテインメント知財事業に多⼤な恩恵をもたらしています。ゲームの世界において、テクノロジーがグラフィックとユーザー体験を向上させたのは誰の⽬にも明らかでしょう。テクノロジーは流通の⾯でも⼤いに役⽴っています。例えば、ガンダムシリーズの最新作「機動戦⼠ガンダム⽔星の魔⼥」は、アジアの様々な国において、Netflixで視聴可能です。これが20年前なら、知財所有者は各国の地上波テレビ局と交渉し、さらに⾔語をローカライズする必要がありました。Netflixに代表されるグローバル・プラットフォームのおかげで、グローバル展開にかかる労⼒は⼤幅に軽減されました。⼀⽅、⾳楽の世界では、Spotifyのような⾳楽ストリーミング・プラットフォームによって業界全体が活⼒を取り戻し、K-POPはYouTubeをうまく活⽤することで、⼈気を⾼めることができました。K-POPは視覚と同時に楽しむことでその良さが伝わると⾔われており、動画での再⽣に適しています。K-POPアーティストの最新動向を追いかける場合、Spotifyのような⾳声のみのプラットフォームより、YouTubeを使うことが多いのが⼀般的です。YouTubeの台頭には、モバイルデータ通信の向上によって、携帯機器で気兼ねなく動画を楽しめるようになったという背景があるのです。
さて、ユーザーへのリーチが格段に容易になった⼀⽅で、様々なメディアが台頭してきたことで、企業はいかにしてユーザーの定着を図るかという問題に頭を悩ませるようになりました。⼈々の時間の使い⽅が断⽚的になり、関⼼が⻑く続かないのです。複数のメディアがひしめきあって⼈々の関⼼を得ようと躍起になっており、⼈々はすぐに気をそらされてしまいます。つまりどれほど⼈気のある知財でも、翌年には他の知財に取って代わられる可能性があります。そのため、複数の「接点」を設けて⼈々とのつながりを保つことが重要になってきます。当ファンドは数年前、韓国のドラマ制作会社と⾯談しました。ところが韓国ドラマの⼈気は確かでも、その会社の創作物である知財には魅⼒が感じられませんでした。ハローキティはいつまでも⾊あせない知財で、何千種類もの商品にプリントすることができますが、ドラマの知財は他ではほとんど使えないからです。全16話のドラマは放映が終わればそれだけで終わりです。関連商品を作って継続的に販売するのは困難で、早晩忘れ去られてしまいます。⾳楽業界も同様で、Spotifyのおかげで独⽴系アーティストの楽曲発表は容易になりましたが、サポートやリソースがなければ、Spotify上の楽曲以外にユーザーと触れ合う接点を作ることはできません。それどころか、ユーザーは楽曲を聴いていてもアーティストが誰なのかさえ知らないことが多いのが実情です。
当ファンドが関⼼を持っているのは、⾃社の知財をさまざまな形態に変換し、顧客との接点を複数作り出すことができると考えられる企業だけです。例えばソニーグループ(耐久消費財・アパレル、当ファンド組⼊銘柄)は⾳楽、映像、ゲームなどの各部⾨間の連携を強化し、より優れた知財を創造、活⽤することを⽬指しています。その好例が、⼈気ゲーム「The Last of Us」のテレビドラマ化です。⾳楽業界では、K-POP企業がこうした⾯で⼀歩先を⾛っています。欧⽶ではアーティストの収⼊の⼤部分をアルバムやコンサートから得るのが⼀般的ですが、K-POP企業は関連グッズの制作やブランドとのコラボレーションなど、派⽣商品を通じた収益確保に積極的です。またYouTubeやTikTokといったソーシャルメディア、あるいはHYBE(韓国/メディア・娯楽)の「Weverse」のようにファンとの交流⽤の独⾃プラットフォームを通じて、より積極的にユーザーと関わっています。その⼀例が、2022年にHYBEからデビューしたガールズグループ、NewJeansです。その成功要因は、メンバーが⾳楽だけでなく、あらゆるところで終始⼈々と関わっていることにあります。具体的に⾔うと、複数のメンバーがGUCCI、CHANEL、Dior、Louis Vuitton、BURBERRY、McDonald's、Coca-Colaといったブランドのアンバサダーになっています。また、NewJeansは⼈気アニメ「パワーパフガールズ」とコラボしたことで、グループの知財をバーチャルな形態にまで拡張しました。つまり同グループは⾳楽だけでなく、もっと深いところでファンとつながっているのです。HYBEが2022年に⼿にした売上⾼のおよそ半分はアルバムとコンサート以外から得たものです。
K-POP関連企業がコロナ禍の恩恵を受けた⼀⽅で、ゲーム会社は全般的に社会活動の再開によって困難に直⾯しました。この明暗を分ける要因となったのが、顧客と複数の接点を確保できたか否かという点でした。コロナ禍の間、⼈々は家に引きこもり、YouTubeを⾒てK-POPファンになりました。そして社会活動が再開すると、コンサートがファンとのつながりを保つための、もう⼀つの重要かつ収益性の⾼い接点となったのです。社会活動の再開によって、YouTubeを視聴する機会は減ったかもしれませんが、⼈々はアーティストを⾒ようとコンサートに⾜を運ぶようになりました。コンサートを観たファンはアーティストにより親近感を抱くようになり、複数のチャンネルを通じてより多くの情報を得ようと努めるようになります。⼀⽅、ゲーム会社には⼀般に⼈々が外出を再開した時にユーザーとの関わりを保つ⽅法が他にありません。
アジアのエンターテインメント知財には投資機会が豊富に⾒いだせますが、その基盤となっているのはアジア各国の⽂化発信⼒の⾼まりと世界的なコンテンツ流通難易度の低下です。適正に⾏いさえすれば、知財の世界的流通は以前よりはるかに容易にできるようになりました。当ファンドはアジアの知財の⼈気がこれから世界的に⾼まると予想し、その好機を⽣かしたいと考えています。当ファンドの優位性は⽇本と他のアジア市場に資本を柔軟に配分できるという点にあり、前述の投資機会を活⽤する上で有利な⽴場にあると考えています。
2023年8月の運用コメント
株式市場の状況
<日本の株式市場>
2023年8月、日本株式市場の代表指数であるTOPIX(配当込み)は前月末比0.43%の上昇となりました。
当月の日本株式市場は、大手格付け会社フィッチ・レーティングス社(米国)による米国債の格下げを背景とした米国株安の流れを受け、下落から始まりました。月半ばは、中国の軟調な経済指標(消費者物価指数など)や、中国不動産開発大手の米国破産法の申請が嫌気され、下げ幅を広げました。月後半は、中国の追加利下げが好感されたほか、ジャクソンホール会議においてさらなる利上げへの懸念が後退したことで値を戻す展開となり、最終的に前月末を上回る水準で月を終えました。
<アジアの株式市場>
当⽉、アジア株式市場は急落しました。⽇本を除くアジア市場に使⽤される⼀般的な指数であるMSCIアジア(⽇本を除く、⽶ドル建て)指数は、前⽉末比6.39%下落しました。米国の経済指標とインフレ率が予想を上回ったため、FRB(⽶連邦準備制度理事会)がさらなる金融引き締めに踏み切るのではないかという懸念が広がり、株式と債券がいずれも下落しました。
また、中国の輸出と住宅セクターの低迷が続いたことで、投資家心理はさらに冷え込みました。中国の前月の輸出(米ドル建て)は前年同月比14.5%減となりましたが、これは世界経済が低迷していることや、米中対立のために市場シェアの継続的な低下が影響していると考えます。中国の不動産開発大手のCountry Garden Holdings社は手元資金が不足し債務返済が滞る可能性があると発表し、それを受けて他の不動産開発業者の株価が下落しました。中国政府は住宅ローンの融資条件を緩和する旨を発表し、不動産セクターへのてこ入れを図りましたが、信頼回復には時間がかかる模様です。
インド市場では大型株が低調な一方、小型株は好調とパフォーマンスに差が生じました。ただし、ここ数年の政府による持続的なインフラ支出と中国からのシェア奪取による輸出増加の効果もあって、経済成長全般は依然堅調です。
ファンドの運用状況
当⽉、当ファンドのパフォーマンスは前⽉末⽐0.29%の上昇、参考指数のMSCI AC Asia Index(円ベース・配当込み)は同2.58%の下落となりました。
当⽉パフォーマンスにプラスに貢献した銘柄は、MakeMyTrip(インド/消費者サービス)、Lemon Tree Hotels(インド/消費者サービス)、アシックス(耐久消費財・アパレル)などでした。一方、ルネサスエレクトロニクス(半導体・半導体製造装置)、JYP Entertainment(韓国/メディア・娯楽)、BOE Varitronix(香港/テクノロジー・ハードウェアおよび機器)などがマイナスに影響しました。
アジアの大部分は北半球に属しており、8月は旅行のピークシーズンにあたります。当ファンドは消費関連銘柄への投資に際し、消費者の支出額が継続的に拡大すると考えられるカテゴリーに重点をおいていますが、その中心をなしているのは旅行と美容だと考えています。例えば即席麺などの場合、どれほど優れた商品が揃っていても、ある一定の水準を超えた時点で消費額の拡大が止まる可能性がありますが、旅行の場合は収入の増加に伴って支出も増え続ける傾向があります。世界は広く、常に新しい発見があることを考えると、これは当然のことかもしれません。また消費財の多くは、例えば紅茶とコーヒーのようにどちらかの消費が増えればもう一方の消費が減る関係にありますが、旅行にはそれに代わる商品がありません。VR(仮想現実)技術は急速に進歩していますが、旅行本来の楽しさを部屋で椅子に座ったまま体験することはできません。したがって、旅行はアジア各国における所得拡大の恩恵を受ける、理想的なセグメントだというのが当ファンドの見方です。
当ファンドが組み入れている旅行関連銘柄は、世界最大のスーツケースメーカーのSamsonite International(香港/耐久消費財・アパレル)、インド最大のオンライン旅行代理店のMakeMyTrip、インド最大のミドルクラスホテルチェーンのLemon Tree Hotelsの3つです。当ファンドがインドの旅行業界に注目する理由は、インドは巨大な人口を抱えているものの、旅行業界はまだ揺籃期にあり、今後数十年間にわたって成長が見込めると考えているためです。そこで当月は「MakeMyTrip」について取り上げます。
インドの旅行市場は2013年から2019年にかけて年平均10%成長しましたが、これは同期間における中国の成長率14%を下回っています。同期間のインドの名目GDP成長率は中国を上回っているにもかかわらず、旅行市場は後れを取ったことになります。2019年のインドの国内延べ旅行者数は23億人で、1人当たりの国内旅行回数は約1.7回と、2010年当時の中国とほぼ同水準でした。インドでは海外旅行が始まったばかりで、2018年の海外旅行者数は推定2,100万人と、中国の同1億5,000万人以上と比べて格段の開きがあります。これは中国では過去10年の間に空港が整備され、高速鉄道網が高度に発達するなど、インフラ整備が進んだためであると考えられます。また中国人消費者の所得水準が高まり、嗜好品への支出を増やせるようになったためであることも、同時期に中国で高級品の売上が大きく伸びたことから明らかです。インドも今後インフラ整備が進み、国民の所得が増加することで、国内旅行と海外旅行がいずれも長期成長局面を迎えることになると考えています。
オンライン旅行代理店(OTA)は、こうした旅行需要増加の恩恵を最も受けることができると当ファンドは考えています。インドの旅行市場におけるオンライン普及率は、2019年のホテル予約のオンライン利用率が推定18%という数字からみられるように、依然低水準ですが、今後オンライン旅行予約へのシフトが進めば、OTAにとって有利に働くと考えています。
MakeMyTripはインドの大手OTAであり、オンライン旅行予約における国内市場シェアは推定40%強、旅行アプリの月間アクティブユーザー数におけるシェアは同70%強です。同社は2000年に現グループ会長のDeep Kalra氏によって設立された会社で、現在は中国最大のOTAであるTrip.com Group社(中国)が株式の約32%を所有しています。同社は「MakeMyTrip」と「Goibibo」という2種類のOTAブランドを運営しています。同社はこれまで扱ってきた航空券やホテルの予約に加え、バスチケット販売プラットフォーム「redBus」を運営しており、既にインドだけでなく、インドネシア、ペルー、コロンビアなどでも事業を展開しています。
同社が成長余地の大きい市場で事業を運営していることは前述のとおりですが、最終的な「勝ち組」になることはできるのでしょうか。インターネット業界についてみると、インドは競合先となる外国企業に対して中国より開放的です。中国には欧米のインターネット事業者が事実上存在しませんが、インドではAmazon.com社(米国)、Alphabet社(米国)、Meta社(米国)など、様々な事業者が存在感を示しています。旅行業界では、Booking Holdings社(米国)、Airbnb社(米国)、Expedia Group社(米国)がいずれもインドに進出しています。そうしたなか、MakeMyTripは強力なブランド名とネットワーク効果を生かして競合を回避し、支配的な地位を維持しています。ネットワーク効果はしばしばインターネット・プラットフォームの大きな強みとなりますが、さらに強力なネットワークを持つ新規参入企業が、競合するサービスのクロスセルを行うことによって、ネットワーク効果が損なわれることもあります。基本的に、インターネットを活用するビジネスモデルの多くはトラフィック(一定時間内におけるインターネット通信量)を売りにしており、ByteDance社(中国、「TikTok」の運営会社)やAmazon.com社のような巨大なトラフィックを持つ事業者の参入は危険です。しかし当ファンドでは、旅行関連サイトは他のインターネット分野とは事情が異なるとみています。旅行は取り扱い金額が大きく、事前の計画が必要で、多くの場合、旅行中の顧客へのカスタマーサービスが高い重要性をもっているため、消費者は自身が最も信頼しているOTAブランドで予約を行うのが一般的です。Amazon.com社はインド旅行市場への直接参入を試みましたが、最終的にはMakeMyTripとの提携を選択しました。MakeMyTripは今後も現状の優位性を維持・拡大することが可能で、インド旅行市場の成長から継続的に恩恵を受けるというのが当ファンドの見方です。
MakeMyTripは長い歴史をもっており、上場を果たしたのは2010年です。売上高は2011年3月期の約1億2,500万米ドルから4倍近く伸び、2023年3月期には約5億9,300万米ドルに達しましたが、株価は低迷していました。同社は市場の創出とユーザー獲得に向けて投資を継続していたため、2011年3月期から2023年3月期までの間に累計12億米ドルの純損失を計上しました。当ファンドが同社の調査を開始した2019年、同社はまだ巨額の赤字を計上していました。業績は芳しくない模様でしたが、1)市場に十分な成長余地があったこと、2)同社が競合他社を圧倒していて勝ち組に見えたこと、3)同社はリーダーの地位を安定的に維持できれば高収益企業になると考えられたことから、調査を継続しました。新型コロナウイルス感染症の流行というきわめて困難な3年間を乗り越え、取扱高が一定規模に達し、業界内の熾烈な競争が多少沈静化した2023年3月期第3四半期(2022年12月に終了する四半期)になって、同社はようやく損益分岐点に達しました。同社はさらに、コロナ禍で業務を合理化したことで、構造的に利益を生み出せる体質に生まれ変わりました。OTAはいったん主導的地位を確立すればきわめて収益性の高い事業であることから、同社収益は過去6ヵ月間継続的に改善しています。
MakeMyTripはNASDAQ市場(米国)に上場していますが、インドの国内投資家の多くは特定の委託業務や市場アクセスに関して制約があり、同社に投資できません。2022年に入ってからは、同社がインドに上場し、同社をよく知るインドの投資家が投資できるようになることで、株価が大幅に上昇するのではないかという期待感が広がりました。しかし、その期待は2023年に同社が「資金調達の必要性を感じておらず、当面は二重上場を検討していない」と発表したことで、見事に打ち砕かれました。この発表を受けて、2023年はファンダメンタルズが引き続き改善したにもかかわらず、株価が急落しました。しかし資金調達が不要だということは、言い換えれば経営陣が自社のキャッシュ生成能力に自信を持っているということなので、悪材料ではなく、むしろ好材料だというのが当ファンドの見方です。当ファンドはようやく好機が到来したと考え、4月に同社に新規投資を開始しました。
インドはきわめて将来有望な市場ですが、その最大の課題は、著名な大型株が非常に高いバリュエーションで取引されているという点にあります。当ファンドは時価総額の大きさに関わりなく、どんな企業にも市場の状況次第で好機があると考えています。インドでは現在、知名度が比較的低く、より割安なバリュエーションで取引されている中型株に、より多くの投資機会があると思われます。当月に当ファンドの調査担当者がインドに出張し、企業の調査を実施しましたので、今後も引き続きインド銘柄について月次報告書にてご報告していく予定です。
2023年7月の運用コメント
株式市場の状況
<日本の株式市場>
2023年7月、日本株式市場の代表指数であるTOPIX(配当込み)は前月末比1.49%の上昇となりました。
当月の日本株式市場は、FOMC(米連邦公開市場委員会)議事要旨にて年内2回以上の利上げが示唆されたことや、米国の雇用統計の結果を受け、利上げ継続への懸念が強まり下落して始まりました。一方で月半ばには、米国のCPI(消費者物価指数)が市場予想を下回り、利上げ停止が近いとの期待から堅調に推移しました。月後半は、日銀によるYCC(イールドカーブ・コントロール)の柔軟化が発表され、一時的に値動きの激しい展開となりましたが、現行の緩和姿勢を維持するとの受け止めから市場に安心感が広がり、最終的に期初を上回る水準で月を終えました。
<アジアの株式市場>
当⽉、アジア株式市場は前月に引き続き堅調に推移しました。⽇本を除くアジア太平洋市場に使⽤される⼀般的な指数であるMSCIアジア太平洋(⽇本を除く、⽶ドル建て)指数は、中国、マレーシア、シンガポールなどが主にプラスに寄与し、前⽉末⽐5.82%上昇しました。中国政府は消費や、住宅セクター、資本市場向けの刺激策を発表しました。民間企業の支援を目的とする31項目ものガイドラインが発表されたことを受け、中国市場に対する投資家心理は改善しました。
AI(⼈⼯知能)の将来性に対する楽観論が、引き続き情報技術関連銘柄の上昇要因となりました。Taiwan Semiconductor Manufacturing Company(台湾/半導体・半導体製造装置)は、AI関連の需要拡大が予想されることから、同分野への設備投資を拡大すると発表しました。しかしスマートフォンやPCは在庫調整がほぼ終了した模様であるにもかかわらず、半導体の需要が引き続き低迷しており、マクロ経済に対する信頼感の低さがうかがわれます。台湾や韓国に拠点を置く他のIT企業も、直近の決算説明会で同様の見解を示しました。
インドとインドネシアは引き続き投資家の注目を集めています。両国は製造業への投資と製造能力の向上を目的に、積極的に外資を呼び込んでいます。インフラ整備はこれまでと同様、今も経済成長の原動力であると当ファンドは考えています。両国では国内消費主導型セクターも好調なパフォーマンスを記録しています。
ファンドの運用状況
当⽉、当ファンドのパフォーマンスは前⽉末⽐0.89%の上昇、参考指数のMSCI AC Asia Index(円ベース・配当込み)は同3.22%の上昇となりました。
当⽉パフォーマンスにプラスに貢献した銘柄は、Mitra Adiperkasa(インドネシア/一般消費財・サービス流通・小売り)、JYP Entertainment(韓国/メディア・娯楽)、SM ENTERTAINMENT(韓国/メディア・娯楽)などでした。一方、Taiwan Semiconductor Manufacturing Company(台湾/半導体・半導体製造装置)、ソシオネクスト(半導体・半導体製造装置)、HDFC Bank(インド/銀行)などがマイナスに影響しました。
中国市場が当ファンドの注視対象に再浮上してきました。中国株式市場は年初に経済再開を巡る期待感から、数ヵ月来の高値を記録しました。しかし2023年1月の月次報告書で述べた通り、当ファンドは景気敏感株が主導する形での株価上昇に疑問を感じ、年初に中国関連銘柄の組入比率を引き下げました。中国株式市場はその後、経済全般、とりわけ不動産市場が予想以上に低迷していることが明らかになったことで、再び下落基調に陥りました。さらに地政学的リスクを巡る報道が相次いだことで、外国人投資家の投資意欲が減退しました。このように中国株式市場は好材料が出て急上昇した後、ゆるやかに下落するというパターンを幾度となく繰り返してきました。
こうした相場変動は短期的利益を追うトレーダーにとっては悪夢でしょうが、幸いなことに当ファンドはそうではありません。当ファンドは中国関連銘柄の組入比率を低めに保ち、好機を待ちました。
中国でいま最も注目されているのは、中国経済が不動産バブルの崩壊によって「バランスシート不況」に追い込まれるのか否かということです。「バランスシート不況」というのは野村総合研究所のチーフエコノミストを務めるリチャード・クー氏が提唱する用語で、ちょうどバブル崩壊後の日本のように、金利がどれほど下がっても民間企業が資金を借り入れようとしない状態を指します。そうなると、金融緩和をどれほど積極的に行おうとまったく機能しません。日本経済はバブル崩壊後、資産価格の急落によって、多額の負債を抱える企業が破綻寸前の状態に陥りました。そうした企業はあらゆる支出を絞ってキャッシュフローを確保することで債務を返済するしかありませんでした。そうして日本の企業は債務超過による苦境とその時に負ったトラウマのために、金利がゼロ近くまで低下しても資金の借り入れを再開しようとしませんでした。バブル崩壊の影響があまりにも広範囲に広がったため、どの企業もバランスシートを修復しようと躍起になった結果、日本経済は深刻なデフレに追いやられたのです。民間企業は借入金の返済ばかりに気を取られ、設備投資や研究開発に資金を投じて競争力を保つことができず、結果として世界の様々な業界で日本企業の存在感が薄れていきました。その後20年以上の年月をかけてバランスシートを修復し、日本の民間企業はどん底から抜け出そうとしています。日本はようやく新たなスタートを切った、それが当ファンドの見方です。
中国に話を戻すと、不動産セクターに対する投資意欲がかなり減退しており、民間不動産開発会社の多くが事実上破綻しています。また、地方政府は多額の負債を抱えています。中国政府は経済が厳しい状況にあることを認識し、各種政策を矢継ぎ早に発表して事態の鎮静化に努めています。政府の経済計画を司る国家発展改革委員会は月半ばに、民間企業の支援を目的とする31項目ものガイドラインを発表しました。またTencent Holdings(中国/メディア・娯楽)会長の馬化騰氏は、国営メディア向けに執筆した記事で、民間企業に対する支援が急務であることを示唆しました。月後半には、共産党の最高意思決定機関である政治局が中央政治局会議を開催し、経済情勢に関する表現が多数変更、不動産政策と地方政府への規制に対するスタンスがより緩和されました。また、中国政府はさらに、地方政府の債務問題への直接的な取り組みを強化することも明言しました。
では中国はバランスシート不況に突入するのでしょうか。当ファンドはエコノミストではないので、この質問に答えられる立場にはありません。しかし、当ファンドの投資候補銘柄を調査した結果、バブル崩壊後の日本の民間企業の状況とは大きく異なると考えています。第一に、大企業や有力企業の多くは財務状態が健全で、バランスシートを修復する必要はないと考えます。第二に、そうした企業の事業拡大や投資に対する意欲に衰えの気配はなく、様々な業界の企業が、外国企業からの市場シェア奪取や海外進出に引き続き意欲的に取り組んでいるようにみえます。例えばBYD Auto社(中国)が既に日本市場に進出し、きわめて競争力の高いEV(電気自動車)を販売していることをご存知でしょうか。月後半にはVolkswagen Group社(ドイツ)が約7億米ドルを投じてXPeng社(中国)の株式を約5%取得し、Volkswagen Group社の一部EVモデルを共同開発すると発表しました。中国はEVをはじめとする一部セクターにおいて世界を大きくリードしていると考えられ、こうした業界において企業に投資に対する意欲や能力がないと捉えるのは不合理だといえます。当ファンドの経験を踏まえると、中国の起業家は成長への意欲を決して失わない不屈の人々の集まりです。衰退したと考えられていた学習塾セクターでさえ、かつて業界首位の座にあったNew Oriental Education & Technology Group社(中国)は、成人向けの再教育ビジネスやeコマース(電子商取引)のライブ配信プラットフォームを経由した商品販売を通じて生き残る方法を新たに見出しています。
以下は同社の決算です。
純利益はまだ2020年5月期の半分以下ですが、同社は学習塾事業が中国政府による規制によって実質的に消滅したあとの巨額損失をようやく取り戻し、生き残りを果たしました。こうした中国企業を見ていると、30年前の日本企業の姿には重ならないと考えます。結局のところ、中国がバランスシート不況に突入するか否かは、当ファンドにとってそれほど重要ではありません。当社は日本企業への投資を30年以上にわたって続け、良好なパフォーマンスを残してまいりましたが、日本はその間、バランスシート不況に陥っていたのです。つまりどれほど厳しい環境下であっても、「勝ち組」は存在します。当ファンドの務めは、過去30年間にわたって日本でしてきたように、勝ち組になる企業を発掘し、投資することです。
当ファンドは当月に入ってから、一部企業が発表した決算や共産党中央政治局会議のトーンの変化を受けて、強気姿勢に転じ、中国関連銘柄の組入比率を徐々に拡大しています。冒頭で述べたように、中国市場は急上昇の後、徐々に下落するパターンを繰り返してきました。市場の慎重姿勢は行き過ぎで、規制や政策、多数の企業による自助努力といった好材料を完全に無視しているというのが当ファンドの見方です。大手消費財企業の株価は、軒並みこれ以上下落しようがない水準まで落ち込んでいると考えます。加えて、グローバル市場全体で投資家心理に一貫性がみられず、Apple社(米国)、LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton社(フランス)、Hermes International社(フランス)、Tesla社(米国)といった中国へのエクスポージャーが大きいグローバル企業が高いバリュエーションで取引されています。当ファンドの見方では、バリュエーションと企業価値の乖離があまりに大きくなっているため、低いリスクで大きな利益を上げる好機が到来するのではと考えています。8月は各社が中間決算の発表を控えているため、当ファンドはその内容を慎重に検証していく予定です。中国株式市場が8月に反発するかは不明ですが、当ファンドの組入銘柄は保有期間内に必ずやリターンをもたらしてくれると考えています。
2023年6月の運用コメント
株式市場の状況
<日本の株式市場>
2023年6月、日本株式市場の代表指数であるTOPIX(配当込み)は前月末比7.55%の上昇となりました。
当月の日本株式市場は、月前半は米連邦債務の上限停止による米国株高の流れを受け、大幅に上昇いたしました。月半ばには、FRB(連邦準備制度理事会)による追加利上げの示唆を受けた軟調な米国株の影響や、衆院解散への期待剥落が嫌気された一方、日銀の金融緩和の維持、米著名投資家の日本株追加投資の発表が好感され、一進一退の動きで推移しました。月後半は、株価上昇の反発と見られる下落の局面もありましたが、米景気悪化懸念の後退と円安進行が下支えをし、最終的に前月末を上回る水準で月を終えました。
<アジアの株式市場>
当⽉、アジア株式市場は堅調に推移しました。⽇本を除くアジア市場に使⽤される⼀般的な指数であるMSCIアジア(⽇本を除く、⽶ドル建て)指数は、前月末比2.81%上昇しました。米国の経済指標が堅調だったことで、投資家心理が世界的に好転し、情報技術セクターを中心に米国の株価指数が軒並み上昇しました。AI(人工知能)の将来性に対する楽観論の広がりによって、アジアの情報技術関連銘柄が引き続き上昇し、中国が大規模な景気対策を打ち出すという観測も市場の下支え要因となりました。
当月は米国のブリンケン国務長官が中国を訪れ、習近平国家主席と会談しました。結果次第では米中関係が改善に向かうのではないかという期待感が広がりましたが、大きな進展はありませんでした。それどころか、米国は半導体製造装置と製品の対中輸出制限を強化する計画を発表し、中国も半導体製造、EV(電気自動車)、通信機器に不可欠な2種類の金属(ガリウムとゲルマニウム)の輸出を制限してこれに応じました。
一方、インドのモディ首相は米国を訪れ、温かい歓迎を受けました。同首相はApple社のティム・クックCEO(最高経営責任者)やTesla社のイーロン・マスクCEOら、米国を代表する企業のリーダーと会談し、今後の投資先としてインドを検討するよう促しました。インドの長期的成長見通しを肯定的に捉える見方が裏付けを得たことで、インドの主要な株価指数のNifty50指数とSENSEX指数が、当月ともに史上最高値を更新しました。
ファンドの運用状況
当⽉、当ファンドのパフォーマンスは前⽉末⽐7.38%の上昇、参考指数のMSCI AC Asia Index(円ベース・配当込み)は同6.86%の上昇となりました。
当⽉パフォーマンスにプラスに貢献した銘柄は、ソシオネクスト(半導体・半導体製造装置)、Classys(韓国/ヘルスケア機器・サービス)、三菱商事(資本財)などでした。一方、Indian Energy Exchange(インド/金融サービス)、FOOD & LIFE COMPANIES(消費者サービス)、H World Group(中国/消費者サービス)などがマイナスに影響しました。
当ファンドは当月、インドネシア企業の調査を目的にジャカルタを訪問し、銀行、生活必需品、鉱業、通信、自動車部品など、様々な業界の企業と面談を行いました。インドネシアの状況は、新型コロナウイルス感染症の拡大以降、大きく変化しています。中でも顕著なのは、同国が製造業の川下への移行を進めていることです。同国はかつて、天然資源の一大輸出国でした。しかし、資源の輸出によって経済は天然資源価格の変動に晒され、付加価値もあまり生まれませんでした。そこでインドネシア政府は川下製造業の発展に力を入れるようになりました。その中できわめて有望な分野がEV(電気自動車)です。同国は一部のEVバッテリーの製造に不可欠な金属であるニッケルの埋蔵量が豊富です。同国は電池素材の製造インフラを構築中で、さらに川下産業であるEV用電池の製造を目指しています。それを裏付けるかのように、Contemporary Amperex Technology社(中国)やLG Energy Solution社(韓国)といった世界的なEV用バッテリー企業がインドネシアへの投資を進めています。同国が川下産業への移行に成功すればアジア地域のEV製造の架け橋になる可能性があり、それは同国に大幅な経済成長をもたらすと当ファンドは考えております。
企業調査の中でもうひとつ目についたのは、インドネシアにおける韓国製品の人気です。ジャカルタのレストランやショッピングモールに入ると、BGMがたいていK-POPであることに気づきます。消費財には韓国アイドルの顔が印刷され、韓国の即席麺や化粧品も人気です。また、インドネシアの企業が韓国製に似せた製品を販売しているものもありました。SM Entertainment(韓国/メディア・娯楽)所属の人気ガールズグループである「aespa」は、当月ジャカルタでのライブツアーを終えたところです。当ファンドはK-POPや韓国食品をはじめとする韓国製品の海外輸出動向をきわめてポジティブに捉えています。
当ファンドが面談した大手消費財企業の一部は、従来と同様の戦略を貫き、利益を上げながら着実に成長しています。インドネシアの消費者の志向に一貫性があり、変化が起きにくいことは、きわめて魅力的な特性です。インドネシア国内に大きな可能性がある一方で、一部のインドネシア企業は既に海外に目を向け、国外で成功を収めているものもあります。例えば、国内最大級の即席麺メーカーであるIndofood CBP Sukses Makmur(インドネシア/食品・飲料・タバコ)は、アフリカ地域や中東地域で好業績を上げ、ナイジェリア、エジプト、トルコなどで圧倒的な市場シェアを持っています。これらの国は人口が多く、即席麺の消費量がまだまだ低水準です。同社がこうした市場で継続的に地位を高め、アフリカ地域以外の国に進出することができれば、市場規模はインドネシアよりさらに大きくなる可能性があります。同社の海外事業は2022年に前年比約19%成長し、売上寄与度はおよそ30%近くに達しています。
ところで、新型コロナウイルス感染症の大流行によって様々な変化が起きたのは確かですが、変化していないこともあります。例えば、医療サービスの需給ギャップは依然大きく、拡大を続ける同国中間層の需要を満たすには供給がまだまだ不足しています。したがって、医療セクターには大いに投資機会があるとみてよいでしょう。
全般的にみて、当ファンドが話を聞いた現地の人々は比較的将来を楽観視していると感じられました。これはデータでも裏付けられており、インドネシア中央銀行の消費者信頼感指数(IKK)は過去最高値圏で推移しています。こうした楽観主義は今後数十年にわたって同国の成長の原動力になる、というのが当ファンドの見方です。インドネシアの未来を楽観視しているのは当ファンドも同様で、当ファンドは参考指数であるMSCI AC Asia Indexを上回る比率で同国銘柄を組み入れています。
なお、当ファンドは当月、ソシオネクスト(半導体・半導体製造装置)の組入比率を大幅に引き下げました。当ファンドは前年末より同社に投資を開始し、保有比率を引き上げていました。同社は自動車、5G(第5世代移動通信)ネットワーク、家電製品など、幅広い用途の顧客向けにカスタマイズされた半導体を設計する半導体設計サービスプロバイダーです。半導体は新しい石油のような存在で、その重要性はかつてないほどに高まっており、多くの企業が自力で半導体を設計することで、自社製品の性能を最適化しようと取り組んでいます。しかし、企業の多くはApple社(米国)やTesla社(米国)のようなリソースや能力を持ち合わせておらず、半導体を自社で全面開発することはできないため、ソシオネクストのような設計サービス企業と契約することで、カスタム半導体の設計と開発を行う必要があります。したがって、同社のような設計サービス企業は半導体市場全体を上回るスピードで成長する可能性があると考えられます。当ファンドは同社が自動車向けの半導体を多数手がけていることを高く評価しており、自動車向け半導体は製品サイクルが長期化する傾向にあり、さらに車載コンピュータの要件が厳格化してきていることで需要拡大が見込めると考えております。同社の株価は当月半ば、生成型AI(人工知能)の登場によってカスタマイズ型半導体需要が拡大するという期待感から、大幅に上昇しました。当ファンドでは、同社の高性能AI関連コンピューティングにおける立場はGlobal Unichip社(台湾)やAlchip Technologies社(台湾)といった競合他社ほど強くないと考えています。したがって、今回の株価上昇要因には何らかの読み違いがあり、短期的にみて過度な上昇であると考えています。そこで当月の上昇局面では組入比率を継続的に引き下げ、当月後半の株価調整直前に保有株式の半数以上を売却しました。長期的な見通しは依然良好であること、株価調整後のバリュエーションは適正に近いと考えられることから、引き続き少額のポジションを保有し、株価が大幅な割安水準に低下した時点で再び買い増す予定です。
一方、今年5月に組み入れたばかりのJSR(素材)は、日本の政府系ファンドである産業革新投資機構(JIC)からの9,040億円の買収提案を受け入れると発表しました。同社は半導体製造に不可欠な化学薬品であるフォトレジストの製造で世界をリードする企業です。同社がJICに買収されて最終的に上場廃止になれば、それは日本の半導体材料セクター再編の足掛かりとなるでしょう。半導体の重要性が世界的な高まりを見せるなかで、日本政府は自国半導体産業の競争力強化に向けた措置を講じています。日本の株式市場は、株主還元が改善することへの期待感から好調に推移しています。しかし、自社株買いや配当だけでは市場の持続的な上昇を促すには不十分であると当ファンドは考えます。政府が業界再編を主導するのもひとつの方法かもしれませんが、結局のところ企業は構造的に強くなり、いかに利益を上げるかを考える必要があります。当ファンドは同社の株価が買収報道を受けて上昇したあと、同社株式を売却しました。
2023年はここまでソシオネクスト(半導体・半導体製造装置)、ルネサスエレクトロニクス(半導体・半導体製造装置)、Samsung Electronics(韓国/テクノロジー・ハードウェアおよび機器)といった半導体関連の組入銘柄が大きくリターンに貢献したため、同セクターで引き続き新銘柄を発掘していく予定です。半導体のサプライチェーンは非常に長くて専門性が高く、国によって強みが異なります。例えば、台湾にはTaiwan Semiconductor Manufacturing Company(台湾/半導体・半導体製造装置)があり、その周辺で多数の設計会社がエコシステム(企業同士が協業・連携することで共存していく仕組み)を形成しています。一方、日本には世界有数の半導体材料や機器を取り扱う企業があり、異なる特徴を持つ企業がサイクルの様々な部分に棲み分けています。当ファンドの優位性は⽇本と他のアジア地域に資本を柔軟に配分できるという点にあり、当ファンドはアジアの半導体に対する投資機会を活用する上で有利な立場にあると考えています。
2023年5月の運用コメント
株式市場の状況
<日本の株式市場>
2023年5月、日本株式市場の代表指数であるTOPIX(配当込み)は前月末比3.62%の上昇となりました。
当月の日本株式市場は、月前半に開催された米国FOMC(連邦公開市場委員会)の結果を受け、一時円高ドル安が進んだことで一進一退の動きで推移しました。月半ばには海外投資家による資金流入が続き、TOPIXと日経平均株価ともに約33年ぶりの高値を更新しました。東京証券取引所の市場改革への期待や、日銀の金融緩和継続姿勢もサポート材料となりました。一方で、月後半には中国の低調なPMI(製造業購買担当者景気指数)や、市場予想を下回る国内の4月の鉱工業生産指数の結果が懸念され、弱含みで推移しましたが、最終的に前月末を上回る水準で月を終えました。
<アジアの株式市場>
当⽉、アジア株式市場はまちまちの値動きとなりました。日本を除くアジア市場に使用される⼀般的な指数であるMSCIアジア(日本を除く、米ドル建て)指数は、前月末比0.46%下落しました。世界経済の減速、米国の債務上限問題、中国における製造活動の鈍化などが懸念され、投資家の間に不安が広がりました。米中関係には未だに緊張緩和の兆しが見られません。中国は「ネットワークセキュリティ上の深刻なリスク」を理由に、主要インフラプロジェクトで大手半導体メーカーであるMicron Technology社(米国)の製品の使用を禁止すると発表しました。米国政府が中国向け半導体製品の輸出を規制したことから、中国当局が対抗措置に踏み切ったという見方が広がっています。
中国では国営企業の改革が引き続き注目の的となっていますが、これは中国政府が国営企業のガバナンスと収益性の改善に向けた取り組みを強化しているためです。ある規制当局の高官は、投資家は中国国営企業の評価にあたって「中国らしい特色をもった企業価値評価システム」を模索すべきだと述べています。こうした要因から、当月は一部国営企業の株価が上昇しました。
当月の好材料としては、テクノロジー関連銘柄の上昇があげられます。半導体設計会社であるNVIDIA社(米国)が好決算と良好な業績見通しを発表したことを受けて、アジアの半導体関連銘柄に対する投資家心理が改善しました。同社の半導体は生成型AI(人工知能)「ChatGPT」などのアプリケーションに幅広く使用されており、過去数ヵ月にわたってそうしたアプリケーションの伸びが加速しています。台湾と韓国の株式市場では、テクノロジーセクターの好調な業績が最大の上昇要因となりました。
ファンドの運用状況
当⽉、当ファンドのパフォーマンスは前⽉末⽐6.99%の上昇、参考指数のMSCI AC Asia Index(円ベース・配当込み)は同2.13%の上昇となりました。
当⽉パフォーマンスにプラスに貢献した銘柄は、ソシオネクスト(半導体・半導体製造装置)、JYP Entertainment(韓国/メディア・娯楽)、Taiwan Semiconductor Manufacturing Company(台湾/半導体・半導体製造装置)などでした。一方、Samsonite International(香港/耐久消費財・アパレル)、Zijin Mining Group(中国/素材)、オリンパス(ヘルスケア機器・サービス)などがマイナスに影響しました。
前述の通り当月の日本の株式市場は好調に推移し、TOPIX、日経平均株価ともに約33年ぶりの高値を更新しましたが、外国人投資家の日本に対する関心はますます高まっていると思われます。東京証券取引所は2023年3月、PBR(株価純資産倍率)が1倍を下回っている上場企業に対し、株主価値の改善に向けた具体的計画を打ち出すよう要請しました。日本株式市場の低迷があまりにも長期にわたっていたことから、東証が市場改革に乗り出した形です。コーポレート・ガバナンスと株主還元の改善は、日本の株式市場において今後も根深い課題であり続ける、というのが当ファンドの見方です。
中国でも同様の事態が起こっており、このところバリュエーションの低い国営企業の株価が上昇しています。中国証券監督管理委員会(中国の証券市場監督機関)の易会満主席は2022年11月に行った講演で、「中国らしい特色をもった企業価値評価システムの模索に努めるべき」と述べました。この発言は同氏が国営企業のバリュエーションは低すぎると考えているという意味に解釈され、国営企業の改革というテーマが再び脚光を浴びることになりました。2023年1月には、国務院国有資産監督管理委員会(主要国営企業の管理監督機関)が新たに国営企業のKPI(重要業績評価指標)を発表し、ROE(株主資本利益率)と営業キャッシュフローを重視すると明らかにしました。日中両国はほぼ同時期に、自国株式のバリュエーションの押し上げに取り組んでいることになります。
中国の国営企業改革が成功すれば国営企業は収益を拡大し、評価を上げることができますが、それは簡単なことではないと考えます。2015年に公表された政府指針によると、国営企業は、(1)国家資本の保全と成長を目的とし、市場原理に則って営利を追求する国営企業、(2)国家の使命を担う必要性から戦略的産業で営利を追求する国営企業、(3)公共の福祉に資する国営企業の3グループに分類されていて(以下グループ1、2、3と略称)、上場国営企業の大半はグループ1と2に属しています。このところ脚光を浴びているのはグループ2の国営企業で、通信、銀行、保険、貿易といった戦略的産業に属し、バリュエーションがきわめて低い状態にあります。先行き不透明な足元の環境下では、こうした企業の配当利回りの高さは好材料とみなされる可能性があります。しかし株価が低いのは、それらの企業が国家の重い使命を背負わざるを得ず、本質的に変革しにくい側面があるためだと考えます。足元では株主還元を重視していても国家の使命を優先する姿勢が変わることはないため、今後政府の意向を最優先とする状態に戻ることも起こり得ます。当ファンドのような長期投資家としては、そうした企業に大きな期待をかけることはできません。
グループ2と3に属する国営企業は国益を担わざるを得ませんが、国営企業がすべて国家の使命を優先しているわけではありません。経営判断に国の意向がどの程度反映されるかは、当該国営企業の規模、政権中枢との組織的な緊密度、業種など、様々な要因によって異なりますが、グループ1に属する国営企業の多くはグループ2、3に属する企業と異なり、経営判断に国の意向を反映する必要がほとんどありません。そうした企業は既に市場原理に則った形で営利を追求しているのに、なぜ経営がうまくいっていないのでしょうか。当ファンドでは、その多くに事業の質の低さと経営陣の能力の欠如という制約があるためだと考えています。国営企業の多くは、素材や汎用品の製造といったオールドエコノミーの業種に属しています。また特定の業種に規制がかけられていることも、一部国営企業が柔軟性を損なう要因となっています。そうした企業が当ファンドの投資基準を満たすことはほぼないでしょう。米国の著名な投資家であるウォーレン・バフェット氏の名言に、「手腕がすばらしいと評判の経営者でも、着任先が利益の出ないことで有名な企業なら、その企業の評価は変わらない」というものがあります。しかし、国営企業はMSCI中国指数組入企業の時価総額の30%超、中国の時価総額全体の50%を占める巨大な企業群です。政府の業界再編によって企業間の競争が緩和する可能性のある分野には選別的な投資機会があると考えられます。
当ファンドの主な投資対象は、グループ1に属し、既に経営が順調で、それほど改革を必要としないと考えられる国営企業です。国営企業はすべて経営状態が芳しくない準政府機関であると考えられていますが、それは必ずしも正しくないと当ファンドでは考えています。国営企業が多額の利益を上げれば、その最大の受益者は国家です。非効率な国営企業は、非効率な従業員、さらに酷い場合は腐敗した経営者にしか利益をもたらしません。したがって、企業から経営陣への利益の移転を防ぐことは、国営企業改革の重要なポイントです。国営企業の中には、長期にわたって市場原理に則った経営を行い、厳しい競争環境の中で生き残ってきた企業もあります。1872年に設立されたChina Merchants Group社(香港)と1938年に設立されたChina Resources Group社(香港)はその好例です。両社はいずれも香港に本社を置き、日本の総合商社のような貿易会社として出発しました。China Merchant Bank社(香港)、China Resources Beer(香港/食品・飲料・タバコ、当ファンド組入銘柄)、China Resources Land社(香港)といったいくつかの子会社は、優良企業へと発展し、過去数年で多大な株主価値を生み出しました。当ファンドはこうした企業群に属すると考えられる国営企業のうち、事業の質が高く、経営者が優秀であると判断した企業へ投資を行っています。国営企業改革による直接的な業績改善はそれほど期待できませんが、少しでも国営企業が改善されれば好材料となるためです。中国の株式市場は当月、パフォーマンスがきわめて低調でした。当月発表された各種指標の結果は芳しくなく、景気が力強く回復するという期待は打ち砕かれました。当ファンドは1月の月次報告書で、中国市場に関して慎重姿勢を強めており、中国銘柄の組入比率を控えめにしたとお伝えしました。現在もその姿勢に大きな変化はありませんが、強力な経済基盤を有し、地政学的リスクが低く、中国における消費拡大の恩恵を長期的に受ける立場にあり、組織や収益構造がシンプルな企業の組入比率を選別的に引き上げています。当ファンドの優位性は⽇本と他のアジア地域に資金を柔軟に配分できるという点にあり、ベンチマークにとらわれず、最も有望な投資先を見定めて組み入れるという手法をとっています。足元は日本の銘柄に注目が集まり、中国の銘柄は見過ごされがちですが、中国の銘柄の魅力が再び高まった時には、躊躇なく組み入れを進める予定です。
2023年4月の運用コメント
株式市場の状況
<日本の株式市場>
2023年4月、日本株式市場の代表指数であるTOPIX(配当込み)は前月末比2.70%の上昇となりました。
当月の日本株式市場は、月前半に軟調な米国経済指標(ADP雇用統計、ISM非製造業景況感指数)が相次ぎ、景気後退懸念が高まったことから下落して始まりました。しかし月半ばには植田日銀総裁の金融緩和維持を支持する発言や、米著名投資家の日本株追加投資を巡る思惑から上昇に転じました。月後半は米地方銀行の巨額預金流出による警戒感から下落する局面もありましたが、日銀が金融緩和維持を決定したことで株式市場に安心感が広がり、最終的に前月末を上回る水準で月を終えました。
<アジアの株式市場>
当⽉、アジア株式市場はまちまちの値動きとなりました。日本を除くアジア市場に使用される⼀般的な指数であるMSCIアジア(日本を除く、米ドル建て)指数は、前月末比2.07%下落しました。世界経済の低迷、米国の銀行危機の波及、中国の製造活動の鈍化に対する懸念が広がり、慎重姿勢をとる投資家が増加しました。米バイデン政権が最先端技術や機器の中国への輸出規制を厳格化する意向を示したことから、米中間の緊張はますます高まりました。
また、スマートフォンやPCの需要低迷が、引き続きテクノロジー銘柄の重石となっています。Samsung Electronics(韓国/情報技術)は、主力の半導体メモリーの需要低迷が原因で、2023年1月~3月期決算が低調でした。Taiwan Semiconductor Manufacturing Company(台湾/情報技術)も、半導体業界の成長が短期的に弱含むという予想を明らかにしました。ただし両社はいずれも、将来的に成長が見込める技術の研究開発と投資を続け、半導体関連製品、とりわけ自動車、AI(人工知能)、データセンター、IoT(Internet of Things、モノのインターネット)の構造的な需要増加に対応していく意向を示しました。
一方、コロナ禍後の回復が続いたことが、アジア全域のサービスセクターの追い風となりました。海外へ出かける人も多く、とりわけ復活祭期間中の旅客数が堅調でした。中国人旅行者の姿が香港に戻り、ショッピングモール等の小売売上高が好調に推移しています。
インドネシアとインドは、外国企業の生産拠点移転先としての人気がますます高まっています。インドネシアに対するルピア建て海外直接投資(FDI)は2023年第1四半期だけで前年同期比20.2%増加し、この勢いは今後も続くと当ファンドは考えています。Apple社(米国)のティム・クック最高経営責任者(CEO)はインドを訪問し、同国への投資をさらに拡大し、同社輸出製品の生産拠点としての役割を漸次拡大していくと発表しました。
ファンドの運用状況
当⽉、当ファンドのパフォーマンスは前⽉末⽐0.71%の上昇、参考指数のMSCI AC Asia Index(円ベース・配当込み)は同1.09%の上昇となりました。
当⽉パフォーマンスにプラスに貢献した銘柄は、Indian Energy Exchange(インド/各種金融)、ソシオネクスト(半導体・半導体製造装置)、JYP Entertainment Corp(韓国/メディア・娯楽)などでした。一方、Taiwan Semiconductor Manufacturing(台湾/半導体・半導体製造装置)、Tencent Holdings(中国/メディア・娯楽)、i-Tail Corporation(タイ/食品・飲料・タバコ)などがマイナスに影響しました。
2023年2月の月次報告書で、当ファンドがどのような観点から日本の総合商社を組み入れているのかという点ついて説明しました。当月にはウォーレン・バフェット氏が東京を訪れ、同氏率いるバークシャー・ハサウェイ社(米国)が日本の5大総合商社の組入比率を7.4%に引き上げたことを明らかにしました。同社の非保険部門担当副会長を務めるグレッグ・アベル氏はCNBC社のインタビューに応え、今後も商社が推進するプロジェクトへの共同投資を考えていると述べました。総合商社のグローバルネットワークと信用、バークシャー・ハサウェイ社が持つ資金力を組み合わせれば、好ましい取引を将来にわたって続けていくことができるというのが当ファンドの見方です。バフェット氏の訪日による投資家心理の好転も一因となって、総合商社の株価は当月、堅調に推移しました。資本循環が活発化し、株主還元が拡大していることなどから、当ファンドは引き続き総合商社をポジティブに見ています。一方、それとは別に、バークシャー・ハサウェイ社が当月、約1,600億円相当の円建て債券を発行しました。市場にはバフェット氏が日本で新たな投資先を探しているという見方が広がっています。日本経済はアジアの途上国と比べると成長が緩やかですが、世界的企業を多数擁していることから、当ファンドは引き続き投資機会を探っていく予定です。
一方で、韓国も有望市場として見逃せないと当ファンドは考えております。韓国も日本と同様、アジアの途上国と比較すると経済成長が比較的緩やかで、高齢化も進行しています。しかし、同国にはアジアや世界で成長する力を持った世界的企業が多数存在していると当ファンドは考えております。韓国は世界のEV(電気自動車)バッテリーや半導体のサプライチェーンにおいて重要な役割を担っています。またテクノロジー関連製品以外にも、Kカルチャー人気の世界的な高まりを背景に、K-POPやドラマといったコンテンツから即席麺、菓子類、美容関連製品にいたるまで、様々な消費財を輸出しています。
当ファンドが組み入れている韓国の銘柄の1つにCLASSYS(韓国/ヘルスケア機器・サービス )があります。同社はHIFU(High-Intensity Focused Ultrasound、高密度焦点式超音波)療法用機器の売上高で世界第2位のメーカーで、2020年には世界HIFU機器市場におけるシェアの約18%を占めています。HIFUは皮膚を傷つけずに行える美容治療法で、皮膚の基本構成要素であるコラーゲンの生成を促します。同社はHIFUで築いた確固たる地位を活用してRF(高周波)美顔器の製造にも参入していますが、これにも肌を引き締める効果があります。同社の追い風となっているのは、1) 従来のスキンケア製品ではもはや細かい点にこだわる消費者の需要が満たされないため、より高度な効果を求めて美容クリニックに通う消費者が増えていること、2) HIFUやRFのような皮膚を傷つけない美容治療法(非侵襲性美容治療法)は整形手術のような痛みを感じずに高い効果を得られるため、世界的に人気が高まっていることなどが考えられます。同社は非侵襲性美容治療法のトレンドに乗る上で有利な立場にあるというのが当ファンドの考えです。
同社は、いわゆる「替え刃モデル(商品の本体を安く売って顧客を囲い込み、その後の消耗品やサービスで儲けるビジネスモデル)」を採用し、HIFU機器やRF美顔器を美容クリニックに販売し、消耗品であるカートリッジの販売を通じて経常的に収益を生成しています。同社は2017年から2022年にかけて、売上高の年平均成長率が約32%に達しました。2022年の売上高の63%は輸出によるもので、ROE(株主資本利益率)は約38%と驚異的な高水準でした。同社は世界中に製品を輸出しており、日本、タイ、ブラジルといった他の大規模美容市場にも積極的に進出する計画です。
同社はHIFU機器市場でいかにして成功したのでしょうか。それはつまるところ、アジア製品の典型的成功例、すなわち高性能な製品を競合より低価格で販売したことによるものだと当ファンドは考えています。HIFU療法用機器に最初に参入したのは欧米企業でしたが、同社は性能が同等で価格が大幅に安い製品で市場に参入しました。コストパフォーマンスの高さが評価された上にマーケティング面での成功も加わって、同社は欧米企業を追い越し、韓国のHIFU機器市場で支配的な地位を確立しました。高性能な製品を低価格で販売するというビジネスモデルはアジアで幾度となく成功を収めてきた手法であることから、当ファンドは今後もこのテーマに沿って投資機会を発掘していく所存です。
当ファンドは2019年にソウルを訪れて同社経営陣と面談し、その経営手法に強い感銘を受けましたが、資本配分には改善の余地があると感じました。当時は同社株の組み入れは行いませんでしたが、モニタリングは継続していました。2022年4月にBain Capital社(米国)がCLASSYS創業者から持株の約61%を取得し、取締役の顔ぶれを一新しました。当ファンドが再検証したところ、コーポレートガバナンスと資本配分が改善する可能性が高いという点が好材料として浮上しました。さらに、Bain Capital社のグローバルネットワークを活用すれば、同社は中国や米国も含めた世界各国への進出も夢ではないと考えられます。そこで当ファンドは従来の見解を変更し、2022年10月に同社に投資を開始しました。
当ファンドの優位性は日本と他のアジア地域に資本を柔軟に配分できるという点にあり、ベンチマークにとらわれず、最も有望な投資先を見定めて組み入れるという手法をとっています。当ファンドは2022年10~12月以降、バリュエーションが割安な韓国銘柄の組入比率を大幅に引き上げました。現在、韓国の組入比率は、参考指数(MSCI AC Asia Index )を上回っています。韓国の組入銘柄の多くは2022年10月以降、市場平均を大幅にアウトパフォームしており、当ファンドのパフォーマンスにプラスに貢献しています。当月、韓国のEVバッテリー企業に対する投資家心理があまりにも強気すぎると考え、同セクターの組入比率を引き下げました。また、大規模な再編を進めている韓国のエンターテインメント関連銘柄を新たに組み入れました。こちらについては今後の月次報告書で取り上げる予定です。
2023年3月の運用コメント
株式市場の状況
<日本の株式市場>
2023年3月、日本株式市場の代表指数であるTOPIX(配当込み)は前月末比1.70%の上昇となりました。
当月の日本株式市場は、FRB(米国連邦準備制度理事会)の利上げ再加速の思惑を受けて米国株式市場が軟調に推移する中、円安が日本株を支える展開で始まりました。月半ばにかけては、米シリコンバレー銀行の破綻に端を発した欧米金融不安の急拡大を受け、リスク回避姿勢が強まったことから大幅な下落に転じました。しかし月後半になると、スイスの金融大手UBSによるクレディ・スイス・グループ買収や米当局による預金保護などの対応で金融システムへの不安が和らぎ、最終的に前月末を上回る水準で月を終えました。
<アジアの株式市場>
3月は何かと出来事の多い月でした。中国では年に1度の全国人民代表大会が開催され、首相や中国人民銀行総裁といった今後5年間の主要人事が正式決定されました。さらに2023年の中国経済や政策課題の方向性も示され、実質GDP成長率目標は5%、財政赤字目標(GDP比)は2022年の2.8%から3%へとわずかに引き上げられた数字が設定されました。これにより、大規模な景気刺激策に対する期待は打ち砕かれ、株式市場の重しとなりました。
その一方で、様々な分野における「自立自強」推進の必要性が訴えかけられ、その一環として科学技術部の再編が発表されました。この再編に関して注目すべき点は、習近平国家主席に直属する形で中央科学技術委員会が設立されることです。同委員会設置の狙いは、全国的なイノベーションシステムの構築、中国の科学技術発展に向けた大型計画や政策の推進、テクノロジーセクターにおける主要な問題の解決に向けた協調などを通じ、科学技術に関する一元的指導力を強化することにあります。このことから、国家戦略の中で科学技術の占める位置が向上しつつあり、その過程で魅力的な投資機会が訪れることになると当ファンドでは考えております。
世界の銀行業界では危機が発生しました。米シリコンバレー銀行が破産を申請し、その余波に対する懸念から地方銀行の株価が全般的に下落しました。幸いなことに、FRB(⽶国連邦準備制度理事会)が迅速に介入したため、足元では危機は収束しています。英国では金融大手のHSBCが米シリコンバレー銀行の英国事業を買収しました。利上げペースの鈍化を予測する声が出てきたことから、ドルと米国債の利回りは下落しました。欧州では、長期にわたって低迷状態にあったクレディ・スイス・グループがスイスの⾦融⼤⼿UBSに買収されたことを発端に、英国のHSBCやStandard Chartered Bank、米国のPrudential Financialなどの国際的大手銀行や保険会社の株価が下落しました。なお、当ファンドは金融セクターの組入比率が比較的低く、またインドやインドネシアをはじめとするアジア新興国の金融銘柄を主力銘柄として組み入れているため、世界の銀行業界で起きた事態の影響はそれほど受けませんでした。
ファンドの運用状況
当⽉、当ファンドのパフォーマンスは前⽉末⽐1.07%の上昇、参考指数のMSCI AC Asia Index(円ベース・配当込み)は同1.36%の上昇となりました。
当⽉パフォーマンスにプラスに貢献した銘柄は、CLASSYS(韓国/ヘルスケア機器・サービス)、Tencent Holdings(中国/メディア・娯楽)、Samsonite International(香港/耐久消費財・アパレル)などでした。⼀⽅、i-Tail Corporation(タイ/食品・飲料・タバコ)、Indian Energy Exchange(インド/各種金融)、Shenzhou International(中国/耐久消費財・アパレル)などがマイナスに影響しました。
「銀行というものは、愚かな過ちさえ犯さなければすばらしいビジネスである」 – ウォーレン・バフェット
当ファンドでは先進国の金融銘柄は組み入れておりません。多くはROEが低く、構造が複雑で、さらに全般的にみて成長性も限られていると考えられるためです。今後の見通しがそれほど良好なわけでもなく、銀行というものは短期間に少しでも多くのリターンを絞り出そうとして、時折「愚かな過ち」を犯し、危険な橋を渡ろうとする傾向があります。米シリコンバレー銀行の場合、コロナ禍後の超低金利期に多額の資産を長期の政府債と住宅ローン担保証券に投じました。金利が上昇し始めると、同行の保有銘柄は資金の回収期間が長いので、時価評価で多額の損失を出しました。一方、同行の預金はスタートアップ企業やベンチャーキャピタルファンドといった特定の大口預金者に集中していたため、預金流出が発生しやすい状態にありました。そこで同行は損失を出してでも回収期間の長い保有債券を売却し、流出に備えざるを得なくなったのです。そして資本調達の必要があることを公表したことで、預金の流出は加速し、破綻に追い込まれました。つまり流動性と資産負債管理の両面で「愚かな過ち」を犯したことが、同行の破綻の原因と考えます。
一方、アジアの新興国はまるで状況が異なります。例えばインドネシアの大手銀行を見れば、それほど高いリスクを取らなくても十分なリターンをあげられることは明らかであると考えます。当ファンドの保有銘柄であるBank Mandiri(インドネシア/銀行)を例に、それを説明しましょう。インドネシアの銀行セクターは寡占市場です。4大銀行のBank Mandiri、Bank Central Asia、Bank Rakyat Indonesia、Bank Negara Indonesiaは小規模銀行を尻目に市場シェアを拡大し、盤石な収益性と健全な財務基盤を維持しています。市場が寡占状態にあることとは別に、インドネシアは銀行の活用率が依然きわめて低く、成人人口の70%以上がいまだに銀行を利用していないか、あるいは十分なサービスを受けていません。加えてインドネシアではEV(電気自動車)バッテリーの主要素材であるニッケルが豊富に産出されるため、同国は資源輸出国からEVバッテリーなどの製造拠点へと転じつつあります。こうした背景から、インドネシアの大手銀行には多大な成長余地があると当ファンドでは考えています。
商業銀行の主力事業は融資で、概ね汎用商品化しています。この事業の成否の鍵を握っているのはコスト面の優位性です。4大銀行の預金額のシェアを合計すると、同国全体の約50%以上に達しています。さらにCASA(当座預金と普通預金の合計額)比率でみると、4大銀行の市場シェアは更に高くなり、10年前との比較でも大きく上昇しています。インドネシアでは給与振込先の多くが大企業との関係が深い大手銀行の口座です。大手銀行は利便性にも優れており、支店網が充実していて、オンラインバンキングアプリも高機能です。こうした要因から、顧客は利息の高い中小銀行をよそ目に、大手銀行への預金を続けるのです。大手銀行は給与の受け取りや公共料金の支払いといった現金取引額で圧倒的なシェアを占めていますが、こうした資金は移動しにくく、コストが低額です。Bank MandiriはCASA比率が約73%程度の水準にあり、は国内第2位です。同行のような大手銀行は質の高い預金を高い割合で獲得していることから、預金コストがきわめて低くなります。こうした大手銀行は、低リスク負債のスプレッドを利用して多額の利益を上げることができます。また規模の経済が機能するため、費用収益比率も低水準に留まっています。また同行は巨額投資によってデジタル化を進めていますが、それでも費用収益比率は業界最低水準にあります。また同行のバンキングアプリ「Livin’」の配信開始以来のダウンロード数は、既に業界最高の2,000万件以上に達しています。同行の2022年の預金増加額の30%は、Livin’を通じて獲得した新規顧客によるものでした。アプリの機能は預金取引以外にも拡大し、航空券の予約といったサービスも始まっています。
一方、成長と利益率は別にして、銀行というものは慎重に融資を行って、損失を回避する必要があります。ウォーレン・バフェット氏の言う「愚かな過ち」とは、多くの場合、資産側で危ない橋を渡ることです。大手銀行はコストの面で優位に立っているので、質の低い借り手に融資するという形で危険を冒さなくても十分なリターンを上げることができます。Bank Mandiriの不良債権比率は低水準にあるため、同業他行より低リスクで高いリターンを上げることができます。大手銀行の利益は業界全体の多くを占めています。Bank Mandiriは上記の優位性を兼ね備えているため、ROA(総資産利益率)が約3.4%、ROE(株主資本利益率)は約23%に達しています。ここで重要なのは、インドネシアの主要銀行はこれほどのリターンを上げながらも、財務内容が先進国の銀行と比べて比較的堅実であることです。例えば、Bank of America社(米国)のCET1比率(普通株式等Tier1比率、普通株式等Tier1をリスクアセットで除した比率)は約11%、ROEは約10%です。一方Bank MandiriのROEは約23%、CET1比率は約18%です。この点が、当ファンドがインドネシアの大手銀行に有望性を感じる所以です。
世界の銀行セクターを取り巻く不確実性は長期化する可能性がありますが、当ファンドは引き続き、本質的に安全性が高く、財務内容が良好で、収益が底堅い銘柄を選好しています。
※Bank Mandiriの数字は銀行本体のみ表示しており、同行傘下関連会社の数字は除外しています。
2023年2月の運用コメント
株式市場の状況
<日本の株式市場>
2023年2月、日本株式市場の代表指数であるTOPIX(配当込み)は前月末比0.95%の上昇となりました。
当月の日本株式市場は、米長期金利上昇などを受け米国株式市場が軟調となる中、円安が日本株を支える展開で始まりました。月半ばにかけては、市場予想を上回る米国のCPI(消費者物価指数)やPMI(総合購買担当者景気指数)を受けて利上げの長期化懸念が再燃し、日本株も下落に転じましたが、月後半にかけては、植田次期日銀総裁候補が所信聴取で金融緩和継続を明言したことや円安の進行が日本株相場を下支えし、最終的に前月末を上回る水準で月を終えました。
<アジアの株式市場>
アジア株式市場の大半は、1月に堅調に推移した後、当月は下落しました。⽇本を除くアジア市場に使⽤される⼀般的な指数であるMSCIアジア(⽇本を除く、⽶ドル建て)指数は、6.81%下落して⽉を終えました。
これは主に、MSCI中国(米ドル建て)指数の同10.37%下落が影響しました。中国の経済活動再開を受けた消費回復に関する好調なデータにもかかわらず、米国領空内の中国の偵察気球疑惑を巡って米中間の緊張が再燃し、人民軍と関係する中国企業に対する制裁が強化されたことで、投資家心理は冷え込みました。また11月以降に大きく上昇していた中国のインターネット関連銘柄も、高まる規制懸念やJD.com社(中国)による積極的な補助金キャンペーンを契機とした価格競争の可能性を受けて、下落に転じました。
米国の力強いインフレおよび労働市場データも、米国利上げのペース加速と長期化に対する懸念を引き起こし、新興市場の株価に下押し圧力を加えました。インドの指数は当月もAdani危機が重石となり、Adani group社(インド)関連銘柄は大幅にアンダーパフォームしました。台湾のテクノロジー企業は、2022年第4四半期決算説明会で2023年第1四半期の低調な収益見通しを発表しましたが、一部の投資家はそれをサイクルの「底」と解釈し、一部企業の株価の下支え要因となりました。また、最近のChatGPT(AIチャットプログラム)の急速な普及が、半導体やメモリの需要増につながる可能性を指摘する声もあります。
ファンドの運用状況
当⽉、当ファンドのパフォーマンスは前月末比1.22%の下落、参考指数のMSCI AC Asia Index(円ベース・配当込み)は同1.29%の下落となりました。
当月パフォーマンスにプラスに貢献した銘柄はMitra Adiperkasa(インドネシア/小売)、Indian Energy Exchange(インド/各種金融)、JYP Entertainment(韓国/メディア・娯楽)、三菱商事(資本財)など、アジアの各地域に分散していました。一方で、Meituan(中国/小売)やAlibaba Group Holding(中国/小売)、リクルートホールディングス(商業・専門サービス)などがマイナスに影響しました。リクルートホールディングスの2023年3月期第3四半期業績が期待外れに終わったことから、当ファンドは同社株を売却しました。米国の求人市場の低迷が長期化し、同社の主力事業であるHRテクノロジー事業の足枷になり続けるとみられるためです。
三菱商事は、2023年3月期通期の純利益予想を1兆300億円から1兆1,500億円に、一株あたり配当(DPS)を155円から180円にそれぞれ引き上げました。また、1,700億円の自社株買いを加えることで、総還元額は純利益の約38%に相当する4,320億円になると予想しています。同社は累進配当を採用しているため、2024年3月期のDPSは、少なくとも180円(2月末時点の配当利回り4%で算出)になると予想されます。
丸紅は、新たな株主還元方針を発表しました。同社は2022年度純利益を、過去最高の5,300億円と予想しています。また、DPSは78円を基点とし、中長期的な利益成長に合わせて増配するという累進配当方針も発表しました。さらに、総還元性向30~35%を目標とした、機動的な自社株買い方針を発表しました。
このような両社の株主還元拡大を、株式市場は好調な増益トレンドとともに好感しています。
日本の総合商社は多くの産業に関与しています。日本は天然資源に乏しい国であり、これらの総合商社は戦後の経済成長期に日本の産業界の輸出入を支える重要な役割を果たしました。1980年代には、貿易を通じて製造業の海外進出を支援しました。総合商社は仲介業者として、商品の輸出入から手数料収入を得ていました。
しかし、過去20年の間にグローバルなサプライチェーンが構築される中で、仲介業者や貿易会社としての役割は大きく低下しました。そのため、総合商社は強力な資本力や幅広い専門知識を活用して、より投資を中心としたビジネスモデルへと進化しています。開発途上国での長年の事業経験を持つことから、総合商社は現地政府へのアクセスを獲得しており、また現地の需要を見極め、さまざまなインフラプロジェクトを調整する能力を有しています。今日の商社は、上流のコモディティから下流の小売事業まで広範な業界を網羅する、事実上のコングロマリットです。例えば、三菱商事は㈱ローソンおよび日本KFCホールディングス㈱の主要株主です。伊藤忠商事㈱は㈱ファミリーマートのオーナー企業であり、㈱デサントの主要株主です。三井物産㈱は、IHH Healthcare社(マレーシア、東南アジア最大級の病院グループの1つ)の主要株主です。
アジアの他の地域では、コングロマリットが現地経済に深く関与しているのが一般的です。
- 貿易会社がコングロマリットになった例:Swire Pacific Offshore Holdings社(シンガポール)、Jardine Matheson Holdings社(香港)
- アジアの富豪が経営する多角化したコングロマリット:香港のCK Assets Holdings社、CK Hutchison Holdings社、インドのReliance Industries社
- 韓国財閥:Samsung Group社、LG社、Hyundai Group社など。Samsung Electronics(韓国/テクノロジー・ハードウェアおよび機器、当ファンド保有銘柄)、SK Hynix社、LG Energy Solution社など、これらの財閥に属する最も価値の高い子会社はいずれも上場しています。そのため、持株会社は株式市場で特に注目されていません。
総合商社は日本固有のもので、海外の同業他社との対等な比較はできません。しかし投資については、他のコングロマリットと比較することが可能です。過去10年間、日本の総合商社の株価リターンは、アジアの主要上場コングロマリットの大半を大きく上回ってきました。CK Hutchison Holdings社、Swire Pacific社(香港)、Jardine Matheson Holdings社の過去10年間のトータルリターンはマイナスからゼロ近辺でしたが、日本の5大総合商社(三菱商事、丸紅、伊藤忠商事㈱、三井物産㈱、住友商事㈱)は米ドルベースで約116%~267%上昇しました。その結果や以下の理由などから、世界のコングロマリットよりも日本のコングロマリットである総合商社が引き続き注目を集めています。
- コングロマリットは、幅広い業界に資本を配分する事業です。総合商社の実質的な価値は、さまざまな業界に跨がる、世界中の専門家で構成される広範なネットワークにあります。商社はこれにより、多様な機会を獲得することができます。アジアのコングロマリットは一般的に、より少数のセクターに集中する傾向があります。例えば、Swire Pacific社は、香港の不動産、飲料、航空事業に注力し、CK Hutchison Holdings社は港湾と通信事業を中心に、欧州に大きな強みを持っています。総合商社は、セクターと地理の面ではるかに多様化しているだけでなく、貿易会社としての経歴を生かし、上流業界と下流業界とのシナジーも創出します。
- 総合商社は、天然ガス、銅、農産品などのコモディティ事業から利益を創出します。供給成長の鈍化、エネルギー転換、世界的な地政学的リスクの高まりを背景に、コモディティ価格が長期的に上昇するリスクが存在しますが、総合商社はこのリスクを低減する幅広い事業を展開しています。
- 多くのアジアのコングロマリットは家族経営で、トップダウン型の意思決定プロセスを採用しているため、経営者の利益が株主の利益と整合するとは限りません。総合商社はプロの経営陣によって運営されています。かつての総合商社は株主還元をほとんど重視してきませんでしたが、丸紅や三菱商事の新たな株主還元方針に見られるように、状況は変化しています。新しい成長分野への資本配分拡大に向けた総合商社の取り組みは改善しており、株主還元も改善しています。
当ファンドは、総合商社のバリュエーションは魅力的だと考えています。当ファンドは、三菱商事と丸紅の2銘柄に投資しています。三菱商事のPBR(株価純資産倍率)は0.9倍を下回っており、2022年度の総還元額は4,320億円になると予想されています。足元の株主総利回りは約6%です。丸紅のPBRは1.2倍を下回っており、78円の予想DPSと、300億円程度の自社株買いを行うと当ファンドでは予想しています。現在の株主総利回りは約5%です。当ファンドはまた、両銘柄が自己資本を1桁台後半ペースで拡大するとみています。
当ファンドは、1)割安なバリュエーション、2)インフレヘッジ、3)将来の成長を牽引する資本配分改善の可能性を備えた銘柄に投資しています。この組み合わせはアジア全域を見渡しても稀だと思われます。当ファンドの戦略の強みは、日本とアジアから最良銘柄の選択が可能でることです。
当月は、当ファンドの組入銘柄にいくつかの変更を加えました。全体としては中国株の保有比率を引き下げ、台湾や東南アジアなどの他地域の保有比率を拡大しました。株式市場の注目は米国のインフレと、今後の⽶国連邦準備制度理事会(FRB)の政策決定に再び集まっています。当ファンドは引き続き、収益フローとキャッシュフロー創出が底堅い銘柄を選好し、収益の裏付けが少ない高成長銘柄を回避していく方針です。
2023年1月の運用コメント
株式市場の状況
<日本の株式市場>
2023年1月、日本株式市場の代表指数であるTOPIX(配当込み)は前月末比4.42%の上昇となりました。
当月の日本株式市場は下落から始まりました。月前半に米サプライマネジメント協会(ISM)が発表した2022年12月の米製造業景況感指数が2年7カ月ぶりの低水準だったことや、中国製造業購買担当者景気指数(PMI)も低迷が続いたことから、景気後退への懸念が高まったのが主な要因と見られます。月半ばには、日銀が金融政策決定会合で大規模な金融緩和を維持すると発表したことを受け、株式市場は上昇に転じました。月後半には、米国連邦準備制度理事会(FRB)の理事が利上げ幅緩和の支持を表明したことや、米有力紙による早期利上げ停止の観測報道を受け、日本でも成長株を中心に株価が堅調に推移した結果、最終的に前月末を上回る水準で月を終えました。
<アジアの株式市場>
2023年はアジア株式市場の大半が好調な滑り出しを見せました。⽇本を除くアジア市場に使⽤される⼀般的な指数であるMSCIアジア(⽇本を除く、⽶ドル建て)指数は、8.22%上昇して⽉を終えました。台湾、韓国、中国、香港が好調だった一方、インド、インドネシアがマイナスとなりました。
中国では経済再開の動きが継続しました。春節(旧正月)期間中の旅行や支出額に関する統計指標は堅調で、新型コロナウイルスの感染者数にも増加の兆しが見られないため、今後も経済再開の動きは継続するものと思われます。これを受けて中国のインターネット関連銘柄、EV(電気自動車)関連銘柄がアウトパフォームしました。
台湾と韓国の堅調なパフォーマンスを牽引したのはテクノロジー関連セクターでした。半導体セクターについては、2023年上半期業績に関する不安感は拭えていないものの、投資家が短期的な株価動向以外にも目を向け、データサーバやAIアプリケーション、自動車、IoT(モノのインターネット)などによってセクター全体が再び構造的成長軌道に乗ることへの期待が高まったため、株価が反発しました。一方、インド株式市場では資金の流出が続きました。その一因は投資家が再び資金を中国、台湾、韓国に配分していることにあります。加えてAdani Group社(インド)の危機で時価総額が約1,080億米ドル(約13兆9,000億円)消失したことによって、国有銀行のコーポレートガバナンスや潜在的損失に関する懸念が生じ、投資家心理が悪化したことも要因の一つです。
ファンドの運用状況
当月、当ファンドのパフォーマンスは前月末比7.64%の上昇、参考指数のMSCI AC Asia Index(円ベース・配当込み)は同5.95%の上昇となりました。中国市場では、経済再開と経済の早期回復に対する期待感から株価が大幅に上昇しました。前年好調だったインドとインドネシアは、中国への資金回帰の影響もあり、いずれも低調なパフォーマンスとなりました。
当月は、Tencent Holdings(中国/メディア・娯楽)、Alibaba Group Holding(中国/小売)、WuXi AppTec(中国/医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス)などがプラスに貢献しました。前月述べたように、当ファンドは直近半導体関連銘柄を積極的に組み入れており、上記以外にTaiwan Semiconductor Manufacturing Company(台湾/半導体・半導体製造装置)、Samsung Electronics(韓国/テクノロジー・ハードウェアおよび機器)、ソシオネクストなどもパフォーマンスに貢献しました。一方、ICICI Bank(インド/銀行)、ICICI Lombard General Insurance(インド/保険)などがマイナスに影響しました。
中国では3年ぶりにコロナ関連の行動規制がない春節が終わったところで、今後の経済回復ペースが注目されます。速報データの内容は以下の通り良好ですが、経済回復の強さが持続的なものになるのか否かを判断するには時期尚早だと考えます。
- 1月7日から1月28日までの公共交通機関による推計旅行者数は前年比約56%増となったが、いまだに2019年と比較すると約53%に留まっている
- 同期間の航空旅客数は2019年と比較すると約70%まで回復した
- 春節期間中の総旅行者数は前年比約23%増の3億800万人に到達、2019年と比較すると約89%にまで回復し、旅行代理店と関連サービスの売上高は約3,750億元(約7兆2,260億円)となり、2019年との比較でも73%に達した
- 春節期間中の劇場興行収入は67億6,000万元(約1,300億円、前年比約12%増)、総入場者数も1億2,900万人(前年比約13%増)となった
- 中国国家統計局が発表した1月のPMIは54.4と大幅に上昇し、7ヵ月ぶりの高水準となった
注目すべきは、中国では春節期間中に国民の大移動が復活したにもかかわらず、新型コロナウイルス感染拡大のピークが過ぎて中国社会の不安感が薄れ、国民の間で生活の正常化に対する期待感が高まっていることです。
春節についてもう一つ例年と異なるのは、中国の国営テレビ、中央電視台(CCTV)が放送する毎年恒例の旧正月年越し歌番組「春節連歓晚会」(春晩)で、紅包(お年玉)のスポンサーにインターネットプラットフォーム企業の名前がなかったことです。インターネットプラットフォーム企業にとって、春晩の紅包配布は貴重な知名度獲得の手段でした。Tencent Holdingsが提供するWeChatが、2015年に春晩の中でWeChat Payを通じて紅包を配布したのが始まりで、翌年以降も続けられて慣例となったものです。WeChat Payはこのイベントによって一夜にして莫大な数のユーザーを獲得し、2日後には2億枚の銀行カードがWeChat Payに紐づけられました。この出来事によって電子決済が急速に普及したことが、その後数年間で他のモバイルインターネットサービスが大きく発展するきっかけとなり、インターネット業界の黄金期が始まりました。それから毎年、インターネットプラットフォーム企業はユーザー獲得手段として紅包のスポンサーを務めてきましたが、今回スポンサー企業が現れなかったことは、インターネット業界が成熟段階に入ったことを示していると考えられます。インターネットプラットフォーム企業はユーザー獲得からコスト管理に注力し始めており、こうした転換はインターネット業界の持続性を高め、健全な成長を促すため、株主にとっても有益であると当ファンドは考えています。
半導体セクターに目を向けると、1) 中国の経済再開によって需要が刺激されて需要の回復が早まる可能性があり、特にスマートフォンでその傾向が強いこと、2) FRBの利上げペースが今後は鈍るという楽観的な見方があること、3) 一部セグメントで在庫のピーク到達が視野に入っていることなどが、株価の下支え要因となりました。当ファンドの組入銘柄では、Samsung Electronicsが半導体メモリ関連の設備投資削減に関する市場の期待を裏切りました。半導体メモリは現在下降サイクルにあり、主要企業が設備投資と生産量を削減することで需給バランスの回復が早まることが期待されるため、同社の動向に注目が集まっていました。同社は2022年第4四半期の決算発表で、2023年のメモリ関連設備投資は2022年並みになる(設備投資を削減しない)と述べました。これを受けて半導体メモリの下降サイクルが長期化する懸念が高まりましたが、同社は設備投資の中でも新規製造設備、研究開発、極端紫外線(EUV)のインフラの割合を増やすとも述べています。これは生産関連の設備投資が減少する可能性があることを意味しており、技術面の競争力を長期的に高めるため、製造設備の最適化や生産ラインのアップグレードもより活発に行われるものと思われます。同社は減産について明言しませんでしたが、こうした製造設備を一時的に最適化すると、その過程が大幅な減産に繋がることがあります。したがって全体でみると、同社の今年の生産量はほとんど伸びないというのが当ファンドの見方です。ここで重要なのは、この厳しい下降サイクルの中で同社の競争力がますます強まっていくと考えられることです。主な競合先であるSK hynix社(韓国)は2022年第4四半期に多額の営業損失を計上し、2023年の設備投資を前年比50%以上減額すると発表しました。半導体業界を取り巻く環境悪化の影響で、競合先の投資余力は低下していますが、Samsung Electronicsは収益源の分散と健全な財務体質に支えられて投資余力を残しており、競合先との差がますます拡大しています。今回の下降サイクルを抜ければ、同社の体力はさらに強くなっていると当ファンドは考えています。
当月は、当ファンドの組入銘柄に大きな変更はありませんでした。中国経済の再開は好材料ですが、経済回復が市場の予想ほど堅調に進むかという点が主要なリスクになると考えます。加えておよそ3年にわたるコロナ禍と不動産市場の低迷によって、中国の消費者心理が冷え込む可能性もあります。当ファンドでは、中国に関して慎重姿勢を強めており、生活必需品のような安定的な収益源を持ち、生活に欠かせないサービスや製品を提供する企業の組入比率を徐々に引き上げています。したがって、中国の回復が期待外れに終わっても、当ファンドは比較的安定したパフォーマンスを維持できると考えています。
2022年12月の運用コメント
株式市場の状況
<日本の株式市場>
2022年12月、日本株式市場の代表指数であるTOPIX(配当込み)は前月末比4.57%の下落となりました。
当月の日本株式市場は、11月30日にFRB(米国連邦準備制度理事会)のパウエル議長が12月のFOMC(連邦公開市場委員会)における利上げ減速を示唆したことを受け、上昇して始まりましたが、その後は米国景気悪化懸念の高まりなどから下落基調をたどりました。月半ばには、欧米中銀の金融引き締め継続による景気悪化懸念や、日銀が長期金利の許容変動幅を修正したことなどを受け、金融政策の転換懸念から株式市場は大幅に下落しました。月後半にかけては、中国が事実上「ゼロコロナ政策」を終了したことでインバウンドや中国経済再開期待が生じる一方、米国の半導体株安や円高の進行を受けて、一進一退で推移しました。
<アジアの株式市場>
アジア株式市場は11月には堅調なパフォーマンスを記録しましたが、当月はまちまちの値動きとなりました。香港市場などは堅調でしたが、韓国、台湾、インドなどのパフォーマンスが振るいませんでした。⽇本を除くアジア太平洋市場に使⽤される⼀般的な指数であるMSCIアジア太平洋(⽇本を除く、⽶ドル建て)指数は、前月末比0.44%下落して⽉を終えました。中国のゼロコロナ政策が予想以上に早期に緩和されたことで、中国と香港の株式市場の地合いが改善しました。新型コロナウイルスの感染者数は今後数週間でいったん急増するものの、その後は中国のビジネスと経済は他国同様に正常化するというのが投資家の見方である模様で、航空、旅行、レストランをはじめとする経済再開の恩恵を受けると期待される銘柄が堅調に推移しました。また、中国政府が不動産セクターなどに対する規制を緩和したことも好材料と見なされたようです。
中国と香港以外では、FRBがさらなる利上げを行ったこと、2023年に世界経済の成長が鈍化するという懸念が広まったことなどから、投資意欲が低調気味でした。韓国と台湾は世界経済への依存度が高いことから、パフォーマンスが振るいませんでした。半導体関連銘柄は、2023年の短期需要見通しが下方修正されたため、株価が下落基調となりました。インドとインドネシアは2022年のパフォーマンスが他市場を上回ったために好材料に乏しく、投資家の関心は中国と香港株式の買い増しに向かいました。また、日銀が長期金利の誘導目標を修正したことも、円高の要因となりました。
ファンドの運用状況
当ファンドの2022年のリターンは前年末比21.99%の下落、参考指数のMSCI AC Asia Index(円ベース・配当込み)は同5.85%の下落となり、 当ファンドにとっては2022年も試練の年となりました。スタグフレーション(景気が低迷する中で物価が上がり続ける状態のこと)に対する懸念から、多くの当ファンド組入銘柄の株価が下落しました。一方、FRBは大規模な金融引き締めによってインフレの抑制に努めました。バリュエーション算出時のリスクフリーレート(リスクがほとんどない商品から得られる利回りのこと)として一般に使用される米国10年債利回りは、2021年末の約1.5%から2022年末には約3.8%まで上昇しました。これは株式、特に当ファンドが選好する成長株のバリュエーションにとって大きな重しとなりました。
その一方で、FRBの金融引き締めで景気後退が発生するのではないかという懸念が生まれ、多数のセクターで成長見通しが下方修正されました。当ファンドが高い比率で組み入れているグローバル成長株は、世界的な景気循環の影響を受けやすい銘柄です。例えばキーエンス、リクルートホールディングス、Taiwan Semiconductor Manufacturing Company(台湾/半導体・半導体製造装置)などがこれにあたります。さらに、コロナ禍中に巣ごもり消費の恩恵を受けた銘柄は、反対に経済再開が逆風となりました。例えばソニーグループ、メルカリなどがこうした銘柄にあたります。魅力的な価値と利便性を提供するオンラインサービスが引き続き成長するという当ファンドの見方に変わりはありませんが、コロナ禍によって世界中でライフスタイルの見直しが起こったことは、短期的に見ると前述の銘柄群にとって不利に働く可能性があると考えます。
中国では2022年に多くの変化がありました。政府が複数回にわたってロックダウン(都市封鎖)を行ったことで、Tencent Holdings(中国/メディア・娯楽)やLi Ning Company(中国/耐久消費財・アパレル)といった当ファンドの組入銘柄は大打撃を被りました。中国国内では年初から新型コロナウイルス感染者数が増加したことで、深センや上海といった主要都市が大規模なロックダウンを実施し、市場関係者に衝撃を与えました。2月にはロシア軍がウクライナに侵攻しました。この不幸な出来事によって、世界の地政学的情勢は大きく変化し、米中関係はこの数年間で最悪の状態にまで悪化し、中国の台湾侵攻に対する懸念が高まりました。10月には中国全国人民代表大会で習近平氏の3期目の主席就任が承認され、権力の集中がさらに進んだことで、市場にまたもや混乱が生じました。中国政府による不動産市場の取り締まりとゼロコロナ政策も経済成長の足かせとなりました。従業員の多くが高所得者層である大手インターネット企業では大規模な人員削減を開始し、消費の低迷に追い打ちをかける形となりました。MSCI中国指数(米ドル建て)は10月に2016年以来の安値まで下落しました。しかし、12月に入るとゼロコロナ政策に対する一連の抗議活動を受けて、中国政府がゼロコロナ政策を緩和し始めました。さらに2023年の1月8日から新型コロナウイルス関連規制の大幅緩和が発表されると、MSCI中国指数(米ドル建て)は経済再開に対する期待を受けて10月の底値から約36%の大幅上昇をみせました。同指数は第4四半期(10月~12月)には約13%の上昇、2022年通年でみると約22%の下落でした。
ゼロコロナ政策の突然の転換は大きなサプライズとなり、中国における政策予測の困難さが浮き彫りになりました。中国共産党上層部の動きを予測することは不可能であると考えます。目に見える動きから今後の動向を予測することしかできず、その変化が大きい場合は迅速な対応が求められます。新型コロナウイルス関連の政策における変化は大きな転換点であり、波乱含みとなる可能性はあるものの、この政策転換によって世界の投資家の関心が再び中国市場に向く可能性があると、当ファンドでは考えています。こうした環境下で、当ファンドでは香港と中国関連銘柄の組入比率を引き上げています。
2023年に入っても先行きの見通せない状況が続いております。インフレ率はピークを付けたという見方もありますが、FRBによる2%のインフレ目標が早期で達成されることは考えにくく、金利は当面高止まりすると思われます。ただし、市場の関心は金利から世界の経済成長見通しの減速に移る可能性があります。中国は世界の経済成長の原動力となる可能性があるため、2023年の世界経済にとって中国の経済再開は重要なポイントであると考えます。中国の動向はアジア各国に大きな影響を与えるため、その経済回復が他のアジア諸国にとっては好機であると考えます。一方、世界第2位の経済大国である中国の経済が再開すれば、商品価格やインフレ率の押し上げ要因となる可能性もあります。中国がこの初期段階をうまく乗り切れば、他国と同様に経済は回復軌道に乗ると思われます。新型コロナウイルスの感染者数がピークを越えたと思われる北京などの都市では、移動や外食などに関わる経済活動が活発になりつつあります。さらに、インターネットなど一部セクターでは規制による逆風が和らいでいます。中国は12月に新規ゲームの承認を再開しました。注目すべきは今回44本もの輸入ゲームが承認されたことです。輸入ゲームが承認されたのは2021年の取り締まり開始以降で初めてで、これは中国政府が健全なゲーム業界を育てたいと考えていることを端的に示しており、規制リスクに関しては最悪の時期を脱したというのが当ファンドの見方です。
当ファンドは2022年に、日本電産など成長見通しが不確実でバリュエーションが割高な組入銘柄を売却しました。2022年末時点では、中国の消費関連銘柄やインターネット関連銘柄、半導体関連銘柄の組入比率が大幅に増加しています。当ファンドは中国に投資するリスクを認識しているため、外食産業、スポーツウェアなどの規制リスクが低い企業やインターネット関連など規制面の逆風が弱まっているセクターを慎重に選別しています。スポーツウェア、フードデリバリープラットフォーム、外食産業などの組入銘柄の一部は経済再開の恩恵を受けることが期待されます。また、繊維製品や医療機器などの製造業や化学関連銘柄がサプライチェーンの混乱緩和や需要回復の恩恵を受けることも期待されます。半導体の一部セグメントも底打ちが近く、バリュエーションにはすでに悪材料が織り込まれていると考えられます。中国経済の回復が世界経済の底上げに寄与できれば、半導体の需要サイクルの底打ちはさらに早まる可能性もあります。当ファンドではこれまで半導体関連銘柄の組み入れにあまり積極的ではありませんでしたが、組み入れを拡大する好機であると考えています。
交付運用報告書
-
交付運用報告書(第7期 2025年9月12日) (930.5 KB)
-
交付運用報告書(第6期 2024年9月12日) (657.9 KB)
-
交付運用報告書(第5期 2023年9月12日) (664.8 KB)
-
交付運用報告書(第4期 2022年9月12日) (619.4 KB)
-
交付運用報告書(第3期 2021年9月13日) (761.2 KB)
-
交付運用報告書(第2期 2020年9月14日) (686.6 KB)
-
交付運用報告書(第1期 2019年9月12日) (630.6 KB)
運用報告書(全体版)
-
運用報告書(全体版)(第7期 2025年9月12日) (1.0 MB)
-
運用報告書(全体版)(第6期 2024年9月12日) (765.2 KB)
-
運用報告書(全体版)(第5期 2023年9月12日) (781.3 KB)
-
運用報告書(全体版)(第4期 2022年9月12日) (728.4 KB)
-
運用報告書(全体版)(第3期 2021年9月13日) (844.8 KB)
-
運用報告書(全体版)(第2期 2020年9月14日) (803.7 KB)
-
運用報告書(全体版)(第1期 2019年9月12日) (769.6 KB)
動画
レポート
-
- ファンドレポート
- スパークス・新・国際優良日本アジア株ファンド
日本アジア厳選投資の魅力(756.0 KB)
-
- ファンドレポート
- スパークス・新・国際優良日本アジア株ファンド
米トランプ政権の政策がファンドに与える影響について(314.2 KB)
-
- ファンドレポート
- スパークス・新・国際優良日本アジア株ファンド
投資で真に成功するための差別化ポートフォリオ(1.6 MB)
主な投資リスク、費用等
- 当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「投資リスク」をご覧ください。 (1.6 MB)
- 当ファンドに係る費用等については、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「ファンドの費用、税金」をご覧ください。 (1.6 MB)
- 本サイトに掲載されている情報は、スパークス・アセット・マネジメント株式会社のご案内のほか、投資信託および投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、特定の商品あるいは有価証券の投資勧誘を目的としたものではありません。提供している情報の正確性や完全性をスパークス・アセット・マネジメント株式会社が保証するものではありません。サイト内に記載されている情報の著作権は、スパークス・アセット・マネジメント株式会社に帰属し、スパークス・アセット・マネジメント株式会社の許可無しに転用・複製・転載等をすることはできません。